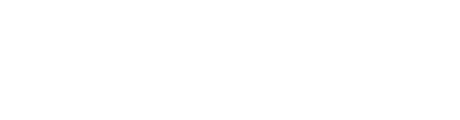※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
ブラックリストに載っていても奨学金は利用できる?利用できない場合の対策方法
目次
これから大学などに進学するために奨学金を申し込もうと考えている方もいるでしょう。その中には、本人やご家族が信用情報のブラックリストに載っていて、審査に不安を感じている方もいるかもしれません。奨学金を申し込む本人がブラックリストに載っていた場合、すぐに審査に影響することはありません。しかし、親がブラックリストに載っている場合、審査に影響を与える可能性があります。奨学金では親が保証人となることが一般的ですが、ブラックリストに載っている人は保証人として認められないためです。とはいえ、他の親族に保証人を頼んだり、日本国際教育支援協会の機関保証制度を利用したりすることで、問題は解決できる可能性が高いでしょう。
奨学金利用者本人がブラックリストに載っていても、審査への影響はほとんどない
ブラックリストとは、信用情報機関に登録された事故情報のことを指し、借金やクレジットカードの支払いを滞納したり、債務整理を行った場合に登録されます。ブラックリストに載っていると、その情報が消えるまで新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。しかし、奨学金の審査では、申請者の学業成績や家庭の経済状況が主な審査基準とされているため、ブラックリストに登録されていることはあまり影響しません。実際に、日本学生支援機構は「個人信用情報機関に登録されている情報は、与信判断(採用時)には利用しません」と公式に明記しています。奨学金機関は、申請者の将来性や社会貢献度を見極めるため、面接や推薦状、学生のモチベーションや教育に対する熱意なども審査に含めて判断します。したがって、利用者本人が金融ブラックリストに載っていても、奨学金を利用できる可能性は十分にあります。
親がブラックリストに載っていると奨学金の利用に影響が出る
奨学金の申請者本人がブラックリストに載っていても、すぐに審査に落ちる原因にはなりません。しかし、親がブラックリストに載っている場合、支障が出る可能性があります。以下では、その理由について説明します。
ブラックリストに載っている人は保証人になれない
奨学金を利用するには、通常、保証人が必要です。保証人には安定した収入があることや、信用情報がクリーンであることなどの要件があります。そのため、親がブラックリストに登録されている場合、保証人としての役割を果たすことはできません。奨学金の保証人はほとんどの場合親が担うため、親がブラックリストに載っていることは奨学金の審査に影響を与える可能性があります。そのため、親がブラックリストに載っている場合、別の保証人を見つけるか、機関保証制度を利用する必要があります。
ブラックリストの確認方法について
ブラックリストに載っているかの確認方法は、信用情報機関に情報開示請求をすることで確認できます。開示請求はオンラインや郵送で行うことができます。信用情報機関には「JICC」「CIC」「KSC」の3つがあり、それぞれ開示請求の方法が異なります。
| 信用情報機関 | 方法 | 手数料 |
|---|---|---|
| CIC | オンライン、郵送 | 郵送請求:1,000円、オンライン請求:500円 |
| JICC | アプリ、郵送 | データ受け取り:1,000円、郵送請求:1,300円 |
| KSC | オンライン、郵送 | 郵送請求:1,679~1,800円、オンライン請求:500円 |
いずれの方法でも本人確認書類が必要ですので、事前に準備しておきましょう。
奨学金の審査に通らない原因
奨学金の審査に落ちる理由は、ブラックリストに載っていることだけではなく、他にもさまざまな要因があります。実際、それ以外の理由が原因である可能性が高いです。
具体的には、以下のようなことが考えられます。
- 世帯収入が条件を満たしていない
- 成績があまり良くない
- 保証人に問題がある
それぞれについて、詳しく解説します。
世帯収入の条件を満たしていない
奨学金の支給条件の一つとして、世帯収入が一定の基準以下であることが求められます。この基準を超えると、経済的支援が必要ないと判断され、奨学金の支給対象外となります。
この基準は奨学金機関ごとに異なるため、申請前に必ず確認しておくことが重要です。また、家庭の収入状況は変動する可能性があるため、申請時には最新の収入証明書類を基に検討する必要があります。
日本学生支援機構の収入基準は以下の通りです。詳細については、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
独立行政法人日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/index.html
●予約採用給付型奨学金●
支援区分の収入基準は以下のように定められています。
第1区分
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。具体的には、あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円未満であること。
第2区分
あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること。
第3区分
あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること。
第4区分
あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること。
※収入は、1月から12月の収入に基づく2024年度の住民税情報を基に算出された支給額算定基準額をもとに審査が行われます。
※支給額算定基準額の計算式は以下の通りです。
(a) 支給額算定基準額=課税標準額×6%-(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)(100円未満切り捨て)
(b) 市町村民税所得割が非課税の場合、(※2)を除き、支給額算定基準額は0円となります。
(c) 政令指定都市に納税している場合、市町村民税調整控除額+市町村民税調整額には4分の3を乗じた額が適用されます。
参照:進学前(予約採用)の給付奨学金の家計基準
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/yoyaku.html
●第一種奨学金および第二種奨学金●
希望する奨学金の家計基準は以下の通りです。
第一種・第二種併用貸与
生計維持者の貸与額算定基準額が164,600円以下であること。
第一種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額が189,400円以下であること。
第二種奨学金
生計維持者の貸与額算定基準額が381,500円以下であること。
※収入は、1月から12月の収入に基づく2024年度の住民税情報をもとに算出された支給額算定基準額で審査が行われます。
※貸与額算定基準額の計算式は以下の通りです:
(a) 貸与額算定基準額=(課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)-(多子控除)-(ひとり親控除)-(私立自宅外控除)
(100円未満は切り捨て)
(a) 市町村民税所得割が非課税の場合、この計算式に関わらず貸与額算定基準額は0円となります。
(b) 政令指定都市に納税している場合、市町村民税調整控除額には3/4を乗じた額が適用されます。
(c) 生計維持者が2人を超える子どもを扶養している場合、超過分1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報またはスカラネット申告人数のうち少ない方を適用します。
(例)生計維持者が「申込者」と「中学生の弟」、「小学生の妹」を扶養している場合、控除額は(3-2)人×40,000円=40,000円となります。
(d) ひとり親世帯の場合は40,000円を控除します。
(e) 私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)・高等専門学校に通い、且つ自宅外通学の場合、在学採用の審査で22,000円を控除します。予約採用の審査では0円となります。
参照:進学前(予約採用)の第一種奨学金の家計基準
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kakei/yoyaku.html
成績が思わしくない
奨学金の審査において、学業成績は非常に重要な要素です。奨学金を提供する機関の基準を満たさない場合、奨学金を受けることができません。特に、返還不要の「給付型奨学金」や無利息で貸与される「第一種奨学金」は、学業に優れた学生を支援するために設けられているため、成績要件は厳しく定められています。そのため、学業成績が低いと他の要素が整っていても奨学金を受ける可能性が低くなります。一方で、利息がつく「第二種奨学金」は要件が比較的緩いため、成績に不安がある場合は第二種奨学金の利用も検討することができます。日本学生支援機構における学力基準は以下のように設定されています。
●給付型奨学金●
高等学校等における全履修科目の認定平均値が、5段階評価で3.5以上であること(※1)。
将来、社会で自立し活躍することを目指し、進学先の大学等で学ぶ意欲を持っていること(※2)。
※1 専修学校の高等課程に通う生徒等は、これに準じた学修成績が求められます。
※2 学修意欲の確認は、高等学校等での面談やレポートの提出などを通じて行います。
日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/gakuryoku/yoyaku.html
●第一種奨学金●
次の(1)または(2)のいずれかに該当することが求められます。
(1)高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均が、5段階評価で3.5以上であること。
ただし、上記基準を満たさない場合でも、以下のア~ウのいずれかに該当し、さらに将来社会で自立し活躍する目標を持ち、進学しようとする大学等で学修意欲(※1)がある者として学校から推薦されれば、第一種奨学金の学力基準を満たすものとして扱うことができます。
ア.生計維持者(原則父母)の貸与額算定基準額が0円である。
イ.生計維持者(原則父母)が生活保護を受けている。
ウ.「社会的養護を必要とする人」(児童養護施設等入所者や里親による養育を受けている者など)である。
※学修意欲の確認は、高等学校等で面談の実施またはレポートの提出を通じて行います。
日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/gakuryoku/yoyaku.html
●第二種奨学金●
次の(1)または(2)のいずれかに該当することが求められます。
(1)高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均が、5段階評価で3.5以上であること。
ただし、上記基準を満たさない場合でも、以下のア~ウのいずれかに該当し、さらに将来社会で自立し活躍する目標を持ち、進学しようとする大学等で学修意欲(※1)がある者として学校から推薦されれば、第一種奨学金の学力基準を満たすものとして扱うことができます。
ア.生計維持者(原則父母)の貸与額算定基準額が0円である。
イ.生計維持者(原則父母)が生活保護を受けている。
ウ.「社会的養護を必要とする人」(児童養護施設等入所者や里親による養育を受けている者など)である。
※学修意欲の確認は、高等学校等で面談の実施またはレポートの提出を通じて行います。
日本学生支援機構 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/gakuryoku/yoyaku.html
保証人に問題がある場合
前述のように、保証人の信用情報に問題がある場合、それが奨学金の審査に落ちる原因となることがあります。
原則として、ブラックリストに載っている人は保証人になることができません。もし親がブラックリストに載っている場合は、他の親族に保証人をお願いすることを検討しましょう。
保証人は4親等内の親族である必要があります。4親等以内の親族には以下のような人々が該当します:
- 父・母
- 祖父母
- 曽祖父母
- 高祖父母
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
- 叔父・叔母
- いとこ
- 大おじ・大おば
もし、どうしても保証人が見つからない場合は、保証人不要の奨学金プログラムや返済不要の助成金を探すことを検討してみましょう。
親がブラックリストに載っていて奨学金が利用できない場合の対処法
親がブラックリストに載っているために保証人になれない場合、他の親族に保証人をお願いするか、日本国際教育支援協会の機関保証制度を利用することで対処できる場合があります。
具体的に解説します。
他の親族に保証人をお願いする
奨学金の保証人は必ずしも親である必要はなく、4親等以内の親族であれば認められます。
親族と相談し、信用情報に問題がない方を保証人として立てることを検討しましょう。保証人を選ぶ際は、できるだけ信用情報に問題がなく、収入が安定している方を選ぶことが望ましいです。
日本国際教育支援協会の機関保証制度を活用する
もし保証人になってくれる親族が見つからない場合は、日本国際教育支援協会の機関保証制度を利用することも一つの選択肢です。
機関保証制度とは、日本学生支援機構の貸与奨学金について、連帯保証人や保証人を立てることなく申込みができる制度です。
一定の保証料を支払うことで、奨学金の元金、利息、延滞金を貸与開始から返還完了まで保証してもらえます。
この保証料は一般的な教育ローンよりも割安であり、負担を少なくして利用できる点が魅力です。
新聞奨学生制度を活用する
一部の新聞社では、独自の奨学金制度を提供しています。
新聞奨学生制度は、通常返還不要の奨学金であり、ブラックリストの影響を受けることなく利用可能です。ただし、日本学生支援機構の給付型奨学金のように完全に給付されるわけではなく、新聞配達の仕事をしながらその給与から奨学金が差し引かれる形となります(差し引かれるのは一部であり、働いた分の給与は受け取ることができます)。
労働によって授業に出られなくなったり、体力的な負担が増すというデメリットもあります。大学生は勉学などで忙しく、支障が出ることも考えられます。
一方で、卒業後に返還する必要がないため、将来の負担を大きく軽減できるという点はメリットです。また、新聞社の奨学金制度を利用することで、無料で寮に入れるほか、食事も提供されるため、生活費を抑えることが可能です。
奨学金制度を提供している新聞社は以下の通りです:
- 朝日奨学会
- 毎日育英会
- 読売育英奨学会
- 日本経済新聞育英奨学会
- 産経新聞奨学会 など
参考:新聞奨学生ガイド https://ad8.jp/shinbun/system/
奨学金の遅延は大きなリスクを伴う
結論として、奨学金の滞納は非常に大きなリスクを伴う行為です。
奨学金を滞納すると、一定期間を過ぎた後に遅延損害金(延滞料)が発生し、信用機関のブラックリストに登録されます。
滞納が長期化すると、最終的には財産の差し押さえに至り、全ての家財を失うことになるため、奨学金の滞納は可能な限り避けるべきです。
奨学金の遅延や未払いを続けることは不可能だと認識しよう
ここでは、奨学金の滞納を続けることによってどのような結果が生じるかを解説します。
奨学金の滞納には一定の猶予期間が設けられていますが、そのまま滞納を続けることはできません。滞納すると、以下のようなデメリットが発生するので注意が必要です。
支払わなければ催促される
奨学金は基本的に口座振替で支払われます。期日までに必要な金額が口座に入金されていない場合、「振替不能」が発生し、翌月分に支払いが繰り越されます。この時、奨学金の機関から電話や督促状が届きます。督促通知は支払いが行われるまで、一定期間ごとに送られ続けるため、支払いをしない限り止めることはできません。
遅延損害金が発生する
奨学金を2ヶ月以上滞納すると、滞納するごとに遅延損害金が発生します。原則として口座振替のため、2回目の引き落とし時点で残高が足りないと、1ヶ月分の遅延損害金が発生します。遅延損害金の金利は、第一種奨学金で1.5%、第二種奨学金で3%となります。借入時期がさらに前の場合は、より高い金利が適用されることもあります。遅延損害金は年利で、返済金額に対して割合で発生するため、借入額が大きいほど遅延損害金も高額になります。また、滞納が解消されない限り遅延損害金は発生し続けます。
保証人に連絡がいく
1回目の振替不能時には本人にのみ通知が届きますが、2回目以降の振替不能が発生すると、保証人にも連絡が行きます。奨学金の保証人は多くの場合親であるため、親に滞納が知られることになります。また、長期滞納が続くと、保証人に返済の請求が届くことになります。長期間の滞納は本人だけでなく、保証人にも大きな影響を与えることになります。
財産の差し押さえが行われる
奨学金の滞納が長期間続くと、最終的に財産の差し押さえが行われることになります。給与の差し押さえや家財の押収など、未納分の回収のための手段が取られ、本人には拒否権はありません。差し押さえられた財産は公売にかけられたり、第三者に売却されたりして未納分に充てられます。公売は「高価有利な売却」が原則とされていますが、入札形式であるため、時には本来の価値よりも安く売却されることもあります。
裁判になる可能性もある
滞納が悪質である場合、訴訟が起こされ、裁判に発展することもあります。裁判が起きると、弁護士を雇わなければならず、弁護士費用や裁判費用も負担することになります。奨学金の滞納は長期化するほど、滞納金、差し押さえ、裁判によって返済がさらに困難になっていきます。そのため、奨学金の支払いが難しくなりそうな場合は、早急に奨学金相談センターに連絡し、支払い猶予や減額を申請することが重要です。
財産はすべて差し押さえられるのか?
差し押さえには制限があり、以下の財産は差し押さえできません:
- 66万円未満の現金
- 生活必需品(家具、衣服、台所用品など)
- 職務に必要不可欠な道具
また、債権についても差し押さえに制限があります。例えば、給与や賞与などの給与債権は原則として1/4までしか差し押さえられません。国民年金、厚生年金、生活保護、児童手当なども差し押さえの対象外です。
奨学金の遅延や未払いを続けることは不可能であると認識し、早期に対応をしましょう。
どうしても奨学金が返せない場合の対処法
ここでは、奨学金の返済が難しい場合に利用できる「返還期限猶予制度」や「減額返還制度」について解説します。
返還期限猶予制度について
返還期限猶予制度は、奨学金の返済が困難な場合に最大10年間の猶予期間を設ける制度です。猶予期間中は返済が免除され、その間、利息や遅延損害金は発生しません。
返還期限猶予には「一般猶予」と「猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類があります。
この制度を利用するためには申請書に記入し、審査を受ける必要があります。一定の条件を満たしていなければ、猶予は認められません。
一般猶予の承認要件は、主に以下の通りです:
- 現在返済が困難であること
- 税込年収が300万円以下(給与所得者以外は200万円以下)であること
猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の承認要件は、次の通りです:
- 第一種奨学金の「猶予年限特例」または「所得連動返還型無利子奨学金」を受けていること
- 新卒であるか、経済的に困難で低収入または無収入であること
返還期限猶予を受けるためには「経済的に困窮し返済が困難な状態である」「収入が一定水準を下回っている」といった条件を満たすことが必要です。
収入がある場合や、なんとなく猶予を希望する理由では承認されませんので注意が必要です。
また、この制度を利用するには現時点で滞納していないことが条件となります。もし滞納中の場合でも、以下の条件を満たせば、滞納している状態で承認される場合があります:
- 返済不能な理由があり、通常の返還期限猶予を申請できない
- 申請事由が「経済困難」で、年収が税込みで130万円〜300万円以下であること
この場合、これを「滞納据置猶予」と呼び、滞納している場合はこちらの制度を申請する必要があります。ただし、承認される難易度は高いとされています。
減額返還制度について
減額返還制度は、返済期間を延長し、月々の返済額を減らす制度です。これは、ローン契約の返済期間を延長する「リスケジュール」に近い仕組みです。
支払いの停止はできませんが、月々の返済額を大きく減額することができます。この制度は「一定の収入があり続ける見込みがある」「減額すれば返済が可能」といった場合に適しています。
また、第二種奨学金を借りている場合、「返済期間を延長すると利息が増えるのでは?」という心配があるかもしれませんが、減額返還制度では、返済期間を最大15年まで延長しても、最終的な総支払額が増えることはありません。
減額返還制度では、1回の申請で15年まで延長するのではなく、毎回12ヶ月ごとの延長となります。そのため、途中で収入が増えた場合、元の返済期間に戻すことも可能です。
ただし、この制度の申請には数週間から1ヶ月程度の期間がかかるため、返済が困難だと感じた場合は、できるだけ早く申請することをおすすめします。
返還免除に該当する場合の確認
奨学金は原則として返済免除にはなりませんが、特定の条件に該当する場合に限り、返済が免除されることがあります。
以下のような場合には、返還免除が適用されることがあります:
- 本人が死亡し、返済が不可能になった場合
- 精神的または身体的障害により労働能力を失った、または高度な制限が発生し、返済が不可能になった場合
これらの事由に該当する場合は、申し出を行うことで返還免除を適用してもらえます。
奨学金が返せないときには、これらの猶予制度や返還免除制度を積極的に活用しましょう。
奨学金が返せない場合の猶予制度
ここでは、奨学金の滞納がブラックリスト入りにつながることについて解説します。
奨学金には信用機関が関わっており、長期間滞納すると信用機関のブラックリストに登録されます。
一度ブラックリストに登録されると、今後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、奨学金を滞納する場合でもブラックリストへの登録だけは避けるようにしましょう。
信用情報について
信用情報とは、お金に関するあらゆる契約情報を含むデータです。クレジットカードの情報、個人情報、返済履歴、利用履歴、金融事故に関する情報などが保管されています。
信用情報は、ローンや賃貸契約など、金銭に関わるサービスを利用する際に「審査」として参照されます。もし事故情報があれば、審査に通らない確率が高くなります。
絶対ではありませんが、契約会社は信用情報を基に、情報に誤りがないか、ブラックリストに載っていないか、支払い能力があるかなどを見て審査の合否を決定します。そのため、ブラックリストに登録されると、住宅ローンやカーローンといった高額契約に大きく影響します。
3ヶ月以上の滞納で信用情報に傷がつく
クレジットカードやローンの滞納によるブラックリスト登録には基準が公表されていないことが多いですが、奨学金に関しては、公式に3ヶ月以上の滞納で信用情報に傷がつくと明記されています。
そのため、ブラックリスト登録を避けるためには、必ず3回目の振替までに支払いを完了しておくことが必要です。
奨学金の遅延は信用情報に影響し(ブラックリストに登録される)
ここでは、奨学金の滞納によってブラックリストに登録されると生じるデメリットについて解説します。
ブラックリストに登録されるのは奨学金の滞納だけでなく、クレジットカードの支払いやローンの返済を滞納しても同様です。
ブラックリストに登録されると、ローン契約や分割払いなど、生活に必要な支払い手段がほとんど使えなくなります。特に、住宅や車の購入時にローン契約を結ぼうと考えている方は十分に注意が必要です。
クレジットカードが使えない
ブラックリストに登録されると、新たにクレジットカードを発行できなくなり、使用できる支払い方法にも制限がかかることがあります。
クレジットカードの発行には審査があり、カード会社は必ず信用情報を確認します。ブラックリストに登録されていると「支払い能力がない」「滞納のリスクがある」と見なされ、発行審査に通りにくくなります。
ただし、審査基準はカード会社によって異なるため、絶対に通らないわけではなく、審査を受けてみないと結果はわかりません。
ローンが組めない
一度ブラックリストに登録されると、5年から10年の間、マイカーローンや住宅ローンなどのローン契約において不利な状況が続きます。
高額な商品の購入に使うローンは、事故情報の有無が審査に大きく影響し、相当な収入や頭金を用意しない限り契約が難しくなります。
特に、分譲マンションや一軒家のような高額な物件の購入では、ブラックリストに載っていることで大きな不利を受けます。両親からの支援金や保証人を立てるなどの対策がなければ、契約はほぼ不可能です。
分割払いができない
ブラックリストに登録されると、高額な商品を分割で購入することができなくなり、すべて一括で支払う必要があります。クレジットカードの分割払い機能や携帯電話の本体代金の分割払いも難しくなります。
一定の金額や支払い回数の分割払いには審査があり、支払い能力が求められます。ブラックリストに登録されていると審査に通りにくいため、一括で支払わなければ商品を購入できないことがあります。
ただし、購入金額が10万円以下の「少額店頭販売品」については分割払いの審査がないため、利用可能です。
何年間ブラックリストに登録されるのか
信用機関におけるブラックリストの登録期間はおおよそ5年から10年です。登録期間は信用機関によって異なるため、心配な方は対象の公式サイトで確認することをおすすめします。
また、現在ブラックリストに登録されているか不安な場合、対象の信用機関に開示請求を行うことで、事故情報の有無を確認できます。ローン契約を検討している方は、事前に確認してから審査を受けると良いでしょう。
お子さんのために早期に借金トラブルを解決しよう
お子さんがこれから奨学金を利用する可能性がある親御さんで、現在借金を抱えている方は、早い段階でその借金を解決することをおすすめします。
ブラックリストが消えるまでには、借金が完済されてから5年かかるため、早期に借金問題を解決することで、お子さんが奨学金を利用する際の不利な影響を避けることができます。
借金問題を解決する方法としては、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの選択肢があります。
自己破産
自己破産とは、借金の返済能力がない方が裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
住宅などの財産は裁判所によって処分されるため失うことになりますが、その代わりに手続きが完了すると借金トラブルから解放されます。
自己破産をした時点でブラックリストに登録されますが、その期間は裁判所での手続き開始から7年で、ブラックリストが消えるまでの時間は他の債務整理に比べて長くはありません。
借金が高額で、収入がない、もしくは少ない方には自己破産が適しています。
個人再生
個人再生とは、借金の返済能力がないおそれのある方が裁判所に申し立てることで、借金を大幅に圧縮し、それを3〜5年で返済する再生計画を立てる手続きです。
自己破産とは異なり、財産が処分されることはありませんが、借金自体は残るため、手続き後も返済を続けなければなりません。
ブラックリストが消えるのは「完済してから」5年後となるため、個人再生の場合、時間がかかることになります。
任意整理
任意整理とは、債権者と交渉し、将来発生する利息をカットしてもらう手続きです。
元金は減りませんが、利息が軽減されることで毎月の返済負担を軽くすることができます。
また、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さないため、手続きはそれほど複雑ではなく、債務整理の中では比較的簡単な手続きといえます。
ただし、利息カット後の債務は3〜5年で返済しなければならないため、ブラックリストが消えるまでには時間がかかります。
まとめ
奨学金を利用する本人がブラックリストに載っている場合、奨学金の審査にはそれほど影響しません。ただし、親がブラックリストに載っていると、親が保証人として立てられず、審査に通らない可能性があります。
もし親が保証人になれない場合は、4親等以内の親戚にお願いすることを検討しましょう。それも難しい場合は、日本国際教育支援協会の機関保証制度を利用することも一つの方法です。
また、新聞奨学生制度など他にも選択肢があるので、自分に合った制度を利用するのが良いでしょう。
さらに、お子さんがこれから奨学金を利用する可能性がある親御さんで、現在借金を抱えている場合は、早い段階で債務整理を行い、借金を解決することをおすすめします。
奨学金の支払いに関するよくある質問
奨学金の支払いに関するよくある質問をまとめました。
奨学金の滞納でブラックリストに登録されると、永遠に消えないのでしょうか?
奨学金を滞納してブラックリストに登録されると、完済後5年が経過するまで事故情報は消えません。
奨学金の返済期間が長期にわたることが多いため、ブラックリストに載った情報が長期間残る可能性があります。
奨学金を滞納すると、どのくらいでブラックリストに登録されるのか?
奨学金の支払いが2ヶ月続けて滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。