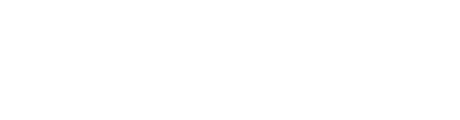※この記事は、広告を含む場合があります。
自己破産は最終的に免責を認められるために手続きをします。免責とは何かと、免責後に残った借金はどうなるかについて解説します。
目次 表示
免責とはどんな制度?
免責とは、法的に借金などの支払い義務がなくなることを指します。
自己破産手続きでは、最終的に免責を認められることが最大のメリットであり、目的です。
借金の返済がどうしても不可能な場合に免責が認められると、返済しなくて済むので、生活の立て直しができます。
自己破産手続きでは、債務者にある財産を調査、換金のうえで債権者に平等に分配され、返済に充てます。
個人の自己破産では、財産を換金後に残った負債の返済免除を求めるために、免責手続きを行うのです。
法人の場合は自己破産手続きをすると残りの借金とともに法人自体も消滅します。
ところが、個人の場合は個人が消滅することは不可能です。そのため、個人は消滅しないままで借金の返済義務のみを消滅させる、免責という制度が採り入れられています。
免責されると借金はどうなる?
免責されると、借金の返済義務が消滅します。ただし、あくまで消滅するのは返済義務だけで、借金そのものが消滅するわけではありません。
法的な解釈では、免責すると返済しなくても法的に問われない借金(自然債権)になると考えられています。
自然債権には法的な支払い義務はありませんが、強制されない任意の返済(任意返済)はできます。
つまり自己破産をした後でも、借金の任意返済は可能ということです。自己破産をしても、家族や友人、知人からの借金はせめて返したい、人間関係を壊したくない、という場合は任意返済ができます。
ただし、家族や友人、知人に対して「自己破産後に任意返済できるから借金は返す」と約束や書面で残すのは厳禁です。
自己破産の免責不許可事由(免責が許可されない可能性のある行為や理由)のひとつである、特定の債権者にだけ返済する行為(偏波弁済)に該当するからです。
法的な効力はないものの、書面などで返済の約束を残すのは避けましょう。
免責の対象にならない負債
免責が認められると、法的に借金の返済義務が免除となります。ただし、すべての支払いが免除となるわけではありません。
免責の対象とならない負債や支払いには、以下のものがあります。
- 税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた生命・身体損害に基づく損害賠償請求権
- 日常の生活費など(夫婦間の相互協力扶助義務、親族間の扶養義務に基づく請求権)
- 婚姻費用(夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権)
- 養育費(子どもの監護義務に基づく請求権)
- 個人事業主が従業員を雇っている際の給料など
- 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権
- 罰金等の請求権
租税等の請求権
租税等の請求権とは、税金や年金、保険料などの公的な支払いを指します。
破産手続開始時に納期限の到来していない、または納期限から1年を経過していない税金や年金、保険料は免責の対象となりません。
税金や年金、保険料が支払えない場合は支払猶予や分納、免税などの措置が取れる場合があります。役所の該当する課へ相談してみましょう。
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
積極的な加害の気持ちや悪意で加えた暴力や精神的苦痛への損害賠償は、支払いの義務が残ります。
たとえば、DVやモラハラなど妻への加害を目的とした場合の慰謝料や損害賠償は支払いの義務が残りますが、妻への悪意がない浮気の慰謝料の場合には支払い義務が免除される場合があります。
破産者が故意または重大な過失により加えた生命・身体損害に基づく損害賠償請求権
故意や悪意を持って相手へ怪我などをさせた場合の損害賠償は、支払いの義務が残ります。
たとえば、わざと車ではねたなど危険運転致死に該当する場合の損害賠償は免責となりません。
一方、ハンドル操作誤りなど故意ではない損害賠償については、免責となる可能性があります。
日常の生活費など(夫婦間の相互協力扶助義務、親族間の扶養義務に基づく請求権)
同居している夫婦や親族間には、相互協力扶助義務や扶養義務が発生します。
夫婦や親族間で同居のさいに発生する生活費や医療費などの債権の支払いは免責となりません。
婚姻費用(夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権)
婚姻費用とは、婚姻によって発生する費用です。
たとえば、夫が浮気によって家を出てしまって生活費を入れてくれなくなると、婚姻関係の継続が難しくなります。
そのため、妻は婚姻費用の分担を請求できます。裁判などで婚姻費用の分担が決まると、夫が自己破産をして免責が認められても、婚姻費用は継続して妻に支払わなければいけません。
養育費(子どもの監護義務に基づく請求権)
子どもの面倒を見る権利(親権)を持つ親は子どもの生活費や医療費、教育費などを支払う義務があります。
離婚をしたあとでも子どもの監護義務は発生しているため、養育費を支払うことになります。
自己破産をした場合、養育費など子どもの監護義務に基づくものは免責になりません。
個人事業主が従業員を雇っている際の給料など
雇い主と従業員の間には、雇用契約が結ばれます。雇用契約とは、従業員は雇い主の元で労働をすること、雇い主は労働の対価として報酬を与えることを約束することです。
従業員は、報酬が支払われなかった場合に雇い主に対して給料や退職金などを請求できる「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権」があります。
この請求権は免責が及ばないため、従業員への給料や退職金などは免責にならず、支払いの義務が継続します。
意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権
自己破産申立てのさいには、債権者一覧表や名簿の提出が義務づけられています。
債権者一覧表や名簿に記載されていない債権者があった場合、その債権者の債権については免責されません。
ただし、故意に債権者を記載しなかった場合のみです。うっかり書き忘れてしまった場合は免責となります。
罰金等の請求権
犯罪を犯した場合に罰として強制的に取り立てられる罰金や科料、追徴金は免責となりません。
まとめ
自己破産をすると、法人の場合法人とともに残債の返済が消滅します。
個人の場合はその後の生活再建を目的に、残債の法的な返済義務が消滅する免責という制度が設けられています。
免責となると法的な返済義務はなくなりますが、強制力のない元での任意返済は可能です。
自己破産後でも、人間関係を保つために家族や友人、知人への返済は続けられます。
自己破産後免責が認められても、税金や保険料、故意の行為による慰謝料、養育費などの返済義務は残っています。
すべての支払い義務がなくなるわけではない点に注意しましょう。個人での自己破産の最大の目的は、免責となって生活を立て直すチャンスが与えられることです。
いつまでも返済が終わらない借金で悩んでいるときには、自己破産も検討するためにまずは弁護士へ相談してみましょう。