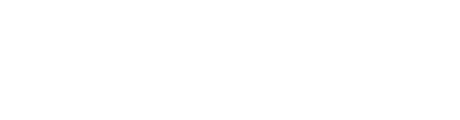※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
奨学金を踏み倒すのは危険!返済遅延のリスクとその対策
目次
近年、卒業後の低収入や収入減少が原因で、奨学金の返済に困難を感じ、踏み倒しを考えるまで追い込まれる方が少なくありません。
日本学生支援機構によると、奨学金を利用している大学生は約5割に達しています。
この記事では、大学生の半数以上にとって身近な問題である奨学金の踏み倒しが可能かどうか、そのリスクと解決策について詳しく解説します。
奨学金の踏み倒しが困難な理由
奨学金は、経済的に困難な中で進学を目指す人にとって頼りになる制度です。
しかし、奨学金を利用した方の中には、「大学卒業後に就職できなかった」「就職しても収入が低かった」「予期しない失業に直面した」などの理由で、奨学金の踏み倒しを考えざるを得ない状況に追い込まれることもあります。
とはいえ、現実的に見て、奨学金の踏み倒しは非常に困難であると言わざるを得ません。
奨学金は時効が適用されにくい
奨学金は、2020年4月1日以降に借りた分については最終返済日から5年、2020年3月31日以前に借りた分については最終返済日から10年が経過すると、消滅時効が成立します(※民法改正により借り入れ時期によって消滅時効の期間が異なります)。
しかし、以下の場合において「時効の更新」が発生し、時効の進行がリセットされます。
- 裁判や法的手続きで請求を受けた
- 強制執行を受けた
- 債務承認をした
前述のように、日本学生支援機構やその債権を譲渡された債権回収会社は、滞納が続く債務者に対して裁判を起こし、その結果として強制執行による財産の差し押さえが行われます。
また、債務者が借金返済の意思を示したり、少しでも返済を行うと「債務承認をした」と見なされ、時効がリセットされるため、時効の進行が最初から再スタートすることになります。
つまり、奨学金の時効は成立しにくいということです。
訴訟を起こされる
その理由は、奨学金の返済が滞ると、奨学金を貸し付けた日本学生支援機構や、その債権を譲渡された債権回収会社から裁判を起こされるリスクがあるためです。
奨学金の返済を延滞し続けると、最終的には裁判所を通じて強制執行の手続きが進行します。
奨学金の返済を踏み倒した結果、裁判所から強制執行が認められると、最終的には預金、給与、家などの不動産を含む財産が差し押さえられることになります。
保証人に対して支払い請求がなされる
奨学金の返済が滞ると、借り入れ時に設定した連帯保証人や保証人に返済の請求が行われます。
多くの場合、連帯保証人や保証人には家族や親族が設定されています。つまり、奨学金の返済を踏み倒すと、家族や親族に一括で返済を請求される可能性があるということです。
家族や親族への影響を考慮すると、奨学金の踏み倒しは非常に高いハードルがあると言えます。
支払義務が第三者である保証人に移る
現在の奨学金は、ほとんどの場合、第三者の連帯保証人を必ず設定する形を取っています。そのため、奨学金を借りている本人が自己破産をしても、保証人である第三者に支払義務が移ります。
つまり、その第三者が自己破産しない限り、奨学金の返済を完全に免れることはできません。
自己破産をすると自分の返済義務は消えますが、保証人がその代わりに支払いを行うことになります。また、奨学金を借りていた人が亡くなった場合でも返済義務は消えず、保証人に返済の督促が行き、支払義務が移行します。
返済を無視すると一括返済を求められる可能性がある
奨学金の支払いを無視して延滞が3ヶ月以上続くと、奨学金の一括返済を求められる可能性があります。
(学資貸与金の返還期限など)
第五条 法第十四条第一項の学資貸与金(以下「学資貸与金」という。)の返還期限は、貸与期間終了月の翌月から6ヶ月を経過した日(第三項で「六月経過日」と記載)以降20年以内で、機構が定める期日とします。返還方法は年賦、半年賦、月賦など機構の定める割賦方式によります。ただし、学資貸与金を受けた者はいつでも繰上返還が可能です。
- 学資貸与金を受けた者が、支払能力がありながら返還を著しく怠った場合、前述の規定に関係なく、その者は機構の請求に基づき、指定された期日までに未返済額の全額を返済しなければなりません。
引用:独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条5項|e-Gov
この場合、請求されるのは「元本」「未払いの利息」「延滞日から発生した延滞金」です。
奨学金の延滞金は、貸与終了時期などによって異なりますが、年率はおおよそ3~10%です。
参考:延滞金|独立行政法人日本学生支援機構
場合によっては職場への連絡が行くこともある
日本学生支援機構などの奨学金の返済を無視して滞納を続けると、状況によっては職場に連絡が来たり、自宅に調査が訪れたりする可能性があります。
(3)事前に承諾を得ている場合や、登録された自宅や携帯番号がないなど他の連絡手段がない場合、本人の勤務先に電話をかけることがあります。
引用:督促|独立行政法人日本学生支援機構
連絡が取れないなど、正当な理由がある場合には、職場への連絡や自宅訪問は法律で許されています。
また、日本学生支援機構が奨学金の回収業務を委託したアルファ債権回収や日立キャピタル債権回収株式会社などからも連絡があるかもしれません。
これらの回収から逃れようと転職する人もいるかもしれませんが、裁判で訴えられて差し押さえが認められた場合、財産の開示が求められ、勤務先が知られることがあります。
訴訟に至れば、こうした取り立てから逃れるのは非常に難しくなるでしょう。
完済するまでブラックリストに載り続ける
延滞金が加算されることになる
奨学金の返済が滞ると、当然ながら延滞金が発生します。これは無利子型でも有利子型でも変わりません。2020年3月28日以降の返済分には年率3%、2014年3月28日以降には年率5%、それ以前の返済分には年率10%の延滞金が課されていました。
※賦課(ふか)とは、税金などを割り当てて負担させることを意味します。
第一種奨学金(無利息)
延滞した割賦金に対して、返還期日の翌日から返済日までの日数に応じて計算されます。
- 2014年3月27日までは年率10%(365日当たり)
- 2014年3月28日から2020年3月27日までは年率5%(365日当たり)
- 2020年3月28日以降は年率3%(365日当たり)
この計算の割合に基づいて延滞金が賦課されます。
奨学金を踏み倒したことによるリスク
奨学金を踏み倒すことで、以下のリスクが生じます。
2ヶ月以上の滞納で延滞金が発生する
奨学金の返済が2ヶ月以上滞ると、延滞金が発生します。
第二種奨学金の場合、延滞している割賦金(利息を除く)に対し、年3%(365日あたり)の割合で、返済期日の翌日から延滞日数に応じた金額が延滞金として加算されます。
3ヶ月の滞納でブラックリストに登録される
さらに、返済開始から6ヶ月が経過し、延滞が3ヶ月以上続いた場合、個人信用情報機関である「全国銀行個人信用情報センター」(KSC)に事故情報が登録されます。
この結果、奨学金返済の滞納により、いわゆるブラックリストに載ることになります。
事故情報の登録期間は、延滞の場合5年です(自己破産・個人再生の場合は7年、任意整理には区分なし)。
事故情報が登録されると、KSCの加盟金融機関に情報が共有され、新たな借り入れやクレジットカードの作成、住宅ローンやカーローンの利用ができなくなります。
参考:全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)
債権回収会社による取り立てが始まる
機構が委託した債権回収会社は、本人、連帯保証人、保証人に対して奨学金回収の手続きを開始します。
その結果、何度も取り立ての電話がかかり、督促状が届くなど、精神的に追い詰められることになります。
半年以上の滞納で差押え手続きが開始される
裁判所から強制執行が申し立てられ、預貯金や自宅などの不動産、給与の一部といった財産が差し押さえられます。
奨学金制度の3つの主要な仕組み
奨学金制度は大きく分けて3つの種類があります。これについても再確認しておきましょう。
貸与型奨学金の特徴
奨学金制度は、名前の通り「学費を借りる」形の制度です。これには、貸付金に利子がつく有利息型と、利子がつかない無利息型があります。日本学生支援機構の奨学金や地方自治体、民間団体の奨学金のほか、教育ローンもこのカテゴリーに分類されます。
日本学生支援機構の奨学金では、無利息型が第一種奨学金、有利息型が第二種奨学金となっており、利率は固定されていても低金利です。例えば、平成19年4月以降に採用された奨学生の利率が適用されます。
教育ローンは、銀行、信販会社、日本政策金融公庫などの金融機関から借りるローンです。これらのローンは、他の奨学金と比べて利息が高く、たとえば日本政策金融公庫では年利約2.15%、銀行や信販会社では平均して年3.0%~5.0%となっています。
給付型奨学金の特徴
名前の通り、こちらは「もらう」形の奨学金制度です。主に地方自治体、民間団体、各学校が提供する奨学金がこのタイプに該当します。この奨学金は返還義務がないため、学業に集中することができ、卒業後に返済の負担を気にすることなく生活を送ることができます。
新聞奨学生制度の特徴
昔の大学生のアルバイトと言えば、新聞配達を思い浮かべる方も多いでしょうが、実は大手新聞社の多くが提供する奨学金制度を活用した「稼ぐ」タイプの奨学金制度もあります。新聞奨学生は進学後、新聞配達の仕事をしながらこの奨学金制度を利用できます。支給額は各新聞社によって異なりますが、月額10万円~15万円の給与に加え、住居や食事が提供される場合もあります。毎月安定した収入を得られる上、卒業後に返済義務はありません(在学中に利用を停止した場合には一部返済の可能性あり)。また、この制度を利用しても卒業後に特定の新聞社に就職する必要はありません。
奨学金選びのポイント:所得連動返還型無利子奨学金制度がおすすめ
日本学生支援機構には、平成24年から導入された「所得連動返還型無利子奨学金制度」というユニークな制度があります。この制度は、無利子の第一種奨学金の一部に適用されます。
所得連動返還型無利子奨学金は、通常の奨学金と同じく貸与型で、元本の返済義務があります。しかし、その返還開始時期に違いがあり、卒業後に収入が一定額を超えるまで返済が猶予される仕組みになっています。
通常の一般猶予は最長5年ですが、所得連動返還型無利子奨学金の場合、猶予期間に制限はありません。ただし、毎年日本学生支援機構への申請と承認が必要となります。
返還猶予が適用される所得基準
会社員などの場合は給与所得が300万円以下、自営業などの場合は所得から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下であることが条件です。
ただし、奨学金を利用している方が結婚などで被扶養者となった場合、以下のいずれかに該当しないと返済猶予を受けることはできません。
返済猶予の条件:被扶養者となった場合
乳幼児を育てる世帯で、当該被扶養者以外に保育を行う者がいない場合、介護や療養を必要とする障害者・要介護者がいる世帯で、当該被扶養者以外に介護を行う者がいない場合、当該被扶養者が妊娠中である場合、または当該被扶養者が身体に障害があり、やむを得ない事情で仕事をすることができない場合。
家族の所得制限が利用条件に影響
所得連動返還型無利子奨学金を利用できるのは、第一種奨学金に採用された者であり、家計を支える者(共働きの場合は両親)の所得が以下の条件を満たす場合に限られます。
- 会社員等の場合:給与所得300万円以下
- 自営業等の場合:収入から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
奨学金返済に困っている方へ
奨学金の返済ができない場合、保証人に迷惑がかかるなど、5つのリスクがあります。
リスクを避けるためにも、まずは【救済制度】について理解しておきましょう。
猶予期間終了後の対応
猶予期間が終了した後、返済残高や1回ごとの返済額、返済回数などに変更は一切ありません。第一種奨学金は無利子であるため、猶予期間中であっても金利が加算されることはありません。
奨学金の時効が成立すれば返済義務は免除される?
奨学金を踏み倒せるとすれば、それは奨学金の時効が成立した時です。
今回は、奨学金の時効や踏み倒しが可能かどうかについて解説します。
奨学金の時効期間は5年から10年の間
奨学金の時効は5〜10年となっています。時効に幅があるのは、民法改正前後で時効の期間が異なるためです。
この「時効」とは、お金を貸した側(債権者)が借金の返済を求める権利が消失することを指します。
借り主(債務者)が一定期間返済をしない場合、債権者が返済を求めなければ、その請求権は失われます(民法第166条)。
なお、改正民法は2020年4月1日に施行されたため、奨学金の契約がいつ行われたかによって時効の期間が異なります。
改正前(2020年3月31日以前)の契約:最後の支払い期日または最終返済日から10年
改正後(2020年4月1日以降)の契約:最後の支払い期日または最終返済日から5年
※奨学金の場合
そのため、最後の支払い期日(一括返済を求められた日)や、最後に支払った日から一定期間が経過すると、時効が成立する可能性があります。
ただし、支払いを免れるためには、時効を主張するための「時効援用」という手続きを行う必要があります。
時効はリセットされるため、成立が難しい
借金は一定期間が経過すると時効が成立しますが、実際には時効を成立させることはほとんどの場合難しいです。
その理由は、特定の行為が発生すると時効のカウントがリセットされたり、一時的に停止したりするためです。
時効の更新
時効のカウントが最初からやり直しになることを指します。
時効の完成猶予
時効のカウントが一定期間停止することを指します。
例えば、以下のような時効更新の理由が生じると、時効はリセットされて最初からカウントが始まります。
- 債務を承認した場合
請求に対して少額の支払いをしたり、支払いについて相談したりして借金があることを認めること - 裁判で判決が確定した場合
判決が確定すると時効が更新され、判決から10年が経過するまで時効は成立しません
これらは一例に過ぎませんが、債権者が裁判で訴えるなどすれば、時効が更新されたり猶予されたりする可能性があります。
債権者としても時効で踏み倒されることを避けたいので、時効が成立する前にこうした手段を取ってくることが考えられます。
そのため、時効を狙って踏み倒すことは現実的には非常に難しいです。
仮に時効の成立を狙ったとしても、支払いを無視し続けて時効が成立するまでの間、連帯保証人が請求を受けたり、ブラックリストに載ったままであったりすることになります。
奨学金返済が困難な場合の対応方法
こうした状況を避けるため、奨学金の返済が難しい場合は、日本学生支援機構が提供している期限延長や減免の制度を利用できる可能性があります。
また、返済が困難な場合に考えられる対処法としては、以下のような方法があります。
- 返還期限猶予制度
- 減額返還制度
- 返還免除
- 奨学金以外の借金がある場合は、個人再生や自己破産を検討する
- 家族や親族に相談する
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、一定期間、返済期限を延長する制度です。
元金や利子が免除されるわけではありませんが、その期間中は利息が加算されることはありません。
延滞者であっても、傷病や生活保護の受給中など、真に返還が困難な場合には、猶予申請と同時に現在の猶予を申請することで、延滞期間中に猶予事由に該当する期間について返還期限猶予を適用してもらうことができます。
返還期限猶予制度には以下の2種類があります。
- 一般猶予
- 猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予
一般猶予
適用期間は通算で10年(120ヶ月)が上限ですが、以下の条件に該当する場合は10年の制限を受けません。
- 災害(注)
- 傷病
- 生活保護の受給中
- 産前休業、産後休業、育児休業
- 一部の大学校に在学中
- 海外派遣
ただし、返還期限猶予は毎年申請が必要です。
(延滞している場合、延滞開始から1年(12ヶ月)ごとに猶予申請書と証明書を提出する必要があります。)
経済的困難を理由に制度を利用する場合、利用条件は以下の通りです。
- 給与所得がある場合:年間収入300万円以下
- 給与所得以外の収入がある場合:年間所得200万円以下
また、所得算定の際には、本人の被扶養者について1人につき38万円が控除されます。
さらに、親等に対して生活費補助を行っている場合も、同様に38万円が控除されます。
(注)災害が原因の場合、同一災害については災害発生から原則として5年が限度となります。
所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予制度
「猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」とは、一定の収入や所得を得るまでの間、返済を猶予してもらいたい場合に申請できる制度です。
(給与所得者の場合:年間収入300万円、給与所得者以外の所得の場合:年間収入200万円)
適用期間に制限はありません。
ただし、本人が被扶養者である場合には、一定の条件が求められます。
留学時
外国の学校に留学する際は、在学猶予手続きを利用できます。
海外の大学に在籍している場合も返還猶予が適用されます。
国内の大学に学籍を残している場合は、その大学を通じて猶予手続きを行う必要があります。
国内の大学院や学校進学時
国内の大学や大学院への進学を希望する場合、一般猶予として返還猶予の申請が可能です。
卒業後1年以内であれば、「入学準備中」として返還猶予を申請することもできます。また、防衛大学校や気象大学校、国立看護大学校などに在籍している場合、大学在学中として返還猶予が認められます。
国内外で研究員として働く場合
国内外で研究員として勤務し、かつ収入が少ない場合は、「外国で研究中」または「特別研究員」として返還猶予が認められます。
その他
災害や事故に遭った場合、または産休中・育児中の場合は、罹患証明書や休業証明書に加えて、経済的困難を証明する書類(前年度の所得証明書など)を提出することで、一般猶予の申請が可能です。
減額返還制度
減額返還制度とは、毎月の返済額を2分の1または3分の1に減額し、返済期間を延ばして返済する仕組みです。
この制度の対象となるのは、災害、傷病、またはその他の経済的理由により奨学金の返済が困難な方で、当初の返済額を減額すれば返済が可能となる方です。
1回の申請で適用される減額返還期間は12か月で、最長15年(180か月)まで延長できます。
経済的困難を理由に制度を利用する場合、利用条件は以下の通りです。
- 給与所得がある場合:年間収入325万円以下
- 給与所得以外の収入がある場合:年間所得225万円以下
また、所得算定時には、一律25万円が収入・所得金額から控除されます。
返還免除
返還免除制度とは、奨学金の残債の全額または一部を免除することができる制度です。
この制度が適用される条件は、以下の2つです。
- 本人が死亡し、返済が不可能になった場合。
- 精神的または身体的な障害により、労働能力を喪失するか、労働能力に重大な制限が生じて、返済が不可能になった場合。
奨学金以外の借金がある場合、個人再生や自己破産を考慮する
上記の制度を利用しても返済が困難な場合、奨学金以外にも借金がある場合などは、奨学金を含めて債務整理を検討することが一つの選択肢です。
債務整理には、以下の3つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
奨学金を含めて債務整理を行う場合、
- 借金を5分の1〜10分の1に減額して分割返済する「個人再生」
- 借金全額の返済免除を求める「自己破産」
のいずれかを選ぶことが一般的です。
ただし、個人再生や自己破産を選択すると、連帯保証人や保証人に返済義務が移るため、事前にこれらの人々と相談することが重要です。
困窮している場合、連帯保証人や保証人が金銭的な援助をしてくれる可能性もあります。
もし連帯保証人や保証人が返済できない場合、彼らも別途債務整理を検討することが推奨されます。
低金利の奨学金には任意整理の効果があまりない
では、任意整理が奨学金の債務整理に有効な方法でない理由は何でしょうか?
結論として、答えは「イエス」です。
任意整理は、債権者と裁判外で交渉し、借金の将来利息を減らして残りの元金を3年から5年で分割返済する手続きです。
ただし、任意整理が効果的なのは、消費者金融やクレジットカード会社など、利息が高い借金に対してです。日本学生支援機構の奨学金の場合、元々利率が非常に低いため、将来利息を削減しても減額効果はほとんど期待できません。
奨学金以外の借金には任意整理が有効な場合も
任意整理で借金減額を実現するには、奨学金については返還期限猶予や減額返還制度を利用し、奨学金以外の高金利の借金(消費者金融やクレジットカード会社からの借金)に絞って任意整理を行うのが効果的です。
奨学金以外の借金が減額されることで、その分のお金を奨学金の返済に充てることができ、さらに個人再生や自己破産のように連帯保証人や保証人に請求が行く心配もなくなります。
家族や親族に相談して支援を求める
奨学金の連帯保証人や保証人には、家族や親族がなることが一般的です。
奨学金の返済を踏み倒すことで家族や親族に影響が及ぶ可能性がある場合、その前に相談することが大切です。もしかすると、返済額を援助してくれたり、一時的に立て替えてくれるかもしれません。
また、連帯保証人や保証人である家族や親族にとっても、奨学金を踏み倒して一括返済を求められるよりは、事前に少しでも金銭援助や立て替えをしてもらう方が負担が軽くなる可能性が高いと考えられるでしょう。
奨学金が返済困難な場合、債務整理を考慮する
上記の制度が利用できず、どうしても奨学金を支払えない場合は、債務整理を検討することをおすすめします。
債務整理とは、法律に基づいて借金を減額したり免除したりする手続きです。
奨学金の返済も、債務整理によって減額や免除が可能な場合がありますが、いくつかの注意点があるため、以下で詳しく解説します。
奨学金は任意整理では減額できない
債務整理の中で最も広く知られている方法は任意整理です。
しかし、奨学金は任意整理によって減額することはできません。そのため、個人再生や自己破産を検討することが必要になります。
任意整理は、弁護士が借り入れ先と交渉して、今後の利息などをカットする方法です。
消費者金融など金利が18%〜20%ほどのケースでは、利息をカットすることで減額効果が期待できる場合もあります。
奨学金の金利は、利率固定方式や見直し方式により異なりますが、約0.01%〜0.9%程度で、住宅ローンのような低金利です。
また、奨学金の返済期間は通常3年〜5年(36〜60回払い)で、月々の負担が増えることになるため、任意整理で解決するのは現実的ではありません。
ただし、奨学金以外に消費者金融などからの借金があり、返済が厳しい場合には、他の借金の負担を減らすことで月々の支払い負担を軽減できる可能性があります。
複数の借り入れ先があり、月々の支払いを軽減したい方には任意整理がおすすめです。
自己破産で返済義務が免除される
収入が少なく、今後も返済が難しい場合や、病気などで働けない状況にある場合は、自己破産を選ぶことで借金の免除を受ける方法が有効です。
自己破産は、裁判所の承認を得て、借金の返済義務をなくす手続きですが、非常に強力な手段である一方で、いくつかのデメリットもあります。
例えば、一定以上の価値がある財産は没収され、債権者に分配されることになります。
また、連帯保証人や保証人にも返済請求が行く点も大きな欠点です。
個人再生と同じように、自己破産を選ぶと連帯保証人や保証人に請求が行きますが、もし奨学金の返済を軽減する方法が利用できない場合は、連帯保証人と相談の上で自己破産を選択することも一つの選択肢です。
場合によっては、連帯保証人と共に自己破産を申請することも可能です。
このように、債務整理にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
どの手続きを選ぶべきか、連帯保証人への請求を回避する方法について不安がある場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
個人再生で借金は最大10分の1まで減額可能
奨学金そのものを減額したいと考えている方や、安定した収入があり計画的に返済できる方には、個人再生を利用して借金を減額する方法がおすすめです。
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額する手続きです。
2022年に労働者福祉中央協議会が実施したアンケートによると、奨学金の借入総額は平均約300万円となっています。
所有している財産によって異なりますが、個人再生を利用すると、借金を100万円まで減額できるケースもあります。
個人再生の場合、借金は原則として3年で完済することになるため、100万円まで減額されれば、無理なく支払うことが可能となるでしょう。
しかし、注意点も存在します。個人再生を選択すると、借り入れた本人だけでなく、連帯保証人や保証人に返済の請求が行くことになります。
そのため、個人再生を選ぶかどうかは、連帯保証人と十分に相談し、慎重に決定する必要があります。
債務整理の相談窓口
債務整理を行う際は、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に相談する際は、借金問題に精通している弁護士や、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
特に債務整理では、無料相談を提供している弁護士も多く存在します。
また、弁護士に依頼すると、取り立てが停止されることがほとんどで、分割払いが可能な場合もあります。
万が一、費用を準備できない場合は、法テラスへの相談を検討するのも一つの方法です。
まとめ
これまで説明してきたように、奨学金の返済を踏み倒すことは非常にリスクの高い行動です。
もし踏み倒しを考えるほど厳しい状況にあるなら、日本学生支援機構に相談し、返還猶予制度や減額返還制度を利用することが賢明です。
これらの制度を活用しながら生活を立て直し、将来の返済再開に向けて準備を整えることが重要です。
もし制度の利用ができない、または制度を使っても借金問題が解決しない場合には、債務整理を検討することをお勧めします。
個人再生や自己破産は借金の減額効果が高い一方で、連帯保証人や保証人に請求が及ぶなどのデメリットも存在します。
もし任意整理で解決できる可能性があるなら、それを選ぶのも一つの方法です。