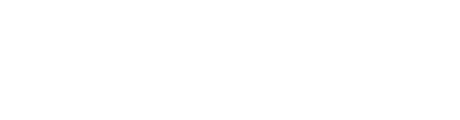※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
クレジットカード滞納でブラックリスト入り? 3カ月の支払い遅れや支払えない場合の対処法を解説!
目次
クレジットカードの支払い遅延は、信用情報に深刻な影響を与える可能性があります。
たとえ1回の支払い遅れでも、ブラックリストに載るリスクが高まります。
3ヶ月以上の滞納が続くと、未払い状態が長期化し、強制執行を受ける可能性が出てきます。
この記事では、クレジットカード滞納のリスクや対処法について詳しく解説していますので、お困りの方はぜひ参考にしてみてください。
クレジットカード滞納とは? 最初に知っておくべき基礎知識
クレジットカードの滞納とは、支払期日までに請求金額を支払わず、未払いの状態が続くことを指します。滞納の期間ごとに、どのようなリスクが発生するのかを詳しく見ていきましょう。
まず、1回でも支払いを延滞すると、どのようなリスクが生じるのかを解説します。
続いて、1ヶ月滞納した場合に影響がどのように現れるのか、そして適切な対応策について説明します。
さらに、2ヶ月以上滞納が続いたときに発生する影響と、それに対する対応策についても詳しく見ていきます。
また、3ヶ月が経過すると、信用情報にどのような影響が本格的に及ぶのかについても確認しましょう。
最後に、滞納が続いた際に起こる利用停止や強制解約の流れについて理解を深めていきます。
1回の支払い延滞で発生するリスクとは?
たった一回の支払い延滞であっても、そのリスクは非常に大きく、決して軽視できません。
例えば、引き落とし口座の残高不足などで支払いが遅れると、金融機関は信用情報を更新し、延滞履歴が記録されます。この履歴は、たとえ数日間の遅延であっても残り、将来的な融資やクレジットカードの利用条件に影響を及ぼす可能性があります。
また、支払いの遅延によって遅延損害金が発生する点にも注意が必要です。遅延損害金は、遅延による損害賠償金のようなもので、クレジットカード会社ごとに利率は異なりますが、一般的には年率14~20%程度に設定されています。そのため、滞納期間が長くなるほど負担額も増えていきます。
例えば、元金50万円を年率20.0%で計算すると、1ヶ月の滞納で約8,200円、3ヶ月では約24,600円の負担となり、差額は1.6万円以上にもなります。このように、一度の延滞が将来的な負担を大きくするリスクを抱えているのです。
さらに、クレジットカードの利用限度額が減少するケースもあり、急な支払いが必要な際に資金調達が難しくなる可能性も考えられます。
こうした問題を防ぐためには、たとえ1回の支払いでも期日を守ることが重要です。小さな遅れが将来的に大きな影響を及ぼす可能性があることを理解し、慎重に対応することが求められます。
1ヶ月の滞納が引き起こす影響と対応策
1ヶ月の滞納が発生した場合、滞納期間が1週間から1ヶ月程度であれば、主にカード会社からの通知や電話連絡が行われる段階にとどまることが一般的です。
この時点では、督促状がメールやハガキで届き、再引き落とし日が設定されるケースもあります。督促状には、延滞している金額と再引き落とし日が記載されており、期日までに入金をすれば滞納状態は解消されます。利用停止となったカードも、短期間で再び使用可能になるでしょう。
しかし、再引き落とし日を過ぎても支払いが行われなかった場合、カード会社から電話による督促が行われるのが一般的です。この際、電話で支払いの意思を明確に示し、指定された期日までの支払い計画を伝えることで、カード会社が柔軟に対応してくれる可能性があります。
また、払込用紙が送付された場合は、速やかに支払いを完了させることで、さらなる督促を回避できるでしょう。支払いの遅れに対して迅速に対応すれば、この段階で信用情報に深刻な影響が及ぶことは少なく、ブラックリストに載るリスクもほとんどありません。
ただし、滞納期間が1ヶ月を超えると状況はさらに悪化する恐れがあります。この段階では、信用情報に滞納としての記録が残り、将来的な借り入れやクレジットカードの利用が制限されるリスクが高まります。
こうした事態を避けるためには、早い段階でカード会社に連絡し、自身の状況を説明することが重要です。延滞によるペナルティや利息について詳細を確認し、無理のない支払い計画を立てることで、問題の解決につなげることができます。
また、滞納が長引く場合は、必要に応じて短期ローンの利用など、追加の資金調達手段を検討することも選択肢の一つです。
最も望ましいのは、滞納が発生する前にしっかりと支払い計画を立てることですが、やむを得ず滞納してしまった場合でも、迅速かつ前向きな対応をすることで、将来的なダメージを最小限に抑えることができます。
2ヶ月以上の滞納が引き起こす影響と対応策
2ヶ月以上の支払い遅れは、非常に深刻な影響を及ぼします。
滞納が続いて2ヶ月目を迎えると、クレジットカード会社の規約に基づき、カードが強制解約される可能性があります。一度強制解約されると、支払いを完了したとしても、同じカードを再び利用することは基本的に難しくなります。
さらに、信用情報には金融事故として登録されるため、いわゆるブラックリスト入りの状態となり、新しいクレジットカードの作成やローン審査が非常に厳しくなるリスクが高まります。
こうした状況を避けるためには、支払い督促の段階で速やかに対応することが重要です。例えば、カード会社からの通知をしっかり確認し、現在の経済状況を正直に伝えたうえで、支払い計画の見直しや相談を行うことで、事態の悪化を防ぐことができるかもしれません。
滞納が2ヶ月を超える前に適切な対応を取ることが、将来の経済的な自由を守るうえでも大切です。
3カ月経過で信用情報への影響が本格化
支払いの滞納が3ヶ月を超えると、信用情報機関に「事故記録」として登録されることがあり、今後の金融取引に大きな影響を及ぼす可能性があります。
信用情報には、クレジットカードやローン契約の履歴、借り入れや返済状況などが記録されており、これらの情報は主に株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録されます。
一度「事故記録」が登録されると、最長で5年間は信用情報に履歴が残り、その間、新たなクレジットカードの発行が難しくなるだけでなく、カードローン、自動車ローン、住宅ローン、さらには携帯電話端末の分割払いなどの利用が大幅に制限される可能性が高まります。
特に、カード会社や銀行は携帯料金の滞納を重く受け止める傾向があり、このような状況は利用者の信用力に直接影響を与え、信頼度の低下が顕著に反映されることもあります。
また、一部のケースでは法的手続きが進行し、最悪の場合、強制解約や差し押さえに至るリスクも否めません。
こうした事態に陥ると、生活や将来の選択肢に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、3ヶ月以上の滞納を防ぐためにも早めの対応が不可欠です。
特に問題が複雑化している場合は、専門家へ相談することが有効な解決策の一つとなるでしょう。
滞納による利用停止や強制解約の流れを把握する
滞納が続くと、支払いの遅延に基づき、カード会社から利用停止や強制解約といった措置が取られる可能性があります。
通常、一定期間を超えて支払いが遅れると、カード会社は利用停止の通知を行います。この通知を受けると、クレジットカードが使用できなくなるだけでなく、未払い分の返済を強く求められることになります。この段階で迅速に対応しなければ、さらに状況が悪化する恐れがあります。
支払いが行われず、期限の利益を喪失すると、債権者であるカード会社から残額の一括返済を求められる場合があります。期限の利益とは、債務者が返済期限が到来するまで支払義務を猶予される権利ですが、滞納が長期化するとこの権利が無効となり、一括返済を拒否することができなくなります。
このような状況に陥った場合は、必要に応じて家族に相談し返済資金を調達する、もしくは専門家に相談して債務整理を検討することも重要です。
さらに、強制解約が実行されると、その記録が信用情報機関に登録されます。これにより、「ブラックリスト入り」となり、将来的に新たなクレジットカードの発行やローン契約が制限されることが一般的です。
そのため、滞納を防ぐためには、計画的な支出と支払いの管理が欠かせません。支払いの遅延は一見小さな問題に思えるかもしれませんが、最終的には大きな不利益や信用への悪影響をもたらす可能性があるため、早期の対応が非常に重要です。
クレジットカードの遅延は何回まで許される?
クレジットカードの支払いができないとき、多くの人が気にするのは「どの程度の延滞なら影響がないのか?」という点でしょう。
実際のところ、一度の延滞であれば大きな問題にならないケースがほとんどです。ただし、延滞に対する対応はカード会社や過去の取引状況によって異なるため、一概にこうだとは断言できません。目安として、以下のように考えておくとよいでしょう。
延滞1回
影響がないケースが多い
延滞2回
信用情報にブラックリスト入りする可能性がある
延滞3回
強制解約や残高の一括請求が行われるリスクが高まる
1回の遅延なら問題ない場合が多い
クレジットカードの支払い日に、引き落とし口座の残高が不足し、後日再引き落としが行われた経験はありませんか? 残高の確認を忘れるなどの理由で、うっかり支払いを延滞してしまうことは誰にでも起こり得ることです。そのため、1回の延滞が大きな問題になることは少ないでしょう。
信用情報には影響しなくても、延滞をすると遅延損害金が発生するため注意が必要です。遅延損害金とは、延滞に対する賠償金のようなもので、延滞の翌日から1日ごとに加算されていきます。
また、カード会社によっては、一度の延滞でも数週間放置するとブラックリスト入りする可能性があるため、「1回だけだから」と油断せず、できるだけ早く返済することが重要です。
遅延の記録が信用情報に残る可能性がある
契約情報を共有している信用機関は、以下の3つです。金融機関やカード会社は、いずれか、もしくは複数の機関に必ず加入しています。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)……クレジット会社、信販会社
日本信用情報機構(JICC)……消費者金融会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC)……銀行
クレジットカード会社の多くが加入しているCICには、異動情報だけでなく、過去2年分の返済情報も記録されます。数日程度の延滞で異動情報が登録されることはありませんが、「返済が遅れた」という履歴が残る可能性はあります。
これだけでブラックリスト入りすることはありませんが、記録が消えるまでの2年間はクレジットカードの増額申請が通りにくくなる場合があります。
連続2回の延滞でブラックリスト入りのリスクが高まる
2回連続でカードの支払いを延滞すると、信用情報に異動情報が登録されるリスクが高まり、放置すればブラックリスト入りする可能性が高くなります。
信用情報機関における「延滞」の異動情報は、以下のように定義されています。
- KSC … 61日以上または3カ月以上
- CIC … 61日以上または3カ月以上
- JICC … 3カ月以上
KSCとCICでは、61日以上の延滞が「異動情報」として扱われることが明示されています。支払日の翌日を延滞1日目と数えると、2回目の返済日は延滞開始から約30日後となり、61日には達しません。そのため、「2回の延滞ではブラックリストに載らない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、実際に信用情報へ異動情報を登録するのは金融会社であり、何日以上の延滞でブラックリスト入りするかはカード会社ごとに異なるため、一概に断言することはできません。
対応が早いカード会社では、延滞が30日程度、つまり1回目の支払いを延滞し、2回目の期日を迎える頃にブラックリスト入りするケースもあります。それ以外の会社でも、60日程度の延滞、すなわち3回目の返済日前後にはブラックになることが一般的です。
連続3回の延滞は非常に危険
3回連続で延滞をすると、信用情報はほぼ確実にブラックリスト入りしているため、他のクレジットカードやローンの利用ができなくなり、審査にも通らなくなっている可能性が高いでしょう。
カードが利用できなくなるだけでなく、強制解約となるリスクもあります。さらに、残高の一括請求を求められるだけでなく、法的措置が取られる可能性もあるため、非常に危険な状況と言えます。
クレジットカード滞納が信用情報に与える影響とは?
クレジットカードの支払いを滞納すると、信用情報に記録されるため、今後のローンや各種契約に影響を及ぼす可能性があります。そのため、支払い期日を守ることが非常に重要です。
カードの利用は計画的に行い、万が一問題が発生した場合は、できるだけ早く対応することで将来のトラブルを回避することができます。
- 信用情報機関に登録される仕組みとその意味
- 「ブラックリスト」に載るとどのような不利益があるのか
- 住宅ローンや自動車ローンの審査に及ぼす影響
- スマホの分割購入や賃貸契約にも不利になる可能性は?
- 信用情報への影響はいつまで続くのか?「5年」という期間の実態
信用情報機関に登録される仕組みとその重要性
信用情報機関は、個人や企業の信用情報を集約・管理する役割を担う重要な機関です。
ここには、クレジットカードやローンの利用履歴、支払い状況といった情報が登録されており、金融機関はこれをもとに貸付の可否を判断します。特に、支払いの遅延や未払いが発生すると、その情報は即座に記録され、一定期間保持されることになります。
この記録が「いつまで」保持されるかについては、各信用情報機関が定めた基準により異なりますが、一般的には長期間にわたり影響を及ぼす可能性があります。信用情報機関は、貸し手と借り手の間で適切な取引を促進する役割を果たしており、例えば、返済の滞納が発生すると、そのネガティブな情報が信用情報に残り、新たな借り入れやローン申請、クレジットカードの審査で不利になることがあります。
この仕組みにより、借り手には責任ある返済を促す効果が期待されますが、同時にその影響が「いつまで」続くのかを把握しておくことも重要です。一度登録された信用情報は、利用者の金融活動に長く影響を及ぼす可能性があるため、慎重な管理が求められます。
ブラックリストに載るとどんな不利益が生じる?
ブラックリストに載ると、多くのデメリットが生じます。
まず、信用情報に問題があると判断されるため、クレジットカードやローンの申請が通りにくくなり、結果として借入れがほぼ不可能になることもあります。金融機関は信用情報をもとに利用者の信用度を評価するため、ブラックリストに載った利用者は審査基準が厳しくなり、リスクが高いと見なされることが主な理由です。
さらに、すでに保有しているクレジットカードの利用限度額が引き下げられる可能性があり、その結果、急な出費に対応できなくなるリスクが高まります。これにより、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。
また、信用情報に傷がつくことで、賃貸契約やスマホの分割購入契約にも影響が及ぶ可能性があります。新たな契約が難しくなるだけでなく、高い金利や不利な条件が提示されることもあり、経済的な負担が増えることが考えられます。
スマホの分割購入や賃貸契約にも不利になる?
クレジットカードの滞納は、スマートフォンの分割購入や賃貸契約に大きな影響を与える可能性があります。
現在、多くの通信キャリアや不動産会社では、契約者の信用情報を審査し、その結果に基づいて契約の可否を判断しています。そのため、信用情報に滞納の記録があると、契約を拒否されるケースも珍しくありません。
これにより、必要なサービスを利用できなくなり、ライフスタイルに支障をきたすリスクが生じます。例えば、スマートフォンの分割購入を希望しても、事前審査で信用情報がネガティブと判断されると、契約が承認されない可能性があります。
また、賃貸契約においても信用情報が確認されるため、滞納歴があると住宅を借りる際の審査に通らない場合も考えられます。
このように、クレジットカードの利用状況を適切に管理しないと、日常生活に深刻な不便を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
住宅ローンや自動車ローンの審査に与える影響
クレジットカードの滞納は、住宅ローンや自動車ローンの審査に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
金融機関は融資の審査時に信用情報を詳細に確認し、その際に滞納履歴が見つかると、審査基準が厳しくなることが一般的です。特に、高額な借り入れとなる住宅ローンや自動車ローンでは、その影響がより顕著になるでしょう。
滞納履歴があると、ローン審査において金利が高く設定される場合があり、その結果、返済負担が大きくなる懸念があります。また、希望する金額で融資を受けられない可能性もあるため、事前に計画的な支出管理と返済計画を立てることが重要です。
さらに、信用情報に傷がつくことで、他のローン審査にも影響を与えることが考えられるため、日頃から信用情報を良好な状態に保つ努力が求められます。
信用情報はどのくらいの期間影響を受ける?「5年」の実際
信用情報への影響は、通常「5年」間続くとされています。
この期間中に新たな信用取引を行う際、過去の滞納や支払い遅延の記録が残っていると、審査が厳しくなる可能性が高くなります。信用情報機関には一定の保存期間が設けられており、一般的な目安として「5年」が基準とされています。
しかし、登録された情報が削除されたからといって、信用評価がすべての金融機関やサービスで一律に回復するわけではありません。それぞれの審査基準によって判断されるため、影響がどの程度続くかは一概には言えません。
そのため、過去の信用情報を振り返り、今後の行動を見直すことが非常に重要です。例えば、計画的な支出管理や支払い期限の厳守を徹底することで、信用評価を向上させることができます。
日々の積み重ねが、信頼される信用情報へとつながり、将来的な金融活動や契約において有利に働くでしょう。「5年」という区切りを意識しつつ、今できる行動を積極的に取り入れることが求められます。
滞納が続くとどうなる?3ヶ月以上の未払いで起こる影響
クレジットカードの滞納が3ヶ月を超えると、さまざまな深刻な影響が生じる可能性があります。
この段階になると、金融機関からの催促の連絡が頻繁になり、法的手続きへ移行するリスクが高まります。さらに、滞納が長期化すると、最終的には給与差押えなどの強制執行が実施される可能性も考えられます。
- 裁判所から支払督促や訴状が届くリスク
- 給与差押えなど強制執行が行われる可能性とは
- 差押えを回避するための緊急対策
カードの利用が停止される
クレジットカードの支払いが遅れると、早ければ翌日から利用が停止される可能性があります。同じクレジットカード会社で複数枚のカードを持っている場合や、家族カードを発行している場合、それらすべてが利用停止の対象となることがあります。
特に、2カ月分以上の支払いを延滞している場合は、未払い分をすべて完済しない限り、カードは再開されません。
また、延滞の日数が長かったり、過去に何度も延滞を繰り返していた場合は、滞納分を支払ってもすぐにカードが使えるようにならず、一定期間利用が制限されることもあります。
カードが強制解約される
クレジットカードの支払いを延滞すると、カード会社によって強制的に解約される、いわゆる「強制解約」になる可能性があります。
強制解約については、どのカード会社の会員規約にも「会員資格の喪失」といった文言で明示されており、その理由の一つとして延滞が含まれています。
第39条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)においては当社が会員資格の喪失を通知したときに、会員資格を喪失します。
(中略)
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
引用元:JCB会員規約
規約上は、一度の延滞でも強制解約が可能となっていますが、実際に解約へ至る基準はカード会社ごとに異なり、具体的な回数は明言できません。
一般的には、2回~3回の延滞で強制解約となるケースが多いですが、過去に何度も延滞を繰り返している場合や、他社のカードでも滞納がある場合は、1回の延滞でも解約される可能性があります。
強制解約になると、家族カードやETCカードなどの付帯カードも同時に解約されます。当然ながら、これまでの支払い義務が免除されるわけではなく、解約後も残額の支払いは継続して求められます。
信用情報がブラックリスト入りする
前述の通り、2回目の延滞から信用情報がブラックになるリスクが高まり、延滞が3カ月に達する頃には、ほぼ確実にブラックリスト入りしている状態となります。
信用情報がブラックになると、新たなローンを組めなくなるだけでなく、他社のクレジットカードが利用停止や強制解約になる可能性もあります。
カード会社は、定期的に利用可能額の見直しを行う途上与信を実施しており、その際には必ず信用情報を確認します。この過程で、信用情報がブラックになっていると判断されると、自社カードの支払いも滞る可能性があるとみなされ、強制解約の措置が取られることがあります。
第39条 退会および会員資格の喪失等
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等、会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
引用元:JCB会員規約
「他のカードが使えるから大丈夫」と安易に考えて支払いを先延ばしにすると、最終的にはすべてのカードが利用できなくなる恐れがあります。返済が滞ることで取り返しがつかない状況にならないよう、十分に注意してください。
残高の一括請求を受ける状況
延滞が2カ月を超えると、本来は分割払いで支払うはずの残高について、一括返済を求められる可能性があります。
私たちが大きな買い物をした際やローンを組んだ際に、分割で支払う権利のことを期限の利益と呼びます。しかし、長期延滞などが原因でこの期限の利益を失うと、残高を一括で支払わなければならなくなります。これを期限の利益の喪失といい、カード会社の規約にも必ず記載されている項目です。
第38条(期限の利益の喪失)
- 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)については相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)については何らの通知・催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)については当社の請求により、当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
引用元:JCB会員規約
期限の利益を喪失すると、カード会社から「期限の利益の喪失通知および催告書」などの名目で郵送による通知が届きます。通知の形式は、「督促状」や「訴訟予告通知」など会社によって異なりますが、いずれも内容は共通しています。
文書には、必ず以下の2点が記載されています。
- 残高の一括返済を求める内容
- 期日までに支払いがない場合、法的手段を取る旨
この通知を無視すると、さらに厳しい措置が取られる可能性があるため、早急な対応が必要です。
カード会社から一括請求された際の対応方法
一括での支払いが難しい場合、カード会社に連絡すれば分割払いに応じてもらえる可能性があります。しかし、必ずしも交渉が成立するとは限りません。
大手のカード会社では、そもそも個人からの交渉を受け付けておらず、弁護士や認定司法書士などの専門家を通じて交渉するよう求められるケースがほとんどです。
また、仮に分割払いが認められたとしても、多くの場合は数回~12回(1年)程度の分割に限られます。さらに、滞納している期間中は利息に加えて遅延損害金も発生し続けるため、その点も考慮しなければなりません。
個人での交渉では、減額に応じてもらうことは難しく、請求された金額を全額支払う必要があることを理解しておく必要があります。
そのため、カード会社から一括請求を受けた場合は、弁護士や認定司法書士に相談し、減額や分割払いの交渉を依頼することをおすすめします。
裁判所から支払督促や訴状が届くリスク
未払いが3ヶ月を超えると、金融機関は債権回収を強化し、裁判所から支払督促が発行される可能性があります。
支払督促が届くと、法的手続きが正式に開始されるため、無視することはできません。適切な対応を取らずに放置すると、訴訟に発展するリスクが高まり、より厳しい措置が取られる可能性があります。
この段階で何の行動も起こさなければ、相手方が法的に有利な立場を確保する一方で、自身の立場はますます不利になってしまいます。例えば、支払いを怠り督促に応じなかった場合、最終的に裁判所から訴状が送付されるだけでなく、裁判の結果によっては強制執行へと進むリスクも生じます。
強制執行が行われると、財産や給与の差し押さえが実施される可能性があり、このようなケースは決して珍しくありません。さらに、法的手続きが進むことで、弁護士費用や裁判費用といった追加の経済的負担が発生し、財務状況が一層厳しくなることも考えられます。
加えて、支払督促や訴訟を無視し続けると、問題が複雑化し、最終的にはより大きな負担を抱える結果となります。支払督促には明確な期限が設けられている場合が多く、その期限を過ぎると強制執行手続きへと移行するリスクが高まるため、十分な注意が必要です。
このようなリスクを避け、問題を早期に解決するためには、できるだけ早く状況を整理し、具体的な支払い計画を立てた上で、迅速に行動を起こすことが重要です。
裁判所から特別送達が届いた場合の対応方法
裁判所から特別送達が届くと、誰でも戸惑うものです。しかし、適切に対処しなければ、強制執行へと進む可能性があるため、内容をしっかり確認し、適切な対応を取ることが重要です。
カード会社が実施する法的措置には、支払督促と訴訟の2種類があります。
訴状を受け取った場合の対応方法
訴状には、裁判所で行われる口頭弁論の日時が記載されており、併せて訴訟内容に対する認否を確認する答弁書が同封されています。
この答弁書を提出せず、口頭弁論を欠席すると、自動的に敗訴となり、財産の差し押さえが実行される可能性があるため、まずは期日までに答弁書を提出することが最優先となります。
訴訟を起こされた際の対応については、認定司法書士や弁護士に依頼することが可能です。特に弁護士であれば代理権を持っているため、裁判所への出廷を代行してもらうこともできます。
支払督促を受け取った場合の対応方法
支払督促とは、裁判所が行う督促のことで、訴訟に比べて手続きが簡単で手数料も低いため、延滞や未払いに対する法的措置として、多くの金融機関が利用しています。
支払督促が届いた場合、以下のいずれかの対応を取る必要があります。
- 2週間以内に一括で支払う
- 同封されている異議申立書を記入し、異議申し立てを行う
一括での支払いが難しい場合は、異議申立書を提出し、分割払いや減額の交渉を行うことになります。しかし、異議申し立てを行うと、自動的に訴訟手続きへと移行するため注意が必要です。
裁判に進んだ場合、答弁書の作成や、平日に裁判所へ出廷する手間が発生します。そのため、どうしても裁判を避けたい場合は、カード会社と交渉し、分割払いや減額の対応を求めることが選択肢の一つとなります。
ただし、前述の通り、多くのカード会社では個人からの交渉を受け付けていないため、確実に交渉を進めるには専門家へ相談することをおすすめします。
給与差押えなどの強制執行がもたらすリスク
支払督促や訴状による法的手続きが進むと、給与差押えといった強制執行のリスクが生じます。
この手続きが実行されると、給与の一定割合が自動的に差し引かれ、直接債権者へ支払われることになります。 特に、訴訟が進展し、適切な対応を取らないままでいると、これらの手続きが迅速に進行する可能性が高くなります。
生活の基盤に直結する給与の差押えは、大きな負担をもたらします。例えば、給与の一部が差し押さえられると、手元に残る金額が少なくなり、生活費が圧迫される事態は避けられません。
強制執行の厳しさは、滞納額や延滞期間によって決定されることが一般的であり、3ヶ月以上の滞納がある場合には、特に厳しい措置が取られる可能性が高まります。そのため、想定以上の経済的負担を強いられるケースも少なくありません。
このような事態を避けるためには、早めの対応が重要です。特に、給与の差押えが実行される前に、債権者と交渉を行ったり、専門家に相談することが効果的な手段となります。
早期の対応を行うことで、訴訟や強制執行のリスクを軽減し、正当な理由による引き落としの停止を防ぐことが可能となります。
突然の給与差押えによる生活の混乱を防ぐためにも、支払いの延滞が3ヶ月以上続く前の段階で適切な解決策を見つける努力が求められます。
差押えを避けるための即時対応策
給与差押えを避けるためには、早期の対応が不可欠です。
まず最初に行うべきことは、クレジットカード会社へ連絡し、延滞状況を説明することです。相手方に事情を理解してもらうことで、柔軟な対応を受けられる可能性があります。 例えば、返済計画の見直しや分割払いの提案を受けられるケースも考えられます。
また、クレジットカード会社との交渉を通じて、信用情報への影響を最小限に抑える努力をすることも重要です。 信用情報に傷がつくと、将来的に金融機関からの借り入れや契約が困難になる可能性が高まるため、できるだけ早めに対処する必要があります。
さらに、債務整理や借金の見直しを検討することも有効な手段の一つです。状況によっては、専門家の助言を受けながら、法的手続きや訴訟リスクへの対応を検討する必要があるかもしれません。
法律的な助言を求めることで、自分に適した解決策を見つけ、差押えを回避するための具体的な行動を取ることが可能になります。特に、信頼できる弁護士や司法書士に相談することで、不明点を解消し、迅速な対応ができるようになるでしょう。
一方で、状況が悪化し訴訟に発展する前に、できるだけ早く行動を起こすことが不可欠です。 迅速かつ効果的な対策を講じることで、給与差押えを回避するだけでなく、経済的な安定を取り戻す道を開くことができます。
このような緊急時には、対応の遅れがさらなる負担を招くリスクがあるため、問題を正しく把握し、積極的に解決策を模索することが大切です。
支払いができない場合の具体的な対応方法
クレジットカードの支払いができなくなると、多くの人にとって精神的な負担や現実的な不都合が生じます。
しかし、状況に応じた適切な対応を取ることで、支払い不能によるリスクを回避できる可能性があります。そのため、まずは冷静に状況を把握し、適切な対策を講じることが重要です。
支払いが難しい場合の対応策
- カード会社への連絡と分割払いの交渉
- 債務整理による返済負担の軽減
- 任意整理:返済計画を見直し、利息のカットや返済期間の調整を行う方法
- 個人再生:借金を大幅に減額できる制度
- 自己破産:法的手続きにより借金を免除してもらう方法
- 公的融資や生命保険契約者貸付制度の活用
このように、支払いが困難な状況でも適切な手順を踏むことで、負担を軽減し、今後の生活を立て直すことが可能になります。
カード会社への連絡と分割払いの交渉方法
支払い不能の状態に陥った場合、最初に取るべき重要なステップは、カード会社への迅速な連絡です。
早めに事情を説明し、どの程度の期間支払えないのか、また支払い可能な時期を明確に伝えることで、柔軟な対応を受けられる可能性が高まります。 これにより、未払いによる不利益を最小限に抑えることにもつながります。支払いの問題を放置せず、早期に対応することが状況の悪化を防ぐ鍵となります。
次のステップとして、分割払いの交渉を行うことが重要です。 多くのカード会社には、返済困難な利用者が相談できる専用窓口が設けられています。
この窓口では、支払い回数の延長や月々の支払い額の減額など、返済条件の再構築について相談することが可能です。こうした交渉を通じて、経済的な負担を軽減し、現実的な支払い計画を立てる道を開くことができるかもしれません。
支払いについて真摯に向き合い、適切な方法で解決を図ることが、健全な経済生活を取り戻すために非常に重要です。
リボ払いや他社借入を避けるべき理由
クレジットカードの返済が難しい場合、リボ払いに変更することで支払い期日を延ばすことが可能です。 また、ネット上では消費者金融から借入をして返済する方法を勧める意見もあります。 確かに、こうした手段を取れば一時的にクレジットカードの延滞を解消することはできます。
しかし、これは根本的な解決にはなりません。 リボ払いや消費者金融は利息が決して安いとは言えず、借金をさらに増やすリスクが高いため、避けるようにしてください。
リボ払いが危険とされる理由
リボ払いは危険だとよく言われますが、その理由を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
リボ払いの特徴は、残高に対する返済金額が非常に低く設定されている点にあります。そのうえ、返済中も残高に対して年15.0%~18.0%の手数料(利息)が加算され続けるため、なかなか完済できない仕組みになっています。
早期に返済を終えるためには、前倒しで支払う必要があります。 しかし、多くのカード会社では、繰り上げ返済の申請から実際の引き落としまでに日数がかかるため、返済金額の管理が難しくなるというデメリットもあります。
他社借入で返済する際のリスク
他社からお金を借りて返済をすれば、一時的に延滞を回避することは可能です。 しかし、新たに借り入れた分には利息が上乗せされるため、結果的に借金が増えてしまいます。
例えば、100万円を借りて15.0%の利息が発生する場合、
100万円+利息15.0%(15万円)=115万円
となり、借金が自動的に15万円増加することになります。
さらに、この金額をまた別の借金で返済することになると、利息分が元金として積み重なり、借金が雪だるま式に増えていく危険性があります。
また、クレジットカードの支払いを終えると利用可能額に余裕ができるため、無意識のうちに借金が減ったような錯覚を持ち、再びカードを使いすぎてしまう人も少なくありません。
他社からの借入で一時的に切り抜けようとするのではなく、借金そのものを減らす努力をすることが重要です。
【絶対に避けるべき】クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化は、緊急時に現金を手に入れる手段として魅力的に思えるかもしれませんが、決して行ってはいけません。
クレジットカードの現金化は法的にアウトであり、少なくともクレジットカード会社の規約違反に該当するため、発覚すれば利用停止や強制解約のリスクがあります。
また、高利率の分割払いやリボ払いが必要になることが多く、結果として高額な返済負担につながる可能性が高いです。
さらに、悪質な現金化業者による詐欺のリスクも存在し、消費者が不利益を被る事例が多数報告されています。場合によっては、意図せず犯罪に関与してしまうリスクもあるため、特に注意が必要です。
また、クレジットカードの現金化を利用すると、自己破産が認められないといった重大な問題に直面する可能性があります。これは、現金化の行為が免責不許可事由に該当する恐れがあるためです。
さらに、信用情報にも悪影響を及ぼし、将来的な金融審査で不利になる可能性も高くなります。
このように、クレジットカードの現金化は短期的には便利に見えるかもしれませんが、長期的には生活の基盤を脅かす非常に危険な行為です。絶対に避けるようにしてください。
債務整理を活用して返済負担を軽減する方法
支払いが困難な状況に陥った場合、債務整理を検討することは、有効な解決策の一つです。
債務整理とは、法律に基づいて借金を整理する手続きであり、これにより返済負担を軽減し、経済的な負担から抜け出す助けとなります。
特に、クレジットカード(クレカ)の利用による借金問題を抱えている場合は、適切な債務整理を行うことで、状況の改善が可能です。
具体的な方法として、任意整理・個人再生・自己破産の3つが挙げられます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、専門家へ相談し、自身の状況に最適な方法を見極めることが重要です。
債務整理の選択肢を知ることで、クレカを含む借金問題を効果的に解決し、安定した経済生活を取り戻すための第一歩を踏み出すことができます。
任意整理による返済計画の見直し方法
任意整理は債務整理の一種であり、個人が債権者と直接交渉し、返済計画を見直す手続きです。
この方法は法的手続きを介さずに行えるため、比較的手軽に実施できるというメリットがあります。 債権者に事情を説明することで、月々の返済額を減額したり、支払い条件を変更することが可能となります。
任意整理を活用すれば、クレジットカードの負債を軽減し、経済的な余裕を確保しやすくなるでしょう。 ただし、任意整理を申し出た時点で、一部のクレジットカードやローンが利用停止となる可能性があるため、その影響を理解した上で対応することが重要です。
また、任意整理では債権者との関係が鍵となり、信頼関係を構築することが求められます。 しかし、すべての債権者が交渉に応じるとは限らないため、そのリスクを事前に考慮する必要があります。
計画的な対応を心掛けることで、債務整理に取り組みやすくなるでしょう。
個人再生による借金の大幅減額制度
個人再生は、深刻な借金問題を抱えた方にとって、有力な債務整理の方法の一つです。
この制度を利用すると、一定の条件を満たせば借金を大幅に減額でき、原則として住宅を保持したまま返済を続けることが可能です。 そのため、特にマイホームを手放したくない方にとっては魅力的な選択肢となります。
個人再生の手続きは裁判所を通じて行われますが、専門家のサポートを受けることで、申立てから認可までをスムーズに進められる可能性が高くなります。
また、この制度では借金の返済期間は原則3年とされていますが、事情に応じて5年に延長することも可能です。 これにより、無理のない範囲で毎月の返済計画を立てることができます。
個人再生を成功させることで、生活の安定を取り戻し、将来的な返済負担の軽減が期待できます。 この債務整理の方法を選ぶことで、経済的再生への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
自己破産による借金の法的免除手続き
自己破産は、債務整理の一つであり、法的に借金を免除してもらうことが可能な制度です。
経済的に困窮し、これ以上の返済が難しい状況にある方にとって、有力な選択肢の一つといえるでしょう。 自己破産を申し立てることで、負担となっている債務から法的に解放されることが期待されます。
しかし、手続きが完了すると信用情報に約5年から10年間影響を及ぼすため、新たな借り入れが難しくなるという点に注意が必要です。そのため、具体的な影響期間や条件を事前に理解しておくことが重要です。
特に、支払いの滞納が3ヶ月以上続いている場合には、自己破産を含めた債務整理の検討を早期に進めることが推奨されます。
この手続きは裁判所を通じて行われるため、法律的な知識や対応が求められます。 そのため、弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けることで、適切かつスムーズに進めることが可能です。
さらに、自己破産を選択する際には、保有している資産の一部またはすべてを処分しなければならない場合があるため、慎重な判断が必要です。
自己破産は最終手段ともいえる債務整理の方法ですが、他の選択肢と比較しながら、自身にとって最適な解決策を見つけることが重要です。
公的融資や生命保険契約者貸付制度の活用方法
支払いが困難になった場合、利用可能な制度として、公的融資や生命保険契約者貸付制度を検討することが考えられます。
公的融資は、地方自治体や国が提供する支援制度であり、必要な手続きを経ることで低金利で資金を借りることが可能です。この制度は、主に生活費の補填や事業資金の確保を目的として活用されることが多く、経済的な負担を軽減する効果が期待できます。
一方、生命保険契約者貸付制度は、保険契約の解約返戻金を担保に融資を受ける方法であり、急な資金が必要な場合に有効な選択肢となります。この制度は、限度額や返済条件が比較的柔軟に設定されるケースが多く、スムーズな支払いを実現しやすいため、経済的な安心感をもたらします。
ただし、これらの制度を利用する際には、信用情報に注意を払うことが重要です。返済が滞ると信用情報に傷がつき、将来的な融資や各種契約に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。
そのため、無理のない返済計画を立て、自身の経済状況に応じた適切な形で制度を活用することが大切です。経済的な困難に直面した場合でも、これらの制度をうまく活用しながら、支払いや資金計画を見直すことで、安定した生活基盤を築くことが可能となります。
クレジットカードの支払い遅延を防ぐための対策方法
クレジットカードの支払い遅延を防ぐためには、計画的な支出管理が欠かせません。
支出を管理する習慣を身につけることで、支払いに対する不安を軽減し、より安定した生活を目指すことができます。
ここでは、クレジットカードの支払い遅延を防ぐために実践できる方法について考えてみましょう。
- 計画的な支出管理の重要性
- 支払いに遅れる前に相談するメリット
- 2回以上の滞納を繰り返さないためのポイント
支払い遅延前に相談する
支払いの滞納が2回以上続くと、信用情報に悪影響を及ぼす可能性が大幅に高まります。
信用情報は、ローンの申し込みやクレジットカードの審査などに影響を与えるため、適切な管理が重要です。そのため、滞納を防ぐための対策を講じておく必要があります。
まず、クレジットカードの利用状況を定期的に確認し、現在の利用額を把握することが基本となります。特に、利用限度額を超える支出を避けることで、無理な借金や支払い不能のリスクを軽減できます。
さらに、支払日を忘れない仕組みを作ることも効果的です。例えば、スマートフォンのカレンダーやリマインダーアプリを活用し、支払日の数日前に通知が届くよう設定すれば、支払い忘れを防ぐことができます。
このような日常的な管理を徹底することで、支払い滞納を減らし、信用情報への悪影響を回避することが可能です。
これらの取り組みを継続することで、長期的に良好な信用情報を維持し、安心して金融サービスを利用できる環境を整えることができるでしょう。
計画的な支出管理が重要
万が一、支払いが難しくなりそうな場合は、事前にカード会社へ相談することが重要です。
多くのカード会社では、支払いが困難な状況に対して一定の理解を示し、支払い条件の変更や分割払いの相談に応じてくれることがあります。こうした対応を取ることで、支払いの滞納によるデメリットを最小限に抑えることが可能です。
特に、早めに連絡をすることで、支払いの遅延が記録される前に適切な対策を講じることができ、信用情報への悪影響を回避しやすくなります。 また、カード会社との信頼関係が築かれることで、今後のやり取りもスムーズになる可能性が高まります。
一方で、事前に相談せずに遅延が発生すると、信用スコアの低下や将来的なローン申請への影響など、さまざまなデメリットが生じることになりかねません。
そのため、支払い遅延の前にカード会社へ相談することは、より良い結果を得るための賢明な選択といえるでしょう。
計画的な支出管理を心がけ、不測の事態が発生した際には、迅速に行動することが大切です。
2回以上の滞納を避けるためのポイント
クレジットカードの支払いを2回以上滞納しないためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
まず、緊急時や急な出費に備えて、あらかじめ予算を見直し、必要な資金を確保しておくことが重要です。 生活費や固定費に加え、クレジットカードの支払い分も考慮することで、支払いが滞るリスクを軽減できます。
次に、支払い期日を忘れないようリマインダーを設定することで、支払い忘れのリスクを減らすことができます。 スマートフォンのカレンダー機能やリマインダーアプリを活用すれば、支払日を視覚的に確認でき、通知を受け取ることも可能です。
また、万が一支払いが遅れてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡を入れることが重要です。支払いが難しい状況を説明し、分割払いの交渉を行うことで、滞納期間を最小限に抑えられる可能性があります。 早めの対応が、2回、3回と滞納が続くことを防ぐ助けとなるでしょう。
さらに、収入減や出費の増加を想定し、あらかじめ対策を講じておくことも大切です。 例えば、昇給や副収入の確保を考えたり、不必要な支出を削減することで、支払いに回せる資金を増やすことができます。
これらの対策を実践することで、2回以上の滞納を防ぎ、信用情報の悪化を回避することができます。 計画的な生活習慣を身につけることで、安心してクレジットカードを利用できる環境を整えていきましょう。
時効によって滞納分が消える可能性はあるのか?
クレジットカードの滞納に関する時効は、法律上5年と定められており、この期間を経過すると、債権者は延滞分の請求を法的に行う権利を失います。
しかし、時効が成立するためには、特定の条件を満たす必要があるため、注意が必要です。 ここでは、それぞれの条件や時効が適用される期間について解説します。
- クレジットカード滞納の時効成立期間は5年
- 時効更新を防ぐための注意点と対策
クレジットカード滞納の時効が成立する期間は5年
クレジットカードの滞納が法的に消滅するまでの期間は、一般的に「5年」とされています。
この5年間は、債権者が法律上、支払いを請求する権利を持っている期間であり、その間は慎重な対応が求められます。
しかし、時効が成立するためには、単に5年が経過するだけでは不十分です。 たとえば、債権者が法的手続きを開始し、請求行為を行った場合、時効期間が「リセット」されるため注意が必要です。
さらに、時効を成立させるには、5年間にわたり債権者からの支払い請求を受けずに経過することが条件となります。
もし、滞納期間中に支払いが困難な状況が続く場合や、対応に悩む場合は、早めに弁護士や専門家に相談することをおすすめします。 専門的なサポートを受けることで、適切な対応策を見つけ、リスクを軽減することが可能となるでしょう。
滞納問題を放置せず、適切な行動を取ることで、将来的なトラブルを回避することができます。
時効の更新を防ぐための注意点と対策
滞納による時効の更新を防ぐためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
まず、債権者からの連絡には迅速かつ慎重に対応することが重要です。 無視をすると、時効が延長されるだけでなく、支払い義務が継続する可能性があり、大きなデメリットとなる場合があります。
特に、支払いの確認や督促状が届いた際には、軽視せず真剣に対処することが大切です。
また、一度でも支払いを行うと時効がリセットされ、再び5年の期間がカウントされることを理解しておく必要があります。この点は、一見すると解決策のように思えるものの、長期的には新たな負担を抱えるリスクを伴う可能性があります。
こうした状況を避けるためには、自身の経済状況を日頃から把握し、早めに対策を講じることが不可欠です。
適切な情報を収集し、それに基づいて対応することで、不必要なトラブルを未然に防ぎ、健全な生活を取り戻すことができるでしょう。
困ったときには専門家に相談しよう!
クレジットカードの滞納や借金問題に直面した際は、専門家への相談が非常に重要です。
債務整理や信用情報に詳しい弁護士や専門家に頼ることで、問題解決への道をスムーズに見つけることができます。
- 滞納や債務整理に詳しい弁護士や専門家に相談する
- 無料相談窓口を活用し、安心して解決を目指す
無料相談窓口を活用して安心して解決を目指す
債務問題に直面した際、無料相談窓口を活用することは、非常に効果的な解決手段の一つです。
多くの法律事務所やNPOが提供する無料相談を利用すれば、初期のステップを気軽に進めることができます。 相談時には、現在の金融状況や希望する解決方法に加え、信用情報の内容についても詳しく伝えることが重要です。
信用情報は、債務整理の過程や適切な解決策を見極める上で、重要な判断材料となります。 無料相談窓口では、専門家が直接アドバイスを提供してくれるため、疑問点や不安に対して具体的な回答を得ることが可能です。
また、無料で情報を収集できるため、経済的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。 特に、債務問題が複雑化し、訴訟リスクが高まる前にこうした窓口を利用することで、的確な対策を講じることができます。
このような窓口を活用することで、問題が深刻化する前に適切なアドバイスを受け、円滑に解決策を模索する第一歩を踏み出すことができるでしょう。
滞納や債務整理に精通した弁護士や専門家に相談する
クレジットカードの滞納による問題を解決するには、信用情報や債務整理に詳しい弁護士や専門家に相談することが非常に有効です。
滞納が続くと、信用情報に悪影響を及ぼし、将来的なクレジットカードの利用制限やローン審査の否決といった重大な問題につながる可能性があります。 そのため、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。
法律的なアドバイスを専門とする弁護士は、個別の状況を詳細に分析し、最適な手続きや解決策を案内してくれるため、非常に心強い存在です。 特に債務整理に関しては、任意整理・個人再生・自己破産などの手続きを含め、それぞれのメリットやデメリットを丁寧に説明し、最適な選択ができるようサポートしてくれます。
こうした専門家の支援を受けることで、精神的な負担を軽減しながら、信用情報の悪化を最小限に抑え、問題解決へと進めることが可能になります。
さらに、専門家の助けを借りることで、必要な手続きをスムーズに進められ、生活の立て直しにかかる時間を短縮できる可能性もあります。
安心して法的な課題に取り組むためにも、信用情報や債務整理に詳しい専門家を頼ることが欠かせません。
3カ月分の延滞解消後の注意点
3カ月連続で延滞していた場合、延滞したクレジットカードは強制解約されているか、利用可能額が0円になっているケースがほとんどです。
クレジットカードが使えないと不便なため、新しいカードの発行を検討する方も多いでしょう。しかし、長期間の延滞歴がある場合、新たにカードを申し込む際にはいくつか注意すべき点があります。
まず、自分の信用情報がブラックになっているかを確認することが重要です。 そのうえで、申し込むカード会社は、延滞をした会社とは無関係のものを選ぶようにしましょう。
また、無闇に複数のカード会社へ申し込むと、それ自体が審査落ちの原因となる可能性があります。 もし審査に落ちた場合は、一定期間を空けてから再度申し込むことをおすすめします。
延滞した会社以外の金融機関を利用する
信用情報がブラックになっていなくても、延滞したカード会社の顧客情報には「長期延滞をした」という記録が残ります。 そのため、再び契約を申し込んでも断られる可能性が高くなります。 これは、いわゆる社内ブラックと呼ばれる状態です。
社内ブラックは、信用情報のブラックとは異なり、年月の経過で自動的に消えるものではなく、半永久的に記録が残る可能性があります。 また、この情報はグループ会社間で共有されるため、別のカードを申し込んでも、同じグループや系列の会社であれば審査には通りません。
新しくクレジットカードを作りたい場合は、延滞したカード会社とは一切関係のない別の会社に申し込むことが必要です。
信用情報を確認する方法
1カ月~2カ月以上延滞した場合、信用情報がブラックになっている、つまり異動情報が登録されている可能性が高くなります。 しかし、ブラックリスト入りしても、本人には一切通知されません。
異動情報が登録されていると、いくら申し込んでもカードやローンの審査には通りません。 さらに、審査に落ちた場合でも、その理由を教えてもらうことはできません。
そのため、まずは自分の信用情報がブラックになっていないかを確認することが重要です。 信用情報は、各信用情報機関で照会することが可能です。
審査に落ちた場合は期間を空けて再申請する
カードを早く作りたいあまり、短期間に何度も申し込む人がいますが、申込回数が多いこと自体が原因で審査に落ちることがあります。 これは、いわゆる申込ブラックと呼ばれる状態です。
クレジットカードやローンの申し込みをすると、カード会社は申込者の信用情報を確認します。 その際、審査結果に関わらず「申し込んだ」という照会記録が信用情報に残ります。
照会記録が残る期間は以下の通りです。
- KSC:照会から1年を超えない期間
- CIC:照会日より6カ月間
- JICC:照会日より6カ月以内
短期間に何度も借入を申し込んだ履歴があると、金融機関は警戒し、「相当お金に困っているのではないか」「カードの不正利用目的ではないか」と疑われ、審査に通りにくくなります。
目安として、1カ月に3回以上申し込むと申込ブラックになる可能性が高まります。 さらに、信用情報に記録された照会履歴は6カ月~1年間消えないため、申込ブラックになった場合は情報が消えるまで待つ必要があります。
カード発行の時期を無駄に先延ばしにしないためにも、やみくもな申し込みは避けるようにしましょう。
まとめ
クレジットカードの延滞は、1回であれば大きな問題にならないことがほとんどですが、延滞が2カ月に達すると信用情報がブラックになる可能性が高まり、カードの強制解約や残高の一括請求といった影響が出始めます。
3カ月連続で延滞すると、残高の一括請求を受けても不思議ではない状況になり、法的措置へと移行する可能性も極めて高くなります。 法的措置が取られた場合、裁判所から特別送達が届き、それを無視すると財産の差し押さえに発展する恐れがあります。
3カ月連続で延滞しそうな場合は、まずカード会社に連絡し、返済の意思を伝えることが重要です。 もし返済が難しい状況であれば、債務整理を検討することを強くおすすめします。
債務整理を行うことで、積み重なった利息や遅延損害金をカットし、支払い計画を立て直すことが可能になります。