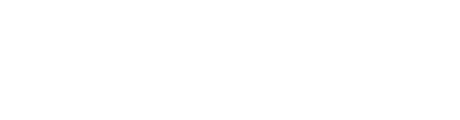※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
自己破産手続き中、してはいけないこととは?制限されるポイントを解説
目次
「自己破産申請中の生活がどうなるのか知りたい」
「自己破産手続き中に避けるべきことは?」
「自己破産手続き中にしてはいけないこととは?」
自己破産を申立てる前、借金返済に追われている状況から一日でも早く抜け出したいと考えている方が多いでしょう。また、自己破産が終了すれば借金がゼロになるため、明るい未来を想像している方も多いはずです。しかし、自己破産申請中の生活はどのような状況になるのでしょうか?
この記事では、自己破産申請中の生活について詳しく解説し、制限されること、されないこと、やってはいけないことを紹介します。さらに、自己破産手続きを成功させるためのポイントも最後に解説するので、これから自己破産を考えている方にとって役立つ情報です。
自己破産の基本情報と重要ポイント
自己破産中の生活について理解する前に、まずは自己破産の基本的な知識を解説します。
自己破産には2つの方法がある
自己破産には主に「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、それぞれに異なる制限があります。したがって、どちらの方法で自己破産するかを確認することが重要です。
種類と概要
| 種類 | 概要 | 費用 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 破産手続きが開始されると同時に、破産手続きが廃止される | 弁護士費用:20万~35万円 |
| 高額な財産がなく、免責不許可事由がない人が選ぶ手続き | 裁判所費用:2万~3万円 | |
| 管財事件 | 破産管財人が選任され、免責事由の調査や財産の換価、債権者への分配が行われる | 弁護士費用:30万~50万円 |
| 高額な財産がある場合や免責不許可事由がある場合に選ばれる手続き | 裁判所費用:50万~60万円 |
どちらの手続きが適用されるか
同時廃止は財産を処分する必要がない人が利用する手続きです。一方、管財事件は以下のような財産を持っている人が対象となります:
- 99万円以上の現金
- 20万円相当の財産
また、免責不許可事由がある場合、破産管財人が選任されて免責事由の調査が行われます。以下のような場合が該当します:
- 財産隠しが疑われる場合
- ギャンブルや浪費が原因で破産した場合
- 偏頗弁済(特定の債権者を優遇した支払い)が疑われる場合
- 前回の自己破産から7年以内である場合
- 詐術による信用取引が行われた場合
- 財産価値を著しく減少させる行為があった場合
自己破産手続きの進行方法
自己破産の手続きの流れは、同時廃止と管財事件で異なります。
同時廃止の場合:
- 裁判所に自己破産の申し立て
- 破産審尋(裁判官との面接)
- 破産手続開始決定・同時廃止決定
- 免責許可申立
- 債権者集会
- 免責審尋
- 破産手続廃止決定・免責決定確定
管財事件の場合:
- 裁判所に自己破産の申し立て
- 破産審尋(裁判官との面接)
- 破産手続開始決定
- 破産管財人の選任
- 破産管財人との面談
- 財産および負債原因の調査
- 財産の売却
- 債権者集会・財産の分配
- 免責許可申立
- 免責審尋
- 破産手続廃止決定・免責決定確定
流れの違い:
破産手続き開始決定までは同じですが、管財事件では破産管財人が選任され、財産や負債原因の調査が行われ、財産の換価後、債権者集会で分配がされます。
自己破産手続きの期間について
自己破産の手続き期間は、裁判所への申立て前の準備期間が2〜3ヶ月、申立てから免責決定確定までの期間は、同時廃止で3〜4ヶ月、管財事件では6ヶ月〜1年程度となります。準備期間を含めると、同時廃止の場合は5〜7ヶ月、管財事件では8ヶ月〜1年3ヶ月ほどかかると考えておくとよいでしょう。
自己破産申請中に制限される生活の側面
自己破産申請中、つまり手続き中の生活において制限されることは、選択する手続きによって異なります。ここでは、管財事件と他の手続き方法に共通する制限事項についてご紹介します。
管財事件の特徴と制限
管財事件の場合、主に以下のようなことが生活において制限されることがあります。
財産処分に関する制限
管財事件の申請中は、自分の財産を自由に処分することができなくなります。これは、手続き中に「管理処分権」を失うためです。この権利は破産管財人に移転し、破産管財人が代わりに財産の換価処分を行います。
ただし、管理処分権が適用されるのは、破産手続開始決定時点で所有していた本人名義の財産のみです。破産手続き開始後に新たに取得した財産や家族名義の財産は処分対象外となります。また、以下の財産は「自由財産」として処分の対象外となります:
- 生活必需品(家具、家電、衣類、寝具、日用品など)
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の価値の財産
- 年金や生活保護費などの公的受給権
- 職業上必要な道具など
居住地変更に関する制限
破産手続き中は、居住地を勝手に変更することはできません。引っ越しや住む場所を変える際は、事前に裁判所や破産管財人の許可が必要です。これは、自己破産を申立てた破産者が自分の所有する財産の内容について、裁判所や破産管財人から求められればいつでも説明できる状態を維持しなければならないためです。
勝手に引っ越しや旅行をして連絡が取れなくなることは避けるべきです。もし許可なく居住地を変更した場合、免責が認められない「免責不許可事由」に該当することがあります。したがって、引っ越しが必要な場合は、事前に依頼している弁護士に相談して、適切な対応を確認しましょう。
郵便物の受け取り制限
管財事件の場合、郵便物を自分で受け取ることができなくなります。これは「通信の秘密の制限」と呼ばれ、破産管財人が財産隠しや偏頗弁済などの免責不許可事由を調査するために行われます。破産手続きが開始されると、破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されることになります。
転送された郵便物は、開封されて内容が確認された後に、まとめて破産者に返却されます。この制限は破産者にのみ適用され、同居している家族宛ての郵便物には影響はありません。また、宅急便やメール便などは制限の対象外となるため、自宅で直接受け取ることができます。
長期旅行に関する制限
居住地の変更と同様に、海外旅行などの長期旅行にも事前に許可が必要です。しかし、許可を求めたからといって必ずしも認められるわけではありません。例えば、数日間の帰省など、合理的な理由がある場合は認められることが多いですが、娯楽目的の海外旅行などは免責の判断に悪影響を与える可能性があります。
そのため、どうしても必要でない限り、出張や帰省以外の旅行は、免責許可が下りるまで控えておく方が無難です。
管財事件と同時廃止の共通点
ここでは、管財事件と同時廃止に共通する制限事項について解説します。
職業制限
自己破産の申請中は、以下のような資格や職業に就くことが制限されます。
- 士業(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など)
- 役員(日本銀行、地方公共団体金融機構など)
- 委員長および委員(公正取引委員会、裁判所職員倫理審査会、中央更生保護審査会など)
- 取締役(銀行、農林中央金庫など)
- 登録資格(不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、中小企業診断士、特定保険募集人など)
- 業種・許可(警備業、探偵業、一般建設業、質屋営業、産業廃棄物処理業、貸金業)
これらの制限は破産法に基づくものではなく、弁護士法や宅建業法など、各職業に関連する法律によって定められた資格制限、罷免事由、解任事由として存在しています。
なお、これらの制限は自己破産後も続くわけではなく、免責決定が確定すれば解除されます。
ブラックリスト掲載による制限
自己破産が登録されると、個人信用情報にその情報が記録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。これにより、以下のような手続きやサービスの利用が制限されることになります。
- クレジットカードの新規申し込み、更新、利用
- ローンの申し込みや新規借り入れ
- スマホや携帯電話本体の分割払い
- 信販系保証会社を利用した賃貸物件の新規契約
- 他人の保証人や連帯保証人になること
ブラックリスト状態となる期間は、信用情報機関ごとに異なります。
| 信用情報機関 | 登録期間 |
|---|---|
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 契約期間中および契約終了後5年間 |
| 日本信用情報機構(JICC) | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| 全国銀行個人情報センター(KSC) | 破産手続き開始決定日から10年を超えない期間 |
各機関での登録期間は異なりますが、情報は独自のネットワークで共有されているため、少なくとも10年間は新しいクレジットカードを作ったり、ローンを借り入れたりすることが難しくなると考えられます。
自己破産申請中にできること
一方、自己破産申請中でも、生活の中でこれまで通り行えることもあります。
資格制限のない職業の続行
前述の通り、他者の財産を扱うような職業や資格は、一定期間制限を受けます。しかし、資格制限がない仕事の多くは、自己破産申請中でも引き続き続けることが可能です。もし自己破産を理由に資格制限のない仕事で解雇される場合、それは不当解雇にあたるため、労働基準監督署などの適切な機関に相談することが必要です。
デビットカード及び家族カードの使用
自己破産によって本人名義のクレジットカードは更新時に使えなくなり、新規で作成することもできませんが、家族カードを利用して買い物をすることは制限されません。また、銀行口座と連携して残高内で利用できるデビットカードも問題なく使用できます。
ブラックリスト状態になるとさまざまな制限が生じますが、デビットカードや家族カードなど、制限がない方法を選ぶことで、日常生活に大きな不便は感じずに過ごせるでしょう。
現在の賃貸物件に住み続けること
現在住んでいる賃貸物件については、自己破産の手続き中であっても、引き続き住み続けることができます。現在、自己破産のみを理由に退去を命じることは違法とされています。ただし、家賃の滞納がある場合には、自己破産を理由に退去を求められる可能性があります。
新しい賃貸物件への申し込み
自己破産申請中でも、新たに賃貸物件を申し込んで入居することは可能です。ブラックリスト状態により、信販系の家賃保証会社が必要な賃貸物件への申し込みは難しくなりますが、他の家賃保証会社を利用したり、連帯保証人を立てることで申し込みができる場合は、従来通り審査に通る可能性が高いです。なお、管財事件で手続きを進める場合は、住所変更などの事前の手続きについて、破産管財人の許可を得る必要があります。
携帯電話やスマートフォンの使用
携帯電話やスマートフォンの利用は、以下の条件を満たす場合に限り、従来通り利用することができます。
- 利用料金の滞納がないこと
- 本体価格が20万円以下であること
また、クレジットカードで支払いをしている場合は、銀行口座振替やコンビニ払いに変更することをおすすめします。
保険の加入や継続
各種保険への加入や継続には特に制限はありません。これまで通り保険を利用できるだけでなく、自己破産を理由に解約を強制されることもありません。新たに保険に加入することも問題なくできます。ただし、解約返戻金が20万円を超える場合、その金額は財産と見なされ、自己破産申請後に解約が必要となります。
生活保護受給
生活保護の受給権は差し押さえ禁止債権に該当するため、自己破産申請中や自己破産後でも引き続き受け取ることができます。特に、生活保護を受給している場合、自己破産を検討する際には次のようなメリットがあります。
- 弁護士費用の自己負担が不要
- 裁判所費用の自己負担が不要
- 自己破産が認められやすくなる
法テラス(日本司法支援センター)の「法律扶助(費用の立て替え制度)」を利用することで、弁護士費用を立て替えてもらえたり、立て替えた費用の返済が免除される可能性があります。また、生活保護を受けていることにより、自己破産が認められやすくなるという利点もあります。
年金受給
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、自己破産をしても基本的に差し押さえが禁止されています。そのため、自己破産の手続き中でも、これまで通り受け取ることが可能であり、自己破産を理由に給付額が減額されることもありません。
一方で、個人で契約している個人年金は、差し押さえの対象となる可能性があります。以下は、年金の種類ごとに差し押さえの対象になるかどうかを示したものです。
| 分類 | 種類 | 差し押さえ対象になるか |
|---|---|---|
| 国民年金 | 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 | ならない |
| 厚生年金 | 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 | ならない |
| 企業年金 | 退職年金、確定給付企業年金 | ならない |
| 個人年金 | 個人年金保険による年金、確定年金、終身年金 | なる |
選挙権の行使・パスポート
選挙権やパスポートの取得については、自己破産中でもこれまで通り制限を受けることはありません。インターネット上で「自己破産すると選挙権を失う」といった誤った情報が広まっていますが、実際にはそのような事実は一切ありません。また、パスポートの取得に関しても影響や失効はありません。
自己破産は犯罪行為ではなく、日常生活に関する制限については誤解が多いため、こうしたデマには注意しましょう。
自己破産申請中にやってはいけない行動
自己破産申請中には「制限されること」だけでなく、「してはいけないこと」もあります。これらの行為は多くの場合、自己破産の免責が許可されない「免責不許可事由」に該当します。次に紹介する行為を行うと、免責が認められず、借金がゼロにならない可能性があります。
偏頗弁済
偏頗弁済(へんぱべんさい)も自己破産申請前や申請中に行ってはいけない行為の一つです。偏頗弁済とは、債務者が特定の債権者に対して借金の返済をしたり、担保を提供する行為のことを指します。自己破産を申請する際、家族や友人に対して借金をしている人が、申請前または申請中に自己破産を避けるためといって勝手に返済を行うことがあります。
しかし、これは債権者平等の原則に反し、免責不許可事由に該当します。たとえ返済先が親族や友人であっても、その人たちだけに返済することは避けるべきです。
具体的には、次のような行為が偏頗弁済に該当します:
「特定の債権者に対して、当該債権者に特別な利益を与える目的で、または他の債権者を害する目的で、担保を供与したり、債務を消滅させる行為を行ったこと。それらの行為が、債務者の義務に属さない方法や時期で行われた場合。」
財産隠しを避けること
財産隠しは、自己破産申請中に限らず、申請前でも行ってはいけません。財産隠しは免責不許可事由に該当し、発覚すれば免責が認められません。さらに、財産隠しが発覚すると「詐欺破産罪(破産法第265条)」で起訴されるリスクもあります。破産法では、次のように財産隠しを免責不許可事由として規定しています。
「債権者を害する目的で、破産財団に属する、または属すべき財産を隠匿、損壊、または不当に処分し、破産財団の価値を減少させる行為をしたこと。」
自己破産では一定額以上の財産が没収され、それが債権者への返済に充てられます。財産隠しは、その没収される財産を意図的に隠す行為に当たります。具体的には、以下のような行為が財産隠しに該当します。
- 一部の預金口座を申告しない
- 預金から現金を引き出して隠す
- 現金や財産を親族や知人に預ける
- 不動産、車、保険などの名義を親族に変更する
- 離婚、贈与、売買などを偽装して財産を譲渡する
自己破産は、借金を免除してもらうための手続きですが、そのためには債権者に誠実に対応することが求められます。全額返済が難しい場合でも、返済可能な財産があればそれを債権者に公平に分配し、残りの借金を免責するのが原則です。財産隠しは債権者を害する行為であり、絶対に避けるべきです。
クレジットカードを現金化する
自己破産の申請前や申請中にクレジットカードの現金化を行ってはいけません。クレジットカードの現金化とは、カードで高価なブランド品やギフトカードなどを購入し、それらをすぐに売却して現金を得る行為です。このような行動は、クレジットカード会社に損害を与えることになります。
さらに、クレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当し、意図的に行うと免責を受けることができなくなります。破産手続きにおいて、次のような行為が免責不許可事由に該当します。
「破産手続開始を遅らせるために、著しく不利な条件で債務を負担し、または信用取引を利用して商品を購入し、それを不利益な条件で処分したこと。」
離婚すること
自己破産の申請中には、特別な理由がない限り離婚は避けた方が無難です。離婚後の財産分与が問題となり、もし財産隠しを目的に離婚したのではないかと疑われる可能性があります。仮にその意図がなかったとしても、財産隠しと判断されると免責が認められなくなり、さらに詐欺破産罪で起訴されるリスクも考えられます。
虚偽の申告で借金をする
返済が不可能だと理解しながら、新たに借金を重ねることも避けるべきです。自己破産は、すでに借金返済の能力が限界を超えている場合に行う手続きです。返済が不可能だと分かっていながらも、返済可能だと虚偽の申告をして借金を増やす行為は問題です。このような行動は過剰な債務を抱えることになり、免責不許可事由に該当します。破産手続き開始の申立てが行われた日から遡り、1年間において、破産原因を知りながら詐欺的手段を使って財産を得る行為も該当します。重要なのは、いつから新たな借金が問題になるかという点です。破産法では、破産手続き開始の申立て日の1年前から、その行為が対象となると定めています。したがって、自己破産を弁護士に相談した後は、これ以上借金を増やさないように注意しましょう。
虚偽の情報を含む書類を裁判所に提出する
裁判所に虚偽の内容を記載した書類を提出することは、決して行ってはいけません。例えば、債権者が実際より少ないかのように見せかけて、特定の債権者にのみ返済するために債権者一覧を変更し、提出することは許されません。また、財産や家計の収支に関する書類に嘘の情報を記載することも同様に問題です。これらの行為は免責不許可事由に該当し、破産手続きにおける信頼性を欠くことになります。破産法では、業務や財産に関する帳簿、書類、その他の物品を隠蔽、偽造、または改ざんすることを禁止しており、虚偽の債権者名簿を提出することも厳禁です。
浪費やギャンブルをすること
自己破産申請中はもちろん、弁護士に依頼した後、破産手続きが完了するまでギャンブルや浪費を控えるべきです。特に、自己破産の原因が浪費やギャンブルだった場合、反省の態度が見えないと判断され、免責が認められないことがあります。浪費やギャンブルによる借金は、原則として免責不許可事由に該当しますが、多くの場合、裁判所の裁量で免責が認められることがあります。しかし、裁量免責を受けるためには、裁判所への協力や反省の意思を示すことが求められ、場合によっては反省文を提出する必要があることもあります。そのため、申請中に浪費やギャンブルを行うことは避けるべきです。
手続きに必要な費用を納付しない
自己破産の手続きを進めるには、基本的に裁判所費用や弁護士費用が必要です。これらの費用を支払わないことは許されません。裁判所費用を納めないと、手続きが進まなくなり、最悪の場合、申請が却下されることもあります。また、弁護士費用を約束通りに支払わないと、弁護士に辞任されることも考えられます。
ただし、自己破産の依頼後に弁護士が債権者に「受任通知」を送って返済を停止し、その後で費用を積み立てられるようにしている事務所もあります。分割払いに対応している事務所もあるので、無理なく支払える方法を相談するのが良いでしょう。
また、分割払いでも費用を支払えない場合は、条件を満たせば法テラスを通じて立て替えをしてもらったり、場合によっては免除されることもあります。
参考:立替制度に関するよくあるご質問|無料法律相談・弁護士等費用の立替
書類提出期限を守らない
自己破産手続きにおいて、裁判所への書類提出期限を守らないことは決して許されません。期限を過ぎて書類が提出されない場合、手続きが遅延し、進行が滞る原因となります。また、裁判所が自己破産に必要な調査を拒否されたと判断すれば、免責不許可事由に該当し、免責が下りない可能性があります。
自己破産中に新たに借金をする
自己破産の手続き前や進行中に新たな借金をすることは許されません。返済できないことを自覚して借り入れを行うと、それは免責不許可事由(破産法252条1号5項)に該当し、免責が認められない可能性があります。
さらに、借金の際に債権者を欺くような行為があったと認定されると、免責を受けられないだけでなく、詐欺罪に問われる危険もあります。加えて、ヤミ金業者から借りることで、個人情報の悪用や犯罪に巻き込まれるリスクも伴います。
生活が困難な場合は、役所の生活保護課や福祉事務所に相談し、生活保護や各種支援を利用することも選択肢の一つです。
自己破産中に制限される職業
自己破産手続き中は、特定の職業や資格に一時的な制限がかかり、その間、いくつかの職業に就くことができなかったり、資格を使用できない場合があります。
主に制限される資格・職業は以下の通りです:
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、公証人、生命保険外交員、警備員、旅行業の登録など
自己破産を隠してこれらの仕事を続けたり、新たに就業したりすると、資格や業務に関する法律に基づいて処分を受ける可能性があるため、十分に注意が必要です。懲戒解雇や損害賠償請求など、重い処分が科されることもあります。
通常、自己破産手続きが終了し、免責決定を受けると「復権」となり、以前のようにその職業に就くことが可能になります。
破産管財人の調査に協力しない
自己破産の手続きが管財事件または少額管財で進行している場合、破産管財人による調査に対して非協力的な態度を取ったり、妨害を行ったりすることは絶対に避けなければなりません。
具体的な例としては、以下のような行為が該当します。
- 破産管財人との面談に応じない
- 破産管財人からの質問に答えない、または虚偽の回答をする
管財事件や少額管財の場合、破産者には破産に至った経緯や財産の有無について、破産管財人に正確に説明する義務があります。この義務に違反すると、免責が認められない「免責不許可事由」と見なされる可能性があります。
許可を得ずに転居や旅行を行う
自己破産が管財事件で進行している場合、手続き中に裁判所の許可なく引っ越しや旅行を行うことはNGです。この制限は、破産法第37条に基づいて破産者に課せられています。
管財事件は、破産管財人による財産や申立人に対する調査が行われる手続きであり、そのため、手続き中は裁判所や破産管財人と常に連絡が取れる状態でなければなりません。引っ越しや旅行をする場合は、事前に裁判所に申請して許可を得る必要があります。
許可なしで引っ越しや旅行を行い、その結果、連絡が取れなくなった場合、免責が認められなくなるリスクがあるため注意が必要です。
自己破産手続きを成功させるためのコツ
自己破産手続きを成功させるためには、以下のポイントに気を付けて進めていきましょう。
財産や債権者の漏れを発見した場合は速やかに対応
財産や特定の債権者を意図的に隠すことは免責不許可事由に該当しますが、もし記載漏れがあった場合は、早急に対処することが重要です。財産については、申立て後に未申告の財産が判明した場合、速やかに裁判所に報告する必要があります。
債権者の漏れについては、破産手続きの進行段階によって対応方法が異なります。
破産手続き開始決定前
- 速やかに裁判所に報告し、「債権者変更上申書」および「漏れた債権者を追加した債権者一覧表」を再提出すれば、特に問題なく手続きを進められます。
破産手続き開始決定後
- 同時廃止の場合: 裁判所に「債権者変更上申書」と「漏れていた債権者を追加した債権者一覧表」を提出し、債権者に「破産手続開始決定通知書」を送付します。
- 管財事件の場合: 裁判所に「債権者変更上申書」と「漏れていた債権者を追加した債権者一覧表」を提出し、破産管財人に対して漏れた債権者への通知書の送付を依頼します。その後、破産管財人から裁判所に報告書が提出されます。
免責許可決定確定後
- 債権者に「免責許可確定通知書」または「免責許可決定通知書」のいずれかを送付します。
いずれのケースでも、記載漏れが発覚した場合は、速やかに弁護士に報告し、その後の対応方法について指示を受けることをお勧めします。
裁判所や破産管財人の指示に従うことの重要性
自己破産は裁判所を通じて行う手続きであるため、裁判所や破産管財人の指示には必ず従う必要があります。破産法では、破産者がこれらの指示に従う義務を定めており、従わない場合には免責不許可のペナルティを受けることになります。
裁判所から書類の提出を求められたり、呼び出しがあった場合は、期日を守り迅速に対応することが大切です。もし間に合わない場合、正当な理由があれば期限の延長を認められることもありますが、破産管財人の指示に従わなかったり、その業務を妨げる行為があると、免責が認められなくなることを覚えておきましょう。
弁護士の指示に従い行動することを心がける
自己破産を円滑に進めるためには、依頼した弁護士の指示やアドバイスをきちんと守ることが大切です。裁判所に提出する書類の準備や打ち合わせなど、弁護士からの連絡に対応しない、または準備を怠ると、手続きが期日までに進まず、最終的に自己破産を申し立てることができず、借金をゼロにする機会を逃すことになります。ひどい場合には、弁護士が代理人を辞任することもあり、その場合、支払った着手金は返金されません。また、新たに別の弁護士を依頼しなければならなくなりますので、弁護士の指示には必ず従うようにしましょう。
自己破産が認められる確率と、認められない場合の対処法
これまでに述べたように、自己破産にはさまざまな制限があり、手続き前や手続き中にうっかりこれらを破ってしまうことも考えられます。しかし、これらの制限があるからといって、自己破産ができないわけではありません。日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、実際には「不許可」のケースは0%でした。つまり、自己破産を申し立てた場合、免責が不許可になる確率は非常に低いということがわかります。
同調査では、負債理由が「ギャンブル」と回答した破産者が約7%、また「浪費・遊興費」は約11%であることが示されています(複数回答)。これらは破産法において免責不許可事由に該当する行為です。しかし、こうした理由で破産した場合でも、裁判所の判断で「裁量免責」が適用されることが多いです。
裁量免責とは、免責不許可事由があっても、以下のような要素を考慮して裁判所が免責を許可する判断を下すことを指します。
- 免責不許可事由の程度が軽微であること
- 破産者が反省していること
- 経済的再建の可能性があること(例:安定した収入がある)
そのため、免責不許可の可能性が不安な場合は、自己破産を検討する際に弁護士と相談し、的確なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、自己破産以外にも任意整理や個人再生といった他の債務整理方法を提案することができるかもしれません。
- 任意整理: 債権者と直接交渉し、借金の利息減額や分割の再構築を行う方法
- 個人再生: 裁判所を通して借金の大幅減額を認めてもらい、原則3年(最長5年)で返済する方法
また、自己破産の申請が不許可となった場合には、「即時抗告」を申し立てて、地方裁判所での判断が正当かどうかを高等裁判所で再審してもらうことも可能です。
自己破産を依頼した弁護士とともに、最適な対応を検討して、借金問題の解決を目指しましょう。
まとめ
自己破産の申請中において制限を受ける内容は、手続きが管財事件か同時廃止かによって異なります。管財事件の場合、財産の処分や居住地の変更、長期旅行、郵便物の受け取りなどに制限があります。対して同時廃止を含む手続きでは、特定の資格や職業に関連する仕事、及びブラックリスト状態により受ける制限が課せられます。
一方、資格制限がない仕事や賃貸物件の申し込み、スマートフォンの利用、年金や生活保護の受給については、制限なく行うことができます。また、自己破産中でも、免責不許可事由に該当するような財産隠しや偏頗弁済、クレジットカード現金化、虚偽の借金申告といった行為は決して行ってはいけません。
自己破産を成功させるためには、裁判所や破産管財人からの指示に従い、漏れなく必要書類を整えて期日通りに裁判所に出頭することが重要です。もし手続き中に財産や債権者の漏れに気付いた場合は、速やかに弁護士に報告し、適切な対応を取るようにしましょう。弁護士はあなたの利益を最優先に考えてサポートしますので、指示やアドバイスに従って自己破産手続きを進め、生活の立て直しに向けて第一歩を踏み出しましょう。