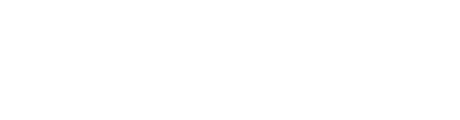※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
奨学金の支払いを遅延するとどうなる?ブラックリスト・リスクについて解説
目次
「奨学金」は大学の入学費や在学中の費用を借りるためのものですが、借りている人の中には、月々の返済額が生活に大きな負担となっている場合も少なくありません。特に新入社員は月給が少ないため、奨学金の返済が生活に支障をきたすことが多いでしょう。この記事では、奨学金の支払いを滞納した場合に生じるリスクや、信用機関のブラックリストとの関連について解説します。
なぜ滞納してしまうのか
延滞のきっかけとなった理由は、「家計収入の減少」が67.1%で最も多く、次いで「家計支出の増加」が39.5%、「入院・事故・災害等による」が18.1%、「忙しかった」が14.1%でした。延滞が続いた理由としては、「本人の低所得」が64.0%で最も高く、「奨学金の延滞額の増加」が39.9%でした。奨学金の返済は、卒業後7ヶ月目(3月卒業の場合は10月)から始まります。収入が少なかったり、予期しない支出が増えたりすると、就職初年度の貯蓄は難しいことがあります。そのため、学生のうちからアルバイトをするなど、返済資金を確保する方法を考えることが重要です。また、奨学金を借りた新社会人は、家計簿を活用して支出を管理し、計画的な生活を心がけることが大切です。無駄な支出を避ける習慣をつけることも不可欠です。さらに、医療費を節約するために、民間の医療保険に加入することも一つの手段です。レギュラータイプであれば、低い保険料で十分な保障を受けることができます。
奨学金の遅延が発生したら、早めに相談しよう
何らかの理由で奨学金の支払いが難しい場合、すぐに借り入れ先や日本学生支援機構に相談しましょう。奨学金は事前に相談することで返済期限を延長できるため、今月支払えないからといって直ちにブラックリストに登録されることはありません。しかし、滞納を繰り返すと信用機関のブラックリストに登録され、今後のローン契約や賃貸契約の審査で不利になる可能性があります。原則として、事前に相談しておけば返済期限の調整が可能ですので、支払いが困難になりそうな場合は早めに相談することをおすすめします。奨学金の遅延は早期に相談しましょう。
【回数別解説】奨学金の支払い遅延時の対処法
ここからは、奨学金の滞納が発生した場合の対応を振替不能回数ごとに詳しく紹介します。奨学金の支払いは、滞納回数ごとに対処方法が明確に決められており、クレジットカードや住宅ローンの滞納よりも内容やスケジュールがはっきりしています。
振替不能1回目
最初の振替不能、つまり初回の引き落とし時に口座残高が足りなかった場合、基本的には翌月の振替日に2ヶ月分をまとめて引き落とされます。この時点では延滞金は課されません。通常、支払いの滞納には金利が適用され、1日ごとに延滞金が発生しますが、奨学金の場合は最初の1ヶ月のみ延滞金が発生しません。2ヶ月分の支払いが必要ですが、次回の振替時にお金を準備していれば問題はありません。
振替不能1回目が発生すると、「奨学金返還の振替不能通知」が届きます。通知には次回振替金額が記載されているため、次回振替日までにお金を準備しましょう。
対応手順
- 口座振替ができなかったことについて電話連絡
- 「奨学金返還の振替不能通知」の発送
- 個人信用情報機関への登録に関するSMS送信
- 2ヶ月分の合計額を口座から振替
もし、今後の支払いが困難な場合は、奨学金相談センターに相談しましょう。
振替不能2回目
2ヶ月分の滞納が発生した場合、延滞金が加算されます。奨学金は原則として口座振替のみ対応しているため、途中で支払って延滞金を抑えることはできません。延滞金の金利は、令和2年以降、第一種奨学金で1.5%、第二種奨学金で3%程度です。
振替2回目でも支払いができない場合、翌月の振替日に3ヶ月分がまとめて引き落とされます。再度「奨学金返還の振替不能通知」が届くので、振替日までに金額を口座に準備しましょう。
対応手順
- 本人と連帯保証人に督促の電話
- 「奨学金返還の振替不能通知」の発送
- 連帯保証人宛てに「奨学金の返還について」の書類発送
- 本人に「個人信用情報機関への登録について(注意)」の通知発送
- 3ヶ月分の返済額と延滞金の合計額を口座から振替
振替不能3回目
3ヶ月分の滞納が発生した場合、延滞金が加算され、翌月の振替で4ヶ月分が引き落とされます。もし次回の振込時でも残高が不足すると、債権回収会社から強制的に徴収され、信用機関のブラックリストに登録されます。
3回目は実質的な最終通告となるため、4ヶ月分の返済額と延滞金を準備する必要があります。奨学金などの支払いは免れることはできないため、支払えない場合は早急に奨学金相談センターに相談してください。
ブラックリストに登録されると、5〜10年間はローン契約ができなくなる可能性があります。仮に結婚してマイホームを購入しようとしても、登録期間中は住宅や車の購入の際にローン契約を結ぶことは難しいと考えたほうが良いでしょう。さらに、支払いができない場合、連帯保証人が代わりに滞納分を支払うことになります。最終的には財産差押えに至る可能性もあるため、長期滞納は避けるべきです。
対応手順
- 本人と連帯保証人に督促の電話
- 「奨学金返還の振替不能通知」の発送
- 連帯保証人宛てに「奨学金の返還について」の書類発送
- 本人に「個人信用情報機関への登録について(警告)」の通知発送
- 4ヶ月分の返済額と延滞金の合計額を口座から振替
奨学金には返済期限を延長する制度もあります。収入が途絶えたり、支払いが難しくなった場合は、早急に奨学金相談センターに相談しましょう。
奨学金の支払いを遅延しないために気をつけるべき3つのポイント
ここでは、奨学金の支払いを滞納しないために今できる対策を3つ紹介します。
在学中に就職が決まらなかった方や新卒の方など、月々の奨学金の返済で生活が厳しくなることはよくあります。金銭的な負担を少しでも減らすために、以下の方法を検討してみましょう。
1. 収支バランスを把握する
社会人になりたての頃は、毎月の収支バランスを把握するのが難しいことがあります。しかし、奨学金の返済がある中で生活するためには、家計簿をつける習慣を早めに身につけましょう。
何にいくら使っているのかを把握することで、倹約できる部分が見えてきます。家賃や保険料といった固定費の見直しは難しいかもしれませんが、食費は自炊で大きく節約できますし、携帯料金を格安SIMに変えるだけで数千円程度の削減が可能です。
また、在学中で就職後に引っ越しを予定している場合、できるだけ家賃の安い場所を選ぶことが賢明です。生活費が不安な場合、身の丈に合わない物件に住むと生活が維持できなくなる恐れがあるので、慎重に選びましょう。
2. 収入を増やす
収支のバランスだけではどうしても返済に充てられるお金が足りない場合、副業を検討するのも一つの手です。
職場によっては副業が禁止されていることもありますが、民間企業では副業を許可しているところも増えてきました。
現在はパソコンやスマートフォン1台でできる副業が豊富にあります。クラウドソーシングサービスやSNSにもたくさんの仕事案件が掲載されているので、自分のスキルを活かせる副業を始めてみるのも良いでしょう。
3. 口座に余裕を持たせておく
返済用の引き落とし口座を他の支払いにも使っている場合、残高不足で奨学金の支払いができなくなるリスクがあります。
例えば、水道や電気料金などの光熱費は毎月の金額が変動するため、引き落とし予定の奨学金分が先に使われてしまうこともあります。
そのため、口座には常に数万円程度の余裕を持たせておくことをおすすめします。近年では、スマートフォンのアプリで口座残高を簡単に確認できるため、奨学金の引き落とし日が近づいたら、最終確認として残高をチェックすると安心です。
奨学金の支払いにカードローンを使ってもいいか?
一時的に奨学金の支払いが困難な場合、カードローンの利用も検討できます。カードローンなら現金を引き出して、実質的に返済期限を延長することができます。コンビニATMを使えるため、急にお金が必要な場合にも対応可能です。
ただし、カードローンは奨学金より金利が高いため、長期的な利用は推奨されません。お金を借りている状態が続くことになるため、カードローンはあくまで一時的な対策として活用しましょう。
奨学金の支払いが厳しい場合は、「返還期限猶予」を確認しよう
ここでは、奨学金の支払いが難しい場合に利用できる「返還期限猶予」の概要を紹介します。奨学金を4ヶ月以上滞納すると、ブラックリスト登録や強制徴収などのデメリットが生じるため、支払いが厳しい時は返還期限猶予をうまく活用することが重要です。
返還期限猶予とは?
返還期限猶予とは、奨学金の支払いが困難な状況に陥った場合、返済期限を一定期間延期できる制度です。主な該当事由としては、以下のものが挙げられます。
- 災害
- 傷病
- 経済的困難
- 失業 など
返還期限猶予が認められると、最大で120ヶ月(約10年)まで返済期限を延ばすことが可能です。さらに、支払いが難しいが少額なら支払える場合は、「減額返還制度」を利用して月々の返済額を減額できます。この場合、最長で180ヶ月まで適用が可能です。
対象者
返還期限猶予には「一般猶予」と「猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類があり、それぞれ承認要件が異なります。
- 一般猶予の承認要件は主に以下の通りです:
- 現在返還が困難であること
- 年収が税込みで300万円以下(給与所得者以外は200万円以下)であること
- 猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予の承認要件は以下の通りです:
- 第一種奨学金の「猶予年限特例」または「所得連動返還型無利子奨学金」を受けていること
- 新卒または経済的困難で低収入もしくは無収入であること
どちらの要件でも、経済的に困難な状態であることが必須条件となります。
注意点
返還期限猶予には審査があり、適当な事由がない限り、返済期限を延ばすことはできません。申請には所得証明書やマイナンバーカードなどの公的書類を提出する必要があり、本当に経済的に困窮していることを証明できないと、承認は難しくなります。
制度の仕組みとして、「趣味にもっとお金を使いたいから」といった理由では申請できないようになっています。
奨学金の滞納が原因で起こる「ブラックリスト」への登録とは?
ここでは、奨学金を4ヶ月以上滞納することによって発生する「ブラックリスト登録」について説明します。奨学金は信用機関が関与する支払いであるため、長期の滞納が続くと、さまざまな借り入れや個人の信用に大きな影響を与えることになります。
ブラックリストとは?
信用機関における「ブラックリスト」とは、金融事故が個人の信用情報に記録されることを指します。実際には、ブラックリストという名前のシステムは存在せず、信用機関に事故情報が登録されることを「ブラックリスト」と呼んでいます。
信用情報は、金融サービスの利用状況や契約内容、契約者の属性を示す個人情報で、クレジットカードやローン契約などに関わる情報が含まれます。事故情報も信用情報の一部であり、これにはクレジットカードの申し込み内容や利用履歴が含まれます。
信用情報は、クレジットカードや賃貸契約など、支払い能力が審査される契約において参照されます。ブラックリストに登録されることで、住宅ローンやカーローン審査に影響が出るのはこのためです。
ブラックリスト登録の期間
ブラックリストに登録される期間は、通常5年〜10年と言われていますが、正確な年数は信用機関によって異なります。この期間はいつまでかは公表されていないため、登録後の具体的な期間は本人にもわかりません。
また、ブラックリストに登録されたことは、原則として本人には通知されません。奨学金の場合は、4ヶ月の滞納がある場合に登録されると明記されていますが、他の支払いに関しては以下の条件で登録されるとされています:
- 2ヶ月以上の滞納
- 短期の滞納を繰り返した場合
- 債務整理を行った場合
ブラックリストに登録されたかどうかを知るためには、「開示請求」というシステムを利用して、信用情報を確認することができます。これにより、自分の信用情報を所定の手続きで請求できます。もし、住宅や車を購入する予定がある場合、事前に信用情報を確認しておくと良いでしょう。
ブラックリストを管理する信用情報機関
国内で個人の信用情報を取り扱う主要な信用機関は以下の3つです:
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
主に信販会社やクレジットカード会社、百貨店などと関連しています。 - JICC(株式会社日本信用情報機構)
主に消費者金融を中心に、ローン契約やカードローンなどの情報を管理しています。 - JBA(一般社団法人全国銀行協会)
主に銀行系の借り入れに関与し、日本学生支援機構もこちらに加盟しています。奨学金に関して滞納した場合、JBAに開示請求をすることが推奨されます。
個人の信用情報は、これらの信用機関間で共有されているため、「CICでブラックリストに登録されているからJBAの加盟店でローン契約を結ぶ」といった行動は意味がありません。
ブラックリストに登録された情報は削除可能か?
一度ブラックリストに登録されると、その情報が誤って記載されていない限り、登録を抹消することはできません。登録が削除されるのを待つしかなく、その間、ローン契約や不動産契約などの審査において不利になります。
SNSやインターネット広告では「ブラックリスト登録を消します」と謳う業者が見受けられますが、これらはすべて詐欺である可能性が高いため、注意が必要です。
ブラックリストに登録されるとできなくなること
ここでは、信用機関のブラックリストに登録されることによるリスクについて紹介します。ブラックリストに登録されると、今後5年〜10年にわたって日々の支払いにおいて大きな不利を受けることになります。
カーローンが組めない
カーローンとは、車の購入代金を毎月一定額で分割返済する契約のことです。カーローン契約時には、支払い能力を確認するために信用情報が参照されます。この際、ブラックリストに登録されていることが相手に伝わり、審査に悪影響を与える可能性があります。必ずしも審査に落ちるわけではありませんが、一定の収入があってもブラックリストに登録されているだけで審査に落ちることが少なくありません。どうしてもローンを組みたい場合は、頭金を多めに準備するか、車の購入予算を下げる必要があります。また、これはカーローンだけでなく、住宅ローンにも同様の影響があります。住宅ローンは金額が大きいため、審査を通過するのはさらに難しくなります。
クレジットカードが作れない
クレジットカードを作る際には審査がありますが、ブラックリストに登録されていると信用力を疑われ、新たにカードを作れない可能性があります。ただし、カードの発行条件は会社によって異なり、A社で審査に落ちてもB社で通ったということもあります。また、ブラックリスト登録はクレジットカードの分割払いにも影響を与えます。10万円を超える分割払いには審査があるため、カードによっては支払い方法を制限されることがあります。
保証人になれない
信用機関のブラックリストに登録されると、家族がローン契約や奨学金を借りる際に保証人になれなくなります。保証人は契約者が返済できなかった場合の担保として登録されるため、事故情報があると保証人として不適任とみなされます。住宅ローンや奨学金など、重要な契約で保証人を必要とする場合が多いため、保証人を立てられないことは大きなデメリットとなります。
賃貸契約が結べないことがある
賃貸契約も契約者の支払い能力を見て審査されるため、ブラックリストに登録されていると審査に通りにくく、選べる物件に制限がかかることがあります。ローン契約より審査の難易度は低いものの、収入に対して高すぎる家賃の物件を選んでいると、落ちる可能性が高くなります。
信用情報には何が登録されるか?
個人の信用情報には「本人の識別情報」「申込内容」「契約内容」「支払い状況」「利用事実」が登録されます。信用機関では、事故情報に限らず支払いに関するあらゆる情報が記録されており、ローン契約や不動産契約の審査では、現時点の収入や貯蓄だけでなく、信用情報も参考にされます。
延滞する前に行うべきこと
3か月間延滞すると、個人信用情報機関のいわゆるブラックリストに登録されます。登録されると、クレジットカードの作成や住宅ローン契約に制限がかかります。さらに、一度登録されると、返済が完了してもその記録は5年間残り続けます。意外と知られていませんが、日本学生支援機構は返還が困難な方のために「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」などの救済措置を用意しています。アンケートの結果によると、返還前にこれらの猶予制度を知っていた人は、延滞者のうち4.8%、非延滞者のうち37.3%でした。これらの制度を事前に知っておくことで、もし返還が難しくなった場合には、日本学生支援機構に早めに相談することが重要です。
奨学金の申請は親が行ってはいけないのか!?
申請手続きを「学生本人」が行った場合、延滞割合が低いことがわかります。一方で、「親などの学生以外」が申請手続きを行った場合は、延滞割合が高くなる傾向があります。「国の教育ローン」の債務者は保護者ですが、奨学金の債務者は学生です。保護者が申請手続きを手伝うことは問題ありませんが、すべての手続きを保護者に任せるのは避けるべきです。そうしないと、子供が奨学金の返済について自分自身の責任を感じなくなる可能性があります。
奨学金の返済義務を自覚しよう
非延滞者のうち、90.1%は「申請手続き前」に返済義務を認識しているのに対し、延滞者ではその割合が51.1%と約半数でした。また、延滞者のうち、貸与終了後に返済義務を知った人の割合は20.1%で、そのうちの半数以上が「延滞通知を受け取った後」に知ったと回答しています。学生本人が奨学金を申請することで返還義務が生じることを認識していれば、「延滞の催促を受け取った後」に初めて知るという事態は避けられます。奨学金を借りる際は、返済義務の有無をしっかりと確認しておくことが重要です。
まとめ
①奨学金の滞納が許容されるのは最大で3回まで
②奨学金を滞納すると、信用機関のブラックリストに登録される
③ブラックリストに登録されると、ローンや不動産契約の審査で不利になる
④奨学金の返済が厳しい場合は、返済期限猶予を活用しよう
⑤万が一の口座残高不足に備えて、少し多めにお金を入れておこう