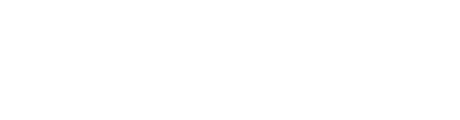※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
株で失敗する理由や予防策、借金解決策の解説!
目次
コロナ禍を契機に資産運用を始める方が増加しています。その中でも株式投資は、比較的ローリスクで、株によってはお得な優待券ももらえることから人気の運用方法です。しかし、運用方法を誤ると、株で借金をしてしまい、借金地獄に陥るケースも少なくありません。この記事では、株で借金をしてしまう仕組みと、その際の対処法について解説します。なお、株式投資が自己破産の免責不許可事由に該当する場合もあります。免責不許可事由については、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひご参考にしてください。
株式投資で直面する可能性のあるリスクと失敗例
株式投資とは、企業の株を購入してその企業の発展に投資することです。投資先企業の成長(利益の向上)と共に、投資額に応じた配当金を受け取ることができ、株式投資を行う多くの人々は、この配当金と株の売買を通じて得られる利益を目指して投資を行います。
株の売買における基本的な目的は、一般の商売と同様に、安く買って高く売ることです。したがって、株価が低い時に購入し、株価が急上昇したタイミングで売ることが株式投資のセオリーと言えるでしょう。ただし、株式投資にはリスクが伴い、投資家はそのリスクを十分に理解し、検討しなければなりません。
株式投資に起こりうる3つのリスク
株式投資には、「値下がりリスク」、「流動性リスク」、「倒産リスク」の3つのリスクが存在します。
株式投資における流動性リスク
流動性リスクとは、市場で取引されている株式の量が不足しているため、株を売りたくても売れないリスクを指します。特に、企業の不祥事や上場廃止の危険が迫る企業の株においてよく発生します。
上場廃止が決まると、株式の売買ができなくなります。このため、ほとんどの株主が株を売ろうとする結果、売値がつきにくくなり、株が売れなくなることがあります。一般的に、企業の不祥事などは予測が難しく、流動性リスクについて過度に心配しても意味がない場合が多いです。
株式投資における値下がりリスク
値下がりリスクとは、株価の減少によって生じるリスクです。購入した株が、購入時の株価を下回った場合、投資した金額を回収できなくなります。しかし、株価は会社の業績に関係なく、株の売買によって変動するため、上昇と下落を繰り返すのは避けられません。
個人投資家には、長期的な視点で株価の上昇を見極める能力が求められますが、業績の悪化などにより、株価が急激に下落することもあります。
株式投資における倒産リスク
倒産リスクとは、会社が倒産することによって生じるリスクです。倒産すると、その会社の株は無価値となり、ただの紙切れになってしまいます。しかし、業績が安定している企業の株を選ぶことで、このリスクを回避することが可能です。
紹介したリスクの中で、一般的に最も懸念すべきリスクは、値下がりリスクです。
株式投資でよく見られる失敗例:投資額の増大
株式投資でよく見られる失敗例として、損切りのタイミングを逃すことや、ナンピン投資を繰り返すことで投資総額が膨らんでしまうことが挙げられます。
損切りのタイミングを逃すことによる投資総額の膨張
ナンピン投資の危険性は、損切りのタイミングや株式を手放す時期を逃してしまうことです。株価がいつか上がることを期待して購入を続けるうちに、投資総額が膨らんでしまうことが、ナンピン投資でよく見られる事例です。
前述のケースを例に取ると、もし株価がさらに300円まで下落したとします。この時、1000株を新たに購入すると、計算式は次のようになります:(500円×1000株 + 400円×1000株 + 300円×1000株) ÷ 3000株 = 400円。つまり、平均購入価格は1株あたり400円となります。
この場合、株価が400円に戻れば損失回復できますが、もし株価が上昇しなかった場合、追加で支払った金額は、400円×1000株 + 300円×1000株 = 700,000円となります。安定した企業であれば株価が戻る可能性がありますが、業績が悪化している企業では、株価がさらに下落するリスクが高くなります。
ナンピン投資の意味と特徴
ナンピン投資とは、株価が下落した際に行う投資方法です。新たに株式を購入することで、既存の株式の平均購入価格を引き上げます。そして、株価が再び上昇した際に、損失を早く回復するために用いられます。
例えば、500円の株を1000株購入した場合、株価が400円に下落したとします。この時、新たに1000株を400円で購入すると、合計で2000株を保有することになります。計算式は次の通りです:(500円×1000株 + 400円×1000株) ÷ 2000株 = 450円。つまり、平均購入価格が1株あたり450円になります。
もし株価が450円に戻った場合、1株あたり450円で購入しているため、損失を回収することができます。一方、もし400円の株を購入せずに放置していた場合、最初に500円で購入した1000株は1株あたり50円の損失(500円-450円)となり、合計で50,000円の損失となり、損失回復は難しくなります。
株式投資で基本的に借金を抱えることはない理由
「株で借金を抱えることはあまりない」と感じる方も多いでしょう。実際、その認識は正しいと言えます。基本的に、株式投資で借金を抱えることはありません。購入した株は社会情勢や市場の動きによって1株あたりの価値が変動するため、購入時より価値が下がることがあります。しかし、例えば100万円で購入した株が大暴落して価値がほぼゼロになった場合でも、それ以上に損失を出すことにはならないです。したがって、株を購入してその価値の上下を楽しむだけであれば、借金を抱えるリスクは基本的にありません。
株式投資で借金を抱える4つのケース
なぜ株式投資で借金を抱えてしまう人が後を絶たないのでしょうか。
株式投資は、パチスロやFXほどの博打性はないものの、儲けが出るかどうかは投資した企業の業績に依存するため、一定のギャンブル要素を含んでいます。そのため、一度投資した株が上昇した経験を得ると、「もっと大きな利益を得る方法があるのでは?」と思い、さらに株にのめり込んでいくことがあります。
株で借金を作ってしまう理由は、主に以下の4つです。
- 借金をして株式投資の資金を調達した
- 信用買いで損失を出してしまった
- 追加証拠金の支払いが発生した
- 空売り(信用売り)で損失を出してしまった
これらの理由について、順を追って解説していきます。
借金をして株式投資の資金を調達した場合
市場が伸びると予測して、借金をして多額の資金を投入したものの、予想に反して大暴落が起こり、借金だけが残ってしまったケースです。特に、IPO株(新規上場株)は値上がりする確率が高く人気がありますが、その購入権を得るのは簡単ではありません。
運良く購入権を手に入れたものの、借金してまで投資する人も少なくないですが、資産運用には「100%儲かる」保証はありません。
儲かった分で借金を返済しようと考えたものの、予期せぬ株の暴落が原因で、あっという間に借金地獄に陥ることもあります。
このような状況に陥ると、別の株で一発逆転を狙ってさらに借金を重ね、泥沼にはまる可能性も高くなります。
信用買いで損失を被った場合
信用取引では、手元の資金以上のお金で株を購入することができますが、株価が下落すると、そのマイナス分を借金で補うことになります。
株の取引には、手元のお金だけでなく、信用取引という方法があります。信用取引では、証券会社に保証金(現金や保有している他の上場株式など)を預けることで、その保証金の約3.3倍までの金額で取引を行うことができます。これにより、手元のお金よりも大きな金額で取引できるため、利益が大きくなる可能性もあります。
例えば、手元に100万円があれば、最大で330万円分の取引ができるようになります。一見するとメリットが大きいように思えますが、信用取引では株価が上がっても下がっても、「利息・手数料・管理費」がかかるため、思った以上にプラスにならないことがあります。また、保証金を超える損失が出た場合、手元以上の資金で取引しているため、負債が発生することになります。
そのため、信用取引で大損すると、借金を抱えるリスクが生じることになります。
空売り(信用売り)での損失が発生した場合
信用取引には、信用買いだけでなく空売り(信用売り)という方法も存在します。空売りは、証券会社から借りた株式を売り、株価が下がったタイミングで買い戻して利益を得る方法です。
例えば、証券会社から借りた株式を100万円で売却し、その後株価が70万円に下がった場合、買い戻して証券会社に返すことで30万円の利益を得られます。しかし、株価が100万円で売った後に150万円に上昇した場合、50万円の損失が発生します。
もちろん、値上がりした後に再び下がる可能性もありますが、値段が上昇し続ける限り、損失はどんどん膨らんでいきます。空売りには強制決済がないため、自分のタイミングで買い戻さなければ損失は増える一方です。
もし損失が膨大になり、手持ちの資金で買い戻せない場合、借金をして買い戻しを行う必要があります。
追加証拠金の支払いが必要になった場合
信用取引を行っていた株で追加証拠金の支払いが必要になったものの、手元にその資金がないため、借金をして支払ったというケースです。
信用取引では、損失が出ると保証金を追加で支払わなければならない場合があります。この追加分の資金を「追加証拠金(追証)」と呼びます。損失が保証金の最低維持率を下回った場合に発生します。
例えば、他の上場株式を保証金としていたがその価値が下落したり、信用取引している銘柄に含み損が生じた場合、追加証拠金が必要となります。もし支払えない場合、強制的に決済(損切り)され、結果的に損失が発生します。
このため、追加証拠金が支払えない場合、損切りするか、借金をして入金する以外に選択肢はなくなります。多くの借金を抱える原因として、追加証拠金が関わるケースは少なくありません。
株式投資で借金を避けるための5つの方法
株式投資に限らず、ギャンブルや投資では、一度借金をしてしまうと「何とか取り返さなければ」と考え、過激な方法に手を出すことが多くなります。
株式投資を長期的に楽しむためには、最初から借金をせずに取引を行うことが最も重要です。
ここでは、借金をせずに株式投資を行うための5つの方法を解説します。
損切りの基準を設定する
株式投資はあくまで投資であり、100%の利益が保証されているわけではありません。得をすることもあれば、損失を被ることもあります。
購入した株が「少し下がっただけで、また上がるかもしれない」と思い粘りたくなる気持ちも理解できますが、もしそのまま放置しても株価がさらに下がる一方だと感じた場合、損切りの決断を下すことも投資においては重要です。
自分自身で「購入時より◯%下がったら損切りする」といったルールを設けることで、大きな損失を防ぐことができます。
損切りを遅らせてしまい、株価がほぼ0円にまで下がってしまった場合、その損失を取り戻そうとハイリスクな方法に手を出すことがよくあります。
過度に感情的にならず冷静に対処するためにも、あらかじめ損切りルールを決めておくことを強くおすすめします。
現物取引による株式投資
株で借金を抱える主な原因は、「信用取引」に手を出すことです。
株式投資の基本的な方法である「現物取引」のみを行えば、借金を抱える心配はありません。
現物取引は、手元の資金で株を購入し、株価の変動を見極めて売るかどうかを決める従来の方法です。購入後に株価が下がると、購入時よりも安く売らざるを得ないことがありますが、追加でお金を払うことはありません。
現物取引で借金を避けるためには、「手元の資金以上の株を買わない」ことが重要です。この方法はシンプルで分かりやすく、借金を避けるためにはとても効果的です。
投資は余裕資金で始める
資産運用は誰でも最初は初心者です。
初めのうちはコツを掴むのが難しく、損をしてしまうこともあります。
もし、人生を逆転させるために株式投資を始めた場合、少しのマイナスが続いただけであっという間に資金が尽きてしまう可能性もあります。
そのため、最初は余裕資金で投資を始めることをおすすめします。極端に言えば、投資した金額がゼロになっても問題ない程度のお金で始めるのが理想です。
投資対象を分散させる
株式投資の銘柄を複数選んで投資対象を増やすことも効果的な方法です。
投資対象を分散させる最大の利点は、1つの株が値下がりしても他の株で損失を補える可能性があることです。
もし手元のお金をすべて1つの銘柄に投資した場合、その株の動きにすべて依存することになります。例えば、100万円分の株を購入した場合、その株が50%下落すると資産は50万円になってしまいます。
こうなった場合、50万円の損切りをするか、株価が上がるまで保有し続けるしか選択肢はありません。
投資対象を増やすことで、複数の株がそれぞれ上がったり下がったりし、リスクを分散させながら株式投資を楽しむことができます。
また、株によっては株主優待券をもらえるものもあり、優待券目当てで複数の株を購入する楽しみもあります。
ミニ株や定額投資サービスを活用する
投資と聞くと、元手がある程度必要で、ハードルが高く感じられることが多いです。
株は100株から購入するのが一般的で、例えば1株5,000円の株を購入する場合、最低でも50万円を準備しなければなりません。これだけの余裕資金を用意するのは、かなり難しいかもしれません。
しかし、最近では少ない元手で株式投資を始められるサービスが増えてきており、ミニ株なら1万円程度から購入できるようになっています。
予算に応じて投資を行えるため、「借金は避けたいけれど株式投資を始めてみたい」と考えている方には、こうした選択肢を検討するのが良いでしょう。
株式投資で失敗しやすい人の特徴とその行動心理
株式投資で失敗する人の特徴と、株式投資における危険な行動心理についてまとめました。
失敗しがちな人に共通する3つの特徴
株式投資で失敗する人には、共通する特徴があります。
生活費を投資資金に回す
株式投資で失敗する典型的な例の一つが、生活費を投資資金に回すパターンです。投資をするために生活費を削ることで、投資に対する期待が大きくなりすぎます。期待値が高くなると、成功するまで続けるという考えにとらわれ、生活資金を超えて借金をしてまで投資を続けるというケースも少なくありません。
結果を急ぎすぎる傾向
投資を始めたばかりの人によく見られるのが、最初から高い効果を期待するケースです。結果を急ぐあまり、初めから高額な金額を投じるため、早い段階で失敗することがほとんどです。株式投資はビジネスであり、利益と損失を長期的な視点でじっくり検討していく必要があります。
投資をギャンブルと勘違いする
株式投資を行うにあたり、ビジネスとして捉えることが非常に重要です。投資で成功している多くの人々は、投資金額に対する費用対効果をきちんと検証し、得られた利益を次の運用資金として活用しています。そのため、ギャンブルと混同している人は成功しづらいのです。
ギャンブルと勘違いしている多くの人は、得た利益を運用資金として使うのではなく、あぶく銭のように消費してしまい、投資で得た利益に目を向けがちです。
株式投資におけるリスクを伴う心理的行動
株式投資では冷静な判断力が求められますが、感情と行動は切り離せません。株式投資における悪影響を及ぼす行動心理をまとめました。冷静な判断力を養うためにも、人間の行動心理を理解することが重要です。
追認バイアスとは?投資における自己正当化の心理
人は自分の行動を正当化したいという傾向があります。自分が選んだ道が正しいと信じるあまり、都合の悪い情報を無視しがちです。しかし、この心理は投資の世界では大きな障害となります。これを「追認バイアス」と呼び、投資した株が間違いないと信じるあまり、肯定的な情報しか受け入れなくなる行動パターンです。その結果、不良債権であるにもかかわらず、見切りをつけられずに手放せなくなることがあります。
プロスペクト理論とは?株式投資における心理的影響
人間の心理状態は状況によって異なり、その心理状態が行動パターンに大きく影響することは明らかです。ここでは、2つの行動パターンを2つの異なるシチュエーションで見ていきましょう。
- 無条件で10万円が貰える場合
- 半分の確率で20万円が貰える場合
この2つの選択肢を提示された場合、どちらを選びますか?実は、借金があるかないかで選択が変わるのが人間の心理です。借金がなければ、ほとんどの人は「無条件で10万円を貰える」方を選ぶでしょう。しかし、もし20万円の負債を抱えている場合、ほとんどの人が「半分の確率で20万円が貰える」方を選びます。
このように、人は損失を抱えるとリスクを顧みず、時には無謀な選択をしてしまうことが分かります。この心理は投資の世界でも同様で、損失を取り戻そうと必死になる人が多いのもこの行動心理に起因しています。
所有効果とは?株式投資における愛着がもたらすリスク
必要がないものでも、長年使い慣れたものを捨てるのが難しい経験をしたことがある人は多いでしょう。実は、株式にも同様の現象が起こり、これを「所有効果」と呼びます。株式に対する愛着が強くなるあまり、株価が暴落しても損切りができず、そのまま保持し続けてしまうケースがよく見られます。
初心者必見!失敗しないための株式投資の始め方
株式投資を始めたばかりのビギナー向けに、失敗を避けるための取り組み方を紹介します。
株式投資を始めるためのステップガイド
株式投資を始めるための流れは、次のようになります。
ステップ1:投資資金の準備
もちろん、お金がなければ投資は始められません。安価な銘柄なら5万円から始めることもできますが、最低でも20~30万円を準備して始めるのが理想的です。
投資予算の設定
投資資金を準備する際には、予算の設定が欠かせません。運用期間を考慮し、準備した資金の中から毎月の予算を決定しましょう。
ステップ2:投資する銘柄の選び方
資金の準備が整ったら、次に投資する株式を選定します。
ステップ3:利益目標の設定
何度もお伝えしますが、株式投資はビジネスであるため、目標設定は不可欠です。投資における目標とは、具体的な目標金額を指します。この目標を達成するためには、利益と損失を慎重に検証し、その上で目標達成に向けた戦略を逆算して計画する必要があります。
ステップ4:損切り基準(損失の上限)の設定
損切りができずに投資総額が膨らむリスクについてはすでに触れました。投資総額が過大にならないようにするためにも、損切りの基準を明確に定めておくことが重要です。
ステップ5:株価と一株利益のチェック
投資先を選ぶ際には、まず投資対象となる企業の株価と一株あたりの利益を確認することが大切です。株価は購入時の株の価格を指し、一株利益は一株あたりの利益を示します。この一株利益は、その株の購入価格を上回るものであるべきです。一株利益は「企業の純利益÷発行株数」で算出されます。
ステップ6:投資の判断
株価と一株利益の関係を示す指標として株価純益率があります。株価純益率は「株価÷一株利益」で計算されます。株価に変動がない場合、一株利益が増加すると、株価純益率は低下します。つまり、株価が変動しない中で株価純益率が減少している場合、その企業の株価が上昇する可能性があると言えます。そのため、過去の株価純益率の推移を参考にして、投資先を選ぶことが重要です。
銘柄選びの方法
銘柄の選定方法について解説します。
身近な商品やサービスを基に銘柄選定する
日常的に自分が使っている商品やサービスを基に、投資する銘柄を選ぶと良いでしょう。膨大な企業の中から選ぶのは難しいため、ターゲットを絞ることで、初心者にとって有効な方法となります。
調査の手順
企業の従業員数、店舗数、時価総額については、会社四季報や日経会社情報を参考にして調べてください。
銘柄選びのメリット
身近な商品やサービスを基に銘柄を選ぶメリットは、常に注意を向けやすい点にあります。自分が興味を持つものを選ぶことで、モチベーションを維持しやすく、日常的に使用することで商品の質にも敏感になれます。その結果、その分野の流行にも自然と敏感になれるためです。
企業調査(取り扱い商品を扱う企業の調査)
ターゲットをある程度絞り込んだら、次は企業の数値的な調査を行います。企業の規模や業績を具体的な数値で把握することで、さらにターゲットを絞り込むことができます。急激な株価の下落や減配、無配のリスクを避けるためには、安定した銘柄を選ぶことが重要です。
競争の激しさ
競争が激しい商品やサービスは、変動が多いため将来的な安定性を担保するのが難しくなります。ですので、株式投資初心者の方には、競争が少ない分野の銘柄を選ぶことをお勧めします。
安定した企業を選ぶための基準
会社の規模を測る指標としては、従業員数と店舗数があります。これらの数が他社と比較して多い企業は、その分野で大きな存在となっていると言えます。また、株価の安定性を把握するためには、時価総額の確認が重要です。時価総額はその会社の利益や資産価値を示す指標であり、1兆円以上を目安にチェックすることをお勧めします。
投資のための6つの基本ルール
投資を行う際の6つのルールを定めました。これから投資を始める方は、ぜひ参考にしてみてください。
余剰資金での投資運用
先程もお伝えしましたが、投資で最も危険なのは、生活費を投資資金に回してしまうことです。投資はビジネスの一環であり、冷静な判断力が求められます。冷静さを保つためにも、生活に影響を与えない範囲で投資を行うことが大切です。
現物取引のみで投資を行う
株式投資には、現物取引と信用取引の2つの方法があります。現物取引は、自分の資金のみを使って行う投資であり、信用取引は、所有する金額以上の資金を借りて投資する方法です。言い換えれば、信用取引は借金をして投資することと同じです。現物取引は損失が出てもその範囲内で済むため、株式投資に不安がある初心者には現物取引で投資を始めることをお勧めします。
現物取引:自分の資金のみで行う投資
信用取引:保有額以上の資金を使った投資
利益は翌期の運用資金として活用する
配当金や株式売買で得た利益は、単なる臨時収入ではありません。ビジネスとして継続していくためには、株式投資から得た利益を来期の予算として、自己の給与と次期の運用資金に分けて管理することが重要です。
予算内で投資を収める
人間の心理では、損失を取り戻すために過剰にお金を投入しがちです。取り返しのつかない状況を避けるためにも、あらかじめ設定した予算内で投資を行うことが重要です。
株を売却するタイミングを設定する
株式を売るタイミングは、目標株価や目標利益を達成した時です。これらの達成は、ビジネス目標をクリアしたことを意味します。せっかく目標を達成したのに、さらに保有し続けると、株価が下落した際に対応が難しくなります。決断が鈍ると、無駄な投資を繰り返して損失を拡大させてしまうこともありますので、目標達成後は株を売却することをお勧めします。
株で借金を抱えた場合の対処方法
「ムキになってお金を元手以上に投資してしまった」「追加証拠金の支払いや信用買いで大きな損失を抱えてしまった」など、投資に失敗して借金をしてしまった場合、地道に返済していくことが必要です。なお、追加証拠金が支払えない場合、取引業者によっては遅延損害金が発生します。未払いの金額に対して日割りで加算されるため、金額が大きくなる前に、借金をしてでも早急に返済することが求められます。もし未払いを放置していると、最終的には裁判所から一括請求が届き、差し押えに繋がる可能性があります。自力での返済が難しいと感じた時点で、債務整理を検討するのが良いでしょう。この章では、債務整理の種類についてご紹介します。
投資を中止し、借金返済計画を立てる
まず、今後の投資は潔く諦めることが重要です。最優先すべきは、借金の返済です。自分の収入と生活費を元に、返済可能な金額を計算し、計画的に借金返済を進める必要があります。
個人再生を利用して借金の返済額を減少させる
個人再生は、借金を5分の1から10分の1程度に減らせる手続きです。この方法のメリットは、財産を手放さずに借金を減額できる点で、特に車や持ち家など大きな財産がある場合に有効です。また、個人再生は投資関連の借金にも適用できるため、自己破産よりも認可される可能性が高いのが特徴です。自己破産を選ぶと、必要最低限の財産を除いて全て失うことになるため、株式投資をしている方や本業がある方で、少額でも支払える場合は個人再生を選ぶ方が良いでしょう。ただし、個人再生は手続きに時間がかかり、複雑で専門的な知識が必要ですので、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
自己破産で全額の借金を免除してもらう方法
自己破産は、債務整理の中で最終手段です。返済がどうしても不可能な場合に利用する手続きであり、裁判所の認可を得ることで借金が免除されます。株で借金をしても、自己破産が認められればその借金から解放されることができます。しかし、その反面失うものも多く、生活に必要な物(衣服、寝具、家具、家電など)や99万円以下の現金、20万円未満の価値のある財産など、法律で差押えが禁止されているもの以外はすべて手放さなければなりません。
重要な点として、自己破産の影響が大きいため、投資での借金はギャンブルによる浪費とみなされることがあります。そのため、自己破産が認められるには、過去の行動にしっかり反省していることを示し、今後真面目にやり直す決意を表明することが求められます。自己破産後は、株式投資を続けることはほぼ不可能になります。
さらに、自己破産手続きは通常のものよりも煩雑になる可能性が高く、管財が行われることも多いため、手続きに時間と労力がかかることを覚悟しておくべきです。
免責不許可事由に該当する可能性について
ギャンブルや風俗など、借金を作った理由が不当である(免責不許可事由)と裁判所に判断されると、自己破産が認められないことがあります。株式投資による借金も、不当とみなされる可能性があります。自己破産や免責不許可事由に関しては、以下の記事もご参照ください。
任意整理で借金の返済負担を軽減する方法
任意整理とは、債権者(金融機関)と交渉し、返済額を減額する手続きです。司法書士や弁護士などの専門家と債権者が交渉し、今後の返済計画を決定するため、債務整理の中では比較的軽い方法といえます。返済額の減額は、借金自体の額ではなく、遅延損害金や利息、手数料など、借金以外の費用を減らすための交渉です。そのため、元金の完済が可能であることが前提となります。
3年から5年の間で完済できる額であれば、任意整理を選ぶことも検討に値するでしょう。
株の借金を他の借金で返済することは避けるべき理由
借金が増え続けると、元金だけでなく利息も膨らんでいきます。返済が滞ると、督促が厳しくなり、最終的には裁判所にまで発展することも考えられます。このような状況に陥ると、今ある借金を返済するために、他の金融機関から借りて返すという考えに至ることがあります。しかし、この負のスパイラルが借金地獄の始まりです。督促が進むと、別の借金で返済することを繰り返し、返済の見通しが立たなくなります。
最も危険なのは、借金返済のために全額を株に投資し、さらに損失を膨らませてしまうことです。このように、焦りから投資をすることで状況が悪化することが多いです。投資はあくまで余裕資金で行うものであり、人生逆転を狙って投資することではありません。このような場合は、株の借金を別の借金で返すことは絶対に避けるべきです。
株で借金を抱えたら、まずは専門家に相談しよう
株で借金を避けるためには、主に以下の2つのルールを守ることが重要です。
- 手元のお金以上の株は購入しない
- 信用取引には手を出さない
とはいえ、株式投資に慣れてきた人にとって、ローリスクな投資は物足りなく感じることもあります。しかし、ハイリスク・ハイリターンの方法に手を出すことで、一気に借金地獄に陥る可能性があります。
多額の借金を抱え、将来の計画が崩れないようにするためにも、無理なく楽しめる範囲で株式投資を行うことが大切です。
まとめ
株式投資を始める際には、できるだけ失敗を避けたいと考えるものです。しかし、借金地獄に陥ってしまうケースも少なくないため、株式投資を行う際は計画的に進めることが重要です。この記事が、株式投資を始めた方や、過去に失敗を経験した方々のお役に立てることを願っています。