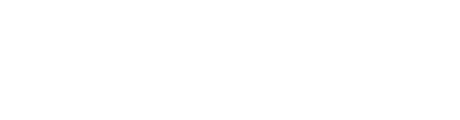※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
債務整理とは?詳細とメリット・デメリットを徹底解説
目次
借金問題を解決するための債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求の4つの方法があります。
これらの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、適したケースとそうでないケースがあります。
自分の状況に合った債務整理を選ぶことで、借金問題を効果的に解決できますので、債務に悩んでいる方はぜひこの記事を参考にしてください。
債務整理の種類とその違い
債務整理とは、借金(債務)の元本を減らしたり、利息をカットしたりすることで、借金を無理なく返済できるようにする手続きです。手続きの内容によっては、借金自体が免除される場合もあります。
債務整理には大きく分けて3種類があり、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
の3つがあり、いずれも法律で認められた合法的な手続きです。
対象となる借金は、銀行や消費者金融からの借金だけでなく、ATMなどで利用するキャッシングやカードローン、クレジットカードのリボ払いによる借金なども含まれ、これらの借金を圧縮することができます。
債務整理の種類:任意整理、個人再生、自己破産の違い
債務整理には種類によって手続きの内容や効果が異なります。
以下では、任意整理、個人再生、自己破産の3つの債務整理方法と、よく併用される過払い金請求を含めた4つの手続きをそれぞれ解説します。
任意整理とは、借金返済を軽減する手続き
任意整理とは、カード会社や消費者金融などの債権者と直接交渉し、借金を無理なく返済できるように新しい返済方法を決定する手続きです。従来の返済方法では返済が難しくなった場合に、利息をカットして返済可能な状況にします。
任意整理を受け入れるかどうかは債権者の判断に依存するため、成立には双方の合意が必要です。また、任意整理の内容についても理論的には交渉による決定です。
債権者が合意しない限り、任意整理は成立しませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、任意整理を成功させる可能性が高まります。任意整理では、将来利息をカットし、元金を3〜5年程度の期間で返済できるように調整します。
個人再生とは、大幅な借金減額を目指す手続き
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額して無理なく返済できるようにする手続きです。
任意整理が裁判所を介さずに行えるのに対し、個人再生は必ず裁判所を通して手続きを進めなければなりません。個人再生は時間や費用がかかるものの、その分借金を大きく減額できるのが特徴です。
個人再生を利用すると、借金は5分の1から10分の1程度に減額され、原則として3年間(最長で5年間)で返済することが可能となります。さらに、一定の条件を満たせば、自宅を手放さずに個人再生を行うこともできます。
ただし、個人再生を利用するには、返済計画に基づいて十分に返済できる見込みがあり、返済できる収入があることが前提となります。
自己破産とは、借金の免除を受ける手続き
自己破産とは、裁判所に債務免責の申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。この手続きは、個人再生と同様に必ず裁判所を通して行わなければなりません。
個人再生が借金の免除を受けないのに対し、自己破産は免責が認められれば、借金自体を返済する必要がなくなる点が特徴です。
しかし、自己破産は借金免除という強力な効果がある一方で、自宅を含む価値のある財産を基本的に手放さなければならないというデメリットもあります。
過払い金請求で払い過ぎた借金を取り戻す方法
厳密には債務整理とは異なりますが、借金(債務)を整理する方法の一つとして過払い金請求があります。
過払い金請求とは、消費者金融や信販会社などに支払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求める手続きです。過払い金が発生している場合、返還請求を行えば、その返還された金額を他の債務の返済に充てることができます。
以下の条件に該当する場合、過払い金が発生している可能性が高いため、専門家に相談することをおすすめします。
- 借金をしたのが2010年6月17日以前
- 借金の金利が年20.0%以上
- 現在借金を返済中、または完済してから10年以内
債務整理のメリットとデメリットを紹介
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、これら全ての方法に共通するメリットとデメリットについて解説します。
債務整理全般に共通するメリットとデメリット
全ての債務整理に共通するメリットとデメリットについて解説します。
債権者からの取り立てや督促が停止する
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、カード会社や貸金業者などの債権者からの取り立てを停止することができます。
借金問題で悩んでいる中で、債権者からの執拗な取り立てに対応しなければならないことは大きなストレスの原因です。返済ができずに苦しんでいる上に、取り立てによって心身がさらに消耗するのは非常に辛いものです。
弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知という書面を債権者に送付することになり、これによって取り立ては一時的に(手続きが完了するまで)停止されます。
受任通知とは、借金をした人が弁護士などの専門家に債務整理を依頼し、その専門家が受任したことを債権者に通知する書面です。
受任通知が債権者に届いた場合、カード会社や貸金業者などは、法律に基づいて取り立てを止めなければならないと規定されています。この取り立ての停止により、精神的な余裕が生まれ、借金整理に前向きに取り組むことができるようになります。
ただし、債務整理の方法に共通するデメリットは、債務整理を行った事実が信用情報機関に登録されることです。これにより、一定期間、クレジットカードやカードローンの審査に通らなくなったり、家や自動車のローンが組めなくなったりします。
以上が債務整理方法に共通するメリット・デメリットです。次に、任意整理、個人再生、自己破産の各手続き方法について、それぞれのメリット・デメリットを確認していきましょう。
借金の減額または免除の効果
全ての債務整理に共通する効果として、借金の返済額が減少する(または返済が免除される)点があります。
どの程度借金が減額されるかは、方法や状況によって異なりますが、一般的に、任意整理よりも個人再生の方が減額の効果が大きいとされています。
自己破産の場合、未納の税金など一部の債務を除き、借金自体が免除されるため(返済しなくてもよい)、非常に強力な効果を持っています。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリットとデメリットを紹介します。
任意整理のメリット
借金の理由に関わらず手続きを進めることができる
過払い金がある場合、その分だけ元本を減額することができる
将来の利息をカットすることで、元本のみの返済にすることが可能な場合がある
やむを得ない事情があれば、特定の借入先とだけ交渉することができる
保証人(連帯保証人)への影響を避けて手続きを進めることができる
基本的に、自宅や車を手放さずに手続きを進めることができる
家族や勤務先に比較的知られることなく手続きを行える
任意整理のデメリット
任意整理に応じるかどうかは基本的に債権者の自由である
個人再生や自己破産に比べて大幅な減額にはならない
信用情報に記載される
任意整理は、銀行や消費者金融などの債権者と個別に交渉する手続きです。これは当事者同士で返済計画を見直す交渉であり、裁判所を通さずに行われるため、個人再生や自己破産で発生するような財産処分に関する法的な制約はほとんどありません。
そのため、任意整理では自宅や車を保ちながら返済計画を見直すことができ、また、特定の借入先とだけ交渉することも可能です(ただし、特定の借入先に対してのみ返済をしないことは偏頗弁済とみなされるため、やむを得ない事情がある場合に限られます)。このように、任意整理は比較的自由度が高い手続きです。
ただし、債権者が交渉に応じるかどうかも自由であるため、任意整理に応じてもらえないこともあります。また、大幅な減額には債権者が応じないことが多いため、個人再生や自己破産などの法的手続きに比べると、減額幅は小さくなるのが一般的です。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリットとデメリットを紹介します。
個人再生のメリット
借金の元本を5分の1から10分の1程度に減額できる
借金の理由に関わらず手続きを進めることができる
基本的に自宅を手放さずに済む
手続き中は資格や職業に制限がかからない
個人再生のデメリット
保証人(連帯保証人)が責任を負うことになる
手続きが複雑で、時間と費用がかかる
信用情報に記録される
個人再生は、裁判所を通じて行う債務整理手続きであり、任意整理と比較して大幅な借金の減額が期待できます。この手続きは法律に基づいて進められ、債権者の同意がなくても借金の減額が可能です。
ただし、個人再生は借金の返済を前提とした手続きであり、返済が免除(免責)されるわけではありません。そのため、返済を続けられるだけの収入を確保できる見込みが必要です。
さらに、個人再生を行うと、債務の支払義務が保証人に移転するため、善意で保証人を引き受けてくれた方に負担をかける可能性があります。手続きを進める際には慎重に検討し、保証人への事前説明が欠かせません。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットとデメリットを紹介します。
自己破産のメリット
税金など一部の債務を除き、借金自体が免責される
無職や主婦でも手続きを行うことができる
自己破産のデメリット
家など一定以上の価値がある財産は手放さなければならない
手続き中は資格や職業に制限がかかる
免責が認められない場合もある
手続きが複雑で、時間や費用がかかる
信用情報に記録される
自己破産は、全ての借金の免責を受ける手続きであり、つまり借金をゼロにすることができます。
強力で明確なメリットがある一方、免責許可を得るための調査や財産処分に関するルールは非常に厳格です。価値のある財産(家や車など)は処分しなければならず、職業制限も生じます。
債務整理後の日常生活への影響
債務整理を行った場合、日常生活にどのような影響があるかについて解説します。
債務整理が結婚に与える影響はあるか?
債務整理を行うことで、結婚生活に直接的な影響があるわけではありません。例えば、夫が債務整理をしたことだけが理由で、妻が自分の名義でクレジットカードを使えなくなったり、ローンの審査に通らなくなったりすることはありません。
信用情報には基本的に本人の情報が記載されるため、妻の信用情報は、夫本人が延滞などの事故情報を持っているかどうかに基づいて判断されるだけです。
ただし、妻に十分な収入や返済能力がない場合、妻名義でカードやローンを審査に通すことが難しいことがあります。その場合、夫が債務整理を行うことで、実質的に家族としてカードを作ったりローンを組んだりできなくなる可能性もあります。
債務整理が結婚生活に与える影響について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
車や家を手放す場合がある
車や家は重要な財産ですが、債務整理の方法によっては、車や家を手放さなければならない場合があります。以下の表をご覧ください。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 車 | 手放す必要なし | ローンが残っている場合、手放す必要あり | 20万円以上の価値がある場合、手放す必要あり |
| 家 | 手放す必要なし | 特例が適用されれば手放す必要なし | 手放す必要あり |
上記の表からわかるように、個人再生や自己破産では、状況によって車や家を手放さなければならない場合があります。
一方、任意整理の場合、返済に問題がなければ基本的に車や家を引き上げられることなく、そのまま所有し続けることができます。
クレジットカードやローンが利用不可になる
債務整理を行うと、その情報が事故情報として信用情報機関に登録されます。これは一般的にブラックリストに載ると言われるものです。
信用情報機関は、返済履歴などの信用情報を管理し、加盟しているクレジットカード会社やローン会社などの照会に応じて、信用情報を提供する機関です。
クレジットカードやカードローンの審査では、信用情報機関への照会が行われます。照会を通じて債務整理をした事実が確認されるため、クレジットカードやローンの審査に通ることがほぼ不可能になります。
住宅ローン、自動車ローン、携帯電話の分割払いが一時的にできなくなる
住宅ローン、自動車ローン、携帯電話(スマートフォン)の本体の分割払いなどでも、信用情報機関に照会が行われるのが一般的です。これにより、住宅や自動車の購入ローンを組むことができなくなったり、携帯電話を分割払いで購入できなくなることがあります。
なお、信用情報機関に事故情報が掲載される期間は限られており、通常は5〜10年程度です。この期間が過ぎると、事故情報は削除されるため、その後はクレジットカードの新規作成や各種ローンの利用が可能になります。
債務整理が職場や仕事に与える影響
債務整理をしたことが職場や仕事に影響を与えるのではないかと心配するかもしれませんが、基本的に債務整理を行ったことが仕事や職場に知られることはありません。
特に、裁判所を通さない任意整理の場合、職場で任意整理を行ったことが明らかになることはほとんどないと言えるでしょう。
個人再生や自己破産が官報に掲載されても、職場への影響は少ない
個人再生や自己破産は裁判所での手続きであり、その結果として官報に掲載されます。しかし、一般的に会社や職場が官報を確認することはほとんどないため、個人再生や自己破産が仕事や職場に影響を与える可能性は基本的に低いです。
ただし、以下のような例外的な状況では、職場や仕事において債務整理をしたことが知られる可能性があります。
- 仕事の取引先や職場が債権者であり、その債務整理が対象となる場合
- 弁護士や警備員など、自己破産中に業務に制限がかかる職業に就いている場合
債務整理の手続きと期間の目安
債務整理には以下の4種類があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
それぞれの手続きには流れや完了までにかかる期間が異なります。まずは、債務整理の種類ごとに詳しく解説していきます。
任意整理の手続きの流れと完了までの期間
任意整理とは、借金の利息を減額して完済を目指す手続きであり、裁判所を通さずに行う債務整理の一つです。特定の債権者(借金の相手)を選んで手続きを進めることができ、生活に支障をきたさない範囲で借金を整理することができます。
手続きの進行過程
任意整理は個人でも手続きを行うことができますが、一般的には以下の専門家に手続きの支援を依頼することがほとんどです。
- 弁護士
- 司法書士
- 法テラス
正式に依頼した後、債務者(借金した本人)が行うべきことはほとんどなく、債権者とのやり取りはすべて弁護士や司法書士が代行してくれます。
任意整理の期間中、何もすることがなく不安に感じる方もいるかもしれませんが、ほとんどの弁護士事務所などでは定期的に、手続きの進捗状況を知らせてくれるため、安心して任せられます。任意整理は次のような流れで進みます。
- 弁護士・司法書士・法テラスに手続き援助を依頼
電話やメールでアポイントを取った後、面談にて相談し、依頼することが決まったら「委任契約書」を交わして正式に手続きを依頼します。 - 受任通知の発送・取引履歴の開示請求
弁護士や司法書士が債権者に、任意整理を行うことを通知する「受任通知」を送付します。同時に、債務者の過去の返済履歴や残高、返済状況を確認できる「取引履歴」の開示請求も行います。 - 債務額の調査
開示された取引履歴に基づき、借金の総額を調査します。また、利息制限法に基づいて法定上限金利を確認し、借金の減額や過払い金の発生についても調べます。 - 引き直し計算の実施
調査結果を精査し、利息の再計算を行う「引き直し計算」を開始します。 - 過払い金返還請求
過払い金が発生していることが確認された場合、過払い金の返還請求を行い、返金される可能性があります。 - 和解案の作成と債権者との交渉
引き直し計算や過払い金の額を基に、1ヶ月ごとの返済可能金額を提示し、和解案を作成します。この和解案をもとに債権者と交渉を行います。 - 和解契約の終結
交渉が成功し、債権者との合意が得られれば和解契約が成立し、合意書(和解契約書)を交わして契約が終了します。 - 返済再開
和解契約で定められた内容に基づき、3年(最長で5年)をかけて借金を返済していきます。借金の残高が確定した後は、通常3年間で返済が進みますが、もし3年での返済が困難であれば、最長で5年間の返済期間に延長することが可能です。
手続き完了までの期間
任意整理が完了するまでの期間は、以下のようになります。
- 受任通知の発送:数日
- 開示請求:数週間~1カ月
- 引き直し計算:1~2週間
- 和解案による交渉:1~3カ月
実際に弁護士や司法書士に任意整理を依頼してから手続きが全て終了するまでには、最低でも3カ月、場合によっては6カ月程度かかることがあります。ただし、債権者が多い場合や書類の準備に時間がかかると、さらに期間が延びる可能性があります。
また、過払い金が発生していることが判明し、過払い金の交渉が債権者との間で裁判に発展した場合、6カ月から12カ月(1年)ほどかかることもあります。
個人再生の手続きの流れと完了までの期間
個人再生とは、裁判所を通じて「民事再生法」のもとで、個人の借金を減額する手続きです。ローン支払い中のマイホームを手放さずに済むという利点がある一方で、収入や借金の総額に一定の条件が設けられています。
個人再生には、債務者の背景に応じて以下の2種類があります。
- 小規模個人再生
個人再生の基本的な形態で、民事再生法に基づいた基準により借金が減額されます。 - 給与所得者等再生
毎月安定した収入が見込まれ、将来にわたって返済が可能と判断されるサラリーマンなどの債務者が対象です。無担保債権が5000万円以下であれば、再生計画に基づき未返済の借金を免除してもらえる特例があります。
参考:個人再生手続き利用にあたって|仙台地方裁判所
小規模個人再生は個人再生の基本形態で、安定した収入があるサラリーマンが無担保の借金5000万円以下の場合、特例として給与所得者等再生が適用されることがあります。
手続きの進行過程
個人再生の手続きは複雑で、自己で行うのは難しいため、ほとんどの人が弁護士や司法書士の支援を受けています。借金問題を早期に解決したいと考えるなら、専門家に依頼することをおすすめします。
個人再生の流れは以下の通りです。
- 弁護士・司法書士への依頼
弁護士事務所や司法書士事務所にアポイントを取り、必要書類を持参して相談します。依頼することが決まれば、「個人再生委任契約」を結び、正式に手続きを依頼します。 - 受任通知の発送・取引履歴の開示請求
受任通知を債権者に送ることで、借金の督促や取り立てが止まり、銀行口座が凍結されます。同時に、過去の返済履歴や残高を確認できる「取引履歴」の開示請求を行います。 - 引き直し計算
取引履歴を元に、利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、過払い金が発生していれば返還請求も行います。 - 申立書類の準備
債務者の家計や収支、財産・資産を調査し、それに基づいて個人再生申立書類を準備します。調査結果により「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらが適切かを決定します。 - 個人再生の申立て
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立書類を提出します。 - 個人再生委員の選出・面談
提出された書類を基に、裁判所が債務者の財産状況をチェックしたり、再生計画に関するアドバイスを行う「個人再生委員」を選出します。選出後、約1週間以内に面談が行われます。 - 履行テストの開始
債務者の返済能力を確認するため、約6カ月間の「履行テスト」を開始します。このテスト期間中に返済が遅れたり滞った場合、個人再生が認められないことがあります。 - 再生手続きの開始
個人再生委員との面談で問題がなければ、裁判所が個人再生手続きを開始する決定を下します。 - 債権届出・債権認否一覧表の提出
裁判所から貸金業者に「再生手続開始決定書」と「債権届出書」が送付され、貸金業者はそれを確認後、6週間以内に債権届出書を裁判所に返送します。同時に、債務者は「債権認否一覧表」を裁判所に提出します。 - 再生計画案の提出
債務者は、返済総額、方法、期間を記載した「再生計画案」を裁判所に提出します。 - 意見聴取・書面による決議
給与所得者再生の場合は意見聴取が行われ、小規模個人再生の場合は書面による決議が行われます。債権者の過半数または借金総額の1/2以上が不同意の場合、個人再生は認められません。 - 再生計画案の認可・不認可決定
裁判所が再生計画案通りに返済できるかを判断し、認可または不認可を決定します。 - 再生計画案に基づく返済の再開
裁判所が再生計画案を認可した後、返済が再開されます。返済期間は原則3年、最長5年となり、返済スパンは毎月、二カ月に一度、または三カ月に一度のいずれかになります。
再生計画案が認可された翌月から返済が始まり、返済期間は3年が基本ですが、最長5年まで延長することも可能です。
手続き完了までの期間
個人再生が完了するまでの期間は以下の通りです。
- 受任通知の発送から口座凍結まで…1~3カ月
- 必要書類の準備…1~2カ月
- 個人再生委員の選任・面談…約2週間
- 履行テスト…原則として6カ月間
- 個人再生手続き開始決定…申立から1か月後
- 再生計画案の提出…申立から2~4カ月後
- 再生計画案の認可・不認可…申立から5カ月後
裁判所によって手続きにかかる期間は異なりますが、東京地方裁判所の場合、申立から個人再生の認可・不認可決定までおよそ6カ月程度かかります。ただし、個人再生委員の選出がない裁判所では、期間が4~5カ月に短縮されることがあります。
弁護士事務所を選び、依頼後に必要書類を集める準備を含めると、トータルで8カ月から1年ほどかかると見込んでおいた方がよいでしょう。
参考:破産・個人再生申立ての実務|東京三弁護士会研修会より
自己破産の手続きの流れと完了までの期間
自己破産は借金が免責される手続きですが、住宅や車などの資産はすべて債権者への支払いに充てられ、職業や資格に制限がかかるなど、いくつかの不自由を強いられることもあります。それでも、借金が膨れ上がった債務者にとっては、債務整理の最終手段となる重要な手続きです。
自己破産には次の2種類があり、それぞれ手続きの方法や期間が異なります。
- 同時廃止
債権者に配当できる財産がない場合に選ばれる方法です。この方法では、破産管財人による財産調査や分配が不要なため、手続きが短期間で完了します。裁判所に支払う手数料や予納金も最低限に抑えられます。 - 管財事件
債務者に財産(33万円以上の現金や20万円以上の価値のある資産)がある場合や、免責不許可事由(ギャンブル、株取引、浪費など)がある場合に適用されます。破産管財人による調査が行われるため、手続きに時間がかかり、費用も高額になります。
参考:自己破産手続きの2つの種類!同時廃止と管財事件の違いを解説|弁護士法人東京新宿法律事務所
手続きの進行過程
自己破産には前述の2種類がありますが、ここでは主に同時廃止手続きの流れについてご説明します。
- 弁護士に依頼
債務整理に詳しい弁護士に相談し、正式に依頼する際に着手金を支払います(分割払いも可能)。 - 受任通知の発送・取引履歴の開示請求
弁護士が債権者に受任通知を送付します。同時に、取引履歴の開示請求を行い、この手続きにより債権者からの取り立てが停止します。 - 引き直し計算を実施
受け取った取引履歴を基に、利息制限法に従って引き直し計算を行い、債務額を確定させます。 - 自己破産申立て
準備した書類を基に、弁護士が申立書や陳述書を作成し、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出して自己破産の申立てを行います。 - 裁判所での面談
裁判官、弁護士、債務者の3者面談が行われ、自己破産に至った経緯を説明します(本人の出席が不要な場合もあります)。 - 破産手続開始決定・同時廃止決定
内容に問題がなければ、破産手続開始と同時廃止の決定が出されます。 - 免責審尋
裁判所での面接が行われ、弁護士と一緒に裁判官との面談が行われます。 - 免責許可決定
面接から1週間後に免責許可決定が下されます。 - 免責許可決定の確定
免責許可決定から約1ヶ月後に法的に免責が確定します。
管財事件の場合、6. 破産手続開始決定から8. 免責許可決定の間に以下の手続きが追加されます。
7-1. 破産管財人の専任
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が専任されます。
7-2. 管財人面接
裁判所での面接後、1〜2週間以内に管財人(弁護士)との面接が行われ、借金の詳細、理由、時期、収支、財産の詳細などについて質問されます。
7-3. 債権者集会・財産の換価および配当
破産手続き開始決定から約3カ月後に債権者集会が開催され、破産管財人が配当の見込みなどを報告します。財産の換価(現金化)や債権者への配当が完了していれば、1回の集会で終了します。
上記の流れは弁護士によって多少異なる場合があるため、詳しくは依頼先の弁護士事務所に確認してください。
手続き完了までの期間
自己破産の免責許可決定確定までにかかるおおよその期間は、以下の通りです。
- 弁護士への相談・契約…2週間前後
- 受任通知の発送から申立ての準備まで…2~3カ月
- 裁判所での面接から開始決定まで…約3週間
- 管財人面接から財産の配当まで…3~6カ月
- 免責許可決定から免責許可決定確定まで…約1カ月
同時廃止の場合は4カ月~5カ月程度、管財事件では7カ月~12カ月以上かかることもあります。また、書類に不備があると、裁判所から修正を求められ、期間がさらに延びることもあります。
お住いの地域の地方裁判所によっては、弁護士に依頼している場合に限り、申立てからすぐに面接を受けることができる「即日面接制度」を利用できることもあります。詳細は担当弁護士にお尋ねください。
特定調停の手続きの流れと完了までの期間
特定調停は、簡易裁判所が仲裁役となり、債権者との和解を目指す方法です。基本的に手続きは債務者本人が行いますが、弁護士を代理人として立てることも可能です。任意整理で和解が成立しなかった場合には、特定調停へ進むことになります。
手続きの進行過程
特定調停の手続きの流れは以下の通りです。
- 申立書類の作成
債務者本人が必要な書類を作成します。 - 特定調停申立
相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に、債務者本人が特定調停を申立てます。 - 債権者への通知書送付
裁判所から各債権者に特定調停が開始された旨の通知が送付されます。 - 調停期日通知書の受け取り
初回の調停日と調停準備日が決定され、その通知書が届きます。都合が悪い場合は、裁判所に電話連絡をし、日時の変更を依頼できます。 - 調停準備日に裁判所へ
必要書類を持参して裁判所に出向きます。調停委員による聞き取りや調停の進行方法について説明があります。 - 調停期日
調停当日は、調停委員が債権者と返済条件や期日について交渉を行います。双方が合意すれば、その内容が「調停調書」としてまとめられます。 - 返済の再開
裁判所から調停調書が届いたら、その内容に基づいて返済が再開されます。
特定調停の特徴は、借金の相手(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申立を行わなければならない点です。複数の債権者に対して特定調停を希望する場合は、まとめて一か所の簡易裁判所に申立をすることができます。
また、合意後に取りまとめられた調停調書は、確定した裁判の判決と同等の効力を持つため、必ずその内容を実行しなければなりません。
手続き完了までの期間
特定調停が完了するまでの期間は、以下のように分けられます。
- 申立書類作成から申立まで…数週間~1カ月
- 申立から調停終了まで…3カ月~4カ月
通常、申立から調停終了までの期間中に、裁判所で行われる月1回の調停に合計で3~4回出席することになります。調停は基本的に平日に行われるため、仕事をしている方はあらかじめスケジュールを調整する必要があります。
債務整理の所要期間目安
債務整理にかかる期間は、選択する方法によって異なります。
一般的な目安として、以下の期間が参考となります。
| 債務整理の種類 | かかる期間の目安 |
|---|---|
| 任意整理 | 3〜6ヶ月程度 |
| 個人再生 | 6〜12ヶ月程度 |
| 自己破産 | 3〜12ヶ月程度 |
特に裁判所を通さずに行う任意整理は、他の方法に比べて最も短期間で手続きを完了できる傾向があります。どの方法を選んでも、債権者の数が多いほど、手続きに時間がかかりやすいことに注意が必要です。
債務整理に必要な費用相場
債務整理を検討する際、費用がどの程度かかるのかは一般的に気になる点です。返済に困っているからこそ債務整理を始めるわけですが、その過程で費用がかかりすぎるのではないかと心配になるのも無理はありません。
そこで、債務整理にかかる費用の相場について、種類別に解説します。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理の費用目安
任意整理の費用は、債権者(お金を借りている貸金業者など)の数によって異なります。債権者が多いほど、交渉回数が増えるため、費用も高くなります。
任意整理の費用の相場は以下の通りです。
- 債権者1社あたり…3〜5万円程度
- 減額報酬…減額された金額の10〜20%程度
減額報酬とは、任意整理によって借金が減額された場合に、その減額額に応じて弁護士などの専門家に支払う費用で、成功報酬のようなものです。
例えば、弁護士に任意整理を依頼した結果、100万円の借金が60万円に減額された場合、減額報酬が10%の場合、減額された40万円の10%、つまり4万円を報酬として支払うことになります。
個人再生にかかる費用の相場
個人再生にかかる費用は、裁判所に納める費用(裁判所費用)と、個人再生手続きを依頼した弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用(専門家費用)の2種類があります。
個人再生にかかる費用の目安は以下の通りです。
- 裁判所費用:17〜30万円程度
- 専門家費用:20〜50万円程度
- 合計費用:37〜80万円程度
個人再生を行うには、裁判所費用を必ず納める必要があります。この費用を支払わなければ、個人再生手続きは進められません。弁護士などの専門家費用は、専門家に依頼せず自分で個人再生を行う場合には発生しません。
しかし、専門家に依頼せずに自力で個人再生を進めることは非常に難易度が高いため、実際には専門家費用が必要になることを考慮しておくべきです。
自己破産にかかる費用の目安
個人再生と同様に、自己破産にも裁判所費用と専門家費用の2種類の費用がかかります。
自己破産に必要な費用の目安は以下の通りです。
- 裁判所費用:10〜50万円程度
- 専門家費用:20〜50万円程度
- 合計費用:30〜100万円程度
自己破産には、財産がない場合の同時廃止事件と、不動産などの財産がある場合の管財事件の2種類があります。一般的に、管財事件は同時廃止事件よりも費用が高くなります。
債務整理にかかる費用や、費用が支払えない場合の対処法について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
関連記事
【債務整理(任意整理)の弁護士費用の相場】
借金で手持ちがなくても行う方法
債務整理を弁護士に依頼する際に、まず気になるのは弁護士費用でしょう。借金に悩んでいる中で、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然です。
弁護士と司法書士、どちらに依頼すべきか
債務整理を依頼する専門家として、一般的に弁護士と司法書士が挙げられます。どちらに依頼すべきか迷うこともあるでしょう。
弁護士と司法書士は、どちらも国家資格を持つ法律の専門家ですが、業務内容には違いがあります。
簡潔に言うと、弁護士は法的業務全般、手続き、交渉などをすべて代理で行うことができます。一方、司法書士は主に裁判所に提出する法的な書類の作成を担当することが主な業務です。
司法書士は費用を抑えられるが、業務対応に制限がある
債務整理を依頼する際のポイントは、「司法書士に依頼すると弁護士よりも費用が安くなることが一般的だが、弁護士の方が対応できる業務範囲が広い」という点です。
任意整理に関して、司法書士(厳密には認定司法書士)に依頼する場合、基本的に1社あたりの借金(債務)が140万円以下である必要があります。もし、1社でも140万円を超える借金があれば、司法書士では対応できず、弁護士に依頼することが求められます。
また、個人再生や自己破産は裁判所で行う手続きですが、場合によっては裁判官との審尋(面談)が行われることがあります。弁護士は審尋に同席できますが、司法書士は基本的に同席できません。
これらを踏まえると、140万円以下の任意整理については、1社あたりの借金が140万円を超えていない場合、司法書士に依頼すると費用を抑えることができる可能性があります。
債務状況が不明確な場合は、弁護士への相談が適切
140万円を超える任意整理や、審尋が行われる可能性のある個人再生や自己破産については、弁護士に依頼する必要があります。また、自身の債務状況が不明確な場合は、最初から弁護士に相談する方が現実的です。
債務整理の費用を抑えようと司法書士に依頼しても、債務総額が140万円を超える場合、その債務整理を扱うことはできません。その場合、弁護士に再度相談する必要があり、借金の解決までに時間がかかることになります。
前述の通り、分割払いの利用や法テラスを活用することで、弁護士事務所への支払いを軽減することができます。費用面で不安がある場合は、支払いについても含めて弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理手続きに必要な書類とは?
債務整理の種類ごとに流れや期間がわかったところで、次に申立に必要な書類について解説します。ここでは、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停それぞれについて見ていきます。
債務整理に必要な書類は何かを確認していきましょう。
【任意整理】に必要な書類
任意整理は裁判所を介さずに行う手続きのため、所定の申請用紙は必要ありません。しかし、弁護士や司法書士に依頼する際に必要となる最低限の書類や持ち物がありますので、忘れずに準備しましょう。
必要な書類:
- 身分証明書(健康保険証・運転免許証・パスポートのいずれか)
- 印鑑(認印可・シヤチハタ不可)
- 借入先のクレジットカード・キャッシングカード
- 借入の利用明細書・請求書・契約書
また、依頼する弁護士や司法書士によっては、以下の書類を求められることがあります。
- 預金通帳
- 収入明細(給与明細)
- 退職金の見込み額がわかる書類
- 住民票
- 世帯単位の家計表
- 債権者(借金相手)一覧表
- 不動産登記簿謄本
- 生命保険証券
- 車検証
法テラスに依頼する場合、依頼を受けられるかどうかの審査に必要な書類もあります。次の書類を準備しておきましょう。
- 直近2カ月の給与明細
- 直近の課税証明書
- 一年分の確定申告書の写し
- 直近の年金証書・通知書の写し
- 3カ月以内に発行された生活保護受給証明書
- その他、上記に準ずる書類
- 資力申告書(生活保護受給者以外)
【個人再生】に必要な書類
個人再生を申立てる際には、各裁判所から入手できる個人再生申立書をはじめ、次のような書類の提出が求められます。
- 個人再生申立書
- 陳述書(申立人の職業、家族構成、収入などを記載)
- 債権者一覧表
- 家計表(申立人の収支詳細を記載)
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 財産目録
- 戸籍謄本
- 住民票
【自己破産】に必要な書類
自己破産の手続きにおいて最低限必要となる書類は、以下の通りです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 財産目録
- 住居に関する書類(賃貸借契約書・不動産登記簿謄本)
- 収入に関する書類(給与明細・源泉徴収票・課税証明書・確定申告書・年金受給証明書・退職金規定など)
- 財産に関する書類(生命保険証書・車検証・預金通帳など)
- 世帯単位の家計表
- 公共料金領収書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 債権者一覧表
- 税金の滞納額が確認できる書類
- 診断書(病気やケガが自己破産の原因の場合)
また、申立て直前に遺産相続を受けた場合は、相続財産や財産分与に関する詳細がわかる書類も必要です。さらに、裁判所によっては同居家族の給与明細や車検証、保険証券を求められる場合もあります。
自己破産手続きでは、書類の収集と準備が非常に重要です。
求められる書類が整っていないと申立てができないこともあるため、優先して準備を進めましょう。
【特定調停】に必要な書類
特定調停には、次の書類が必要です。
- 特定調停申立書
- 関係権利者一覧表
- 財産状況を示す明細書(その他、特定債務者であることを明示する書類)
- 資格証明書(相手方が法人の場合)
- 予納郵便切手
参考:特定調停申立てQ&A|東京簡易裁判所
申立先の簡易裁判所では、特定調停に必要な書類の一覧やひな形を確認できる場合があります。申立てを行う裁判所が決まったら、その裁判所のホームページをチェックして、確実に準備を進めることができます。
債務整理を進める際の注意点
債務整理の手続きを進める際には、いくつかの注意点があります。種類ごとに詳しくご説明しますので、参考にしてください。
債務整理の手続きを行う際の注意点
【任意整理】の手続きで気をつけるべき点
裁判所を通さない任意整理では、手続き終了後の支払いに関して注意すべき点があります。
任意整理が終わるまで新たな借金を避ける
任意整理をした後、借金の返済が終わるまでは新たに借り入れをしないようにしましょう。任意整理後は約5年間、信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト」に載ることで、新たな借り入れやローンの契約が難しくなります。
ただし、任意整理の場合、一部のクレジットカードを手元に保持することができ、そのカードを使って新たに借り入れをしてしまうこともあります。せっかく借金が減ったのに、再度借金を重ねると返済が滞る原因となってしまいます。任意整理で借金を完済するまでは、追加の借金をしないことが基本です。
支払条件の変更は不可能
任意整理により債権者との和解が成立した後は、和解契約書に記載された支払い条件を変更することはほぼ不可能です。たとえやむを得ない事情で支払いが難しくなった場合でも、一度決められた支払い条件を変更してもらうことは難しいと考えましょう。
もし任意整理後に支払いが困難になった場合、借金の負担を軽減するためには自己破産しか選択肢がなくなります。そのため、決まった月々の返済額を確保できるよう、支出や収入の管理をしっかり行うことが重要です。
【個人再生】手続き時の留意点
個人再生を進める際の注意点は、こちらの2点です。
保証人が負担する借金は減額対象外
個人再生を行う際、借金に保証人がついている場合、債務者本人が借金の減額を受けても、保証人の借金は減額されません。個人再生を申請し、再生計画案が認可されるまで、借金の支払いは一時的に停止されますが、この期間中に債権者が保証人に支払いを求めることもあります。そのため、保証人には事前に個人再生手続きを行っていることを伝えておくことが重要です。
借金の金額によっては、保証人も個人再生を検討した方が良い場合があります。しかし、個人再生を申請できるのは、収入が安定して得られる見込みがある人のみです。現在、フリーターや主婦が保証人になっている場合は、個人再生を申請できない可能性があります。保証人の債務についても確認するため、担当の弁護士に相談しておくことをおすすめします。
過失による返済困難では「ハードシップ免責制度」は適用外
個人再生で借金を返済中の方が、やむを得ない事情で返済が難しくなった場合、「ハードシップ免責制度」により、残りの借金を全額免除されることがあります。ただし、この制度を利用するには、次の一定の要件を満たす必要があります。
- 確定している弁済額の3/4以上を返済済みであること
- 免責の決定が債権者の一般的な利益に反しないこと
- 再生計画を変更・延長しても支払いが困難であること
- 支払えなくなった理由が本人の責任によるものでないこと
つまり、ハードシップ免責制度を利用するには、事故や病気、失業、災害などの不慮の事情で返済が困難になった場合に限られます。返済が遅れたり、ギャンブルなどの自己の過失による原因で返済ができなくなった場合は適用されません。
もし計画通りに返済できない場合、「再生計画の取り消しの申立」が行われ、借金は元の金額に戻ってしまいます。返済ができなくなった場合は放置せず、できるだけ早く弁護士に相談して、今後の対応について確認することが重要です。
【自己破産】手続きの注意点
自己破産を進める際に注意すべき点は、手続きにかかる経費や免責されない債権についてです。
場合によって「予納金」が必要
自己破産を進める際に注意すべき点は、手続きに必要な経費や免責されない債権についてです。
自己破産の手続きを開始するには、裁判所に「予納金」という手続き費用を納める必要がある場合があります。この予納金の金額は、個々の事案によって異なり、破産に至った状況や保有資産に応じて裁判所が決定します。予納金の内訳とおおよその金額は以下の通りです。
予納金の種類
- 内訳
- おおよその金額
- 郵便切手
申立人や破産債権者に送付する通知に必要
1,000円~4,000円 - 官報掲載費用
国が毎日発行している官報に掲載するための費用
同時廃止:1.2万円~
管財事件:1.5万円~ - 管財費用
破産管財人を担当する弁護士に支払う費用
20万円~
税金や養育費は免責されない
自己破産をしても、税金や養育費の支払いなど、一部の債権は免責されないことがあります。これを「非免責債権」と呼び、以下のようなものが該当します。
- 租税などの請求権(税金、健康保険税、年金、水道料金など)
- 罰金
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失で加えた人命または身体に対する不法行為による損害賠償請求権
- 扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(養育費、婚姻費用)
これらの債務は、自己破産をしても免責されないため、注意が必要です。
【特定調停】手続きで気をつける点
特定調停では、過払い金が発生していることが判明しても、別途手続きを行う必要があります。特定調停でも、他の債務整理と同様に、利息制限法に基づく法定上限金利で引き直し計算を行います。しかし、引き直し計算の結果として過払い金があっても、特定調停の場ではその返還を請求することはできません。
特定調停は、残った借金をどのように返済するかについて合意を得るための手続きです。調停委員は返済に関する交渉を行いますが、過払い金の返還交渉は行いません。
過払い金の返還を受けるためには、過払い金返還請求訴訟を起こすか、個別に債権者と交渉する必要があることを覚えておきましょう。
調停がうまくいかないことも
特定調停には、以下のような手続き上の注意点があります。
過払い金の返還は別途手続きが必要
特定調停では、過払い金が発生していることが分かっても、それに関する別の手続きが必要です。特定調停でも他の債務整理と同様に、利息制限法に基づいた法定上限金利で引き直し計算が行われます。もし計算の結果、過剰に支払った利息があった場合でも、特定調停内では過払い金を請求することはできません。
特定調停は、残りの借金をどのように返済するかについて合意を得るための手続きであり、調停委員は返済に関する交渉を行いますが、過払い金返還の交渉は行いません。
過払い金の返還を受けるには、過払い金返還請求訴訟を起こすか、個別に債権者との交渉を行う必要があることを理解しておきましょう。
まとめ
債務整理はその種類によって手続きの流れや必要な期間が異なります。また、必要書類もケースや内容によって変わり、どのタイミングでどの書類が必要かは個別の状況に応じて異なります。
特に裁判所に申立を行う債務整理では、書類の記入ミスや添付忘れがあると、決定までの期間がさらに長くなることがあります。そのため、できるだけ弁護士などの専門家のサポートを受けながら、書類の不備がないように準備を進めることが重要です。
債務整理の手続きには様々な注意点があり、自己処理を試みると予期しないトラブルが発生することもあります。そのため、法律知識を持つ弁護士の助けを借りて手続きを進めることをお勧めします。無理に自分で進めず、プロに頼むことでスムーズに進行できます。
債務整理に関するよくある質問
債務整理に関するよくある質問について、以下で詳しく解説します。
- 債務整理は自分で行えるか?
- 家や車のローンを残したまま債務整理は可能か?
- 法人の代表者が任意整理を行った場合、会社に影響はあるか?
家や車のローンを残して債務整理は実行できるか?
債務整理を行った結果、家や車のローンがどう扱われるかは、選んだ手続きの方法によって異なります。
任意整理の場合、家や車のローンについては、任意整理の対象から外してそのまま支払いを続けることで、家や車を手放すことなく債務整理が可能です(他の借金を任意整理することで、返済が十分に可能になるケースもあります)。
一方、自己破産を選択した場合、ほとんどの債務は免責されますが、基本的に財産を手放さなければなりません。結果として、家や車のローンは免除されますが、家や車自体は基本的に手放すことになります。
ローンの種類による車を残した個人再生の可否
車のローンについては、個人再生を行った場合の結果がローンの種類によって異なります。
まず、車のローンが所有権留保の場合、車の所有権はローン会社にあります。この場合、個人再生を行うと、ローン会社によって車を引き上げられることが一般的です。
ただし、例外として「別除権協定」という方法があります。この方法では、個人再生を行っても車のローンを支払い続けることで、車を手放さずに維持することが可能です。しかし、この方法を利用するにはローン会社と裁判所の両方の承認が必要であり、車を仕事で使用しているなど、特定の条件が満たされている場合に限られます。したがって、一般的なケースではあまり適用されない方法です。
次に、銀行系(銀行や信用金庫など)の車のローンの場合、所有権は購入者である債務者にあります。この場合、個人再生を行っても、ローンを払い続ける限り、基本的には車を引き上げられることなく所有を維持できます。
個人再生で住宅ローン特則を利用する可能性
個人再生を行う場合、家のローンと車のローンの取り扱いは異なります。家のローンについては、住宅ローン特則を利用することで、家を手放すことなく個人再生を進めることが可能です。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、住宅ローンの返済を継続しながら、それ以外の債務を個人再生によって減額できる制度です。この特則を利用するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 保証会社による代位弁済後、6ヶ月以上が経過していないこと
- 住宅ローン以外の抵当権がその不動産に設定されていないこと
- その不動産が本人の所有で、本人が居住している住宅であること
- 不動産の床面積の半分以上が居住用であること
特に、保証会社が住宅ローンの代位弁済を行った後、一定の期間が経過してしまうと、住宅ローン特則を利用できなくなる可能性があるため、早めに債務整理を検討することが重要です。
債務整理を自分で進めることは可能か?
債務整理は理論的には自分で行うことも可能ですが、いくつかのデメリットがあるため、基本的には弁護士などの専門家に依頼することを強くおすすめします。
まず、債務整理を自力で行う場合、債権者(消費者金融やカード会社など)と交渉することは可能ですが、以下のようなデメリットが存在します。
- 法律の知識が不足しているため、不利な条件で返済について和解してしまうことがある
- 素人だと見なされ、債権者がまともに取り合ってくれない場合がある
- 受任通知を出さないため、借金の取り立てが止まらないリスクが高い
次に、個人再生や自己破産など、裁判所で手続きが必要な場合についてです。これらも、専門家に依頼せずに自分で行うことは可能です。しかし、個人再生や自己破産は、裁判所に提出しなければならない書類が多く、書式も専門的です。状況によっては裁判官との面接を受ける必要もあり、自分で対応するには手間も時間もかかります。さらに、書類作成に失敗すれば、せっかく費やした時間が無駄になってしまう可能性もあります。
このようなリスクを避けるため、債務整理は専門家に依頼して進めることをおすすめします。
法人代表者が任意整理を行うことで会社に与える影響
法人の代表取締役が自己破産を行う場合、破産手続きの開始によって代表取締役としての任期が終了し、その結果、代表取締役は解任されることになります(ただし、破産後に再任されることは可能です)。一方で、任意整理や個人再生の場合、法的には代表取締役が解任される必要はありません。
法人代表者が任意整理などの債務整理を行うと、その情報が事故情報として信用情報に記載されるため、法人代表者自身が名義で借り入れをしたり、クレジットカードを作ることが非常に難しくなります。法人代表者の事故情報が直接的に会社に影響することはありませんが、会社名義での借り入れの際に代表者の信用情報が参照されることがあり、その結果、借り入れができなくなる可能性は存在します。
さらに、法人代表者が任意整理を行った場合、会社に影響を与えるリスクもあります。例えば、法人代表者が個人保証をしている場合、その金融機関や関連会社からの債務について任意整理を行うと、会社の債務が一括請求される可能性があります。また、個人保証をしている金融機関や関連会社の債務を任意整理すると、会社名義の預金口座が凍結されるリスクもあります。
これらのリスクを軽減するためには、任意整理を行う際に、法人代表者が個人保証をしている金融機関や関連会社を整理の対象から除外する方法があります。
法人代表者や経営者が債務整理を行う際には、一般的な債務整理とは異なる注意点が存在します。弁護士に相談して、事業や生活への影響を十分に確認した上で進めることをおすすめします。