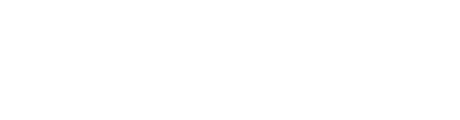※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
借金は死んだらチャラ?残ったローン・借金は家族に返済義務が生じる?
目次
「借金は亡くなったらどうなるのか?」これは多くの人が抱える重要な疑問です。特に、「独身の場合、亡くなった後の借金はどうなるのか」「アコムなどの借金がある場合、死亡後はどうなるのか」「亡くなった後、家族や子供にどんな影響があるのか」といった具体的な問題に直面している方々には、これらの疑問は切実です。この記事では、借金と死亡に関する法的な処理や相続放棄の流れを、具体的な事例をもとに詳しく解説します。借金の相続方法や、家族や独身の相続人が直面する可能性のある法的側面について、わかりやすく説明します。
借金は死亡後に消えるのか?真実を解明
「借金が死んだらチャラになる」と考えがちですが、これは誤解です。実際には、故人の借金は法定相続人に引き継がれます。しかし、これは自動的なものではなく、相続人には相続放棄の権利があります。相続放棄をすることで、借金を引き継がずに済みます。相続放棄を行うには、故人の死を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。もし申し立てを行わなければ、相続人は故人の借金を相続することとなります。
独身者の場合、借金は死後どうなるのか?
独身者が亡くなると、その借金は直系の親族や兄弟姉妹に相続されることがあります。ただし、相続人は相続放棄をすることで、借金の責任を免れることが可能です。相続放棄は家庭裁判所に申し立てることで行われ、この手続きによって、故人の財産と同様に借金も相続しないことが確定します。
配偶者や子ども以外にも、両親や兄弟が影響を受ける可能性が高い
相続人というと、通常は子どもを思い浮かべるかもしれません。でも、実際には亡くなった人の相続人は子どもだけではなく、両親や兄弟、さらには祖父母まで、血縁関係にある多くの人々が該当することがあります。
相続人が誰になるかは、民法で細かく定められており、順番までしっかりと決まっています。
第1順位
亡くなった人の子ども
※すでに子どもが亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続します。
第2順位
亡くなった人の直系尊属(両親や祖父母)
※存命中の、亡くなった本人に最も近い世代の人が該当します。
第3順位
亡くなった人の兄弟姉妹
※兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が相続します。
【参考:相続人の範囲と法定相続分–国税庁】
さらに、配偶者は常に相続人となります。したがって、配偶者と子どもがいる場合、その両者が相続人として財産を相続します。もし子どもが相続を放棄した場合、次に相続するのは亡くなった人の両親になります。このように、誰かが相続を放棄した場合は、次に順位が高い人が相続人として自動的に決まります。
もし、親族全員が亡くなった人の借金を背負いたくないのであれば、相続放棄の手続きを全員が行う必要があります。しかし、連絡が取れない兄弟が相続放棄の手続きを期限内にできず、知らず知らずのうちに借金を背負ってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
アコムの借金が死亡時にどうなるか
アコムなどの消費者金融からの借金も、他の借金と同じように扱われます。もし故人がアコムから借り入れをしていた場合、その借金は相続人に引き継がれます。ただし、相続人が相続放棄をすることで、借金を負担せずに済むことができます。また、故人が保険に加入していた場合、その保険金を使って借金を清算することも可能です。
身寄りがない場合の死亡と借金の扱い
身寄りのない人が亡くなった場合、その人の借金は通常、法的に消滅すると見なされます。この場合、借金は「無相続人財産」として処理され、返済義務を負う相続人がいないためです。日本の民法では、相続人がいない、もしくは全ての相続人が相続放棄をした場合、故人の財産は国に帰属することになります(民法第940条)。その結果、故人の財産は国庫に組み込まれ、借金も事実上無効となります。
しかし、この場合に注意すべき点があります。それは、故人が残した財産も借金と同様に国庫に帰属するため、相続人がいれば受け取れた可能性のある財産を手に入れることができなくなるということです。さらに、故人が生命保険に加入していた場合、もし受取人が指定されていなければ、その保険金も国のものとなります。
このように、身寄りのない人が亡くなると、その財産や借金には特殊な法的処理がされ、通常の相続のルールは適用されません。この点を理解しておくことは、相続計画や借金管理において重要です。
亡くなった人の借金は家族が引き継ぐことになる
先生、相続という言葉を聞いたことがありますか?
基本的に、誰かが亡くなると、その人が所有していた財産は、家族などの相続人が引き継ぐことになります。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続が開始された時点から、故人の財産に関する全ての権利義務を承継する。ただし、故人に専属するものはこの限りではない。
【引用:民法896条–e-Gov法令検索】
「一切の権利義務を承継する」というのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含めてすべてを受け継ぐということです。
現金や預金、不動産、車などのプラスの財産に加え、借金の返済義務も相続されることになります。
例えば、消費者金融などから借りたお金だけでなく、次のような支払い義務もすべて相続されます。
- 未払いの家賃、光熱費、携帯代
- 滞納していた税金や健康保険料
- 未払いの買掛金(事業をしていた場合など)
さらに、もし亡くなった方が誰かの借金の保証人になっていた場合、相続人はその保証人としての責任も引き継がなければならないことを覚えておきましょう。
亡くなった人の借金における時効の扱い
借金には時効があり、一定の期間返済が行われないと、時効によって返済義務が消滅することがあります。通常、この時効は最後の返済から5年となります。しかし、故人が亡くなると、その時効は停止し、相続人が時効の援用を行わなければなりません。相続人が時効を主張することで、返済義務から解放されることが可能になります。
借金が残った場合、死後の子供への影響
親が亡くなった際、子供が受ける影響は特に借金の相続において重要です。法律では、故人の借金は原則としてその子供たちに引き継がれますが、これは自動的なものではありません。子供や他の相続人は、故人の死を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることで、その借金を引き継がずに済むことができます。
もし相続放棄をしない場合、子供は故人の借金を相続し、その返済責任を負うことになります。例えば、故人が500万円の借金を残していた場合、その全額が子供に引き継がれることになります。これは子供の将来の財産計画や資産管理に大きな影響を及ぼす可能性があります。
未成年の子供の場合、相続放棄の手続きはその法定代理人、通常は親権者が行う必要があります。相続放棄が認められれば、子供は故人の財産だけでなく、借金からも解放されます。ただし、この選択には故人の財産を一切受け取れなくなるというデメリットも伴います。
親の死後、子供が直面する借金の相続は、財産管理と個人の財政計画において非常に重要な決断となります。したがって、適切な法的アドバイスを受け、故人の財産と借金の全体像を理解した上で慎重に相続について決定することが大切です。
親の借金が残った場合の死後の対処法を知恵袋から学ぶ
親が亡くなった際に発生する借金については、多くの人が悩みを抱える問題です。インターネットの知恵袋などでは、実際の体験に基づいたアドバイスが多く共有されています。これらの情報を参考にすることで、借金の相続放棄手続きや、それに伴う法的な問題について理解を深めることができます。しかし、法的なアドバイスが必要な場合には、専門家に相談することをお勧めします。
自殺による死亡時には生命保険は支払われない
借金で困窮している場合、「生命保険を利用して借金を返済しよう」と考え、最終的に自殺を選択することがありますが、これは解決策にはなりません。実際、自殺によって生命保険の保険金が支払われないという法律が存在します。
【保険法 第51条(保険者の免責)】
保険契約において、次の場合には保険金が支払われません:
- 被保険者が自殺した場合。
そのため、借金返済のために自殺を選んでも、生命保険からの支払いはされません。結果として、残された家族にはさらなる負担がかかることとなります。
借金問題は死後に解決するものではありません。生きているうちに弁護士に相談し、借金を減らす方法を検討することが重要です。
上述した借金問題だけではなく「人生の終わりを迎える」際には、さまざまな疑問で頭を抱える方は多いでしょう。以下のような情報も参考になるため確認しておくことをおすすめします。
葬儀・お葬式は信頼の葬儀社|公益社
終活に役立つ情報満載|みんなが選んだ終活
借金が残った場合、死後の家族への影響
親や家族が借金を抱えて亡くなった場合、その借金は相続人にどのような影響を及ぼすのでしょうか。借金の有無による家族への影響について、以下に詳しく説明します。
借金が残った場合、死後に家族が直面する現実
家族が亡くなると、借金の相続が家族にとって大きな財政的負担となることが多い現実があります。例えば、故人が200万円の借金を残していた場合、法定相続人である家族はその借金も相続しなければなりません。これは、故人の財産だけでなく借金も含まれるという法律の原則によるものです。結果として、相続人は故人の借金を返済する義務を負い、家計に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、相続人には借金を相続しないための選択肢があります。それが「相続放棄」です。相続放棄は、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで行えます。この手続きを通じて、相続人は故人の借金を含むすべての財産の相続を放棄することになります。このため、相続放棄を選択する際は、故人が残した財産と借金の全体をよく考慮し、慎重に判断することが求められます。
家族が亡くなった際の借金の相続は、家族にとって非常に重要な財政的決断を伴います。そのため、法的アドバイスを求め、故人の財産と借金の詳細をしっかり把握することが、適切な対応をするために必要不可欠です。
借金が残った場合、死後に相続放棄を選ぶ方法
相続放棄は、故人の借金だけでなく、財産もすべて相続しないという選択肢です。この手続きを選ぶことで、借金の返済義務から解放されますが、その反面、故人の財産も一切受け取ることができなくなります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、手続きが完了することで実行できます。相続放棄を検討する際は、故人が残した財産と借金の全体像をよく理解し、慎重に判断することが大切です。
家族が残す借金の法的影響と対処方法
故人が遺した借金の法的側面は、相続において非常に重要な要素です。法律では、故人の借金も相続財産の一部と見なされ、故人の財産と共に相続人に引き継がれることになります。日本の民法によれば、相続人は故人の財産と借金を法定相続分に基づいて分け合うことになります(民法第900条)。例えば、故人が1000万円の財産と800万円の借金を残した場合、相続人は200万円の残り財産を分ける一方で、800万円の借金を共に負担することになります。
しかし、故人の借金がその財産を上回る場合、相続人は自分の個人財産を使って借金を返済しなければならないことがあります。この点は非常に重要で、相続人が自分の財産を守るために相続放棄を選択することが考えられます。相続放棄をする場合は、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続放棄を選択すると、相続人は故人の借金を含めた財産すべての相続を放棄することになり、個人の財産を保護するための重要な手段となります。
このように、故人が遺した借金に対してどのように対処するかは、相続において非常に重要です。相続人は、故人の財産と借金の全体像を理解した上で、適切な法的アドバイスを受け、自身の財政状況に最も適した決断を行う必要があります。
相続時の借金問題:家族に与える影響とは
家族が亡くなると、相続人は故人の財産だけでなく、借金も相続することになります。この結果、故人の借金返済の責任が家族に引き継がれることになります。特に借金の額が大きい場合、家族の生活に深刻な影響を与えることが考えられます。そのため、相続が発生した際は迅速に対応し、必要に応じて相続放棄の手続きを検討することが重要です。
家族が取るべき借金処理の手順
家族が故人の借金を相続する際には、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。まず、故人の財産と借金の総額を正確に把握することが必要です。その後、借金の返済計画を立て、必要に応じて相続放棄を検討します。相続放棄を行う場合、家庭裁判所への申し立てが必須となります。相続放棄が認められた場合、故人の借金からは解放されますが、その代わりに故人の財産も受け取れなくなることを理解する必要があります。
借金を抱えた人が亡くなった場合、遺族はどう対応すべきか?
残された家族が借金を背負うことは非常に重い負担であるため、そのような状況を避けることが重要です。しかし、予期せぬ事故や病気により、不慮の死を迎える可能性は誰にでもあります。もし借金を抱えたままで亡くなった場合、遺族がどのように対応すべきかについて、適切な手続きを踏むことが必要です。
借金返済を選択する場合の対応方法
借金の返済には、主に次の2つの方法があります。
- 借金を全額支払う方法(単純承認)
- プラスの財産の範囲内で借金を支払う方法(限定承認)
それぞれの方法について、詳しく説明します。
単純承認とは|借金全額を支払う方法
何も手続きをせずに、すべての財産を引き継ぐことを単純承認と言います。これは、一般的な相続を意味します。この場合、借金も全額相続することになります。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたとき、無限に被相続人の権利義務を承継する。
【引用:民法第920条–e-Gov法令検索】
また、単純承認を意図していなくても、次のような行為を行うと、単純承認をしたと見なされることがありますので注意が必要です。
- 亡くなった人(被相続人)の財産を一部使用したり処分したりした場合
- 被相続人名義の預貯金を解約したり払戻しを行った場合
- 被相続人名義の不動産や自動車の名義変更を行った場合
- 被相続人名義の不動産の賃貸料の振込先を自分の口座に変更した場合
これらは一例に過ぎません。もし財産と一緒に借金が残っている場合、知らないうちに単純承認をしてしまう可能性があるので、注意が必要です。相続財産に手を付ける前に、弁護士に相談することをお勧めします。
「単純承認」を知らずに行ってしまった!借金を支払うことに?(法定単純承認)
借金を支払うつもりがなくても、特定の行為を行うことで、単純承認をしたとみなされることがあります(民法921条)。これを「法定単純承認」と呼びます。以下の3つの状況で、法定単純承認が適用されます(民法921条各号)。
- 相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合(1号本文。例外あり)
- 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄の手続きをしなかった場合(2号)
- 相続人が、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産を隠匿、消費、または目録に記載しなかった場合(3号本文。例外あり)
相続放棄や限定承認を期間内に行わないと、法定単純承認が成立してしまいます(2号)。この期間については、後ほど詳しく説明します。また、以下のような行為を行うと、1号に基づき法定単純承認となり、期間内であっても相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
- 亡くなった人(被相続人)名義の預貯金を解約・払戻し、消費する
- 被相続人名義の不動産や自動車の名義変更を行う
- 被相続人名義の不動産の賃貸料振込先を自分の口座に変更する
- 被相続人名義の家屋を取り壊す
- 生前に被相続人が行った贈与契約に基づき、不動産の登記を第三者に移転する
また、たとえ期間内に限定承認や相続放棄を行った場合でも、上記のような行為をすると、3号に基づき法定単純承認が成立するおそれがあります。
遺された多額の借金を負担したくない場合は、相続財産に手をつけないことが重要です。もし相続財産を処分する必要がある場合は、事前に相続問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。例えば、相続財産の価値を下げないために行う修繕などの「保存行為」であれば、法定単純承認にはなりません。しかし、保存行為の判断を誤ると相続放棄ができなくなる恐れがあるため、事前に専門家に相談しておくことが重要です。
借金をプラスの財産の範囲内で支払う方法(限定承認)
借金を全額ではなく、プラスの財産の範囲内で支払う方法を「限定承認」と呼びます。限定承認を行うには、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述しなければなりません(民法923条、924条、915条1項)。ただし、相続財産の調査に時間がかかるなどの場合には、3ヶ月の熟慮期間を延長することができる場合もあります。
2020年度における限定承認の申立て件数はわずか739件であり、相続放棄の24万8374件に対して約0.3%に過ぎません。この理由として、限定承認を選択すべきケースがそもそも少ないこと(マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は相続放棄で足りることが多いこと)と、相続人全員の協力が必要で手続きが煩雑であることが挙げられます。また、相続放棄は書類提出のみで済みますが、限定承認の場合は相続財産の管理や目録作成が必要であり、手続きがより複雑です。
限定承認は、借金を引き継いでも残したい財産がある場合などに選ばれる、例外的な手続きとして位置付けられています。
相続放棄で借金の返済義務を免れる方法
まず最初に考えるべき手続きは、相続放棄です。相続放棄とは、「亡くなった家族の資産や負債を一切相続しない」と主張する手続きです。相続放棄を行うには、家族が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で申し立てをしなければなりません。ただし、「私は相続したくない」と言うだけでは認められないため、注意が必要です。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
【引用:民法第938、939条–e-Gov法令検索】
借金を相続しないのはありがたいですが、その場合、プラスの財産も全て相続できなくなります。実際に相続放棄をする人は少ないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。
実際、令和2年の司法統計によると、相続放棄をした人はなんと25万人近くに上ります。一方、後述する「限定承認」、つまり借金を含めて財産を引き継ぐ方法を選んだ人はわずか739件で、相続放棄を選んだ人と比較しても0.3%しかいません。借金を抱えたまま亡くなった場合、ほとんどの遺族は相続放棄を選択しているのが現実です。
相続放棄をしても保証人としての義務は残る
亡くなった方が借金をしており、相続人がその借金の保証人になっている場合、相続放棄をしても保証人としての返済義務は免れません。これは、保証人としての支払義務が故人のものではなく、保証人本人に課せられるためです。
もし保証人としての返済が困難な場合、債務整理を通じて負担を軽減したり、場合によっては返済を免除する方法もあります。
相続放棄の手続きとその期限について
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に相続放棄の申述書などを提出する必要があります。主な必要書類と手数料は以下の通りです:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手
また、相続放棄を行う場合、申述人の立場に応じて他にも必要書類があるため、具体的な要件については被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に問い合わせることをお勧めします。
相続放棄後に、もし被相続人に対してお金を貸していた債権者から請求があった場合は、相続放棄が受理されたことを示す書面(「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」)を提出し、支払いを拒否することができます。
「相続放棄申述受理通知書」は相続放棄の手続きが完了した際に家庭裁判所から発行されますが、紛失しても再発行されませんので、注意が必要です。もし紛失しなかった場合は、「通知書」のコピーを提出しましょう。また、「相続放棄申述受理証明書」は手数料(1通150円)で再発行が可能です。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、基本的に単純承認をしたものと見なされ、相続放棄はできなくなりますので、注意してください。ただし、相続財産が存在しないと信じていた場合や信じるに足る理由があった場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。借金が後で発覚した場合については、どのように知ったか、または知らなかったのかを弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
また、相続放棄を行った場合、代襲相続は発生しません。例えば、親が相続放棄をした場合、親の親(祖父母)の財産が孫に代襲相続されることはありません。
参照:相続放棄の申述|裁判所–CourtsinJapan
相続放棄を行う際の重要な注意点
これまで説明したように、借金を残したまま亡くなった場合、遺族は相続放棄を選ぶことが一般的です。相続放棄を行う際の注意点をまとめて解説します。
被相続人の死亡後、3ヶ月以内に手続きを完了させる必要がある
相続放棄を行いたい場合、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと、法律により認められません。
(相続の承認または放棄を行うべき期間)
第九百十五条 相続人は、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを行わなければならない。ただし、この期間は利害関係者または検察官の請求により家庭裁判所で延長が可能です。
【引用:民法第935条–e-Gov法令検索】
「相続の開始を知った日」とは、被相続人の死亡を知った日を指します。
この3ヶ月を過ぎると、消費者金融などの借金や未払いの税金、家賃などすべての財産を相続することになってしまうため、早急に対応することが重要です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必須
相続放棄をするには、家庭裁判所で正式に手続きを行う必要があります。
親族が亡くなると、相続する権利を持つ家族が集まり、遺産分割協議(遺産をどのように分けるか話し合うこと)を行います。
この際、ただ「自分は相続しません」と言うだけでは、相続放棄として認められませんので注意が必要です。
また、債権者からの取り立てに対して「私は相続しません」と伝えても、債権者はそれを受け入れませんので、覚えておいてください。
相続を完了した後は相続放棄ができない
相続放棄を行う前に、すでに相続が開始されたと見なされると、相続放棄ができない場合があるため注意が必要です。
相続が開始されたとみなされる具体的なケースは、以下の4つです。
- 財産をすでに使用してしまった
- 遺品を整理してしまった
- 協議書に印鑑を押してしまった
- 知らずに債務を承認してしまった
①すでに財産を使い果たしてしまった
亡くなった方の財産の一部でも使用または処分してしまうと、それは相続したと見なされてしまいます。
相続放棄とは「全ての財産の相続を放棄すること」を意味します。
つまり、財産のほんの一部でも使ってしまうと、その財産を相続したことになるということです。
②遺品の整理を済ませてしまった
家族が亡くなると、遺産分割協議などで遺品を分ける場面があるかもしれません。しかし、遺品の整理に関わることで相続放棄ができなくなるリスクが高くなります。
その理由は、遺品整理の過程で法定単純承認に該当する行為をしてしまう可能性があるからです(民法第921条)。
これは、単純承認に該当する内容であり、例えば、被相続人の財産の名義変更も単純承認に当たるため、相続放棄を検討しているのであれば、遺産には触れない方が賢明です。
相続放棄を考えているなら、遺品には触れず、家庭裁判所で放棄の手続きをするのが一番です。弁護士に相談すれば、さらに確実に進められます。
③遺産分割協議書に署名・押印してしまった
遺産分割協議に参加し、その協議書に署名や捺印をしてしまうと、相続放棄は認められなくなります。協議書に印を押すことは、自分が相続人の一員であることを認めたこととみなされるからです。相続放棄を考えている場合は、遺産分割協議が始まる前に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
④知らずに借金を認めてしまった
知らずに故人の債務を承認してしまい、相続が成立する場合もあります。例えば、亡くなった家族宛ての公共料金の請求書を代わりに支払った場合などが該当します。どんなに少額であっても、債務の一部を支払ってしまうと、借金を含むすべての財産を相続することになってしまうため、注意が必要です。
相続放棄の期限を過ぎても認められる場合がある
相続放棄の申し立て期限は法律で3ヶ月と定められていますが、実際には柔軟に対応される場合もあります。3ヶ月を過ぎても、相続放棄が認められるケースがあるのです。特に以下のような状況では、期限を過ぎていても相続放棄が受理されやすいです。
- 被相続人との交流がほとんどなかった
- 財産がほとんど見当たらなかった
- 財産調査を弁護士に依頼したが、その時点では借金が確認されなかった
- 債務に関する証拠(借用書、契約書など)が破棄されていた
2020年の司法統計によると、相続放棄の申し立てが却下された件数は426件で、全体の約23万件中、0.18%に過ぎません。もし相続放棄の期限を過ぎてしまっても、諦めて借金を背負う前に、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
相続後に借金が判明した場合の対応方法3選
家族が亡くなった場合、相続前に借金があることがわかれば、相続放棄をするのが最善の方法です。しかし、相続手続きを終えた後に借金が発覚することも考えられます。ここでは、相続手続き後に借金が明らかになった場合の3つの対処法について説明します。
- 相続人が返済をする
- 消滅時効の援用
- 債務整理を行う
1. 相続人が借金の返済を行う
相続手続きを完了した後は、相続放棄や限定承認といった選択肢を取ることができません。つまり、被相続人の借金は相続人が返済しなければならなくなります。ただし、複数の相続人がいる場合、借金は法定相続分に従って分割され、それぞれの相続人がその分を返済することになります。したがって、借金全額を一人で負担することはほとんどありません。
【法定相続分】
第900条 同順位の相続人が複数いる場合、その相続分は以下のように決定されます。
- 子どもと配偶者が相続人の場合、子どもと配偶者はそれぞれ半分ずつ相続します。
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
- 子ども、直系尊属、または兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は均等に分けられます。ただし、父母が異なる兄弟姉妹の場合、その相続分は半分になります。
【引用:民法第900条–e-Gov法令検索】
とはいえ、亡くなった方の借金をよく理解せずに相続し、返済しなければならない状況は納得しづらいものです。こうした場合には、時効援用や債務整理を検討することが有効です。次のセクションで、これらの方法について詳しく説明します。
2. 時効を援用して返済義務を免れる
もし被相続人に借金があった場合、長期間返済が行われておらず、債権者から裁判も起こされていない場合、借金が時効にかかっている可能性があります。消費者金融などからの借金は、最終返済日から5年が経過すると消滅時効が成立します。
ただし、古い借金だからといって、そのまま無視してしまうのは避けるべきです。消滅時効を成立させて返済義務を免れるためには、時効援用という手続きを踏まなければなりません。
もし時効援用を検討する場合、債権者に連絡を取ったり、借金の一部を返済したりする前に、まず弁護士に相談することが重要です。債権者に連絡をしてしまうと、時効が成立しない恐れがあるため、注意が必要です。
3. 債務整理を行い返済負担を軽減する
相続で引き継いでしまった借金がどうしても支払えない場合、早期に債務整理を行うことをお勧めします。
債務整理とは、法律を利用して借金を合法的に減額するための手続きで、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。各手続きの方法や減額の幅は異なります。
債務整理は、民事再生法や破産法など、法律で定められた正当な手続きです。意図しない相続ややむを得ない事情で借金を抱えてしまった人にとって、救済措置として活用できます。
どの債務整理が最適かは、個々の状況によって異なるため、借金の返済が困難な場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
住宅ローンは死亡後に免除されるのか?
住宅ローンを支払っている方が亡くなった場合、「相続放棄をしないと残った住宅ローンを支払わなければならないのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。しかし、相続放棄をすると、住宅を手放さなければならないのが一般的です。
とはいえ、相続放棄をしなくても、住宅ローンの残額を支払わずに済む場合もあります。住宅ローンを契約する際に、団体信用生命保険(団信)に加入している場合があります。団体信用生命保険は、住宅ローンの債務者が返済中に死亡した場合や高度な障害を負った場合に、ローン残高を保険でカバーする仕組みです。このため、遺族は住宅ローンの支払いを免除され、そのまま住宅を相続して住み続けることができます(ただし、相続放棄をした場合には住宅も相続できないため、他の相続人に使用してもらう場合を除いて住み続けることはできません)。
ご家族の住宅ローンに団体信用生命保険が付いているかどうかを確認しておくことが重要です。団体信用生命保険は、一般的に住宅ローン契約時にのみ加入できるため、後から加入することはできませんので注意が必要です。また、団体信用生命保険には、「がん」「脳血管疾患」「心疾患」の三大疾病や、「高血圧症」「糖尿病」「慢性腎不全」「肝硬変」「慢性膵炎」などの八大疾病になった場合にも支払いが免除される特約があるので、加入時に内容を確認して、必要に応じて検討することをおすすめします。
保険内容や保険料は保険会社によって異なるため、契約前に不明点を確認しておくことが大切です。
参照:機構団体信用生命保険特約制度のご案内|住宅金融支援機構
住宅ローンは基本的に相続対象となる
住宅購入時に契約した住宅ローンは、銀行からの借入れであるため、他の借金と同様に扱われます。つまり、住宅ローンも原則として相続の対象となります。もし残されたローンの金額が大きく、返済が困難な場合には、相続放棄や限定承認を選択肢として検討することになります。
団体信用生命保険加入時は住宅ローンは相続されない
団体信用生命保険(団信)に加入している場合、残った住宅ローンを相続する必要はありません。団信とは、住宅ローン契約者が死亡したり、重い障害で働けなくなった際に、保険会社が残債を肩代わりしてくれるサービスです。住宅ローン契約では、団信に加入しているケースが多いです。この保険に加入していれば、残りの住宅ローンを相続せずに済み、家はそのまま住み続けることができます。住宅ローン返済中に家族が亡くなった場合、団信に加入しているかどうかを必ず確認しましょう。
借金は亡くなっても解決しない!弁護士に相談して解決策を探そう
借金は、亡くなった後も相続されるという現実があるんです。実は、団体信用生命保険(団信)も、かつては消費者金融などでも利用できることがありました。しかし、自殺などで命を失うことで借金を帳消しにしようという考えが広がる恐れがあったため、こうした仕組みは廃止されました。つまり、死んでも借金問題は解決しません。
その代わり、返済が難しくなった場合、弁護士に相談することで解決の道が開ける可能性が高いです。これは、借金を相続してしまった人も、現在元気で借金が将来家族に相続されることを防ぎたいと考えている人も同様です。借金問題に直面したら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
債務整理で借金を合法的に減額する方法
借金がある場合、「死後に相続放棄してもらえれば大丈夫」と安易に考えず、終活の一環として債務整理を検討することをお勧めします。債務整理を行った後、借金をせず年金で生活できる状態であれば、少しでも財産を遺すことができるかもしれません。
たとえ相続財産を残せなかったとしても、遺族にかかる負担—返済の負担や相続放棄の手続きの負担—は軽減できる可能性があります。また、長期間の借金返済が続いている場合、過払い金が発生して返還請求できることもあります。さらに、長期間返済を停止している業者があれば、消滅時効によって返済義務を免れる場合もあります。
債務整理には主に以下の3種類の方法があります。
- 任意整理
支払い過ぎた利息(過払い金)の再計算を行い、残った負債については返済期間を延ばして毎月の支払額を減らす方法です。債権者と個別に交渉を行います。
詳細についてはこちらをご覧ください。 - 個人再生
支払いが困難な場合に、裁判所に申し立てて負債を減額し、減額後の負債を3年以内に分割払いで返済する方法です。所持している財産や負債の総額に応じて減額される幅が決まります。住宅ローンの残債がある場合でも、自宅を手放さずに済む可能性もあります。
詳細についてはこちらをご覧ください。 - 自己破産
支払い不可能な負債がある場合、裁判所に申し立てて、ほとんどの負債の支払義務を免除してもらう手続きです。ただし、一定の財産は手放さなければならない場合があります。
詳細についてはこちらをご覧ください。
どの手続きが最適かは、負債の総額や家庭の経済状況によって異なりますので、しっかりと判断し、適切な方法を選びましょう。
借金問題の相談は無料で対応可能!
弁護士に相談するのは高いと思うかもしれませんが、その心配は必要ありません。借金問題に関しては、ほとんどの法律事務所が初回相談を無料で行ってくれます。借金で悩んでいる方々が相談費用を工面するのも難しいことを、弁護士はよく理解しています。
借金は放置しておくほど利息が増え、負担が大きくなっていきます。そのため、問題が深刻になる前に早期に解決することが大切です。ですので、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします!
まとめ
この記事の要点は以下の通りです。
借金を抱えた人が亡くなると、基本的にはその借金の支払い義務は相続人に引き継がれます。遺族が選択できる方法は次の3つです。
- 単純承認:借金全額を支払う
- 限定承認:プラスの財産(預貯金や不動産など)内で借金を支払う。ただし、手続きが複雑で、実際に利用されるケースは非常に少ない
- 相続放棄:借金を一切支払わない
住宅ローンを組んでいる人が亡くなった場合、その人が「団体信用生命保険」に加入していれば、遺族はローンの残りを支払う必要はありません(団信に加入していることがほとんどですが、確認は必要です)。
相続人が相続放棄などの方法で借金の支払いを免れることができますが、生前に借金を整理しておけば、相続人の負担を減らすことができます。そこで、借金の返済負担を軽減または解消するために「債務整理」を利用することをおすすめします。