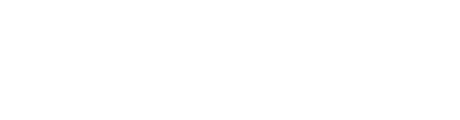※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
返済がきつい奨学金!返せない人が知っておくべき対処法
目次
- 返済がきつい奨学金!返せない人が知っておくべき対処法
経済的な理由で進学をあきらめなくて済むように、奨学金制度が存在します。しかし、一般的に奨学金には返済の義務が伴い、卒業後に返済がキツイ、辛いと感じる人も多いのではないでしょうか。
奨学金の返済ができないからと言って放置すると、さまざまなペナルティが課される可能性があるため、困難を感じた際には適切に対処することが重要です。この記事では、返済が厳しくなった場合にどう対処すべきか、奨学金制度の仕組みや、払えない場合のリスクについて解説します。
奨学金の概要について
奨学金に似たものとして、教育ローンや借金があります。ここでは、奨学金との違いやその概要について解説します。
奨学金について
奨学金とは、修学や研究を支援するための資金であり、国や自治体、企業、各種法人などが学生に提供しています。希望すれば、この奨学金制度を利用することが可能です。
借金と教育ローンの違い
奨学金とよく比較されるのは教育ローンです。奨学金は学生が教育費用の支援を受けるための制度であり、借り主は学生本人です。また、奨学金を受け取れるタイミングは入学後となるため、受験料や入学金には使用できません。
一方、教育ローンは親(保護者)が子どもの教育費用のために利用するローンで、入学金や授業料、塾の月謝など教育に関連する費用に幅広く使用できます。教育ローンには、国が運営するものと銀行や信用組合などが運営するものがあり、それぞれの条件が異なります。
教育ローンのメリットは、子どもに返済義務がないため、将来の不安を軽減し、入学前に必要な資金を準備できる点です。しかし、奨学金と比較して金利が高く、他のローンやクレジットカードの審査に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
借金は教育費用以外の幅広い目的で利用される一般的な資金借入れを指します。借り入れ時の審査は利用者の信用状況や収入に基づいて行われ、利用目的に制限はありません。
| 項目 | 奨学金 | 教育ローン | 借金 |
|---|---|---|---|
| 借主 | 学生本人 | 保護者 | 個人または法人 |
| 受け取り時期 | 入学後 | 入学前・入学後 | いつでも |
| 条件 | 学力基準有り・一定収入以下 | 国:一定収入以下、民間:一定収入以上 | 収入や担保の審査が必要 |
| 返済開始時期 | 卒業後 | 借入れの翌月から | 借入れの翌月から |
| 利息 | 低金利または無利息 | 奨学金と比較して高金利 | 金融機関の利率に基づく |
| 返済期間 | 最長20年 | 最大10~20年 | 借入れ契約に基づく |
3つのタイプの奨学金
奨学金にはさまざまなタイプがあり、単に「奨学金」といってもその内容は異なります。給付型奨学金は返済が不要ですが、貸与型奨学金の場合、長期間にわたり返済を続ける必要があります。また、返済期間が長くなるほど、特に有利子の奨学金では返済総額が増加し、負担が大きくなることがあります。ここでは、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を例に挙げ、奨学金の種類や返済額について解説します。
奨学金の種類
奨学金は、大学などに進学するために支給される仕組みで、貸与型の奨学金は通常、学校を卒業してから返済することになります。奨学金は主に「給付型奨学金」と「貸与型奨学金」の2つに分かれ、給付型は返済が不要です。
貸与型奨学金には、日本学生支援機構の「第一種奨学金」「第二種奨学金」「入学時特別増額貸与奨学金」の3つの種類があります。第一種奨学金は無利子で、第二種奨学金は利息が付きます。入学時特別増額貸与奨学金は、主に入学金などの支払いに使う目的で貸与されます。
これらの貸与型奨学金は、いずれも学校を卒業した後に返済義務が発生し、日本学生支援機構の場合、返済は卒業月の7ヶ月目の27日から始まります。その後、毎月27日に指定された口座から返済が引き落とされる形になります。返済方法には、「月賦返還」と「月賦・半年賦併用返還」の2つの方式があります。
月賦返還は毎月一定額を返済する方法で、月賦・半年賦併用返還は、毎月返済する額の半分を支払い、残りを半年に1回(1月・7月)返済する方法です。後者は、毎月の返済額を少なくし、ボーナス時にまとまった金額を返済するという特徴があります。
給付型奨学金は、学力や世帯収入など厳しい条件があるため、受給できる人は限られています。そのため、多くの奨学金利用者は貸与型を利用しており、卒業後の返済に悩むことが多いと言えます。
給付型と貸与型の特徴
奨学金は、大きく分けて「貸与型」と「給付型」の2つの種類に分類されます。
給付型
給付型奨学金は、返済不要なタイプの奨学金です。この奨学金は、学業成績が優れており、かつ経済的に困難な状況にある学生に教育を受ける機会を提供することを目的としています。給付型奨学金の最大の魅力は、返済が不要な点です。これにより、学生は将来の返済に悩まされることなく、学業に専念できます。ただし、給付型奨学金は受給資格や条件が厳しく、利用できる学生は限られています。
貸与型
貸与型奨学金は、その名の通り「貸与」されるタイプの奨学金で、将来的には返済が必要となります。貸与型奨学金の利点は、審査基準が比較的低いため、多くの学生が利用でき、必要な金額を調達しやすい点です。しかし、申し込む際には保証人が求められることがあり、返済ができない場合には個人信用情報機関に登録されるというデメリットも存在します。
第一種と第二種の特徴
貸与型奨学金は、さらに「第一種」と「第二種」に分類されています。
第一種
第一種奨学金は、無利子で提供される奨学金です。この奨学金は、学業が優れていて、経済的支援が必要な学生を対象にしています。貸与額は、進学先や学生の居住形態(親元か独立して生活しているか)、そして家庭の収入に基づいて決められます。高校生が申し込む際には、一定の成績基準(例えば、5段階評価で3.5以上)を満たす必要がありますが、経済的に非常に困難な家庭の場合、成績基準が免除されることもあります。
第二種
第二種奨学金は、利息が付くタイプの奨学金です。利率は経済情勢に応じて変動しますが、上限は3%に設定されています。貸与額は2万円から12万円の範囲で、学生は希望する月額を選ぶことができます。申込資格には、学業成績が平均以上であること、特定の分野での優れた資質や能力、学業の確実な修了見込み、そして家庭年収が一定額以下であることなどの条件があります。
返済状況を確認する手段
日本学生支援機構の奨学金返済状況は、「スカラネット・パーソナル」に登録すればすぐに確認できます。公式サイトから簡単に登録できるので、まだ登録していない方は早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
また、スカラネット・パーソナルでは住所変更や繰り上げ返済など、さまざまな手続きをWeb上で行うことができ、非常に便利なサービスです。
奨学金の返済金額
奨学金の返済は、無利子のものでは貸与された総額を定められた返還回数で割り、毎月返済を続ける形になります。有利子の場合は、貸与総額に利息を加えた金額を毎月返済していきます。
返還回数は、日本学生支援機構の場合、貸与額によって156回(13年)から240回(20年)に設定されています。例えば、4年制大学に通った場合の返済シミュレーションは以下のようになります。
第一種奨学金(国公立大学)
- 通学形態:自宅
- 貸与月額:45,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 毎月返済額:12,857円
- 返還回数:168回(14年)
- 返済総額:2,160,000円
- 通学形態:自宅外
- 貸与月額:51,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 毎月返済額:13,600円
- 返還回数:180回(15年)
- 返済総額:2,448,000円
第一種奨学金(私立大学)
- 通学形態:自宅
- 貸与月額:54,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 毎月返済額:14,400円
- 返還回数:180回(15年)
- 返済総額:2,592,000円
- 通学形態:自宅外
- 貸与月額:64,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 毎月返済額:14,222円
- 返還回数:216回(18年)
- 返済総額:3,072,000円
第二種奨学金(有利子)
- 貸与月額:30,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 貸与総額:1,440,000円
- 返還回数:156回(13年)
- 年利別返済額:
- 0.5%: 毎月9,557円、返済総額1,491,061円
- 1.0%: 毎月9,892円、返済総額1,543,214円
- 2.0%: 毎月10,580円、返済総額1,650,545円
- 3.0%: 毎月11,293円、返済総額1,761,917円
- 貸与月額:50,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 貸与総額:2,400,000円
- 返還回数:180回(15年)
- 年利別返済額:
- 0.5%: 毎月13,874円、返済総額2,497,419円
- 1.0%: 毎月14,428円、返済総額2,597,188円
- 2.0%: 毎月15,574円、返済総額2,803,404円
- 3.0%: 毎月16,769円、返済総額3,018,568円
- 貸与月額:100,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 貸与総額:4,800,000円
- 返還回数:240回(20年)
- 年利別返済額:
- 0.5%: 毎月21,069円、返済総額5,056,654円
- 1.0%: 毎月22,172円、返済総額5,321,420円
- 2.0%: 毎月24,478円、返済総額5,874,754円
- 3.0%: 毎月26,914円、返済総額6,459,510円
- 貸与月額:120,000円
- 貸与月数:48ヶ月
- 貸与総額:5,760,000円
- 返還回数:240回(20年)
- 年利別返済額:
- 0.5%: 毎月25,282円、返済総額6,068,011円
- 1.0%: 毎月26,606円、返済総額6,385,730円
- 2.0%: 毎月29,373円、返済総額7,049,746円
- 3.0%: 毎月32,297円、返済総額7,751,445円
このように、貸与月額が多くなると、毎月の返済額も増加します。さらに、有利子の奨学金では年利と貸与月額が高いほど、返済総額が大きく膨らむことがわかります。
奨学金の種類とその返済方法
独立行政法人日本学生支援機構の「令和2年度学生生活調査結果」(2022年)によると、大学生(昼間部)の約49.6%が奨学金を借りており、これは前回の平成30年度調査から約2ポイント増加しています。また、労働者福祉中央協議会の「『奨学金や教育費負担に関するアンケート調査』調査結果の要約」(2019年)によると、奨学金の借入総額の平均は324万3,000円、毎月の返済額の平均は1万6,880円で、返済期間の平均は14.7年です。借入金額や利息によって変動するものの、順調に返済が進むと、30代後半から40歳にかけて完済する人が多いと言えるでしょう。
奨学金を利用する約半数の人が、どのような条件を満たしているのでしょうか。以下に奨学金の種類と条件、返済に関する詳細をご紹介します。
奨学金の種類と条件
- 給付奨学金
返済の義務がない奨学金です。受給には、本人と生計維持者の収入や資産の基準、本人の学業への意欲などの条件を満たす必要があります。貸与型奨学金と併用することも可能です。 - 貸与型第一種奨学金
返済の義務がありますが、無利子で借りられる奨学金です。対象には、高校での全科目の評定平均が5段階評価で3.5以上であることや、生計維持者の収入基準などが求められます。第二種奨学金と併用することも可能です。 - 貸与型第二種奨学金
返済の義務があり、利息がかかる奨学金です。第一種よりも条件が緩やかですが、高校または専修学校の評定が平均水準以上で、学業意欲があることや、生計維持者の収入基準を満たす必要があります。第一種奨学金との併用も可能で、返還方法としては、利率固定方式か、利率見直し方式を選択できます。
奨学金の返済開始は、貸与終了月の翌月から7カ月目に始まる
奨学金の返済は、貸与(借り入れ)終了から数えて7ヶ月目の翌月から始まります。例えば、貸与が3月に終了した場合、その年の10月から返済がスタートします。返済額は、指定された金融機関の口座から毎月27日に引き落とされます。もし27日が休業日である場合は、翌営業日に引き落としが行われます。
奨学金の返済方法と期間の目安
奨学金の返済方法には、定額返還方式と所得連動返還方式の2つの方法があります。それぞれの特徴と返済期間の目安について、以下のようにまとめました。なお、利息のつく貸与型第二種奨学金の場合は、所得連動返還方式を選ぶことはできません。
返済方式
- 定額返還方式
毎月の返済額が借り入れ金額に基づいて決まり、定額で返済していく方法です。返済の完了時期が予測しやすい点が特徴です。 - 所得連動返還方式
前年の課税所得に基づき、毎年10月から翌年9月までの返済額が決まる方式です。年収が低い時期でも無理なく返済できますが、返済額が少ない場合、返済期間が長くなるという特徴があります。所得連動返還方式は、無利子の貸与型第一種奨学金のみ選択可能です。
奨学金返済が厳しい理由
奨学金の返済がなぜきついきついのかは、社会人になりたての頃の給与の低さが挙げられます。独立行政法人日本学生支援機構の「令和2年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」(2022年)によると、延滞している理由は「本人の低所得」の割合が62.9%で最も高く、次いで「奨学金の延滞額の増加」が41.4%でした。
厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」(2019年)の調査では、東京都の初任給は22万500円ですが、東京で一人暮らしをするとなると生活費に20万円前後かかります。生活費に加えて、返済額の平均値16,880円ほどを初任給から捻出するには、上手にやりくりする必要があります。
奨学金を返済しないまま放置すると、延滞金がかかり、さらに返済がきつくなりますので注意が必要です。返済がきつい場合は、延滞金がかかる前に対策していくようにしましょう。
奨学金返済者の実際の状況
四年制大学を卒業した際の初任給の平均は、額面で212,000円、手取りで169,000円となっています。一方、34歳以下でひとり暮らしをしている人の1ヶ月の支出額、具体的には家賃、食費、交際費などの平均は155,000円です。つまり、給料から生活費を差し引くと、単純計算で残るのは14,000円になります。しかし、この14,000円には借金の返済や貯金が含まれていません。そのため、この金額から奨学金の返済を行わなければならないことになります。
さらに、34歳以下の月々の奨学金返済額の平均は17,000円で、場合によっては返済額が月3万円に達することもあります。どう考えても、この状態では赤字になります。つまり、どこかで生活費を切り詰める必要があるということです。電気の使用を控える、食費を削るといった方法で調整しなければならず、どの方法を取ったとしても生活の厳しさは避けられないと言えるでしょう。
Aさん(27歳)のケース
Aさんのケースは、まさに現代の奨学金問題が抱える厳しい現実を物語っています。農業を営む家の長男として生まれ、母子家庭で育ったAさんは、家庭の経済的な困難を乗り越え、奨学金を活用して勉強に励みました。大学進学は親の支えもあって実現しましたが、奨学金を借りることが必要だったのは、非常に多くの学生と同じ状況です。Aさんは大学生活を支えるためにアルバイトを重ね、学費と生活費を自分で工面していましたが、問題はその後に起こりました。
新卒で就職した会社が自分には合わず、家業の農業に戻ることになったAさん。しかし、農業だけでは生活できず、日雇い労働に頼らざるを得なかった。ここから奨学金の返済が滞り始め、督促状を見逃した結果、どんどん深刻な状況になっていったようです。しかも、生活が安定し始めた矢先、今度は祖母の体調不良が重なり、農業を支える必要が強くなりました。
そして、ある日、生活が一変します。ATMからお金が引き出せないという事態に直面し、その原因が住民税の滞納による差押えだったことが判明。Aさんは債務一覧表を作成し、ついに膨れ上がった借金の総額が1100万円に達していたことを認識します。奨学金の一部は母親が保証人になっており、さらに親族も保証人になっているという状況では、自己破産の選択肢を取るのは非常に難しい状況にあります。
「大学に行ったことを後悔している」と語るAさん。その言葉には、奨学金を利用して進学したことで負った重い負担がどれほど大きかったのかが垣間見えます。奨学金がもたらす経済的な負担が、本人だけでなく、周囲の親族にも影響を及ぼす現実を、多くの人が知るべきでしょう。このような事例は、奨学金の返済問題に直面している学生や卒業生が抱える深刻な課題を浮き彫りにしています。
知恵袋に投稿された意見
ある日、知恵袋に投稿された大学2年生の質問が話題になりました。質問内容は「母子家庭で、祖父母、母、弟と一緒に住んでおり、月10万円の奨学金を借りている。現状で奨学金を減額するのは難しいのか?」というもので、家庭の状況が詳しく記されていました。この投稿に対して、多くのアンサーが寄せられました。その一部を紹介します。「地方公務員として月26,000円を返済しているが、正直言って厳しい。奨学金には後悔していないが、学生のうちに何らかの対策をすべきだった」「240回払いの返済は20年も続くため非常に大変で、結婚や子どもを持つことを諦めなければならないこともある」「やむを得ず返済が滞ると、住宅ローンの審査が通らない可能性もある」といった意見が寄せられました。
奨学金返済滞納時の4つのリスク
奨学金の返済が順調であれば特に問題はありませんが、何らかの理由で支払いが遅れてしまった場合には注意が必要です。返済が滞った際に発生するリスクは主に以下の4つです。
奨学金返済の滞納による4つのリスク
- 延滞金が発生する
- ブラックリストに載る
- 一括返済を求められる
- 連帯保証人に請求がいく
これらのリスクが実際に発生すると、生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。これらのリスクがどのように生活に影響するのかを詳しく説明していきます。
リスク① 延滞金の発生
日本学生支援機構の奨学金の返済が遅れると、年率3.0%以上の「延滞金」が発生するため、注意が必要です。年率での計算になるため、1〜2ヶ月程度の遅れではそれほど大きな負担にはなりませんが、延滞が長引くほど延滞金も増加します。
後述しますが、奨学金の返済が困難な場合には、日本学生支援機構には様々なサポート制度があります。早めに手続きを行うことで、少なくとも延滞金の発生を避けることができますので、状況に応じて検討してみましょう。
リスク② 信用情報に記録される
奨学金は借金であるため、毎月の返済が遅れると、その情報が信用情報機関に登録されます。3ヶ月以上の滞納が続くと、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになり、この履歴は5年間残ります。
信用情報に傷がつくと、日常生活で様々な不都合が生じるため、注意が必要です。例えば、クレジットカードの新規発行や新たな借り入れができなくなったり、住宅ローンやカーローンを利用できなくなったりします。また、スマートフォンの分割払いにも対応してもらえないことがあるので、滞納する前に必要な手続きを行うことが重要です。
リスク③ 一括返済を要求される
奨学金の返済を滞納した場合、特に注意すべきなのは、3ヶ月以上の滞納が続くと「一括返済」を要求される可能性が高くなる点です。日本学生支援機構は公的な機関であり、場合によっては裁判所を通じて返済の請求が行われることもあります。
返済残高の金額にもよりますが、奨学金は数百万円に及ぶことも多いため、一括返済に応じるのは非常に厳しい状況となるでしょう。
リスク④ 連帯保証人に返済請求が行く
裁判所を通じて一括返済を要求され、対応ができない状況が続くと、次に連帯保証人に対して一括返済の請求が行われます。奨学金の性質上、親や親族が連帯保証人になっていることが多いため、その結果、周囲に迷惑をかけてしまう可能性があります。
連帯保証人に請求が行われる場合、延滞金も上乗せされるため、まとまった金額を一度に返済しなければならなくなります。もし連帯保証人に資産に余裕があれば、そもそも奨学金を借りることはなかったはずです。こうした状況に陥ると、自己破産などの債務整理を検討せざるを得ない事態に発展することもあります。
奨学金返済期間の目安
奨学金返済に苦しんでいる人々の現実について、少しはご理解いただけたでしょうか。次に、奨学金の返済にかかる期間や返済の開始時期、リレー口座とは何か、実際にどれくらいの期間で返済が終わるのかについて解説していきます。これから奨学金を借りることを考えている方にとって、非常に重要な情報です。しっかり確認して、返済計画を早めに考えてみてください。それでは、詳しくご説明します。
奨学金返済開始のタイミング
在学中に奨学金を利用していた場合、返済は貸与終了後、つまり在学期間が終わった月の翌月から7ヶ月目に開始されます。卒業後でも中退した場合でも、最終的に奨学金を借りた月が貸与終了月、いわゆる基準月として計算されます。また、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度を利用している場合、毎月の引き落とし日は27日です。例えば、2021年3月に卒業した場合、返済はその年の10月27日から始まることになります。
リレー口座の仕組みとは
リレー口座とは、返済されたお金が次の世代の学生の奨学金として、リレー形式で利用される仕組みを指す奨学金特有の用語です。なお、このシステムには対応している金融機関と対応していない金融機関があるため、利用前に確認しておくことが重要です。
奨学金完済に必要な実際の期間
返済期間は、主に返済方法によって決まります。この返済方法については、次の項目で詳しく説明いたします。奨学金の返済が毎月一定額で行われる場合、返済期間(回数)は次の式で求めることができます:返済期間(回数)=借入総額 ÷ 割賦金の基礎額 × 12ヶ月。ここで、割賦金とは、複数回に分けて支払う金額を指します。割賦金の基礎額は、年間に支払う金額を示すもので、奨学金の借入額に応じて異なります。そのため、計算を行う際には「奨学金返還年数算出表」を参考にする必要があります。次のシミュレーションでは、この算出表の詳細についても説明しますので、ぜひご確認ください。
奨学金返済の方法とシミュレーション例
前の項目で説明した奨学金の返済方法には、定額返還方式と所得連動返還方式の2種類があります。これから奨学金を借りようと考えている方にとっては、まだ馴染みのない言葉かもしれませんね。今回は、これらの返済方法について詳しく解説し、実際の返済を想定したシミュレーションも行っていきます。奨学金の返済がこれから始まる方や、奨学金の利用を検討している方にとって、非常に役立つ情報になると思いますので、一緒に確認していきましょう。
奨学金返済に必要な金額はどのくらい?
定額返還方式は、借入額に応じて毎月の返済額が決まり、返済が完了するまでその額を支払い続ける方法です。この方式は、第二種奨学金を利用する人に適用されます。返済額は借入総額に対して割賦金の基礎額に基づき、次のように設定されます。
- 借入総額 〜 20万円 → 月々 3万円
- 借入総額 〜 40万円 → 月々 4万円
- 借入総額 〜 50万円 → 月々 5万円
- 借入総額 〜 60万円 → 月々 6万円
- 借入総額 〜 70万円 → 月々 7万円
- 借入総額 〜 90万円 → 月々 8万円
- 借入総額 〜 110万円 → 月々 9万円
- 借入総額 〜 130万円 → 月々 10万円
- 借入総額 〜 150万円 → 月々 11万円
- 借入総額 〜 170万円 → 月々 12万円
- 借入総額 〜 190万円 → 月々 13万円
- 借入総額 〜 210万円 → 月々 14万円
- 借入総額 〜 230万円 → 月々 15万円
- 借入総額 〜 250万円 → 月々 16万円
- 借入総額 〜 340万円 → 月々 17万円
- 借入総額 340万1円〜 → 借入総額の20分の1
これらの基準を参考にして、返済に必要な期間や月々の返済額を算出することができます。次に、実際の例を見てみましょう。
奨学金返済方法とシミュレーション① 定額返還方式の仕組み
定額返還方式は、借入金額に基づいて毎月の返済額が決まる方法で、返済が完了するまでその一定額を支払い続けます。この方式は、第二種奨学金を利用する人に適用されます。具体的な返済額は、借入総額に応じて以下のように設定されています:
- 借入総額 〜 20万円 → 月々 3万円
- 借入総額 〜 40万円 → 月々 4万円
- 借入総額 〜 50万円 → 月々 5万円
- 借入総額 〜 60万円 → 月々 6万円
- 借入総額 〜 70万円 → 月々 7万円
- 借入総額 〜 90万円 → 月々 8万円
- 借入総額 〜 110万円 → 月々 9万円
- 借入総額 〜 130万円 → 月々 10万円
- 借入総額 〜 150万円 → 月々 11万円
- 借入総額 〜 170万円 → 月々 12万円
- 借入総額 〜 190万円 → 月々 13万円
- 借入総額 〜 210万円 → 月々 14万円
- 借入総額 〜 230万円 → 月々 15万円
- 借入総額 〜 250万円 → 月々 16万円
- 借入総額 〜 340万円 → 月々 17万円
- 借入総額 340万1円〜 → 借入総額の20分の1
この基準を基に、返済にかかる期間や月々の返済額を算出できます。次に、実際の例を見ていきましょう。
240万円を借りた場合の返済シミュレーション
この場合、返済期間は240万円を16万円で割り、その結果に12ヶ月を掛けることで計算できます。240万円 ÷ 16万円 × 12ヶ月 = 180ヶ月、つまり15年の返済期間が必要です。さらに、月々の返済額は240万円 ÷ 180ヶ月で計算すると、約13,334円となります。
400万円を借りた場合の返済シミュレーション
この場合、返済期間は400万円を20万円で割り、その結果に12ヶ月を掛けて計算します。400万円 ÷ 20万円 × 12ヶ月 = 240ヶ月、つまり20年間の返済期間となります。月々の返済額は400万円 ÷ 240ヶ月で計算すると、約16,667円となります。ただし、どちらの計算も利息を含まない単純な計算であり、実際には利息分も加算して計算する必要があります。
奨学金の返済方法とシミュレーション② 所得連動返還方式
所得連動返還方式とは、奨学金返済者の前年の収入を基に、その年の月々の返済額が決定される返済方式です。この方式は、低所得者の負担を軽減するための救済措置として、2017年4月から導入されました。対象となるのは、第一種奨学金を利用している人です。所得連動返還方式を選択する場合、マイナンバー(個人番号)の提出が必須となります。最も特徴的なのは、年収に応じて返済額が変動し、返済期間に上限が設けられていない点です。毎月の返済額は、前年の収入の9%を12ヶ月で割った金額として計算されます。最小の返済額は2000円で、計算した金額が2000円を下回る場合でも、月々の返済額は2000円になります。なお、初年度に収入がない場合は、定額返還方式に基づき割賦金の半額を毎月返済することとなります。返済が難しい場合は、申請を行うことで月々2000円の返済に変更することも可能です。
奨学金返済が困難な場合の対処法
独立行政法人日本学生支援機構では、経済的に困難な状況や失業、傷病、災害などにより奨学金の返済が難しくなった場合、条件を満たせば以下のような救済措置を利用できることがあります。問題が発生したら、できるだけ早く日本学生支援機構などの奨学金提供機関に相談することをお勧めします。
さらに、地方公共団体と地域産業界が連携し、地元企業に就職した場合に奨学金返還を支援する仕組みも存在します。各地方公共団体のWEBサイトで詳細を確認することができるので、ぜひチェックしてみてください。
年収325万円以下の方は「減額返還制度」の利用が可能
減額返還制度は、毎月の奨学金返済額を減らし、支払いを軽減できる仕組みです。この制度を利用できる収入の基準は以下の通りです。
【収入・所得金額の目安】
- 給与所得者の場合
年間収入金額が325万円以下(所得証明書等の提出が必要)
本人の被扶養者については、1人につき38万円を収入・所得金額から控除し審査します。 - 給与所得以外の所得が含まれる場合
年間所得金額(必要経費等控除後)が225万円以下(所得証明書等の提出が必要)
本人の被扶養者については、1人につき38万円を収入・所得金額から控除して審査されます。
引用:日本学生支援機構「減額返還制度の収入・所得金額の目安」
このように、年収が325万円以下の方は減額返還制度の対象となります。主に、自然災害や病気・ケガ、経済的理由などで返済が難しくなった方々に向けた制度です。
一度手続きを行えば、適用期間は12ヶ月で、最長180ヶ月(15年)まで延長可能です。急な経済的困難に直面した際に助けとなる制度です。
手続きはスカラネット・パーソナルなどから行え、申請に必要な書類は次の通りです:
- 住民税非課税証明書(原本)、所得証明書(原本)、または市・県民税(所得・課税)証明書(原本)のいずれか1つ
- 失業中の場合:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、または失業者退職手当受給資格証のいずれか1つのコピー
また、2018年9月以降、減額返還申請時にはマイナンバーの提出が必須となりました。これにより、一部の書類提出が省略できる場合があります。
減額される具体的な金額は個々の状況によりますが、毎月の返済額が最大で3分の1から2分の1程度まで減らせる可能性があり、返済負担を軽減できるでしょう。
制度の詳細
減額返還制度は、月々の返済額を減らし、その代わりに返済期間を延ばす制度です。具体的には、返済額を半額(2分の1)または3分の1に減らす代わりに、返済期間もそれぞれ2倍または3倍に延長されます。
制度利用の対象となる条件
この制度は、災害、傷病、その他の経済的な理由に該当する人が利用できる制度です。
利用時の注意点
この制度は「月々の返済額を減額する」ことを目的としており、借入総額が減少するわけではありません。また、利息は引き続き発生するため、注意が必要です。制度を利用するには、必要な証明書を提出し、その内容が制度の要件に合致していることが求められます。
年収300万円以下の場合は「返還期限猶予」の申請を検討
自然災害や病気・ケガ、失業などの経済的困難が原因で奨学金の返済が難しい場合、減額返還制度と同様に「返還期限猶予」を申請することができます。返済が始まる前に手続きを行うことで、返済を一時的に猶予してもらうことが可能です(すでに延滞している場合でも認められることがあります)。
申請が受理されると、返済期限が猶予されますが、その分返済終了時期も延長されることを覚えておきましょう。手続きには、奨学金返還期限猶予願とマイナンバー提出書を記入し、返済が難しい理由を示す証明書を添えて、日本学生支援機構に提出する必要があります。
返還期限猶予は、毎年届出を行う必要があり、最大で120ヶ月(10年)まで猶予を受けることができます。手続きはスカラネット・パーソナルからオンラインで行えます。
申請に必要な所得基準としては、年収300万円以下となっており、詳細は日本学生支援機構の公式サイトで要件を確認して、自分が該当するかどうかをチェックしてください。
最大10年の猶予を受けるための利用条件
この制度の猶予に上限が設けられるのは、現在失業中であることや、経済的に困窮していることが理由で利用した場合です。
無期限猶予を受けるための利用条件
猶予に期限が設定されないのは、傷害や疾病、生活保護の受給中、現在失業中、経済的に困窮している場合、特別研究員、新卒、災害の影響を受けた場合、産前・産後休業や育児休業中、大学在学中、海外に住んでいる、今年国外から帰国する、海外に派遣されている、国外で研究している、または海外留学中の場合です。失業や経済的困難は、これらの状況に該当する可能性があることに注目していただければと思います。
「所得連動返還方式」への変更が可能な貸与型第一種
日本学生支援機構から無利子の奨学金である第一種奨学金を受給している場合、「所得連動返還方式」に変更できる可能性があります。この返還方式では、返済額が所得額に応じて変動します。
申請の条件としては、2017年4月以降に第一種奨学金を受けた方が対象で、手続きはスカラネット・パーソナルや郵送で行うことができます。毎年10月に返還月額が更新され、例えば2022年10月のケースでは、年収300万円で月額約8,600円、年収450万円で月額約15,400円となっています。
定額返還方式(毎月同額返済)の場合、月額約13,333円となるため、年収300万円の人では月々約5,000円の負担軽減が見込まれます。しかし、年収が増えると、定額返還方式よりも返済額が増える点に注意が必要です。
なお、月々の返済額は減っても、総返済額は変わらないため、返済期間が長期化します。これは債務そのものを減らすものではないため、あくまで一時的な返済負担軽減策として利用することが考えられます。
日本学生支援機構に相談する方法
奨学金の返済に関する不安や問題がある場合、まずは日本学生支援機構(JASSO)に相談することが効果的です。日本学生支援機構は、奨学金制度を運営しており、返済に関する専門的な知識と情報を提供しています。
返済が難しいと感じる学生や卒業生には、具体的なアドバイスや解決策が提供されます。返済計画の見直しや返済方法の変更、支援制度の案内など、個々の状況に応じた対応を受けることができます。
返済に関する悩みや問題を抱えている場合、まずは日本学生支援機構に相談することをお勧めします。
債務整理を検討する方法
奨学金の返済が長期的に困難な状況にある場合、債務整理を検討する必要があります。債務整理には、個々の経済状況に応じて「個人再生」「自己破産」「任意整理」などの選択肢があります。
個人再生
個人再生は、裁判所を介して債務の一部を免除し、残りの債務を分割払いで返済する方法です。この手続きにより、返済額を大幅に減らすことができます。個人再生は、多額の借金があるものの、処分したくない資産を持っている場合に有効な選択肢です。ただし、申立てには特定の条件があり、財産状況や収入によっては利用できないこともあります。
自己破産
自己破産は、裁判所の決定により、全ての債務を免除してもらう方法です。この手続きによって、ほぼすべての債務から解放されることが可能ですが、自己破産には深刻な影響があります。家や車といった資産は全て処分され、信用情報にも長期間悪影響を及ぼします。そのため、新たな借入やクレジット契約が一定期間できなくなるなど、最終的な手段として慎重に選択する必要があります。
任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉を行い、債務の条件を見直す方法です。この手続きを通じて、返済額や返済期間を再交渉し、負担を軽減することができます。任意整理は裁判所を介さないため、手続きが比較的簡単で、信用情報への影響も比較的少ないです。しかし、債権者全員の同意を得る必要があり、交渉がうまくいかない場合もあります。
身近な人に相談することの重要性
日本学生支援機構の制度が利用できなかったり、利用したくない場合は、信頼できる身近な人に相談することが重要です。悩みを一人で抱えていても、どのように対処すべきか分からず、状況が悪化する可能性があります。
早めに相談をすることが理想ですが、一度滞納してしまうと、連帯保証人に日本学生支援機構から連絡が行くため、その前に相談しておくと良いでしょう。もし家族に返済を立て替えてもらえるなら、滞納を防ぐことが可能です。
立て替えてもらう際には、後々のトラブルを防ぐために、借用書を作成し、返済方法について事前に合意しておくことが重要です。また、奨学金の返済が難しいからといって、安易にカードローンを利用することは避けましょう。カードローンの金利は奨学金よりも高いため、根本的な解決にはならず、返済がさらに厳しくなります。
日本学生支援機構が提供する各種制度と併せて検討し、適切な方法を見つけることが大切です。
いずれにせよ、奨学金の返済に関する問題は、身近な人にも影響を及ぼすことを理解するべきです。問題を先延ばしにしていると、事態が悪化する可能性があるため、勇気を出して話し合うことが非常に重要です。
やむを得ない状況の場合、「返還免除」が適用されることがある
以下の条件に該当する場合、手続きを行うことで「返還免除」が認められることがあります。
・本人が死亡し、返還が不可能になった場合。
・精神的または身体的な障害により労働能力を喪失した、または高度な制限がかかり、返還ができなくなった場合。
本人の状況に応じて、返還免除が全額か一部かが決定されます。申請には医師の診断書(日本学生支援機構所定の用紙が必要)などの提出が求められるため、公式サイトで申請条件や必要書類を確認してから手続きを行いましょう。
市や企業による奨学金返還支援制度
一部の地方公共団体や企業では、奨学金の返済を支援する「返還支援制度」を導入しています。この制度の内容やそのメリットについて、以下で詳しく説明します。
返還支援制度の基本情報
返還支援制度とは、日本学生支援機構の貸与型奨学金を利用していた方に対して、その返済額の一部または全額を企業が代行して返済する仕組みです。
企業はこの制度を福利厚生の一環として導入でき、奨学金を利用した社員と企業の双方にメリットがあります。これらのメリットについては、次の段落で詳しく説明します。
企業による支援活動
企業が返還支援制度を導入すると、企業が直接日本学生支援機構に代理で奨学金の返済を行うことになり、このプロセスを通じて企業側にもさまざまなメリットが生まれます。
そのメリットには、税金負担の軽減、従業員のサポートによる離職率の低下、採用活動でのPR効果などが含まれます。
地方公共団体による支援活動
日本の各地方公共団体は、地元で働く奨学金を受けた人を対象に、返還支援制度を提供しています。この制度では、奨学金の返済を代行することにより、地元企業への定着を促進し、都市部からのUターン就職の活性化を図ることができます。現在、33府県と487の市町村がこの返還支援制度を実施しています。
経済的に余裕ができた場合、一括返済や繰上返済を検討する
経済的に余裕ができ、奨学金の返済を早期に終わらせたい場合は、一括返済や繰上返済を活用することができます。これらの返済方法を利用することで、完済までの期間が短縮されるだけでなく、利息の総額を減らすことも可能です。
奨学金を早期完済したい方におすすめの繰上げ返済とは?
返済が厳しい方に焦点を当てた制度の紹介を行いましたが、逆に経済的に余裕があり、できるだけ早く完済したいと考える方もいらっしゃるでしょう。そんな方には「繰上げ返済」がおすすめです。この制度では、引き落とし日前に返済金を繰上げて一括で支払うことができます。第一種奨学金でも第二種奨学金でも、どちらでも利用可能です。利用するためには、スカラネット・パーソナルにアクセスする必要があります。申し込み手続きはスカラネット・パーソナル内で完了しますが、郵送やFAX、電話での申し込みも受け付けています。ただし、郵送やFAXを利用する際には、スカラネット・パーソナルで書類請求を行う必要があるため、アクセスができない場合は「奨学金電話相談センター」に連絡して手続きを進めましょう。
奨学金利用者が押さえておくべき注意点
奨学金を利用する際には、事前に知っておくべきことや注意すべき点がいくつかあります。これらを簡潔にまとめると、返済の滞納は絶対に避けること、返済のために借金をしないこと、初任給が少なく、その金額の上昇が簡単ではないこと、ひとり暮らしは生活費の負担が大きいこと、そして詐欺に気をつけることです。これから奨学金を借りる予定の方や、返済が始まる方、すでに返済を開始している方も、改めて注意が必要な内容となっています。それぞれの点について、順番に確認していきましょう。
①奨学金の返済は絶対に滞納しない
奨学金の返済は絶対に滞納してはいけません。滞納をすると、遅延金が発生し、連帯保証人にも返済の請求がいきます。また、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、全額の一括返済を求められる可能性もあります。さらに、給料や財産が差し押さえられるといった事態も考えられます。例えば、個人信用情報機関に登録されると、その情報は5年間保持され、その後奨学金を完済してもクレジットカードの発行やローンを組む際に大きな影響を与えることになります。最終的に自己破産を選んだ場合でも、その影響は家族にも及びます。滞納することによって、一層経済的に厳しい状況が生じるため、奨学金は借金であることを十分に認識し、滞納が招くリスクを理解しておきましょう。
②奨学金返済のために金融機関からの借入は避ける
奨学金の返済を金融機関からの借金で工面することは避けましょう。この方法では、いわゆる自転車操業に陥ってしまいます。奨学金を返済しても、その返済額と同じ額の借金が残り、さらにその借金には利息が加算されます。結果として、借金は少しずつ確実に膨らんでいくことになります。また、もし金融機関への返済が滞ると、遅延金が発生し、気づけば自力では返済できない額になってしまう可能性もあります。さらに、個人信用情報機関に登録されることも避けられません。その結果、金融機関を頼る前よりも状況が悪化する恐れがあります。返済が苦しい時には、制度を活用するなどして、金融機関からの借金に頼るのは再考すべきです。
③就職後の給与は低めで、昇給は簡単ではないことを理解しておく
「社会人になれば毎月給料が支給されるし、返済が厳しいなんてことはないだろう」と楽観的に考えている方もいるかもしれません。しかし、奨学金返済者の現状を説明した部分でも触れたように、四年制大学卒業者の初任給の平均は額面で212,000円、手取りで169,000円です。この金額を見て「でも、昇給するから大丈夫だろう」と考えるかもしれません。しかし、ある調査によれば、2019年の昇給額の平均はわずか5,997円です。昇給額とは、その年と前年の同月の収入の差を比較して算出された増額のことを指し、つまり1年間で平均しておよそ6,000円弱の昇給があるということです。実際にはほとんどの場合、この昇給額では奨学金の月々の返済額にすら届かないのが現実です。奨学金を借りる際には、就職後の給与に頼りすぎることが危険であることを、再確認しておくことが重要です。
④一人暮らしでは生活費が高くなる
再度触れますが、34歳以下のひとり暮らし世帯の月々の平均支出額は155,000円です。この内訳は、家賃64,000円、水道光熱費7,000円、ガス代2,500円、通信費7,000円、保険医療費3,600円、交通費7,200円、食費39,000円、洋服7,700円、交際費12,000円、理美容サービス2,000円、理美容品3,000円となり、総額で155,000円を超えています。節約できる部分はあるかもしれませんが、贅沢な暮らしではないことがわかるでしょう。初任給の平均額を考慮すると、生活費が給料の大部分を占めることは明らかです。昇給があったとしても、生活費が大きな負担となり、昇給分はほとんど意味をなさない場合が多いのが現実です。支出の中には奨学金返済以外にもさまざまな費用が含まれていることを、忘れずに考慮する必要があります。
⑤奨学金に関連する詐欺に警戒する
最後に注意していただきたいのが詐欺の問題です。実際に、日本学生支援機構の職員を名乗る詐欺師が「高校時代の奨学金を合わせて一括返済してほしい」と言って現金をだまし取ろうとした事例があります。確かに日本学生支援機構は奨学金を融資する機関ですが、滞納時の現金回収は債権回収業者が行い、機構自体が現金を回収することはありません。また、他にも詐欺の手口が存在しており、返済者の保護者に対して「奨学金返済に250万円の滞納があり、このままだと法的措置を取ることになる。指定の連絡先に連絡してほしい」と非通知で電話がかかってきたケースも報告されています。仮に滞納があったとしても、そんな大きな滞納額が蓄積されてから保護者に連絡が行くことは通常あり得ません。万が一詐欺に遭ったり、疑わしい場合は、奨学金相談センターに連絡して確認をしましょう。
奨学金返済の滞納時に気をつけるべきポイント
奨学金の返済が滞ると、以下のようなリスクが発生します。
奨学金返済の滞納によるリスク
- 延滞金の発生
- 個人信用情報への登録
まず、返済期日に引き落としができない場合、延滞金が発生します。延滞金は返済期日の翌日から支払日までの日数に基づいて計算されるため、滞納した場合は速やかに返済を行うことが重要です。
さらに、滞納が3ヶ月以上続くと、信用情報機関に滞納情報が記録されます。信用情報に滞納の記録が残ると、分割払いの利用やローンの申請ができなくなったり、クレジットカードの作成が難しくなったりするため、十分な注意が必要です。
奨学金返済の滞納を避けるための節約術
奨学金の返済を滞らせないためには、家計をしっかり管理し、毎月の返済額を確保することが大切です。以下に、実践しやすい4つの節約方法を紹介します。
節約方法
- 家計簿をつけて、月々の収支を把握する
- 生活費の見直しと節約を行う
- ふるさと納税を活用する
- クレジットカードを賢く利用する
毎月の収支を把握するために家計簿をつける
毎月の収支を家計簿に記録して把握し、定期的に見直すことで、無駄な支出や節約できる項目を洗い出すことができます。収支管理には、ノート型の家計簿やアプリの活用に加え、利用履歴が残るキャッシュレス決済を使うのも一つの方法です。
返済計画を立てて完済までの道筋を明確にする
返済を順調に進めるためには、しっかりとした返済計画を立てることが重要です。完済までの期間を明確にし、毎月の返済額を事前に計算しておくことがポイントです。また、将来の収入の見込みやキャリアプランを考慮し、返済計画を柔軟に調整することも大切です。計画的に返済を行うことで、金銭的な負担を軽減し、返済の見通しを立てやすくなります。
クレジットカードを上手に活用して節約する
日々の支払いをクレジットカードでまとめると、利用金額に応じてポイントが貯まり、お得に活用できます。貯まったポイントは家電や他社ポイント、マイルなどに交換できるため、節約にもつながります。また、クレジットカードの利用履歴はWEB明細で確認できるので、家計簿をつける手間が省けます。収支を把握したり、支出の見直しをしたり、クレジットカードを効果的に活用したりすることが重要です。まずはできるところから始めてみましょう。
ふるさと納税を利用して節約する
ふるさと納税も節約の方法としておすすめです。応援したい自治体に寄付すると、2,000円を超える寄付金については、所得税や住民税の控除を受けることができ、さらに自治体からの返礼品として特産物をもらうことができます。食費の節約には、肉や魚などの食材を返礼品として選ぶと効果的です。ただし、控除を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。
生活費の見直しで節約を実現する
生活費を節約するためには、携帯電話料金や水道光熱費、サブスクリプションサービスなどの毎月の固定費を削減することが重要です。料金プランをより安いものに変更したり、使っていないサービスを解約するなどして、契約内容を見直してみましょう。
奨学金返済を楽にするための実践方法
奨学金の返済は、多くの人にとって非常に負担が大きいものです。しかし、その負担を少しでも軽減することは不可能ではありません。この項目では、高校生、大学生、そして社会人がそれぞれできること、考えるべきことを分けてご紹介します。奨学金を利用している方々ができることや意識すべきことを、少しずつ取り組んでいくことで、返済の苦しさを和らげる手助けになるでしょう。
高校生ができる奨学金対策
まずは高校生ができることについてです。大学進学の際に奨学金を利用しようと考えている人は少なくないでしょう。そんな高校生ができることとして、教育費用(例えば予備校や塾など)の見直し、返済が不要な給付型奨学金の利用を考えること、国公立大学への進学を選択肢として考慮すること、そして奨学金自体についての知識を深めることが挙げられます。奨学金を借りる前に、なぜ多くの大人が返済に困っているのか、その根本原因を理解することが大切です。将来、後悔しない選択をするために、じっくりと考えることが必要です。また、高校生の段階から費用の見直しを行い、その結果得られたお金を学費に充てるなどの資金調達方法も重要になってきます。
大学生が実践できる奨学金対策
次に、大学生ができることについてです。返済が始まる日を見据えて、奨学金を借りている大学生は、大学内で提供されている給付型奨学金を積極的に活用し、社会人としての生活に関わるお金についての知識を身につけることが重要です。また、必要以上に奨学金を借りないようにすることも大切です。過剰に借りると、将来的に返済時に自分自身を苦しめることになります。さらに、各大学で提供されている給付型奨学金を活用することで、成績を向上させる動機にもなり、学業へのモチベーションアップにもつながります。そして、お金に関する知識をしっかり学んでいくことが重要です。特に保険については、就職前に自分に必要かどうかを考え、必要な準備をしておくことをお勧めします。
社会人が実践すべき奨学金返済対策
最後に、奨学金を返済する社会人ができることについてです。社会人として奨学金を完済するためには、家賃を安易に引き上げないこと、残業代やボーナスなどの変動する収入を生活費に使わないこと、昇給に向けて努力をすること、そして万が一返済ができなくなった場合の対処法を理解しておくことが重要です。生活水準をむやみに上げることは避けるべきです。また、残業代やボーナスに頼って生活すると、期待した額が入らなかった場合に困窮する恐れがあるため、このような収入に依存しない生活を心掛けましょう。そして、最も大切なのは、もし奨学金が払えなくなったときの対応策を事前に知っておくことです。支払いができなくなった場合は、すぐに日本学生支援機構に連絡をし、その旨を伝えることが大切です。誤魔化すのではなく、早期に行動することが問題解決への第一歩となります。
奨学金がクレジットカードの審査に与える影響はない
最後に、奨学金を返済する社会人ができることについてです。社会人として奨学金を完済するためには、家賃を安易に引き上げないこと、残業代やボーナスなどの変動する収入を生活費に使わないこと、昇給に向けて努力をすること、そして万が一返済ができなくなった場合の対処法を理解しておくことが重要です。生活水準をむやみに上げることは避けるべきです。また、残業代やボーナスに頼って生活すると、期待した額が入らなかった場合に困窮する恐れがあるため、このような収入に依存しない生活を心掛けましょう。そして、最も大切なのは、もし奨学金が払えなくなったときの対応策を事前に知っておくことです。支払いができなくなった場合は、すぐに日本学生支援機構に連絡をし、その旨を伝えることが大切です。誤魔化すのではなく、早期に行動することが問題解決への第一歩となります。
返済が困難な場合は債務整理を考慮する
日本学生支援機構の制度を利用したり、身近な人に相談しても返済の見通しが立たない場合、「債務整理」を選択肢として考えることができます。債務整理には主に、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、いずれも債権者との交渉や裁判所を通じた手続きが必要です。これらの基本的な仕組みについて理解しておくことが大切です。
また、債務整理を行うことで、自分自身だけでなく家族や親族にも影響が及ぶことがありますので、慎重に判断することが求められます。具体的にどのような仕組みで債務整理が行われるかについて、これから詳しく解説します。
任意整理を行うのは難易度が高い
「任意整理」とは、裁判所を通さず、債権者と直接交渉をして利息の減額を求める方法を指します。通常、元金を3~5年の期間で返済する方法ですが、奨学金の場合、上限金利が3.0%であるため、利息をカットしても返済総額にはあまり大きな違いはないかもしれません。
また、日本学生支援機構が任意整理に応じる可能性は非常に低いと言えます。機構は公的機関であり、任意整理よりも手続きが簡便で迅速な救済制度を提供しています。そのため、任意整理の選択肢が適用されることは少ないです。
さらに、仮に任意整理を実施できた場合でも、連帯保証人の返済義務は消えません。そのため、家族や親族に返済請求が行くことになりかねません。債務整理を行う際は、自分一人で決めるのではなく、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが大切です。
法テラス(日本司法支援センター)や各市区町村の相談窓口を利用すれば、専門家の紹介を受けることができます。債務整理を検討する際は、早めに相談し、初回相談が無料の場合も多いので、整理した質問をメモして分からない点を遠慮せずに尋ねることが重要です。
専門家に相談すると、自分では気づかない点に気づくことができ、どのように生活を立て直すかについて客観的なアドバイスが得られます。ただし、最適な方法は人それぞれ異なるため、複数の意見を参考にし、慎重に判断することをお勧めします。
自己破産
「自己破産」とは、持っている財産や収入状況では債務を返済する見込みがない場合に行える手続きであり、裁判所の許可を得ることで、原則として債務の支払義務が免除される仕組みです。なお、自己破産により債務の支払義務が免除されるための要件は以下のとおりです。
【自己破産の要件】
・裁判所に支払不能であると認められていること
・過去7年以内に免責を受けたことがないこと ※個別の事情を考慮し、認められる場合もあります
自己破産を行う最大のメリットは、債務が免除されることで借金に関する悩みから解放され、ストレスからも解放される点にあります。これにより、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能となるでしょう。
一方で、自己破産をすると、まず信用情報機関に金融事故情報として登録され、クレジットカードの作成や新たな借入ができなくなるなどのデメリットが発生します。もともと多額の借金に悩んでいるケースであるため、しばらくは生活再建に専念し、新たな借入を控えるのが無難です。また、個人再生と同様に官報に掲載されるほか、自己破産の手続きが完了するまで、保険外交員や警備員など就けない職業がある場合もあります。
さらに、ローンを返済中の高価な財産は処分しなければならず、結果として持ち家や自動車を手元に残すことができなくなる可能性が高いです。当面の生活費や身の回りのものなど、一定の財産の所有しか認められないため、自己破産直後は暮らしに不自由さを感じる部分も多いでしょう。
また、本人が自己破産を行ったとしても、連帯保証人の債務までが免除されるわけではありません。例えば奨学金の場合、本人が自己破産すると連帯保証人に請求が行く可能性が高くなります。連帯保証人への請求を避けるためには、本人と一緒に自己破産をする必要がありますが、その後の生活の立て直しや親族との関係を考えると、慎重な判断が求められます。
自己破産は、債務を返済する手段がどうしても見つからない時の最終手段でもあるため、弁護士や司法書士などの専門家の意見を聞き、気になる点は遠慮なく尋ねることが大切です。お金のことで悩んでいると視野が狭くなりがちなので、第三者の意見も取り入れ、冷静に対処することが必要です。また、自己破産を行わなくても借金問題を解決できる方法があるならば、諦めずに取り組むことも重要です。
個人再生
「個人再生」は、裁判所に再生計画を提出し、その計画に基づいて債務を大幅に減額してもらう手続きです。この手続きを利用することで、減額された債務を3〜5年かけて返済し、残りの借金については支払い義務が免除されます。
債務の減額率は状況によって異なり、通常は元金の5分の1から10分の1程度まで圧縮される可能性があります。例えば、借金が300万円ある場合、5年間(60ヶ月)で返済する際には、月々50,000円を支払う必要がありますが、減額後は5分の1となれば月々の支払いは10,000円にまで軽減され、大きな負担減となります。
自己破産では、価値のある財産を処分しなければなりませんが、個人再生の場合、住宅ローンについては「住宅資金特別条項」により別枠として扱われるため、マイホームを手放すことなく手続きを進めることが可能です。これにより、生活環境を大きく変えることなく債務の削減を目指すことができるのは大きな利点です。
個人再生は、任意整理では対応できないほどの多額の借金がある場合や、家を手放したくないケースに適しています。また、特定の職業(例えば保険外交員や警備員など)についている場合で、自己破産が難しい状況にも有効です。
さらに、個人再生を進める際にカーローンが完済されていれば、所有する自動車を手放さずに済みます。ただし、カーローンの支払いが残っている場合、ローン会社が自動車を引き取ることになるので注意が必要です。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼すれば、督促が停止します。これは、貸金業法第21条に基づき、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った貸金業者は、それ以後、債務者本人に直接連絡することが禁止されているためです。
一方で、個人再生にはデメリットも存在します。手続き内容や氏名、住所などが官報に掲載されますが、官報は一般的に目にすることは少ないため、周囲に知られる可能性は低いと言えます。
また、個人再生は債務の減額交渉の手段に過ぎないため、減額後の債務の返済は続けなければなりません。したがって、返済を続けるための安定した収入がない場合、個人再生手続きは進められませんので、十分に収入状況を考慮する必要があります。
奨学金返済は計画的に進めよう
奨学金制度は、進学を希望するものの経済的に困窮している若者を救うありがたい仕組みです。しかし、学校を無事に卒業し就職に成功すると、以後はその返済に追われることとなります。生活をひっ迫させずに返済を継続できる人であれば問題はありませんが、家庭の事情などにより毎月の返済が苦しいというケースもあります。
このように、奨学金にはメリットとデメリットという二面性があり、そのデメリットとなる問題を改善してくれるのが、奨学金返済に関する各種制度です。
今回の記事では、以下のポイントについて解説しました。
・奨学金の概要について
・奨学金の種類について
・奨学金の具体的な返済額と返済期限の例
・奨学金の繰上げ返済について
・奨学金の返済に関する各種制度について
・地方公共団体や企業が実施している奨学金返済の支援制度について
奨学金はさまざまなタイプが存在し、その種類によって返済が必須となる場合と不要な場合に分かれます。どの奨学金が自分に適しているかを十分に考慮することが大事です。また、奨学金返済に関する支援制度も多様で、どの種類があるのかをしっかりと把握することで、返済の苦労を軽減できるでしょう。
今回の記事を参考にして、奨学金返済の辛さを乗り越えていただければ幸いです。奨学金に関して悩みがある場合は、日本学生支援機構の奨学金返還相談センター(03-6743-6100)への相談もおすすめします。