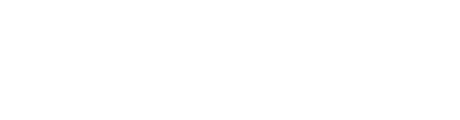※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
奨学金が返せないときはどうする? 相談先と救済制度の利用方法を解説
目次
- 奨学金が返せないときはどうする? 相談先と救済制度の利用方法を解説
- そもそも奨学金とはどのような制度なのか?
- 奨学金が払えなくなるのはなぜか
- 返済を無視していると発生するリスク
- 奨学金が支払えないとどうなるの?
- 奨学金は時効が成立すれば、踏み倒すことができるのか?
- 奨学金が返せないとき、どこに相談すべきか?
- 日本学生支援機構に、救済制度が利用できるかどうか相談する
- 例:減額返還制度を利用した場合
- 減額返還制度の利用条件
- 減額返還制度の利用方法
- 返還期限猶予制度とは
- 例:返還期限猶予を利用した場合
- 返還期限猶予制度の利用条件
- 返還期限猶予制度の利用方法
- 実際に返還期限猶予制度を利用した人の体験談
- 返還免除制度とは
- 返還免除制度の利用条件
- 返還免除制度の利用方法
- 弁護士に債務整理を利用して借金を解決できるか相談する
- 債務整理とは
- 債務整理の種類と適用ケース
- 債務整理のデメリット
- 任意整理とは
- 奨学金における任意整理の利用について
- 任意整理を利用できる目安
- 個人再生とは
- 個人再生と奨学金の関係
- 個人再生を選択すべきケース
- 自己破産とは
- 自己破産の条件
- 自己破産のデメリット
- 奨学金の返還を延滞し続けると、どうなるのか?
- 奨学金の返還を延滞するとどうなるのか?
- 【返還期日の翌日から】延滞金が発生する
- 奨学金の延滞金について
- 延滞金の計算方法
- 【返還期日の翌日以降】電話や文書による督促が行われる
- 奨学金の延滞による督促について
- 用語集:債権回収会社とは?
- 電話による督促の内容
- 延滞が2か月以上続いた場合
- 【延滞が3ヶ月以上続くと】信用情報機関に事故情報が登録される
- 奨学金の延滞が3か月を超えると信用情報に影響が出る
- 用語集:信用情報機関とは?
- 奨学金を滞納した場合の信用情報への影響
- 【延滞が9ヶ月以上続くと】一括返還が請求される
- 延滞が9か月以上続くと一括請求の可能性がある
- 用語集:期限の利益とは?
- 一括請求への対応について
- 【延滞が9ヶ月以上続くと】差押えなどの法的措置が取られる可能性もある
- 一括請求を放置するとどうなるのか?
- 主な差押えの対象
- 最も差押えられやすいのは給与
- 奨学金は踏み倒せるのか?その難しさの理由を紹介
- 多くの奨学金には返還義務があることに注意が必要です
- 奨学金が払えない時に利用できる救済制度
- 奨学金がを払えないときの対処法
- 万一、奨学金を払えないときの対処法
- 奨学金を払えないときの主な対処法
- 支出を削減する
- 支出を減らして奨学金の返還に備える
- 具体的な支出の見直し方法
- 固定費の削減が効果的
- 収入を増加させる
- 収入を増やして奨学金の返還に備える
- 具体的な収入を増やす方法
- 状況に応じた収入の増やし方
- 奨学金の救済制度の活用も検討
- 所有している物を売る
- 不用品を売って奨学金の返還資金を作る
- 売却方法の選択肢
- フリマアプリの例
- 日雇いアルバイトで収入を増加させる
- 収入を増やして奨学金の返済に備える
- 日雇いバイトの注意点
- バイト情報サイトの例
- 債務整理を利用する
- 奨学金以外にも借金があり、完済の目処が立たない場合の対処法
- 債務整理の主な方法
- 債務整理を選択する際の注意点
- 親族に援助をお願いする
- 親族から援助を受けて奨学金を返還する
- 援助を受ける際の注意点
- 金融機関から融資を受ける
- カードローンを利用して奨学金を返還する方法について
- 金融機関からの借入で一時的に対応できる
- 奨学金が返せない場合に避けるべきNG行動
- まとめ
高校や大学への進学時に奨学金を利用する人は多いでしょう。特に、日本学生支援機構の奨学金制度は、多くの学生が利用し、卒業後に返還が必要となります。返済を延滞すると、信用情報機関に事故情報が登録されるなど、借金と同様の対応が取られるため注意が必要です。もし奨学金の返済が払えない場合は、そのままにせず、早めに専門家へ相談しましょう。本記事では、日本学生支援機構の奨学金を例に、返済ができない際に起こることや、救済制度、対処法、相談先について解説します。
そもそも奨学金とはどのような制度なのか?
奨学金は、学生自身が契約できる学資ローンとは異なります。これは、経済的な理由で進学が難しいものの、優秀な学生が学業に専念できるよう支援するために設けられた制度です。運営を担うJASSO(日本学生支援機構)は営利団体ではなく、一般的な金融機関と比較して低金利で貸付を行っています。
奨学金制度とは
経済的な事情により修学が困難な優れた学生に対し、学資の貸与を行う制度です。さらに、経済や社会の状況を考慮しながら、学生が安心して学べるよう「貸与」または「給付」による支援が提供されています。
奨学金を払えない若者が増加している
奨学金制度を利用したものの、卒業後に収入が安定せず返済が難しくなる人は決して少なくありません。
奨学金を返済できない人の割合が増加していることから、制度自体の見直しが必要だという議論が、ニュースでもたびたび取り上げられています。
奨学金の滞納が各新聞社でも報じられる
奨学金が返せない原因は学費よりも「一人暮らし」
近年、教育費や奨学金に関するニュースが多く報道されています。その発端となったのは、2016年4月に放送された「奨学金の返済に困り、風俗店で働く人がいる」という衝撃的なニュースでした。この報道をきっかけに、2017年度から給付型奨学金の導入や大学の授業料無償化が急きょ検討されるようになりました。
奨学金が返済できない主な理由は経済的な生活の不安定さ
奨学金を返済できなくなる最も大きな要因は、卒業後の経済的な不安定さにより、毎月の決まった返済額を支払うことが難しくなるためです。
このように、多くの人が不安定な生活を送る背景には、まず景気の悪化による正規雇用の減少があります。安定した職に就けない人が増えていることが、返済困難の大きな要因となっています。また、少子化の影響で学費が高騰し、借入額が大きくなっていることも重要な問題です。
現在、奨学金の返済問題は一部の人だけに影響するものではなく、社会全体に広がる深刻な課題となっています。
奨学金を受給している割合は5割
以下は、日本学生支援機構が実施した調査による、大学生の奨学金受給率に関する割合です。
参照元:日本学生支援機構「平成28年度学生生活調査結果」
日本学生支援機構の平成28年度学生生活費調査によると、日本学生支援機構や大学などが提供する何らかの奨学金を利用している学生は、全体の約5割弱にのぼります。さらに、貸付を受けられなかった学生や、希望はあったものの申し込まなかった学生も含めると、奨学金を必要としている学生は5割以上に達すると考えられます。
奨学金を払えない人への厳しい取り立てが横行している
JASSOでは、奨学金の返済が滞っている人に対し、督促措置を講じたり、信用情報へ記録したりする対応が取られています。JASSOは営利団体ではないものの、同時に慈善団体でもないため、返済が滞ると制度の運営自体が難しくなってしまうのです。
未納が続くと最終的には給料や財産の差押えに
奨学金を滞納し続けると、その期間に応じて対応が厳しくなっていきます。
まず、滞納すると割賦金の額に対し、年間10%の延滞金が発生します。さらに、滞納が3か月続くと個人信用情報機関に個人情報が登録され、いわゆるブラックリスト扱いとなるため、ローンなどの審査が通らなくなります。加えて、滞納が9か月以上に及ぶと、強制執行が可能となり、給料や財産の差押えが行われることになります。
奨学金が払えなくなるのはなぜか
奨学金の返済が難しくなる原因は、どこにあるのでしょうか。
人によって事情は異なりますが、多くの場合、主な理由として以下の2つが挙げられます。
奨学金が払えなくなる主な原因
実際に奨学金の返済ができずに滞納すると、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
返済を無視していると発生するリスク
延滞が続くと、最大10%の延滞金が発生する
滞納が3か月続くと、信用情報機関に滞納記録が登録される
9か月以上滞納すると、財産の差押えが可能になる
申込時に保証人となった人に迷惑がかかる
奨学金の返済ができない状況が続くと、これらのような問題が生じてしまいます。
それぞれのリスクについて詳しく確認していきましょう。最悪の場合、人生設計に影響を及ぼす可能性もあるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
奨学金を払えない場合に生じるリスク
延滞が続くと、最大10%の延滞金が発生する
滞納が3か月続くと、信用情報機関に滞納記録が登録される
9か月以上滞納すると、財産の差押えが可能になる
申込時に保証人となった人に迷惑がかかる
奨学金の返済ができない状況が続くと、これらのような問題が生じてしまいます。
それぞれのリスクについて詳しく確認していきましょう。最悪の場合、人生設計に影響を及ぼす可能性もあるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
最大10%の延滞金が発生し、さらに状況が厳しくなる
JASSOでは、返還期日(※)までに返済が行われない場合、本来の返済額に延滞金を加えて請求されます。
奨学金の借入時期によって延滞金の負担額は異なりますが、最大で年間10%にもなる可能性があります。たとえば、平成26年に借りた場合、第一種奨学金(無利息)では5%、第二種奨学金(利息付き)では5%が発生し、合計で最大10%の延滞金がかかることになります。
滞納が続くと、差押えが行われる可能性がある
奨学金の滞納が続くと、ブラックリスト入りするだけでなく、財産の差押えが行われる可能性があります。
JASSOでは、滞納が3か月から9か月の間は債権回収会社に委託し、返還を求めます。しかし、それを過ぎると法的措置による回収が行われることになります。
強制執行(差押え)となると、不動産や高価な財産はもちろん、給料も差押えの対象となります。このような状況になれば、家族だけでなく、勤務先にも迷惑をかける可能性があるため、早めに対応することが重要です。強制執行の手続きが進む前に、滞納を解消するよう努めましょう。
返還金回収の強化
JASSOでは、延滞3か月以上9か月未満の初期延滞債権についてはサービサー(債権回収会社)に回収業務を委託し、9か月以上の滞納者については法的処理の対象とするなど、回収の強化を進めています。
▶ 参考:第2事業の状況|日本学生支援機構
滞納が3ヶ月続くと、記録が残り、ローンの審査が通りにくくなる
奨学金を滞納した状態が3か月以上続くと、その滞納情報が信用情報機関に記録されてしまいます。
この情報は、銀行が加盟する全国銀行個人情報センターにのみ登録されますが、クレジットカードやローンに関する情報を管理するCICやJICCといった信用情報機関とも共有されます。その結果、いわゆるブラックリスト入りとなり、クレジットカードの発行や住宅ローンの審査時に大きな不利となってしまいます。
さらに、この記録は5年から10年間保管されるため、避けるべき重大な事態といえるでしょう。
「信用情報」とは
ローンやクレジットの利用など、信用取引に関する過去から現在までの客観的な取引事実を示す情報のことです。
▶ 出典:JICC指定信用情報機関株式会社日本信用情報機構
信用情報の異動情報は5年間消えない
クレジットカード、ショッピングローン、キャッシングなどの支払いを3か月以上延滞すると、個人信用情報機関に滞納情報が登録されます。一度登録されると、最低でも5年間はクレジットカードの発行やローンの契約ができなくなります。しかし、完済日から5年が経過すると、自動的にブラックリストの状態が解除され、登録情報も抹消されます。
自己破産に至る場合もある
奨学金の返済が滞り続けると、負担がさらに大きくなり、最終的には自己破産を選ばざるを得ないケースもあります。
しかし、奨学金を借りた本人が自己破産しても、返済の責任は保証人に引き継がれるため、奨学金の返済義務から完全に逃れることはできません。その結果、保証人となった家族や親族に大きな負担をかけてしまうことになります。
保証人になってもらった人に負担がかかる
奨学金を借りる際、有料の保証制度を利用しない限り、親や親族に連帯保証人や保証人になってもらう必要があります。
万が一、奨学金の返還が滞ると、親や親族が本人と同様に返済の責任を負うことになり、大きな迷惑をかけてしまいます。その結果、社会だけでなく、家族からの信用も失いかねません。
奨学金が払えない場合、まずは電話で連絡を取る
奨学金の返済が支払えない場合、そのまま放置するのは避けるべきです。
後ほど紹介する救済措置には限りがありますが、何も連絡しないよりも、返済ができない状況を誠意をもって電話で伝えることが大切です。
奨学金相談センター(日本学生支援機構)
電話番号:0570‐666‐301(ナビダイヤル)
受付時間:月曜~金曜 9:00~20:00 (※土日祝日・年末年始を除く)
奨学金が支払えないとどうなるの?
結論として、奨学金を踏み倒すことはできません。理論上は可能かもしれませんが、現実的には非常に厳しいのが実情です。
奨学金の返済を無視し続けると、踏み倒しが不可能となるさまざまなリスクが発生します。
ここでは、奨学金を踏み倒せない理由と、それに伴うリスクについて解説します。
完済するまでブラックリストに載り続けるから
さらに、奨学金を3か月以上滞納すると、いわゆるブラックリストの状態になるため注意が必要です。
クレジットカードや借金の返済状況は、信用情報機関に信用情報として記録・保管されています。
信用情報は、クレジットカードの新規発行をはじめ、カードローンやキャッシング、住宅ローンなどの審査時に重要な参考資料となります。奨学金を滞納すると、この信用情報に延滞の記録が残るため、新たな借り入れの審査に通りにくくなってしまいます。
ブラックリスト入りした場合、延滞の記録が消えるのは完済から5年後となります。そのため、高額な奨学金を返済し終えた後、さらに5年間が経過しなければ、クレジットカードや住宅ローン、車のローンなどを借りられない可能性があります。
このように、奨学金を踏み倒すことにはさまざまなリスクが伴うため、決しておすすめできません。
裁判で訴えられ、差押えを受けることになる
奨学金の返済を無視し続けると、最終的には裁判で訴えられることになります。
裁判で日本学生支援機構の主張が認められると、判決や和解調書といった文書が作成され、差し押さえの実行がいつでも可能な状態になります。
裁判は本人が不在でも進められるうえ、住所が不明であっても裁判の通知が届いたとみなされ、判決が下される「公示送達」という手続きが適用されることがあります。
さらに、差し押さえの手続きが進むと、借り入れた側は裁判所に出廷し、自身の財産を開示しなければなりません。この義務を果たさず出頭しない場合、刑事罰が科される可能性があります。
こうした手続きを経て財産の差し押さえが開始されると、銀行口座や給料などが差し押さえの対象となります。特に、給料の差し押さえは裁判所から勤務先へ通知が送られるため、会社にも知られることになるでしょう。
状況によっては、職場に連絡が届くことがあるから
日本学生支援機構などの奨学金を支払わずに無視し続けると、場合によっては職場に連絡が入ったり、自宅へ調査に来たりする可能性があります。
(3)事前に承諾を得ている場合や、自宅・携帯番号の登録がないなど、他に連絡を取る手段がない場合には、本人の勤務先に電話をすることがあります。
▶ 引用:督促|独立行政法人日本学生支援機構
連絡が取れないなどの正当な理由がある場合、職場への連絡や自宅への訪問は法律上許可されています。そのため、日本学生支援機構が奨学金の回収業務を委託しているアルファ債権回収や日立キャピタル債権回収株式会社などから連絡が入る可能性があるでしょう。
こうした取り立てから逃れるために転職を考える人もいるかもしれません。しかし、裁判で訴えられ差し押さえが可能になると、財産の開示が求められるため、新たな勤務先の情報が判明する可能性があります。
一度訴えられてしまうと、このような取り立てから逃れることは極めて難しくなるでしょう。
未納分の奨学金が一括請求される
奨学金を支払わずに放置すると一括返済を求められる可能性がある
奨学金の返済を無視し続けると、延滞が3か月以上続いた場合に、一括返済を請求される可能性があります。
奨学金の返還期限に関する規定(抜粋)
(学資貸与金の返還の期限等)
第5条(概要)
- 奨学金の返還期限は、貸与期間終了後の翌月から6か月経過した日以降20年以内に、機構が定める期日までに返済することとされている。
- 返済方法は年賦・半年賦・月賦などの割賦払いで行われる。
- ただし、繰上返還(早期一括返済)も可能。
第5条5項(概要)
- 支払能力があるにもかかわらず、割賦金の返還を著しく怠った場合、機構の請求に基づき、一括返済を求められることがある。
▶ 引用:独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条5項|e-Gov
一括請求される際の返済対象
機構から一括請求された場合、支払う必要があるのは以下の3つです。
- 元本(借りた奨学金の残額)
- 未払いの利息
- 延滞日から発生した延滞金
奨学金の延滞金の年率は、貸与終了時期などによって異なりますが、おおよそ3〜10%です。
▶ 参考:延滞金|独立行政法人日本学生支援機構
支払えない状況に陥る前に、早めに相談・対処することが重要です。
連帯保証人に対して請求が届くから
人的保証で連帯保証人がついている場合、連帯保証人に請求が行われる可能性があります。
日本学生支援機構も、本人が返済しない場合は①連帯保証人、②保証人の順番で請求を行うと明記しています。
▶ 引用:第一種奨学金の人的保証制度|独立行政法人日本学生支援機構
連帯保証人は、借りた本人が返済できなくなった際に代わりに返済義務を負う立場であるため、奨学金の全額を支払わなければなりません。その結果、本人が返済しないことで、両親や親族にまで大きな負担をかけることになります。
奨学金は時効が成立すれば、踏み倒すことができるのか?
奨学金を踏み倒せる可能性があるとすれば、それは時効が成立した場合でしょう。
ここでは、奨学金の時効や踏み倒しが実際に可能なのかについて解説します。
奨学金の時効期間は5年から10年の間
奨学金の時効は5〜10年とされています。この期間に幅があるのは、民法の改正によって時効の期間が変わったためです。
時効とは、お金を貸した側(債権者)が持つ借金の返済を求める権利が消滅することを指します。借りた側(債務者)が一定期間返済を行わず、債権者も請求を行わなかった場合、その請求権は失われることになります(民法第166条)。
なお、改正民法は2020年4月1日に施行されたため、奨学金の契約時期によって時効の期間が異なります。
時効の期間
- 改正前(2020年3月31日以前の契約)
最後の支払い期日や最終返済日から10年 - 改正後(2020年4月1日以降の契約)
最後の支払い期日や最終返済日から5年
※ 奨学金の場合
そのため、最後の支払い期日(または一括返済を求められた日)や、最後に支払った日から一定期間が経過すれば、時効が成立する可能性があります。
ただし、時効が成立したとしても、そのまま返済義務が消えるわけではありません。支払いを免れるためには、「時効援用」と呼ばれる手続きを行い、正式に時効を主張する必要があります。
時効はリセットされるため、成立するのは難しい
借金は一定期間が経過すると時効が成立しますが、実務上、時効を成立させるのは難しいケースがほとんどです。
その理由は、特定の行為が発生すると時効のカウントがリセットされたり、一時的にストップされたりするためです。
時効に影響を与える要因
- 時効の更新
時効がリセットされ、最初からカウントし直しになる - 時効の完成猶予
時効のカウントが一定期間ストップする
例えば、以下のような時効の更新事由が発生すると、時効はリセットされ、再び最初からカウントされることになります。
- 債務の承認をした場合
少額の支払いを行ったり、返済について相談することで、借金があることを認めたと判断される - 裁判で判決が確定した場合
裁判で判決が確定すると時効が更新され、その判決から10年間が経過しない限り時効は成立しない
これは一例ですが、債権者が裁判を起こすなどの対応を取れば、時効が更新されたり、猶予されたりする可能性があります。債権者側としても、時効によって踏み倒されることを防ぐため、時効成立前に何らかの手段を講じることが考えられます。そのため、時効によって奨学金を踏み倒すのは現実的に難しいといえます。
仮に時効の成立を狙ったとしても、その間、支払いを無視し続けることで連帯保証人に請求が行われたり、信用情報に延滞記録が残り続け、ブラックリスト状態が継続することになります。
奨学金が返せないとき、どこに相談すべきか?
奨学金の返済が難しい場合、当月分を支払えないときは、翌月の振替日までに2か月分を入金するようにしましょう。翌月には2か月分が振替されますが、この時点では延滞金は発生しません。
もし翌月以降も返済が困難な場合は、日本学生支援機構の救済制度が利用できるかどうか相談してみましょう。
しかし、以下のような状況に該当する場合は、弁護士に借金問題について相談することを検討しましょう。
- 他の借金や支払いの影響で、奨学金の返済が難しくなっている
- 救済制度を相談したものの、対象外だった
このような場合、債務整理という方法を利用することで、借金の返済負担を軽減したり、場合によっては免除されたりする可能性があります。
日本学生支援機構に、救済制度が利用できるかどうか相談する
日本学生支援機構では、さまざまな事情により返済が難しくなった人に向けて救済制度を用意しています。
一定の条件を満たせば、以下の制度を利用できる可能性があります。
- 減額返還制度:毎月の返済額を減額できる
- 返還期限猶予制度:一定期間、返済を一時的に停止できる
- 返還免除制度:残高の一部、または全額が免除される
次の項目では、それぞれの制度について詳しく解説します。
※本記事の内容は2024年10月時点の情報です。最新情報については、必ず日本学生支援機構の公式サイトをご確認ください。
▶ 参考:返還が難しくなった場合|JASSO
減額返還制度:毎月の返済額を減らしてもらう制度
減額返還制度とは、経済的な理由で返済が困難な場合に、毎月の返済額を1/2、1/3、1/4、2/3のいずれかに減額できる制度です(適用期間は最長15年)。
この制度を利用することで、毎月の負担が軽減され、無理なく返済を続けることが可能になります。
ただし、この制度で減額されるのは毎月の返済額のみであり、以下の2点には注意が必要です。
- 返済予定額の総額は減らない
- 返済期間が延びる
例:減額返還制度を利用した場合
- 制度利用前:返還額15,000円/月(返還期間20年)
- 制度利用後:
- 返還額 7,500円/月(返還期間15年)
- +返還額 15,000円/月(返還期間12.5年)
減額返還制度の利用条件
給与所得者の場合
- 年収:400万円以下
- 扶養する子どもが2人の場合は500万円以下
- 扶養する子どもが3人以上の場合は600万円以下
給与所得以外の所得がある場合
- 年間所得金額:300万円以下
- 扶養する子どもが2人の場合は400万円以下
- 扶養する子どもが3人以上の場合は500万円以下
減額返還制度の利用方法
「スカラネット・パーソナル」または書面申請により、日本学生支援機構へ申請を行います。
※1年ごとに更新申請が必要です。
▶ 参考:減額返還制度の申請手続き|JASSO
返済を一時的に停止してもらう「返還期限猶予制度」
返還期限猶予制度とは
返還期限猶予とは、災害、傷病、経済的困難、失業などの理由で返済が難しい場合に、最長10年間返済を猶予してもらえる制度です。
ただし、この制度はあくまで一時的な猶予であり、返還総額が減額されるわけではないため注意が必要です。
例:返還期限猶予を利用した場合
- 制度利用前:返還額 15,000円/月(返還期間 20年)
- 制度利用後:返還額 15,000円/月(返還期間 30年 ※返済期限猶予10年)
返還期限猶予制度の利用条件
新卒等
- 新卒者や退学者で、無職・未就職などによる低収入の場合(直近年度の卒業者に限定)
失業中
- 失業後6か月以内で、かつ再就職(正社員・派遣社員・アルバイトなど雇用保険加入者)できていない場合
経済困難
- 給与所得者:年間収入金額 300万円以下
- 給与所得以外の所得がある場合:年間所得金額 200万円以下(※必要経費等控除後)
- 扶養する親族がいる場合、1人につき38万円控除
傷病
- 給与所得者:年間収入金額 200万円以下
- 給与所得以外の所得がある場合:年間所得金額 130万円以下(※必要経費等控除後)
その他対象となるケース
- 産前産後休業および育児休業
- 災害による影響
- 生活保護受給中 など
返還期限猶予制度の利用方法
「スカラネット・パーソナル」または書面申請により、日本学生支援機構へ申請を行います。
▶ 参考:返還期限猶予の願出はスカラネット・パーソナルをご利用ください|JASSO
実際に返還期限猶予制度を利用した人の体験談
20代女性のケース
- 奨学金の借入総額:400万円
- 返済できなくなった理由:失業・収入減
- 滞納期間:3か月
勤務していた会社が自分に合わず、転職を考えて退職しました。転職活動は退職前から始めていましたが、退職時点では新しい職場が決まっておらず、今後の生活に不安を感じていました。
転職先が決まり、給与を受け取るまでの間はほぼ無収入になるため、その期間だけ返還期限猶予制度を利用しました。
事前に申請していたため、転職先で安定するまでの間は返還をストップでき、転職活動や新しい仕事に集中することができました。
残高の減額、または免除を受ける「返還免除制度」
返還免除制度とは
返還免除制度とは、本人が亡くなった場合や、深刻な障害によって働くことができなくなった場合に、未返済の奨学金の全額または一部の返済が免除される制度です。
この制度の利用には、厳格な条件が設定されています。
返還免除制度の利用条件
- 本人が亡くなった場合
- 精神または身体の障害によって、労働能力を完全に失った場合、または労働能力に高度な制限がかかり、返済が困難になった場合
返還免除制度の利用方法
書面にて、日本学生支援機構へ申請を行います。
▶ 参考:死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除|JASSO
弁護士に債務整理を利用して借金を解決できるか相談する
債務整理とは
債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者(お金を貸した側)との合意または裁判所の決定に基づき、借金問題を解決する方法です。
債務整理には主に3つの方法があり、状況に応じて適切な手段を選ぶ必要があります。
債務整理の種類と適用ケース
任意整理
- 奨学金以外にも借金がある場合(元金のみであれば分割返済が可能)
個人再生
- 奨学金以外にも借金がある場合(元金を1/5~1/10程度に減額し、分割返済が可能)
自己破産
- 奨学金以外に借金はないが、返済が厳しい場合
- 病気などの理由で働けず、日本学生支援機構の「返還免除」が受けられなかった場合
債務整理のデメリット
債務整理を行うと、すべての方法において信用情報機関に事故情報が登録されるデメリットがあります。
これはいわゆる「ブラックリストに載る」状態となり、一定期間新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されることになります。
しかし、奨学金を長期間延滞すると、結果的にブラックリストに載ることになるため、すでに延滞の可能性が高い場合は、早めに債務整理を検討することも一つの選択肢となるでしょう。
任意整理を行うことで、奨学金以外の借金の返済負担が軽減される
任意整理とは
任意整理とは、債権者と交渉することで、和解後に発生する利息(将来利息)をカットし、毎月の返済額を減額したり、返済スケジュールを調整したりする解決方法です。
和解が成立した後は、3~5年程度での完済を目指すことになります。
奨学金における任意整理の利用について
任意整理は、奨学金の返済そのものを減額する方法としては適していません。
そのため、「奨学金以外にも借金がある場合に、その返済負担を減らし、奨学金の返済を続けやすくする」という目的で利用を検討するのが一般的です。
理由は以下のとおりです。
- 奨学金は低金利かつ長期分割払いのため、任意整理で減額できる幅が小さい
- 日本学生支援機構は、任意整理の交渉に応じないことが多い
- 奨学金を任意整理の対象から外し、そのまま返済を続けることで、保証人への影響を抑えられる
任意整理を利用できる目安
任意整理を行う場合、「対象とする借金の元金を3〜5年で分割返済できること」が、利用の目安となります。
個人再生を利用すると、奨学金を含む借金が1/5~1/10程度に減額される
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を5分の1~10分の1程度(最低100万円まで)に減額してもらう手続きです。
減額された借金については、原則3年(最長5年)での完済を目指します。
個人再生と奨学金の関係
個人再生は、任意整理とは異なり、特定の借金だけを対象から外すことはできません。
そのため、奨学金を含むすべての借金が減額対象となりますが、減額された分の奨学金は、連帯保証人や保証人に請求が行われる点に注意が必要です。
例えば、個人再生によって奨学金の残債400万円が100万円まで減額されたとしても、保証人には残りの300万円が請求されるため、大きなデメリットとなります。
個人再生を選択すべきケース
個人再生は、「奨学金以外にも借金があり、元金を1/5~1/10程度に減額すれば分割返済が可能な場合」の選択肢となるでしょう。
自己破産を申請すると、奨学金を含む借金の返済が免除される
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、ほぼすべての借金の返済を免除(免責)してもらう手続きです。
奨学金についても、以下の条件を満たしていれば返済が免除される可能性があります。
自己破産の条件
- 支払い不能な状態であること
- 借金の理由が免責不許可事由*¹に該当しないこと
- 借金が非免責債権*²に該当しないこと
*¹ 免責不許可事由(浪費・ギャンブルなど)
*² 非免責債権(税金・一部の慰謝料・養育費など)
自己破産のデメリット
自己破産を行うと、持ち家や車などの高価な財産は処分されるため、大きなデメリットがあります。
また、保証人のいる借金(奨学金を含む)に関しては、保証人が残りの返済を請求されることになるため注意が必要です。
自己破産を解決手段として選ぶべきかどうかは、慎重に判断するようにしましょう。
奨学金の返還を延滞し続けると、どうなるのか?
奨学金の返還を延滞するとどうなるのか?
奨学金の返還を延滞すると、どのような影響があるのでしょうか。
以下では、延滞期間ごとに適用される措置をまとめました。
▶ 参考:日本学生支援機構「よくあるご質問 – 万一、奨学金の返還を延滞した場合は、どうなりますか。」
次の項目で、具体的に解説していきます。
【返還期日の翌日から】延滞金が発生する
奨学金の延滞金について
返還期日の翌日(延滞発生日)から、延滞した日数に応じて延滞金が発生します。
日本学生支援機構の奨学金における延滞金の利率は年率3.0%と定められています(令和2年3月28日以降)。
▶ 参照元:日本学生支援機構「延滞金」
延滞金の計算方法
延滞金は以下の計算式で求められます。
延滞金 = 延滞している金額(円) × 延滞金の利率(%) ÷ 365(日) × 延滞日数(日)
※ うるう年は366日で計算
<計算例>
たとえば、延滞している割賦金が9万円で、延滞期間が6か月(180日)の場合、
90,000(円) × 0.03(3.0%) ÷ 365(日) × 180(日) = 1,332(円)
このように、延滞期間が長引くほど延滞金も増えていくため、注意が必要です。
【返還期日の翌日以降】電話や文書による督促が行われる
奨学金の延滞による督促について
延滞をしてから数日(一般的には2〜3日)が経過すると、日本学生支援機構の職員、または機構が委託した債権回収会社から、電話や文書による督促が行われます。
用語集:債権回収会社とは?
債権回収会社とは、債権者から委託を受ける、または債権を譲り受け、債務者(お金を借りた側)に対して債権の回収を専門に行う会社です。
この業務は、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づいて行われています。
電話による督促の内容
電話での督促では、以下のような内容が事務的に通達・確認されるのが一般的です。
- 返還が遅れていること
- いつまでに返還が可能か
延滞が2か月以上続いた場合
延滞を解消せず、延滞期間が2か月以上になると、本人への督促に加えて保証人や連帯保証人にも通知が行われます。
そのため、基本的に保証人・連帯保証人に延滞の事実が知られることになる点に注意が必要です。
【延滞が3ヶ月以上続くと】信用情報機関に事故情報が登録される
奨学金の延滞が3か月を超えると信用情報に影響が出る
延滞が3か月を超えると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。これは、いわゆるブラックリストに載る状態を指します。
事故情報が登録されると、主に以下のような影響を受けることになります。
- クレジットカードやローンなどの審査に通らなくなる
- 契約中のクレジットカードやカードローンが強制解約される
- 賃貸契約ができなくなる場合がある
- 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
- ローンや奨学金などの保証人になれない
用語集:信用情報機関とは?
信用情報機関とは、クレジットカードやローン契約の内容、支払い状況(残高・延滞情報など)を金融機関や貸金業者から収集・蓄積し、必要に応じて提供する機関です。
日本には、以下の3つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
奨学金を滞納した場合の信用情報への影響
奨学金を滞納すると、日本学生支援機構が加盟している全国銀行個人信用情報センター(KSC)に事故情報が登録されます。
さらに、KSCに登録された情報は他の信用情報機関(CIC・JICC)にも共有されるため、すべての金融機関や貸金業者が事故情報を確認できる状態になります。その結果、上記のような影響を受けることになるのです。
【延滞が9ヶ月以上続くと】一括返還が請求される
延滞が9か月以上続くと一括請求の可能性がある
延滞期間が9か月以上に及ぶと、「期限の利益」を喪失し、利息や延滞金を含めた返還未済額を一括請求される可能性があります。
用語集:期限の利益とは?
期限の利益とは、契約で定められた期日が到来するまで、債務(借金の返済や代金の支払いなど)を履行しなくてもよいという債務者側の権利を指します。
期限の利益を喪失すると、債権者から一括返還を求められても拒否することができません。
一括請求への対応について
とはいえ、すでに返還できずに放置していた場合、一括返還に応じるのは現実的に難しいといえるでしょう。
【延滞が9ヶ月以上続くと】差押えなどの法的措置が取られる可能性もある
一括請求を放置するとどうなるのか?
一括請求を無視し続けると、保証機関が日本学生支援機構に対して債務を弁済(代位弁済)します。
その後、保証機関から代位弁済額の一括請求が行われ、これに応じない場合、裁判所を介した「支払督促」が実施されます。
最終的には、強制執行による財産の差押えが行われる可能性もあります。
主な差押えの対象
- 手取り給与の4分の1(手取りが44万円を超える場合は、33万円を超過した分が差押え対象)
- 一定以上の現金、自動車、バイク、貴金属、骨とう品など
- 預貯金、生命保険などの金融資産
- 土地、建物などの不動産
最も差押えられやすいのは給与
これらの中で、最も差押えられやすいのが給与です。
給与の差押えが行われる際には、裁判所から勤務先へ通知が送られるため、必然的に借金問題があることが職場に知られることになります。
生活に必要な財産を失うだけでなく、仕事や人間関係にも影響を及ぼす可能性があるため、できる限り回避することが重要です。
奨学金は踏み倒せるのか?その難しさの理由を紹介
奨学金は多くの学生に利用されており、現在では大学生の約2人に1人が利用している状況です。
しかし、その中には返済が困難になるケースも少なくありません。
そのような状況で「踏み倒す」という選択肢を考える人もいるかもしれませんが、実際にはそれを実行することは極めて難しいのが現実です。
人的保証の場合、保証人に対して請求が行われる
奨学金を借りる際には、保証人(連帯保証人)を設定しています。
そのため、奨学金の返済が滞ると、保証人に請求が行われることになります。
保証人には「機関保証」と「人的保証」の2種類があります。
人的保証を選択している場合、親や親戚が保証人となっているため、本人が踏み倒したとしても保証人に請求が行き、大きな迷惑をかけることになるでしょう。
奨学金は時効が成立するのが難しい
奨学金の返済と消滅時効
奨学金の返済にも民法の「消滅時効」が適用されます。
時効の年数は法改正により、利用した時期によって異なります。以下の期間、返済をしていなければ、借金は時効により支払わなくてよくなる可能性があります。
- 2020年4月1日以降の奨学金:最終返済日から5年
- 2020年3月31日以前の奨学金:最終返済日から10年
時効がリセットされるケース
以下のいずれかに該当すると、時効の進行がリセットされます。
- 裁判や支払督促を受けた場合
- 強制執行を受けた場合
- 一部返済を行った場合
奨学金の時効が成立しにくい理由
奨学金の時効は、一般の消費者金融の借金とは異なる仕組みになっています。
多くの奨学金では、「期限の利益喪失特約」(延滞による一括請求)がないケースが多く、「各分割返済期日」ごとに時効が進行するため、全額の時効が成立するまでに非常に長い時間がかかります。
さらに、裁判を起こされるとその都度時効がリセットされるため、実際に時効が成立するケースはほとんどありません。
機関保証の場合の時効進行について
機関保証を利用している場合、保証機関が代位弁済を行った時点で、全額に対する時効のカウントが始まるため、人的保証よりも時効が成立するまでの期間が短くなる傾向があります。
積極的に訴訟を起こす
奨学金の返済が長期間滞ると、裁判に発展するケースがあります。
特に、日本学生支援機構は法的手続きを厭わない姿勢で知られており、裁判で返済義務が認められると、最終的に強制執行が行われる可能性があります。
強制執行とは、「差押え」を意味し、多くの場合、差押えの対象となるのは「預金」と「給与」です。
多くの奨学金には返還義務があることに注意が必要です
奨学金の返還義務とその影響について
奨学金を払えないとどうなるかを理解したうえで、多くの奨学金には返還義務があることにも注意が必要です。
日本学生支援機構の調査によると、奨学金の「返還義務を知った時期」について、
- 申込手続きを行う前と回答した割合は、
- 延滞者:50.3%
- 無延滞者:89.4%
この結果から、奨学金が返還義務のある制度であることを十分に理解せずに申し込み、督促を受けて初めて気づく人もいることが分かります。
奨学金の種類
奨学金には、以下の2種類がありますが、一般的なのは貸付型奨学金です。
- 給付型奨学金:返還の義務がない奨学金
- 貸付型奨学金:返還の義務がある奨学金(無利子・有利子の両方がある)
貸付型奨学金の返済が滞るとどうなる?
貸付型奨学金の返済が滞ると、本人だけでなく、保証人や連帯保証人にも影響を及ぼす可能性があります。
また、延滞が続けば、本人の将来にも大きな影響を与えるため、督促が来た際には、自身がどの種類の奨学金を借りているのかをしっかり確認することが重要です。
奨学金が払えない時に利用できる救済制度
奨学金の救済制度について
奨学金の貸与機関によっては、災害・病気・経済的理由などにより返済が困難な場合、返還猶予や免除などの救済制度を利用できることがあります。
例えば、日本学生支援機構では、以下の3つの救済制度を設けています。
- 減額返還制度
- 返還期限猶予
- 返還免除
次の項目で、それぞれの制度について詳しく解説します。
返還額減額制度
減額返還制度とは
減額返還制度とは、毎月の返還額を1/2または1/3に減額しながら返済を続けられる制度であり、最長15年(180か月)まで延長が可能です。
この制度では奨学金の返還総額自体が減額されるわけではありませんが、毎月の返還負担を軽減できる点が特徴です。
減額返還制度の利用条件
減額返還制度を利用するには、以下のような適用条件を満たしている必要があります。
- 災害・傷病による影響
- 経済的理由(年間収入金額の条件あり)
減額返還制度の申請方法
制度を利用するには、「奨学金減額返還願」を郵送またはインターネットで提出する必要があります。
返還期限の猶予制度
返還期限猶予とは
返還期限猶予とは、一定期間、元金や利子の支払いを猶予できる制度であり、通算最大10年(120か月)まで返還を先送りすることが可能です。
ただし、元金や利子の支払いが免除されるわけではなく、猶予期間が延びる分、返還終了年月日も遅くなるため注意が必要です。
返還期限猶予の適用条件
この制度は、以下の理由により申請が可能です。
- 災害・傷病による影響
- 経済的困難
- 失業などの事情
また、現在返還を延滞中であっても、上記の条件を満たし審査を通過すれば適用される可能性があります。
この場合、延滞期間のうち猶予事由に該当する期間についても、返還期限猶予が適用されます。
返還期限猶予の申請方法
制度を利用するには、郵送またはインターネットで「奨学金返還期限猶予願」を提出する必要があります。
返還の免除制度
返還免除とは
返還免除とは、以下のいずれかに該当する場合に、奨学金の返還が完全に免除される制度です。
- 本人が死亡した場合
- 精神または身体の障害により労働能力を喪失する、または労働能力に高度な制限を受けた場合
返還免除の手続き方法
- 本人が死亡した場合
- 相続人などが必要書類を揃え、書面で申請を行う必要があります。
- 精神や身体の障害による免除を申請する場合
- 日本学生支援機構へ直接相談し、必要な提出書類を確認した上で手続きを進めます。
企業が奨学金の返済を代行してくれる返還支援制度
奨学金返還支援制度を導入する企業の増加
近年、奨学金返還支援制度を福利厚生の一環として導入する企業が増加しています。
企業にとっても、節税効果だけでなく、人手不足の解消や従業員の定着率向上といったメリットがあります。
企業による奨学金返済支援の内容
奨学金の返済支援額は企業ごとに異なりますが、例えば月2万円を上限として、最大360万円まで支援する企業もあります。
2024年5月末時点で2,023社がこの制度を利用しているため、日本学生支援機構の公式ページから対象企業を探すのがおすすめです。
▶ 参考:企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度|独立行政法人日本学生支援機構
都道府県が提供する奨学金返還支援制度
都道府県による奨学金返還支援制度
都道府県でも奨学金返還支援制度を実施しており、特に人口減少が課題となる地方では、この制度を活用して移住者を増やすことを目的としています。
奨学金返還支援制度の一例
各自治体によって条件は異なりますが、以下は具体的な支援事例の一部です。
- 青森県
- 対象企業への就職や県内居住などの条件を満たした人が対象
- 山口県
- 2024年以降に大学などを卒業後半年以内に、定住の意思を持ち、県内で居住・就業すること
- 北海道余市町
- 申請前年度の3月1日から継続して余市町に居住し、今後も居住する意思がある30歳以下が対象
- 長野県松本市
- 市内に居住し、市内に本社・本店を有する中小企業へ就職した35歳未満が対象
制度を利用する際の注意点
各都道府県や市区町村によって適用条件は異なります。
- 年齢制限がある場合が多い
- 特定の技能が求められるケースがある
- 補助金額の上限が低い自治体もある
利用を検討する際には、自身の状況に合った支援制度かどうか慎重に確認することが重要です。
▶ 参考:「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進|地方創生
奨学金がを払えないときの対処法
万一、奨学金を払えないときの対処法
奨学金の返済が難しくなった場合に備えて、適切な対処方法を知っておくことが重要です。
なぜなら、奨学金の救済制度には審査があり、申請しても理由によっては適用されない可能性があるからです。その場合、家計を見直すなどの対策を講じる必要があります。
また、他にも借金を抱えており、返済が困難な状況であれば、「債務整理」などの法的救済措置を検討することも選択肢の一つです。
奨学金を払えないときの主な対処法
- 支出を減らす
- 収入を増やす
- 親族から援助を受ける
- 金融機関から借り入れる
- 債務整理を活用する
次の項目で、それぞれの方法について詳しく解説します。
支出を削減する
支出を減らして奨学金の返還に備える
奨学金の返還が厳しいと感じても、支出を見直すことで工面できる可能性があります。
まずは、奨学金の返還額を把握し、その分の金額を確保できるように支出を見直すことが重要です。
具体的な支出の見直し方法
- スマートフォンのプランを変更する
- 電力会社や電気料金プランを見直す
- 保険料の見直しを行う
- 不要なサブスクリプションサービスを解約する
- 家賃の安い物件に引っ越す
- 食費・生活費・交際費を削減する
固定費の削減が効果的
特に、固定費の削減は家計の改善効果が高く、長期的な負担軽減につながります。
まずは、すぐに見直せるものから優先的に削減していきましょう。
収入を増加させる
収入を増やして奨学金の返還に備える
すでに支出を減らしていても、奨学金の返済が厳しい場合は、収入を増やす方法を検討することも重要です。
具体的な収入を増やす方法
- 不用品を売る
- 副業やアルバイトを始める
- 資格やスキルを身に付ける
- 転職する
状況に応じた収入の増やし方
一時的に奨学金の返還が厳しい場合は、不用品の売却や短期のアルバイトなどで資金を補うのも一つの方法です。
一方で、収入を大幅に増やしたい場合は、資格取得や転職を視野に入れるとよいでしょう。
奨学金の救済制度の活用も検討
また、一定水準以下の収入が続き、奨学金の返済が困難な場合は、日本学生支援機構の救済制度を利用できる可能性があります。
制度の適用条件を確認し、活用できるかどうか検討しましょう。
所有している物を売る
不用品を売って奨学金の返還資金を作る
一時的に奨学金の返還が難しい場合、手持ちの物を売却して資金を確保するのも有効な方法です。
例えば、ブランド品のカバンや移動手段として使っていたバイクなどを売却すれば、返済資金をまかなえる可能性があります。
売却方法の選択肢
- リサイクルショップを利用すれば即日で現金化が可能
- 時間に余裕があるなら、フリマアプリを活用すると高く売れる可能性がある
フリマアプリでは自分で価格設定ができるため、買い叩かれる心配がないのもメリットです。
フリマアプリの例
- メルカリ(公式サイト)
- ラクマ(公式サイト)
- ショッピーズ(公式サイト)
- minne(公式サイト)
日雇いアルバイトで収入を増加させる
収入を増やして奨学金の返済に備える
現在の収入だけでは返済が難しい場合、返済の助けになる程度に収入を増やす方法も検討できます。
特に、短期間で報酬が支払われる日雇いアルバイトを活用すれば、数日間の勤務で1ヶ月分の返済額をまかなえる可能性があります。
日雇いバイトの注意点
ただし、日雇いアルバイトであっても「即日払い」とは限らないため、すでに返済期日が迫っている場合は、給与の支払いタイミングを事前に確認することが重要です。
バイト情報サイトの例
- バイトル
- fromAnavi(フロムエー)
- マイナビバイト
- タウンワーク
債務整理を利用する
奨学金以外にも借金があり、完済の目処が立たない場合の対処法
奨学金に加えて他にも借金があり、日本学生支援機構の救済制度や一般的な対処法を利用しても完済の見通しが立たない場合は、債務整理の検討が必要です。
主な方法は以下の3つです。
債務整理の主な方法
1. 自己破産
- 裁判所に申し立て、すべての借金を免除(免責)してもらう手続き
- 奨学金の返還も免除の対象となる
- ただし、保証人付きの奨学金の場合、本人が自己破産すると保証人に残債が請求される
2. 個人再生
- 裁判所に申し立て、債務を大幅に減額する手続き
- 奨学金のように保証人付きの借金も手続きに含まれるため、保証人に請求が行われる
3. 任意整理
- 債権者と交渉し、今後発生する利息をカットまたは長期分割返済(3~5年)を目指す方法
- ただし、奨学金はもともと金利が低いため、任意整理によるメリットは少ない
債務整理を選択する際の注意点
債務整理の方法は、現在の借金の状況や奨学金の契約形態(保証人付きか機関保証かなど)によって適切な選択肢が異なります。
そのため、どの方法が最も適しているか慎重に検討することが重要です。
親族に援助をお願いする
親族から援助を受けて奨学金を返還する
家族や親族からの援助を受けることも、奨学金の返還を乗り切る一つの方法です。
例えば、奨学金の返済を代わりにしてもらう、または一時的に立て替えてもらうといった形で支援を受けることが考えられます。
援助を受ける際の注意点
ただし、親族とはいえ、無計画に援助を受けるのはおすすめできません。
お互いに気持ちよくやり取りをするためにも、返済プランを立てるなど、事前によく話し合うことが大切です。
金融機関から融資を受ける
カードローンを利用して奨学金を返還する方法について
カードローンなど借りやすい方法を活用し、奨学金の返還に充てることも一つの手段ではあります。
しかし、カードローンは奨学金よりも金利が高く、最終的に返済額が増えるため、基本的にはおすすめできません。
さらに、奨学金の返還分を常に金融機関から借り続けると、借金が膨らみ続け、返済負担がますます大きくなるため、慎重に判断する必要があります。
金融機関からの借入で一時的に対応できる
奨学金の返済に困ったときの対応
身近な人に助けてもらえたり、自力でお金を用意できるのであれば、それが最善の方法でしょう。
しかし、お金の問題は他人に相談しにくく、簡単にまとまった金額を用意できないことも少なくありません。
そのような場合には、状況に応じて、金融機関からの一時的な借入を検討することも一つの選択肢です。
カードローンを選択肢として考える
カードローンを利用するという選択肢
例えば、カードローンを利用してお金を借りる方法もあります。
カードローンとは、ATMを利用して現金を借入できるカード型のローン商品です。
具体的には、テレビCMでも知られている「アコム」や「プロミス」などが、代表的なカードローンの一種です。
少額の借入ができるため、借りすぎを防ぎやすい
カードローンは必要な金額だけ借入可能
多くのローン商品では、1万円単位での借入が基本となっている場合があります。
しかし、奨学金の返済額は必ずしも1万円単位とは限らず、数千円で済むこともあるため、必要以上に借りすぎてしまう可能性があります。
一方で、一般的なカードローンであれば、借入方法によっては1,000円単位での借入も可能です。
つまり、必要な分だけ最低限の借入ができるため、無駄な借りすぎを防ぐことができます。
制限なく使用できる
カードローンの利用用途と奨学金返済への活用
一般的なローン商品では、規約で定められた用途の範囲内でしか借入金を使用できない場合があります。
一方で、カードローンは事業性資金としての利用を除けば、基本的にどのような用途にも使用できるため、柔軟な資金調達が可能です。
そのため、一時的に奨学金の返済に充てることも可能ですし、「奨学金を返済したことで生活費が不足した」という状況でも活用できる点がメリットといえます。
早ければ、即日で融資を受けることも可能
審査が早いカードローンの活用
例えば、審査が早いカードローンの利用を検討するのも一つの方法です。
特に、最短30分で審査が完了するカードローンであれば、早ければ当日中に資金を用意することも可能です。
「今日・明日中に奨学金の返済をしなければならない」という差し迫った状況にある場合、迅速な審査が可能なカードローンが力になってくれるでしょう。
無利息期間が設けられている
消費者金融の無利息期間を活用する
大手消費者金融は利息が高いイメージがありますが、多くの消費者金融では無利息期間を設けています。
この無利息期間内であれば、借りた金額のみを返済すればよいため、奨学金の返済に足りない分だけ少額を借りて、期間内に返済すれば利息の負担なく利用することが可能です。
奨学金が返せない場合に避けるべきNG行動
奨学金が返せない場合の対処法と避けるべき行動
これまで紹介したように、奨学金の返済が難しくなった場合でも、取れる対処法は多数あります。
「奨学金の返済のために何が何でもお金を作らなければならない」と焦る必要はありません。
まずは、前述した相談先に事情を伝え、適切なサポートを受けることが大切です。
しかし、以下のような行為は将来に深刻な悪影響を与えるため、絶対に避けるべきです。
絶対に避けるべき行為
1. 闇バイトをする
違法行為に関与する「闇バイト」は、犯罪の実行犯として刑事罰を受ける可能性があります。
〈闇バイトの可能性がある求人の特徴〉
- 「誰でも大金が稼げる」「すぐに高額報酬」「ホワイト案件」などの文言が使われている
- 仕事内容に見合わない高額報酬が提示されている
- 「口座買取」「マネーロンダリング」などの違法行為が記載されている
- 「受け子」「出し子」「UD」「叩き」などの隠語が使われている
- 「Telegram」「Signal」などの匿名性が高いアプリでの連絡を求められる
▶ 参考:警察庁「闇バイトは犯罪実行者の募集です」
▶ 参考:東京都「どっちが闇バイト?クイズでわかる“危険な求人情報”の見分け方」
2. 銀行口座を売る
銀行口座の売買・譲渡は違法行為であり、刑事罰を受ける可能性があります。
また、以下のような深刻な影響を及ぼします。
✅ 将来的に銀行口座が作れなくなる
✅ 就職や転職において不利になる
SNSやネット掲示板で「口座買取」を持ちかけられても、決して応じてはいけません。
▶ 参考:全国銀行協会「銀行口座の売買」
3. 闇金・ソフト闇金を利用する
「闇金融(ヤミ金)」や「ソフト闇金」からの借入は絶対に避けましょう。
ヤミ金とは、貸金業者としての登録を受けず、無許可で営業している違法業者です。
登録貸金業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。
ヤミ金業者の特徴
⚠ 法外な高金利で貸付を行う
⚠ 違法で過激な取り立てを行う
⚠ 個人情報を犯罪行為に利用するリスクがある
また、SNSやネット掲示板に掲載されている
「お金貸します」「すぐに融資します」といった投稿も、ほとんどがヤミ金業者に関連しているため注意が必要です。
▶ 参考:金融広報中央委員会「ヤミ金とは」
▶ 参考:金融庁「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」
適切な対処法を選び、違法行為に手を出さない
奨学金の返済が難しい場合は、冷静に状況を整理し、適切な支援制度を利用することが大切です。
違法行為に手を出してしまうと、将来の人生に大きな悪影響を及ぼすため、焦らず慎重に行動しましょう。
まとめ
奨学金の延滞は信用情報に影響するため早めの対処が重要
奨学金の返済を延滞し続けると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
さらに、本人だけでなく保証人にも督促の連絡が入るため、「奨学金だから返還が遅れても問題ない」と考えるのは誤りです。
返済が難しいと分かった時点で、できるだけ早く対処することが重要です。
奨学金の救済制度と借金問題の相談先
日本学生支援機構では、さまざまな救済制度を設けています。
また、奨学金を含む多額の借金に悩んでいる場合は、債務整理の専門家に相談することも解決策のひとつです。
早めに対処することで、選べる解決手段が増えます。
借金問題に悩んでいる場合は、まず専門家に相談することを検討しましょう。