※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
親の借金、返済義務は?肩代わりしないための相続対策を解説
目次
親が借金をしていた場合、原則として子供に返済義務はありません。ただし、親が亡くなり、子供が相続人になると、親の借金の返済義務を引き継ぐことになりますので、注意が必要です。また、子供が親の借金の保証人や連帯保証人である場合、返済義務を負うこともあります。この記事では、親の借金を子供が返済しなければならないのか、どのような場合に返済義務が生じるのか、肩代わりしない方法をわかりやすく解説します。
親の借金の可能性を把握する
「うちの親に借金はないはずだから関係ない」と思っている方も注意が必要です!親は子どもに心配をかけたくないものです。そのため、借金があることをわざわざ伝えないことが多く、「家族に内緒で手続きをしたい」、「親の借金を背負いたくない」という悩みが多くあります。備えあれば憂いなし! ですので、この記事で紹介する内容はぜひ覚えておいて、いざという時に役立ててください。
以下のチェックリストは、私がこれまで司法書士として多くの借金問題を取り扱ってきた中で、借金をしやすい傾向やきっかけをまとめたものです。ぜひ親のことを思い浮かべながらチェックしてみてください。もし、1つでも当てはまる項目があれば、親の借金の可能性が高いでしょう。各項目の解説も以下に記載しています。
- 親はパチンコなどのギャンブルが好き
これは男女問わず、私の経験では借金の原因として最も多いケースです。自分ではやめたいと思いながらも、なかなかやめられず、家族には秘密でパチンコに行く方が多いのが特徴です。 - 教育費に関しては惜しまない家庭
親は子どもに不自由のない生活をしてほしいと思っています。特に、子どもが大学に進学した際に発生する高額な入学金や学費、仕送りがきっかけとなり、借金を重ねてしまう親を多く見てきました。 - 親は自営業をしている
自営業の親の場合、収入が不安定で波があることが多く、事業資金や初期費用、追加融資のために借金を重ねることがあります。サラリーマンの親よりも借金を抱えるリスクが高いと言えます。 - 親は転職回数が多い
転職によって収入が減少し、それを補うために借金をするケースがよくあります。また、転職活動中に無職となり、そこで金銭的に困って借金をすることが多いです。 - 親戚に自営業者がいる
兄弟から頼まれて保証人になるなどして、最終的に自己破産に至るケースも多く見てきました。 - 兄弟が3人以上いる
お子さんが多ければ、それだけ生活費や教育費がかかり、結果的に借金をする可能性が高くなります。 - 親に離婚歴がある
離婚が借金のきっかけとなるケースは男女問わず非常に多いです。男性は離婚後に自暴自棄になり浪費することがあり、女性は離婚時に子どもが小さくて収入の確保が難しいため、借金をしてしまう傾向があります。 - 両親は夫婦仲が悪い
経済的に苦しい状況では、夫婦関係が悪化することが多く、それが借金を重ねる原因になることがあります。
これらのチェック項目を参考にして、親の借金の可能性があるかどうかを判断し、早期に対処することが大切です。
親の借金に対する法律的な視点
親の借金に関して、子供が返済義務を負うかどうかは、親が生存しているかどうかによって異なります。親がまだ生きている場合、原則として子供に返済義務はありません。ただし、子供が親の借金の保証人や連帯保証人である場合、返済義務を負うことがあります。一方、親が亡くなり相続が発生すると、親の借金の返済義務を子供が引き継ぐことになります。** 返済義務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄や限定承認などの手続きを行う必要があります。 それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
親の借金を子どもが払う義務はない
親子だからといって、親の借金を子供が払う義務があるのかという疑問に対する答えはNOです。日本の法律では、親子関係があっても、子どもが親の借金の責任を負わなければならないということは一切ありません。親がいくら借金をしていても、親の保証人や連帯保証人でなければ、子どもにその借金を支払う義務は全くないのです。
それでも、借金取りから「親の借金だから子どもが道義的に返すべきだ」とか、「親を助ける気持ちがないのか?」 などと、言葉巧みに返済を迫られることもあります。貸金業者からの場合、貸金業法により、「債務者等以外の者に対して、債務者に代わって返済を要求することは禁止されています(貸金業法21条1項第7号)」ので、金融庁に通告することができます。
また、法律的に返済義務のない人に対して返済を強要する行為は、脅迫罪や強要罪に該当する可能性もあります。しつこい場合は、警察に相談することを検討しましょう。
亡くなった親の借金は相続することになる
親の借金を子どもが返済する義務は法律的には全くありません。しかし、借金のある親が亡くなった場合、亡くなった親の借金は残念ながら子どもに相続されます(民法第896条参照)。「相続」という言葉には、財産を受け取るというイメージが強いですが、借金も相続されることは確かな事実です。相続とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて引き継ぐ制度であるため、借金も対象となります。
その場合、他にも相続人がいれば、法定相続分などに基づき決まった割合で借金を相続することになります。具体的なイメージを持っていただくため、下に妻と子ども二人が借金を相続した場合の例を図解します。意外と知られていないこの「親の負債は相続される」という事実を忘れずに覚えておきましょう。
まずは親の借金の有無を確認しよう
親は子どもに心配をかけたくないという気持ちが強いため、借金の詳細を子どもに伝えることはほとんどありません。しかし、親の借金額や借入先を子どもが知っていれば、親の再起を支援する方法を一緒に考えることができ、また万が一の相続発生時にも相続放棄するかどうかの判断材料として役立ちます。そこで、親の借金の調べ方を紹介します。
親や親戚、親の知人に聞き取りを行う
親の借金状況を金融業者や信用情報機関に確認することは、親が生存している限り基本的に難しいです。これは、個人情報保護の観点から、金融機関や信用情報機関が本人以外からの問い合わせに応じないためです。
親の借金の実態を知るためには、親に直接確認することが最も確実な方法となります。また、親の知人や親族に対して「親が誰かからお金を借りているか」や「誰かの保証人になっていないか」をさりげなく尋ねることも有効な手段です。こうした方法で得られる情報が、親の借金状況を把握するための手がかりになるかもしれません。
亡くなった場合の対応:個人信用情報機関に開示請求を行う
個人信用情報機関(CICクレジットカード会社、JICC、KSCなど)には、借入、返済、滞納などの借金に関する情報が記録されています。親が亡くなっている場合、個人信用情報機関に情報開示を請求することができます。
親が生存している場合、本人のみが開示請求を行うことができますが、親がすでに亡くなっている場合、以下の書類を提出することで親の借金情報を開示してもらえます。
- 本人確認書類:マイナンバーカードのコピーなど
- 法定相続人であることを証明する書類:戸籍謄本のコピーなど
- 親が亡くなったことを証明する書類:死亡診断書のコピーなど
親の郵便物や通帳を確認して調べる
郵便物や通帳を確認することで、借金に関する情報を発見できる場合があります。まず、銀行の通帳の入出金履歴をチェックしましょう。もし、銀行名や消費者金融の名前が記載されていれば、借金の可能性が高いと考えられます。次に、借用書や契約書などの書類も探してみましょう。
また、親宛に届いた郵便物の中に借金に関する証拠が含まれていることがあります。例えば、金銭消費貸借契約書が見つかれば、それは借金があることを示唆しています。さらに、貸金業者からの督促状や督促メール、裁判所からの書類が届いていないかどうかを、注意深く確認することも重要です。
亡くなった親の借金を確認する方法
「亡くなった親から借金のことを聞いていなかったが、どう調べれば良いのか?」という相談は私もよく受けます。
- 郵便物を確認する
借金があれば、請求書や利用明細書などが亡くなった親宛てに届くことがあります。過去の郵便物も確認して、見慣れないものがあれば注意しましょう。 - 個人信用情報機関から信用情報を取り寄せる
信用情報を調べる方法として、個人信用情報機関から情報を取り寄せることができます。亡くなった方の配偶者(妻・夫)や2親等以内の血族(子どもも含まれます)であれば、相続人として請求を受け付けてもらえるため、この方法を試してみましょう。取得した情報を元に、調査を進めることができます。
不動産の登記事項証明書や抵当権を調べる
親が土地や建物を所有している場合、その不動産に抵当権が設定されているかどうかを確認することで、借金の有無を調べることができます。抵当権とは、銀行や金融機関が貸付を行う際に、土地や建物を担保として設定する権利です。借金の返済が滞った場合、抵当権を持つ銀行や金融機関は、不動産を売却して貸付金を回収します。
こうした抵当権の有無は、不動産の登記事項証明書で確認できます。この証明書は、インターネットの「登記情報提供サービス」や「登記・供託オンライン申請システム」を利用して調べることができます。
もし抵当権が設定されていれば、親に借金がある可能性があります。ただし、建物に設定された抵当権が住宅ローンに関連している場合も多いため、親の死亡時に団体信用保険によってローンの支払いが免除されていることも考えられます。そのため、住宅ローンを組んでいるかどうかを確認するために、契約書などをチェックしておくことをお勧めします。
親の借金に対する返済義務はない
親の借金が発覚したとき、子どもたちは返済義務があるのかと心配になることがあります。しかし実際には、親の借金が明らかになっても、基本的に子どもには返済義務はありません。というのも、親の債務はあくまで親自身の責任であり、法律的には子どもがその負担を負う必要はないためです。
注意!連帯保証人かどうかは確認できない場合がある
親が金融機関などから借りていた借金は、信用情報を取得すれば確認できます(3-1の信用情報)。しかし、誰かの連帯保証人になっていた場合は、信用情報ではその事実を知ることはできません。借りている人が返済をきちんとしている限り、保証人には明細の発行などもないため、生前に確認しておかないと、何年も後になって突然保証債務を請求されることになり、驚くことになります。
親の借金を肩代わりする必要がある場合とは?
親が借金をしている場合、その返済は親自身の責任であるため、原則として子どもが親の借金を肩代わりすることはありません。
しかし、以下で説明する3つのケースにおいては、子どもが親の借金を肩代わりしなければならない場合があります。
親が亡くなり、借金を相続した場合の対応
親が亡くなったら、相続人である子どもは故人の遺産を相続します。遺産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続時に親が借金を抱えていた場合、その返済義務も相続することになります。
親が子どもの名義で借金をしていた場合
子どもが成年の場合、親に借金に関する代理権を与え、その代理権に基づいて借入をした場合、名義人である子どもが返済をしなければなりません。
ただし、親に代理権を与えた覚えがなく、子どもの名義で親が勝手に借金をしていた場合は、子どもは返済義務を負いません。
一方、子どもが未成年(18歳未満)の場合、親には「子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を子どもに代わって行う権限」(民法824条本文)があります。
そのため、親は子どもの名義で契約を結ぶことができ、親が子どもの利益を考えて子どもの名義で借金をした場合、子ども自身が返す義務が発生することになります。
親の借金で子どもが連帯保証人になっている場合
親の借金に関して、子どもが連帯保証人になっている場合、親の返済が滞ったり、親が亡くなった場合には、連帯保証契約に基づいて、子どもが借金を返済しなければならなくなります。
さらに、連帯保証契約は通常の保証契約と異なり、「催告・検索の抗弁権」が認められていません。この「催告・検索の抗弁権」とは、以下の権利を指します。
- 債務者本人にまず請求するよう主張する権利
- 債務者本人に資力がある場合、まずそちらから取り立てを行うべきだと主張する権利
これらの権利がないため、連帯保証人は実質的に「自分が借金を負っているのと同じ状態」といえるでしょう。
親の借金があなたに影響を及ぼした時の対応方法
本章では、債権者から親の借金返済を迫られた場合や、借金を相続してしまった場合の具体的な対処方法をご紹介します。
親の債権者から返済を求められたら、きっぱりと断りましょう
「親の借金を子どもが返済する義務はない」ことを大前提として忘れないようにしましょう。親を助けたいという子どもの気持ちに付け込むのは、借金回収のプロの手口です。代わりに返済することは断固として拒否しましょう。それでもしつこく返済を迫られた場合、脅迫に該当する可能性もあるため、警察に相談することを検討することも大切です。
親の借金の保証人や連帯保証人になることは絶対に避けるべき
よく見られるのが、親の借金の連帯保証人や保証人を子どもがしているケースです。例えば、親が借金の返済期限を迎えられなくなり、債権者から「期限を延ばす代わりに子どもを保証人にしてほしい」と頼まれ、子どもが保証人になる場合があります。この場合、債権者の本音は「子どもから回収しよう」というものもあります。
子ども側も、保証人という法的責任の重さを十分に理解せずに保証人になってしまっていることが多いでしょう。私は、「保証人や連帯保証人は自分で借金をするのと同じ」と考えています。親に関することだけでなく、借金の連帯保証人や保証人になることは避けるべきです。実際、保証人になったことで人生が狂ってしまった人が多いのは事実です。
例えば、親が破産することになり、その連帯保証人である子どもが数千万円の保証債務を負うことになり、結果として子どもも自己破産せざるを得なくなり、購入した住宅が競売にかけられるということが起こり得ます。
再度言いますが、連帯保証人になることは避けましょう!
親には債務整理を提案してあげましょう
親が借金をしており、これ以上支払いが難しい状況の場合、親に「債務整理」を勧めてあげると良いでしょう。債務整理とは、借金で困っている人が、司法書士や弁護士に依頼して、債権者と交渉し、利息をカットしてもらう任意整理、裁判所に申し立てをして借金を実質的にゼロにする自己破産、住宅を守りつつ借金を強制的に減額できる個人再生など、借金問題を解決するために専門家に依頼する手続きの総称です。
以下に、債務整理の手続きの比較表を記載します。各手続きのメリットとデメリットも説明しますので、参考にしてください。
債務整理手続き比較表
※1 資格制限とは?
自己破産の申立てをすると、司法書士、弁護士などの士業や保険外交員、警備員など、一定の職業・資格に一時的に就けなくなります。ただし、資格制限の期間は破産手続きの開始決定から、免責決定が下されるまでの間のみです。
「自己破産をすると家の中の物もすべて没収される」などの誤った情報を信じている人も多いです。特に高齢者の中には、借りたものは必ず返さなければならないと考える人が多く、自己破産をすると人生が終わるように感じて拒否する人もいます。
もちろん、借りたものは返すのが当然ですが、債務整理は経済的な再起を助けるために認められた法律的な仕組みです。借金の支払いが困難な場合、債務整理を利用することをおすすめします。
ただし、債務整理の手続きは必ず本人が依頼しなければならないことに注意が必要です。子どもが親のために司法書士等に依頼することはできないので、親自身が手続きを行う必要があります。
自己破産
親の借金の連帯保証人になっていたり、借金を相続した場合、親の借金を肩代わりしなければならないことがあります。
そのような状況で、借金の金額が明らかに返済不可能な額に達している場合、自己破産を考えるべきです。
支払能力がなく、一般的かつ継続的に債務を弁済できない状態であれば、裁判所が自己破産を認めれば債務の弁済が免除されます。
- 一般的とは、支払期日が来た時に、すべての債権者に通常通り返済することができること
- 継続的とは、一時的な収入減ではなく、今後も返済困難な状況が続くこと
ただし、ギャンブルなどで借金が膨らんでしまった場合は、自己破産が認められないことがあります。
また、自己破産が認められると、所有している財産(家や車など)は差し押さえられる可能性があるため、十分な注意が必要です。
もし、親の借金を一切肩代わりしたくない場合、上記のように自己破産を選択することになりますが、そうでない場合は、他の債務整理手続きを検討することになります。具体的には、任意整理や個人再生などの債務整理手続きがあります。
限定承認
不動産などの特定の財産を相続したいが、マイナスの財産がどの程度あるか不明なため、相続自体を躊躇する場合もあるかもしれません。そのような場合には、限定承認を選択することが考えられます。
限定承認とは、相続によって得るプラスの財産を上限として相続する方法です。相続によって引き継いだプラスの財産からマイナスの財産を清算し、もし残ったプラスの財産があれば、相続人がそれを受け継ぐことができます。
ただし、限定承認を行うには家庭裁判所で手続きが必要であり、労力を要します。また、清算手続きが完了するまではプラスの財産の処分を行うことができません。さらに、他の相続人がいる場合は、全員が共同で限定承認を行う必要があります。
時効援用
時効援用は、債務者が債務の時効成立を主張することで、債権者からの請求を免れる法的手段です。この手続きは、一定の期間が経過した後、債務者が債権者に対して時効の成立を明確に伝えることで効力を発揮します。
時効の期間は債務の種類によって異なります。貸金業者からの借入れは5年、個人間の借金は10年です。ただし、これらの期間は2020年3月31日以前に開始した取引に適用されます。2020年4月1日以降に発生した債務には、改正民法が適用され、「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方が適用されます。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人から受け取る予定の全ての財産を放棄する手続きです。この手続きを行うと、親の借金を肩代わりする必要がなくなる一方で、プラスの財産も受け取れなくなります。そのため、負債が資産を上回っている場合に有効な手段と言えるでしょう。
一般的に、親が亡くなり、相続人として財産を承継することが判明した後、3ヶ月以内に手続きをしなければならないことになっています。ただし、財産調査を十分に行わなければ、後で高額な資産が発見された場合に不利益を被る可能性があります。また、相続放棄を行うことで、次順位の相続人に権利が移るため、争いが起こるケースもあります。
親の借金を相続した場合、相続放棄を考えましょう
親が亡くなると、子どもであるあなたは「法定相続人」となります。財産があればそれを相続しますが、同時に「借金」などの負債も相続することになります。親が亡くなり借金を相続した場合、「相続放棄」という手続きを選択することを検討しましょう。
相続放棄のやり方とは、家庭裁判所に申し立てを行い、相続放棄を認めてもらうことによって、その相続について自分は無関係になる手続きです。
- 相続放棄の期限:相続人となることを知った時から3ヶ月以内
- 申立先:被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所
【相続放棄の手続き完全版】流れ、費用、必要書類、注意点を簡単に解説します。
相続放棄を考えるべき場合の例
① 借金の額が財産の額を上回っている → この場合、特に解説の必要はないでしょう。
② 他の相続人との関係が悪く、相続に関わりたくない → 相続放棄をすると、最初から相続人でなくなるため、遺産分割協議などの相続手続きに関わることがなくなります。
③ 亡くなった親とは疎遠で、借金の有無すらわからないため不安だ → 相続放棄をすれば、後から知らなかった借金などを請求されても安心ですが、財産も受け取れなくなるので、よく考えてから手続きを行いましょう。
④ 亡くなった親が自営業をしていたが、事業を引き継ぐつもりはない → 例えば、自営業を営んでいた父が亡くなり、相続人は事業を引き継ぐ長男Aと引き継がない次男Bの場合、遺産分割協議で長男Aが全財産を相続すると決まったとします。この場合、次男Bが相続する負債に関しては関係ないと思いがちですが、それは間違いです。相続した負債についての責任は、次男Bも負わなければならないのです。なぜなら、遺産分割協議の結果は相続人間で効力を持ちますが、債権者には関係がないからです。多くの方が「何も受け取らない」ことで相続放棄したと勘違いしていますが、これは誤解です。
認知症の親が借金を抱えていた場合の注意点
親が借金をしている場合、債務整理や時効援用などが対処方法として考えられます。ただし、親が認知症を患っている場合、これらの手続きは成年後見人によって行われなければなりません。ここでは、親が認知症の場合のリスクを軽減する方法や、成年後見人について解説します。
債務整理や時効により借金が減額または免除される可能性
親が認知症を患うと、借金の管理や返済に支障が出てくるため、遅延損害金が増加し、債権者から子どもに返済を迫られる可能性もあります。そのような場合には、「債務整理」を検討することが重要です。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払猶予を求める手続きです。具体的には、以下の4つの手続きがあり、状況に応じて適切な方法を選びます。
- 任意整理
裁判所などの公的機関を通さずに、直接業者と交渉し、債務の支払い方法を合意する方法です。弁護士や司法書士が債権者と話し合い、毎月の支払い額を減額することを目指します。 - 自己破産
債務者が裁判所に申し立てを行い、最終的に借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。利息制限法に基づいて債務を圧縮してもなお多額の負債が残り、返済が不可能な場合に検討されます。 - 個人再生
債務者が裁判所に再生計画を提出し、その認可を得ることで借金を減額する法的手続きです。自己破産とは異なり、債務は完全には免除されず、返済可能な金額に減額した後、一定期間で返済を続けることを目指します。 - 特定調停
簡易裁判所が仲介し、債務者と債権者が返済条件の緩和などを話し合いで合意する手続きです。任意整理と同様に、債権者から取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく利息の引き直し計算を行い、減額された元本をもとに分割返済を進める方法です。
親が認知症であっても、子どもが勝手に親の債務整理や時効援用を行うことは法律上認められていません。このような状況に対応するためには、成年後見制度の活用が必要不可欠です。成年後見制度については、以下で詳しく解説します。
債務整理や時効援用には成年後見人が必要になる場合がある
成年後見人制度は、判断能力が低下した人を支援するための法的仕組みで、知的障害、精神障害、認知症などによって、契約や手続きが困難な方が対象です。
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、審判を経て成年後見人が選任されます。成年後見人には、家族や弁護士、司法書士などの専門家が任命されることもあります。
選任された成年後見人は、財産の管理や身上保護を担当し、不利益な契約の取り消しを行うこともできます。認知症の親の借金問題に関しても、成年後見人が代理として債務整理や時効援用を行うことが可能です。
成年後見人の手続きの進め方
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。この手続きにはいくつかの必要書類があり、まず医師の診断書が求められます。この診断書は、本人の判断能力に問題があることを証明するためのものです。
申立ての流れとしては、診断書を取得後に申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。裁判所は、提出された書類を審査し、申立ての正当性を確認したうえで、後見人の選任を決定します。
後見人は、本人や家族からの提案を基に選ばれることが一般的ですが、提案がない場合は裁判所が適任者を選びます。手続きには時間がかかるため、早めに対処することをお勧めします。
参考:申立てをお考えの方へ(裁判所)
親の借金を知らずに相続してしまった場合の対応方法
亡くなった親の財産の中に借金があることを知らずに相続してしまった場合や、借金があるにもかかわらず相続放棄の手続き期限を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。
裁判所が認めれば、後からでも相続放棄ができる場合がある
相続放棄は、原則として親が亡くなり、「自分が相続人であることを知った時から3か月以内(熟慮期間)」に手続きを行わなければなりません。しかし、この期間を過ぎた後でも相続放棄が可能な場合があります。
相続人がプラスの財産もマイナスの財産も全く存在しないと信じていた場合、これに相当する理由が認められるときには、親の死去を知ってから3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄ができなかった場合の対処法として債務整理を検討する
相続放棄を行わなかった場合に、マイナスの財産がプラスの財産を大幅に超えてしまうような状況では、自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理を検討する必要があります。各手続きの特徴は、以下の表の通りです。
| 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
|---|---|---|---|
| 債務のカット | あり(一部を除き全額カット) | あり(約80%カット) | 原則なし(返済期間の変更や利息のカットにとどまる) |
| 返済期間 | なし(返済不要) | 3~5年 | 3~5年 |
| 特定の財産を残すことの可否 | 不可 | 可 | 可 |
| 官報への掲載 | あり | あり | なし |
| 裁判所の関与 | あり | あり | なし |
親の借金で困ったときの重要ポイントと注意すべき点
親の借金に関して困った場合の主なポイントと注意点は、以下の通りです。
- 相続放棄をするまでは親の財産に手をつけない
- 親が存命のときには相続放棄はできない
- 相続放棄や限定承認は相続開始から3ヶ月以内に行う
- 相続放棄の期限は延長できる場合がある
- 限定承認は相続人全員で行う必要がある
- 過払い金請求は返済から10年以内に行う
これらの注意点をしっかりと把握し、あらかじめ準備しておくことが重要です。
相続放棄するまでは親の財産に触れないようにする
相続放棄を検討している場合、熟慮期間中および期間延長中は親の財産に関与しないことが重要です。借金の一部返済や預金の解約を行うと、それが単純承認とみなされ、相続放棄の権利を失う恐れがあります。
債権者に返済の猶予を求めるだけでも、単純承認と判断されるリスクがあるため、十分に注意しましょう。例外(生命保険や葬儀代など)はありますが、原則として相続放棄が確定するまでは相続財産に手を触れないことが賢明です。
うっかり財産を扱ってしまい、相続放棄の機会を逃すことがないよう、細心の注意を払うことが必要です。相続に関する行動を起こす前に、専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄は親が生存している間にはできない
親の借金を回避するための注意点として、生前に相続放棄はできないことを理解しておくことが重要です。親に多額の借金があり、相続することでマイナスの資産が多くなると予想される場合でも、生前に相続放棄を行うことはできません。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行いますが、親が生きている間は手続きを受け付けてもらえない点に注意が必要です。
相続放棄の期限は延長可能な場合がある
相続放棄の熟慮期間が3ヶ月では足りない場合、期間内に裁判所へ「相続放棄の期間延長申立て」を行うことで、延長が可能です。ただし、正当な理由が求められます。
例えば、被相続人との関係が疎遠であったり、他の相続人との連絡が難しい場合や、財産調査が長引く場合には、延長が認められることがあります。しかし、仕事が忙しいなどの個人的な都合では、申立てが却下されることもあるため、十分に注意する必要があります。
相続放棄と限定承認は相続開始から3ヶ月以内に手続きが必要
相続放棄や限定承認の手続きは、自分が関係する相続があることを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、法律上「単純承認」とみなされ、親の資産と負債の全てを引き継ぐことになります。
相続が発生した際には、速やかに財産状況を精査し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを検討することが重要です。
限定承認は全ての相続人が協力して行う必要がある
限定承認は、相続人全員の合意が必要な手続きです。この手続きを進めるためには、すべての相続人が家庭裁判所での手続きに参加しなければなりません。そのため、1人でも反対する相続人がいると、限定承認は成立しません。
さらに、相続人の誰かが単純承認をしてしまうと、他の相続人が希望していても、限定承認はできなくなります。このリスクを避けるためには、相続人間で十分に話し合い、合意を得ることが重要です。
過払い金請求は返済後10年以内に行う必要がある
過払い金請求には時効があり、最後の取引日から10年以内に請求しなければなりません。完済した借金の場合は「借金を完済した日」、返済中の借金の場合は「最後に返済をした日」が消滅時効の起算点となります。
時効が過ぎると、過払い金が発生していても回収できなくなります。最後の取引日を確認するためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があり、これには時間がかかることもあるため、早めに準備をしておくことが重要です。
親の借金を肩代わりする際は贈与税に注意が必要
子が自発的に親の借金を肩代わりすると、子が借金を返済することになり、親はその返済義務を免れることになります。この場合、「子が親に対して肩代わりした金額を贈与し、その後親が返済した」と評価されることになります。
そのため、この金額が年間110万円を超えると、贈与税が発生するため、注意が必要です。
ただし、「子が借金を肩代わりした後に親から肩代わり分を返済してもらう」場合、贈与税がかからない可能性があります。
相続放棄の重要ポイント
ポイント1:相続放棄の期限は延長可能
「相続放棄」と聞いて、期限を過ぎたら諦めなければならないと思う方も多いかもしれませんが、実は3ヶ月の期限内に財産調査が難しい場合、その期限を延ばす手続きがあります。家庭裁判所に申し立てを行えば、期限の延長が認められることがあります。しっかりと準備して、期限を守りましょう。
ポイント2:相続放棄を検討中は相続手続きを控えよう
相続放棄を考えている場合、親が亡くなった後、親の相続財産に関する手続きを始めるのは避けた方がいいです。例えば、親の預金を解約してしまうと、「単純承認」をしたと見なされ、相続放棄が難しくなることがあります。慎重に行動しましょう。
ポイント3:相続放棄しても遺族年金や生命保険金は受け取れる
相続放棄をしても、遺族年金や生命保険金は受け取ることができます。なぜなら、遺族年金や生命保険金は相続財産ではないからです。しかし、生命保険の場合、受取人が亡くなった本人になっている場合は受け取れないこともありますので、生命保険の受取人はしっかりと確認しておきましょう。
ポイント4:相続放棄の期限を過ぎてもあきらめないで
相続放棄の期限を過ぎても認められる場合があります。例えば、親が亡くなってから数年後に保証債務の請求書が突然届くケースもあります。このような場合、負債の存在を知った時(請求書を見た日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることもあるので、諦めずに検討しましょう。
限定承認について
親の借金を相続してしまった場合、相続放棄の他に限定承認という手続きも選択肢に入ります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。もし、マイナスの財産が予測以上に多いが、どうしても相続したい財産がある場合(例えば不動産など)に選ぶことができます。
限定承認には相続人全員の合意が必要です。もし、一人でも反対する相続人がいる場合、この手続きは使えません。手続きが複雑で、注意しないとトラブルに繋がることもあるので、相続に強い司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。
まとめ
親が亡くなった際に、子が親の借金を肩代わりしなければならないかどうかは、「相続をするかしないか」によって決まります。
相続を選ぶ場合、親のプラスの遺産を相続することができますが、借金を含むマイナスの遺産も引き継ぐことになります。
一方で、相続放棄を選ぶ場合、プラスもマイナスも含めて一切の遺産を相続しないことになります。相続放棄の手続きは、「自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内」に行わなければならないため、迅速に手続きを進める必要があります。
もし期限を過ぎるなどして相続放棄が認められなかった場合、自己破産などの債務整理手続きを検討しなければならないかもしれません。
もし相続をどうすべきか、または親の借金の肩代わりについて悩んでいる場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問
親の借金の肩代わりに関するよくある質問をまとめました。
親の住宅ローン残金は相続後どうなる? 子が返済する必要はあるのか?
亡くなった親の住宅ローンの残金の返済については、団信(団体信用生命保険)の加入状況が大きく影響します。団信とは、住宅ローンの返済中に契約者が亡くなった場合などに、住宅ローンの返済が不要になる保険です。ほとんどの金融機関では、住宅ローンを組む際に団信への加入を条件としています。
ただし、団信に加入しないで住宅ローンの融資を受けることも可能な場合があります。その場合、親が亡くなっても住宅ローンの返済義務が残るため、この点を踏まえて相続をするか、相続放棄をするかを慎重に判断する必要があります。
親に無断で保証人にされた場合の対処法
親が自身や第三者の利益のために、勝手に子を保証人としていたような場合、子は借金を返済する必要はありません。ただし、子が自分の意思で「返済する」と決めたのであれば話は別です。
借金の時効とは?消滅時効について
借金には時効があり、時効を迎えた後に相手方へ時効の利益を主張すると、返済義務がなくなります。
これを「消滅時効」といい、以下のいずれかの短い期間が経過すると成立します(民法166条1項)。
① 借金の弁済期(返済期日)後、債権者が返済請求できることを知ったにもかかわらず、5年間請求しなかった場合。
② 借金の弁済期(返済期日)後、債権者が返済請求できる状態が続き、10年間請求しなかった場合。
離婚や絶縁した親の借金はどう扱うべき?
親が離婚していた場合、亡くなった親の元配偶者は相続人にはならないものの、その間に生まれた子どもは故人の遺産を相続する権利があります(民法887条1項)。そのため、子どもは借金も含めて相続するか、相続放棄をするかを決める必要があります。
また、子どもが亡くなった親と絶縁していて一切連絡を取っていなかった場合でも、法律上は親子関係が存在しているため、この場合も相続するかどうかを判断する義務があります。
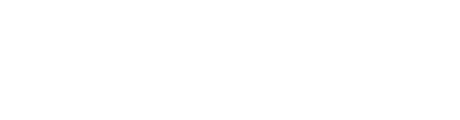


[…] 遺言書により相続人が指定されていた場合でも、手続きをとることで、相続を放棄することが可能です。手続きとは、裁判所に所定の書類を提出することになります。放棄の対象は、遺言書による相続部分だけではなく、借金なども含まれまるので要注意です。参考:親の借金、返済義務は?肩…|あけるさいむ […]