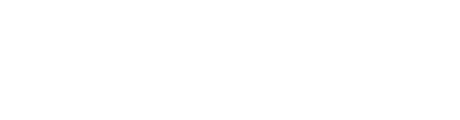※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
子供の借金は親が返済するべきか?借金発覚時の注意点と解決方法
目次
「子供の借金は親が返済する義務があるのか」
「子供の借金を解決する方法はあるのか」
子供に多額の借金があると知り、親として何とかしたいと考えている方もいるかもしれません。
本記事では、子供の借金を知った際の注意点や解決策についてご紹介します。
子供の借金は親が返済しなければならないのか?
子供の借金について、子供が返済できない場合には親が返済しなければならないと考える方もいるかもしれません。
しかし、結論として、子供の借金を親が返済する義務はありません。これは親だけでなく、配偶者や子供も同様です。借金の返済義務を負うのは、借金をした本人(この場合は子供)であり、契約当事者ではない親が返済を求められることは原則としてありません。
ただし、例外として親に返済義務が発生するケースもあります。たとえば、親が子供の借金の保証人や連帯保証人になっている場合、子供が返済できないときには親が代わりに返済しなければなりません。
保証人となるには、ご自身が署名捺印をしている必要があります。子供の借金が発覚した際には、ご自身が保証人となっているかどうかを必ず確認しましょう。
保証人でなければ、借金を負担する必要はない
家族が借金を抱えていたとしても、親が「保証人」や「連帯保証人」として契約を交わしていなければ、親には返済の義務はありません。
保証人と連帯保証人は、借金をした人が返済できなくなった際に代わりに返済する義務があるという点では共通しています。しかし、貸金業者から返済を求められた場合、保証人であれば「まずは借金をした本人に請求してください」と主張できますが、連帯保証人にはその主張ができないという違いがあります。そのため、貸金業者にとっては連帯保証人のほうが有利であり、一般的に「保証人になる」ということは「連帯保証人になる」と考えられることが多いです。
さらに、配偶者や兄弟姉妹など、子供以外の家族の借金であっても、保証人や連帯保証人になっていなければ、返済義務を負うのは契約者本人のみです。貸金業者が法律上支払い義務のない人に対して請求を行うことはありません。それだけでなく、過度な取り立ての協力を求めることも禁止されています。
もし、貸金業者が執拗に支払いを求めてくる場合は、監督官庁に対し行政指導や行政処分の申し立てを行うことが可能です。
年齢によって扱いが変わることもある
子の借金に関しては、未成年かどうかによって異なる点があります。
クレジットカードで借金をした場合
クレジットカードの申し込み条件は「18歳以上」となっているケースが多く見られます。ただし、18歳や19歳の場合は、どれほど安定した職業についていて年収が高くても、保護者の同意が必要です。
また、大学生や専門学校生であれば、「学生カード」と呼ばれる学生向けのクレジットカードを利用することもできます。さらに、親が持っているクレジットカードの「家族カード」を発行してもらう方法もあります。
しかし、その場合、子供がクレジットカードで買い物をしすぎて返済に困るケースも考えられます。こうした状況に対して、「自分で頑張って返済しなさい」と人生経験として本人に任せるか、親が肩代わりするかは、それぞれの家庭の判断によるでしょう。
消費者金融の場合の扱い
消費者金融の大手では、借り入れの基準として「20歳以上で安定した収入があること」と明記されています。そのため、20歳以上で安定収入があれば、学生であっても社会人であっても借入は可能です。しかし、アルバイトなどで安定収入があっても、20歳未満の人は大手の消費者金融では借り入れができません。
ただし、数は少ないものの、学生向けに「学生ローン」を専門に扱う中規模の消費者金融も存在します。学生ローンの対象は、大学生・大学院生・専門学校生であり、業者によっては「18歳以上で安定収入のある学生」と明示している場合もあります。
ただし、未成年者が借り入れをする際には、保護者の同意が必要です。これは未成年者を保護するために民法で定められているため、まず確認しておくべき重要なポイントとなります。
成人した子供の借金が増えてしまった場合
20歳以上であれば、自分で貸金業者から借金をした場合でも、前述の通り、親が保証人や連帯保証人でない限り支払い義務はありません。これは大人としての責任であり、たとえ返済が難しい状況であっても、安易に援助するのではなく、自分の行動に責任を持たせることが大切です。借金をした本人が、自ら解決する必要があります。
「誰にも頼らず、自分で考えて対処する」という選択肢もあれば、親が金銭的援助をするという方法もあります。また、それらに代わる手段として、司法書士など専門家に相談することも検討する価値があります。しかし、親が簡単に援助をしてしまうと、同じことを繰り返す可能性があるため、慎重な判断が求められます。
子供の借金を知った際の注意点
子供に借金があり、返済が難しくなっていることを知った際には、注意すべきポイントがあります。
主な注意点は以下の2つです。
子供の借金が発覚した際の注意点
- 借金の状況を確認する
- 早めに弁護士へ相談する
それぞれについて、詳しくご紹介します。
借金の状況を把握する
まずは、子供の借金の状況をしっかりと確認することが重要です。
特に、以下の点を明らかにすることが大切です。
子供の借金について確認すべきポイント
- どこから借金をしているのか
- 借金の総額はどのくらいか
- 金利はどの程度か
特に、複数の貸金業者から借金をしている場合は、できるだけ早く状況を整理し、適切に対処する必要があります。
複数の金融機関や貸金業者から同時に借入れを行っている状態は「多重債務」と呼ばれ、この状態が続くと借金が雪だるま式に増えてしまう可能性があるため注意が必要です。
借金の状況を整理した上で、金利の高い借入先から優先的に返済するなど、借金がさらに膨らまないよう対策をとりましょう。
早期に弁護士へ相談する
借入状況や契約内容によっては、自力での返済が難しいケースもあります。
そのような場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、本人の状況に応じた最適な手続きとして、任意整理・自己破産・個人再生などの選択肢を提案してもらうことができます。
経済的な再スタートを切るためにも、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
子供の借金を解決するための方法
子供の借金問題を解消する方法はいくつか考えられます。
主な解決方法は以下の通りです。
子供の借金を解決するための主な方法
- 親が代わりに子供の借金を返済する
- 子供にお金を貸して返済を支援する
- 債務整理の手続きを進めるよう促す
それぞれの方法について、順にご紹介します。
子供に貸付を行う
贈与税の発生を防ぐ方法として、子供にお金を貸すという選択肢も考えられます。
子供に貸付を行う場合、贈与には該当しないため、贈与税の納税義務は発生しません。ただし、この方法を選ぶ際には、必ず借用書などの契約書類を作成し、記録として残しておくことが重要です。
親子の関係では、口頭で「貸す」と言っても、実際には返済を求めないケースが十分に考えられます。しかし、実際に返済を求めない場合、貸付ではなく贈与と見なされ、贈与税の納税義務が発生する可能性があります。
口約束では貸付を証明することができないため、税務署から調査を受けた際に「贈与ではなく貸付だった」と証明できるよう、借用書などの書類を必ず残しておきましょう。
なお、実際には親が子供にお金を与えて借金を返済していたにもかかわらず、「貸付だった」と偽ることは脱税にあたるため、絶対に避けてください。
親が子供の借金を代わりに返済する
親が代わりに子供の借金を返済することで、借金を無くすことを考える方もいるかもしれません。
しかし、親が借金を支払う場合には、贈与税が発生する可能性がある点に注意が必要です。
贈与税がかかるのは、110万円以上の借金を支払うお金を子供に与えた場合です。そのため、子供の借金が110万円を超えている場合、親が立て替えると、子供に贈与税の納税義務が生じます。
また、金額が大きくなるほど課税率も上がるため、場合によっては贈与税の支払いが増え、それが原因で新たな借金をするという本末転倒な事態になる可能性もあります。そのため、親が110万円以上の借金を支払うお金を子供に与える際には、事前に贈与税が発生することを伝えておくなど、十分に注意しましょう。
なお、親から借金の返済資金を受け取った場合、子供は税務署に申告書を提出し、納税する必要があります。申告をせずに発覚した場合は税務署の調査が入るため、子供が適切に申告できるよう促すことが大切です。
債務整理の手続きを進めるよう促す
子供の借金の金額が大きく、返済が困難な場合は、債務整理を提案してみましょう。
債務整理とは、利息のカットや毎月の返済額の見直し、借金自体の減額、さらには全額免除などを通じて、返済の負担を軽減し、経済的な再起を目指す手続きです。
債務整理の方法には、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。
- 任意整理:債権者と交渉し、将来利息のカットや毎月の返済額を調整することで、負担を軽減しながら借金を完済する方法。
- 個人再生:裁判所に申し立てを行い、借金総額を5分の1程度に減額し、それを3~5年で返済する手続き。
- 自己破産:裁判所に申し立てを行い、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続き。
どの方法を選択しても、一定期間は信用情報機関に記録が残り、クレジットカードやローンの審査が通らなくなるというデメリットがあります。しかし、返済が難しくなった借金の負担を軽減し、経済的に立ち直るためには非常に有効な手続きです。
債務整理を検討する際は、弁護士に相談し、子供の状況に最適な手続きを選ぶためのアドバイスを受けることをおすすめします。
亡くなった際に借金が残っていた場合
たとえば、子供が家出をして長年音信不通だったところ、ある日突然、警察から「亡くなった」という連絡が入ったとします。子供は結婚しておらず、子供もいない状況でした。その後しばらくして、貸金業者から両親に対して「子供の借金の残額を支払ってほしい」と請求があったら、どう対応すべきでしょうか。
法律上、亡くなった子供に配偶者や子供がいない場合、相続人は直系尊属、つまり親が相続することになります。相続では、資産だけでなく借金も引き継ぐことになりますが、「相続放棄」の手続きを行うことで負担を免れることが可能です。そのため、できるだけ早めに専門家に相談することをおすすめします。
もし両親が相続放棄をすると、次の相続人は祖父母になります。さらに、祖父母全員が相続放棄をした場合、子供の兄弟姉妹がいれば、その人が相続人となります。そのため、関係者全員に事情を説明し、早めに協力を得ることが重要です。
これは、親が借金を残して亡くなった場合にも同様です。借金のような負の財産だけを放棄することはできず、資産と借金を一体として放棄するか、すべてを引き継ぐかのどちらかを選ばなければなりません。こうしたケースでは、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。
まとめ
子供が借金の返済に困難を感じていることが分かった場合、まずは借金の内容を整理することが重要です。
各借入先や借金の金額、金利など、全体の状況を正確に把握しなければ、適切な対応を取ることができません。中には、一部の借金だけを全てだと思い込み、代わりに返済した後で、実は他にも多額の借金があることが発覚するケースもあります。
最初からすべての借金を把握していれば、一部の返済に踏み切らず、債務整理の手続きを行うことで抜本的な解決を図ることができた、という場合もあります。そのため、借金の全容を把握することは非常に重要です。
また、借金の返済が困難な状態が長引くと、高い利率の利息が加算され、状況がさらに悪化してしまう可能性があります。早期の対応が肝心なため、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。