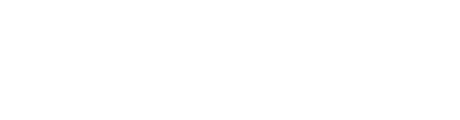※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
夫の借金が発覚!妻に返済義務はある?離婚せずに解決するための方法
目次
「旦那が借金してるかも…」「住宅ローンの審査が通らず、1,000万円の借金が発覚!」
このような状況に直面したとき、妻である自分にも返済義務があるのではないか と不安に感じる方は多いでしょう。
実際のところ、夫が借金を内緒にしているケースは少なくなく、夫婦間の借金問題に関する相談も多数寄せられています。 むしろ、借金を隠している割合の方が高いのが現状です。
結婚前に作った借金であれば、相手に言いにくいと感じるのも理解できますが、婚姻中に生活費のために作った借金であっても、妻に内緒にしているケースは少なくありません。
本記事では、旦那の借金を調べる方法 をはじめ、債務整理のメリット・デメリット について詳しく解説していきます。
旦那の借金が発覚!妻に支払い義務は発生するのか?
旦那の借金が発覚しても、基本的に妻に支払い義務はありません。 しかし、支払い義務が発生するケースも存在します。
以下で、その詳細について詳しく見ていきましょう。
基本的には、妻の返済義務はない
旦那の借金の原因には、ギャンブル、FX、風俗などさまざまなケース があります。 しかし、旦那の借金が発覚しても、妻に支払い義務があるわけではありません。
なぜなら、借金の返済義務は本人にしか及ばない ためです。 実際、貸金業法 においても、以下のように規定されています。
(貸金業法第21条第1項 取立て行為の規制)
「貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は以下に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはなりません。
ー債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」
つまり、「妻に借金の取り立てがくる」「旦那の代わりに妻が返済しろと言われる」 というような事態は、違法である可能性が高い ため、すぐに専門家へ相談する必要があります。
ただし、妻に借金の支払い義務が発生するケースもあるため、注意が必要です。
夫の借金滞納が妻の財産に与える影響はない
夫の個人的な借金の返済状況が、妻の財産に直接影響を及ぼすことはありません。たとえば、夫が借金を滞納したとしても、妻名義の財産や給与が差し押さえられることはありません。
ただし、マイホームが夫名義の場合には、差し押さえの対象となる可能性があります。また、妻が連帯債務者になっている場合には、夫だけでなく妻自身にも返済義務が生じるため、一括返済を求められることもあります。そのため、夫の借金が生活に影響を及ぼす可能性があることを考慮し、早めに対策を検討することが重要です。
支払い義務が生じる場合
旦那の借金について、妻に支払い義務が発生する主なケースは以下のとおりです。
【妻が保証人であるケース】
妻が 借金の保証人または連帯保証人 になっている場合は、借金の返済義務が生じます。
保証人とは、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をする責任を負う者」 と 民法第446条 に規定されています。 そのため、ローン契約時に保証人として署名・押印をしている場合、妻が返済しなければならなくなります。
ただし、以下のような場合は 契約自体が無効 となる可能性があるため、すぐに専門家へ相談しましょう。
- 「実印を持ち出され、勝手に保証人にされていた」
- 「身に覚えがないのに保証人になっていた」
【日常家事債務のケース】
旦那の借金が「日常家事債務」に該当する場合、妻にも返済義務が発生します。
日常家事債務 とは、日常生活に必要な費用 のことを指し、以下のような支出が含まれます。
- 家賃
- 食費
- 生活費
このように、借金の種類や契約内容によっては、妻にも返済義務が生じるケースがあります。 不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
夫の借金の保証人・連帯保証人である場合
夫の借金に対する保証人・連帯保証人の責任とは?
夫の借金の保証人または連帯保証人に妻がなっている場合、その借金の返済義務を負うことになります。
保証人としての責任
たとえば、夫が主債務者として借りたカーローンや住宅ローンの保証人に妻がなっているケースでは、夫に返済能力がなくなったときに限り、妻が保証人として返済義務を負うことになります。
連帯保証人の場合は要注意
一方、妻が 「連帯保証人」 になっている場合は、さらに注意が必要です。保証人とは異なり、夫に返済能力がある場合でも、妻が直接返済義務を負うことになるからです。
そのため、夫が返済を滞納すると、クレジットカード会社や消費者金融から 妻に直接請求が来る 可能性があります。また、請求を無視すると 給料や預金の差し押さえがある ことも考えられます。
夫が勝手に保証人にしていた場合
ただし、保証契約が妻の意思によるものではなく、夫が 勝手に印鑑を持ち出して保証人として契約していた場合、その契約は偽造にあたります。もし、その事実を証明できれば、原則として保証契約は 無効 となり、妻に返済義務は生じません。
ただし、特に 実印が使用された場合、無断で持ち出されたことを証明するのは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要になります。そのため、このような問題が発覚した場合には、早めに 弁護士に相談する ことをおすすめします。
妻が夫の借金を請求される2つのケース
借金は 借りた本人が返済義務を負う ため、妻が保証人になっていない限り、夫の借金を返済する義務はありません。
ただし、夫の借金について妻が請求される可能性がある2つのケース には注意が必要です。
- 夫の借金が「日常家事債務」に該当すると認められる場合
- 妻が夫の借金の保証人になっている場合
それぞれのケースについて、詳しく説明していきます。
妻が夫の借金の保証人になっている場合
夫の借金に対し、妻が「保証人」または「連帯保証人」になっている場合、妻にも同等の返済義務が発生します。
お金を借りる際に保証人を求められると、「保証人」または「連帯保証人」 のどちらかを選択することになります。
「保証人」と「連帯保証人」の違い
どちらも、債務者本人が借金の返済ができなくなったときに代わりに返済する義務を負う点では共通しています。 しかし、保証人には次の 3つの権利 が認められています。
保証人の3つの権利
- 催告の抗弁権:「まずは債務者本人に請求してください」と主張できる権利
- 検索の抗弁権:債務者本人に返済能力がある場合、その財産に対して強制執行を求める権利
- 分別の利益:保証債務が複数の保証人によって分割され、それぞれの責任が限定される利益
連帯保証人には3つの権利が認められない
一方で、「連帯保証人」は 保証人とは異なり、債務者本人と同じ責任を負います。 そのため、妻が夫の借金の連帯保証人になっている場合、夫の借金をすべて返済する義務を負うことになります。
保証人になる際は、保証契約の内容をしっかり理解した上で判断することが重要です。
夫の借金が日常家事債務に該当する場合
夫婦間では、本当に夫の借金が夫本人だけのものなのか、「日常家事債務」に該当しないかを確認することが重要です。
夫の借金が「日常家事債務」に含まれる場合、妻にも返済責任が生じる可能性があります。
日常家事債務とは?
日常家事債務 とは、夫婦が日常生活を送る上で必要な範囲で負担する債務 を指します。 生活必需品の購入など、夫婦が共同生活を営む上で発生する費用 が該当します。
基本的に、夫婦が公平に負担すべき支払いには以下のようなものが挙げられます。
- 家賃
- 公共料金(電気・水道・ガス)
- 食費
- 教育費
- 医療費
- 日用品の購入費
ただし、「日常家事債務」に該当するかどうかの明確な線引きはありません。 そのため、専門家に相談しながら判断することが望ましいでしょう。
とはいえ、上記のような生活費に関する支払いは、夫婦双方が把握していることが多い ものです。 夫が妻に内緒で借金をしている場合、その借金が「日常家事債務」に該当する可能性は低いため、原則として夫のみが返済義務を負うことになります。
夫の借金が原因で離婚する際のメリットとデメリット
夫の借金が発覚し、「信用できない」「トラブルに巻き込まれたくない」と離婚を検討する人もいるかもしれません。
そこで、夫の借金が原因で離婚することのメリットとデメリット について詳しく見ていきましょう。
夫の借金が原因で離婚することのメリット
夫の借金が原因で離婚した場合、信頼できない相手と生活を共にしなくて済む など、以下のようなメリットがあります。
- 信頼できない相手と一緒に暮らさなくてよい
- 夫が浪費していたり、経済DVを行っていた場合、離婚によって経済的に安定する可能性がある
夫の借金が発覚し、二度と信頼できない、一緒に暮らすのが難しい と感じる場合は、離婚を選択肢の一つとして考えるのも良いかもしれません。
夫の借金が原因で離婚することのデメリット
夫の借金が発覚し離婚した場合、子供を育てる環境が変わることがデメリット となるケースもあるでしょう。
夫の借金が原因で離婚することによるデメリット は、以下の通りです。
- 引っ越しなどにより、子供の教育や育児環境が変わる恐れがある
- 離婚によって、子供の心身に影響を及ぼす可能性がある
- 子供が父親と会えなくなることを嫌がる場合がある
- 自分が専業主婦の場合、離婚後に家計が苦しくなる恐れがある
こうした 子供への影響や経済的な状況、借金の理由 などを踏まえた結果、離婚せずにもう一度夫と向き合い、夫婦で協力して借金を返済する道を選ぶ ことも考えられるでしょう。
夫の借金が発覚した際に確認すべき6つの重要なポイント
妻が知らなかった夫の借金が発覚した場合、夫婦で協力して返済するのか、それとも別の選択をするのかを慎重に判断する必要があります。
適切な判断を下すためにも、まずは以下の6つのポイントを確認しましょう。
- 滞納や督促の有無
- 保証人がついている借金があるか
- 借入総額
- 担保のついた借金があるか
- 借入先
- 借金の理由
これらの情報をしっかり把握することで、今後の対応を冷静に考えることができます。それぞれの項目について、何を確認すべきか詳しく説明していきます。
滞納や督促があるかどうかの確認
夫が返済中の借金の中に、「滞納」しているものや「督促」されているものがないかを確認しましょう。
特に、返済が遅れ督促を受けている借金を放置している場合、担保が設定されていたり、連帯保証人がついている場合は注意が必要です。 そのままにしておくと、生活に支障をきたすだけでなく、連帯保証人にも迷惑をかけてしまう可能性があります。
担保付き借金の有無
夫の借金に、自宅や自動車などを「担保」にした借入れがないかを確認することも重要です。
お金を借りる際、担保を設定することで審査が通りやすくなり、借入限度額も増えるため、担保付きの借金がある可能性を否定できません。
担保とは?
担保とは、債務者が返済できなくなった場合に、債権者の損失を補填するために差し出す財産的価値のあるものを指します。
代表的な例として、住宅ローンを組む際に、自宅不動産に抵当権を設定するケース があります。この場合、住宅ローンが返済できなくなると、自宅が競売にかけられ、強制的に借金の返済に充てられることになります。
一般的に、担保として差し入れるのは自宅などの不動産が多いですが、担保付きの借金を返済できなくなれば、担保にした財産は差し押さえられてしまいます。
そのため、夫の借金に担保が設定されているかどうか、契約内容をしっかり確認することが大切です。
また、夫から聞いた内容に不安がある場合は、法務局で「不動産登記事項証明書」を取得することで、自宅に担保(抵当権)が設定されているかどうかを確認できます。
借金に保証人がついているかどうかの確認
夫の借金に「保証人」が付いていないか、その有無を必ず確認しましょう。
もしも保証人や連帯保証人がついている借金がある場合、夫が返済できなくなると、その保証人に迷惑をかけることになります。
保証人がいる場合は、夫婦だけでなく、その保証人も交えて話し合う必要が出てくる可能性があります。
また、逆に夫が誰かの借金の保証人になっていないかを確認することも重要です。
借金の総額
夫がどこからお金を借りたのか、借入先だけでなく「借入総額」も必ず確認することが重要です。
また、「毎月の返済額」や「返済日」を明確にすることで、今後の「返済計画」を立てやすくなります。
もし、借金が膨れ上がり支払いが困難な状況にある場合は、借金地獄から抜け出す方法も検討する必要があります。 そのためにも、「利用明細」や「契約書」などを提示してもらい、正確な借金の状況を把握しましょう。
借金の総額によって、毎月の返済額も異なりますし、その金額を家計から捻出できるかどうかによって、解決策も大きく変わる可能性があります。 そのため、夫には正直に話してもらうように、冷静に粘り強く確認することが大切です。
借入先の確認
借金返済に向けて、どこからお金を借りたのか、「借入先」を確認することが重要です。
銀行なのか、貸金業者なのか、また借入先が1社だけなのか、それとも複数社から借りているのか によって、毎月の返済負担は大きく異なります。
特に注意すべきなのは、借入先に闇金が含まれている場合です。 このようなケースでは、放置すると家族へ取り立てが及ぶなど、深刻な影響を受ける可能性があります。
闇金問題は、一般的な借金問題とは異なり、適切な対応が必要です。 根本的に解決するためには、闇金対応の専門弁護士に依頼し、法的な手続きを進めてもらうことが最善策となるでしょう。
借金の理由
まずは、夫が隠れて借金を重ねてきた「理由」を確認することが大切です。
例えば、
- 「給料が減ってしまい、それを補填しようとしたが相談できなかった」
- 「会社の運転資金としてやむを得ず借りた」
といった事情であれば、たとえ内緒で借金をしていたとしても、同情の余地を感じるかもしれません。
しかし、借金の理由が
- 「ギャンブルなどの遊興費」
- 「キャバクラ通いなどの娯楽費」
- 「浮気相手との旅行やプレゼント購入費」
といったものであれば、その原因となる行動を断ち切らない限り、また借金を繰り返す可能性が高いでしょう。 こうした場合、夫婦関係の修復も難しくなると考えられます。
特に、収入を超えた「浪費」や「ギャンブル」などが原因で借金を繰り返す傾向がある借金癖が場合は、妻が家計管理を徹底することが必要です。
また、ギャンブルと借金がセットになっている場合、問題が根深いため、単に借金を清算するだけでは解決しないこともあります。 再発防止のためには、断固とした対応が求められ、場合によっては医学的なカウンセリングを受けることも検討するべきでしょう。
旦那の借金を調べる方法
旦那に借金があるか疑わしい場合、どのように調べればよいのでしょうか。
スマホや通帳を確認することで、ある程度の手がかりを得ることはできますが、借金の正確な総額を把握するのは難しいものです。
旦那の借金を詳しく調べるには、信用情報機関で信用情報を開示する方法があります。 ただし、信用情報の開示は本人(旦那)による手続きが必要となるため、内緒で問い合わせることはできません。
信用情報を管理している機関は、以下の3つです。
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
多くの消費者金融やクレジットカード会社は、JICCとCICの両方に加盟しているため、これら2つの信用情報機関を開示することで、より詳細な借入状況を確認できます。
ここでは、JICCとCICの開示方法について詳しく解説していきます。
JICCで信用情報を確認する方法
JICCの情報開示手続きは、スマホで簡単に完結できます。
消費者金融やクレジットカードのローン情報、返済状況などを素早く確認できるため、借入状況を把握するのに便利です。
スマホでの手続きが難しい場合は、郵送での申請も可能です。
スマホでの情報開示手続きの流れ
- 専用アプリをダウンロードする
- 本人認証を行う
- お客様情報を入力する
- 手数料の支払い(1,000円・税込)
- 開示結果を受け取る
この方法を利用することで、JICCの信用情報をスムーズに開示できます。
CICで信用情報を確認する方法
CICの情報開示手続きも、スマホやインターネットで簡単に行うことができます。
CICの情報開示手続きの流れ
- 支払い方法の確認(クレジットカードまたはキャリア決済)
- 受付番号の取得
- お客様情報の入力
- 利用手数料の決済(500円・税込)
- 開示情報の表示(PDFファイルで確認可能)
この手続きを行うことで、CICに登録されている信用情報を確認できます。
また、家族の借金が発覚した場合、本人以外でも債務整理の相談や依頼ができるのかについても気になるところです。 その点について、詳しく解説していきます。
夫の借金返済をサポートするために必要な準備
夫の借金の内訳を確認した上で、妻も返済に協力するのであれば、状況に応じて次の準備を進めましょう。
それぞれの準備について、詳しく説明していきます。
妻の個人財産を使って返済する方法
特有財産とは、婚姻前に築いた財産 や 相続などによって得た個人の資産 を指します。
この「特有財産」は夫婦共有の財産には含まれないため、もし夫の借金を妻の特有財産で返済した場合、妻は夫に「肩代わり分」を請求することが可能です。
ただし、たとえ夫婦間の取り決めであっても、口約束で済ませるのではなく、「債務承認弁済契約書」を作成しておくと安心です。
債務承認弁済契約書とは?
借金があることを正式に認め、その借金の原因・発生日・弁済方法などを明記する契約書のことを指します。
契約書には、以下の内容を記載しておくことが望ましいでしょう。(あくまで最低限の事項であり、追加の記載が必要になる場合もあります。)
- 妻から夫に貸した金額と貸し付けた日
- 夫が妻に対して返済義務を負っている旨
- 返済期日と返済方法
- 保証人を付ける場合は、その保証に関する内容
このように契約書を作成しておけば、夫婦間のトラブルを防ぐことができるため、慎重に準備を進めることが大切です。
借金の原因となるものを絶たせる
夫の借金の原因が個人的な場合、早急に対処を
夫の借金の原因が 個人的な要因 であった場合、できるだけ早くその原因を断つようにしましょう。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- ギャンブル
- 高額商品の購入
- 過度な飲酒による出費
- FXや株取引
繰り返される借金のリスク
これらのケースでは 妻に隠れて借金をしていることが多く、たとえ一度返済できたとしても、再び同じような借金を繰り返す可能性があります。そのため、借金の完済だけでなく 根本的な解決策を講じる 必要があります。
貸付自粛制度の活用
夫自身の協力が得られる場合は、 金融機関からの借入れを5年間制限できる「貸付自粛制度」 を活用するのも一つの方法です。これを利用することで、新規の借り入れを制限し、借金を防ぐことができます。
ただし、この制度を利用すると 住宅ローンの審査やスマートフォン端末の分割払い などにも影響が出るため、慎重に判断することが大切です。
妻が徹底的にお金の管理を行う
借金問題を再発させないために、夫のお金の「管理」は妻が徹底して行うようにしましょう。
たとえ夫からクレジットカードやローンカードを取り上げたとしても、家賃や住宅ローンの支払いに充てるべきお金を手にすれば、使い込んでしまう可能性があります。
そのため、夫の毎月の収入を把握できる「給与明細」などの証拠資料を確認し、受け取った給料はすべて妻に渡してもらうようにすることが大切です。
そして、夫が自由に使えるお金は一定額に制限し、「お小遣い制」にすることで安心して管理できるようになります。
妻が収入を得て借金返済をサポートする
妻が働きながら夫の借金返済を手伝うケースも考えられます。
たとえば、まとまったお金は手元にないものの、妻の給料から毎月1万円や2万円を夫の借金返済に充て、協力して完済を目指す方法です。
しかし、借金の原因が「浪費」「ギャンブル」「不倫などの不貞行為」である場合、なぜ苦労してまで借金返済に協力しなければならないのか、そもそも肩代わりしたくないと感じることもあるでしょう。
また、仮に肩代わりしたとしても、「支払った分を返してほしい」と思うのは当然のことです。
いくら夫の代わりに返済した金額を、書面にしっかり記録しておくことが大切です。
この場合、都度お金を貸す形となるため、返済期日の異なる「借用書」を複数作成しなければなりません。 そこで、それらをひとつにまとめるために「準消費貸借契約書」を作成することをおすすめします。
準消費貸借契約書とは?
貸したお金を一括して整理し、返済条件などを明確にするための契約書です。
「債務承認弁済契約書」とほぼ同様の内容を記載すると考えてよいでしょう。
書面の名称にかかわらず、貸したお金の詳細を記録し、書面に残しておくことが非常に重要です。
借金返済のための計画を立てる
夫の借金を完済するために、具体的な「返済計画」を立てましょう。
「いつまでに完済するのか」という目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
まず、毎月の給料から、必要な生活費や貯金額を先に差し引き、返済に充てられる金額を明確に把握します。
また、返済に使用するカードや口座の管理は妻が行い、夫が自由にお金を使えない環境を整えることで、借金を繰り返すリスクを防ぐことができるでしょう。
しかし、無理のある返済計画を立ててしまうと、新たな借金を生む原因になったり、ストレスが増えてしまう可能性があります。そのため、無理のない範囲で収入を増やしつつ、支出を見直して削減することが重要です。
借金の原因を根本的に断ち切る
夫の借金の原因が「浪費」「ギャンブル」「浮気」などである場合、その根本的な原因を断ち切ることが重要です。
もし原因を絶たないまま借金を完済しても、再び同じ問題が発生するリスクが残ります。
そのため、「お金の使い方」「交友関係」「生活習慣」などについて、夫婦でしっかりと話し合い、見直すことが必要です。
また、ギャンブルなどの「依存症」が原因の場合、単なる話し合いだけでは解決が難しく、専門的なカウンセリングを受けることも検討すべきでしょう。
夫の両親に相談する
夫の両親に相談することも考えましょう。両親が借金を肩代わりしてくれれば、返済することができるかもしれません。また、立て替えてもらうだけでも、返済先が夫の両親になれば、消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れの利息よりも、返済金額を少なくすることができ、返済期間の融通もききやすいでしょう。
夫婦だけでは解決できない場合に検討するべき3つの債務整理方法
これまで見てきたように、夫の借金を解決するには妻の協力が欠かせません。
しかし、夫婦だけで借金問題を完全に解決できるとは限らず、協力して取り組んだとしても、自力では解決が難しい場合もあります。
そのようなときは、専門家の力を借りることを検討しましょう。
借金問題を解決するための主な3つの債務整理の方法は以下のとおりです。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの方法について、詳しく説明していきます。
任意整理
「任意整理」とは、債権者と直接「交渉」し、将来利息のカットなどによって借金を減額し、3~5年で返済する手続きです。
この方法では、整理する借金を選択できるため、保証人が付いたものを除いて手続きが可能です。
任意整理を司法書士や弁護士に依頼する際に準備すべき書類
依頼時には、以下の書類を用意しておきましょう。
- 身分証明書
- 印鑑
- キャッシュカードやクレジットカード
また、借金の状況によっては、次の資料も必要になる場合があります。
- 収入証明書
- 源泉徴収票または給与明細
- 貸金業者と交わした契約書または借用書
- 借金の入金明細や返済時の領収書
- 債権者一覧
- 内容証明郵便・督促状
- 預金通帳
任意整理をスムーズに進めるために、どの書類がいつ必要になるのかを司法書士や弁護士に事前に確認しておくことをおすすめします。
なお、夫が任意整理を行うと、夫名義の家族カードは使用できなくなりますが、妻名義でのローンやクレジットカードの利用には影響しません。
個人再生
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行い、借金を約5分の1まで大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済する手続きです。
この手続きでは、すべての借金が対象となるため、連帯保証人が付いた借金がある場合、連帯保証人に影響を及ぼす可能性があります。
ただし、夫名義の住宅ローンを返済中の自宅については、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、家を手放すことなく借金を減額できる仕組みがあります。
自己破産
個人再生は、裁判所を通じて行う手続きで、借金の一部(目安として5分の1)を返済することを条件に、残りを免除してもらう制度です。原則として3年間で定められた額を支払うことで、残りの借金が免除されます。借金の大幅な減額が可能な点は任意整理と共通していますが、個人再生では利息だけでなく、借金の元本自体も減額できる点が大きな違いです。 安定した収入がある人、借金の総額が大きい人(300万~400万円以上)、任意整理では返済が難しい人などが、個人再生を選択する傾向にあります。
旦那に債務整理をさせることのメリットとデメリット
借金を債務整理することには、以下のようなメリットがあります。
- 借金の返済負担を軽減できる
- 新たな借り入れができなくなることで、借金の増加を防げる
一方で、債務整理には以下のようなデメリットもあります。
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 住宅ローンや車のローンを組む際に影響が出る可能性がある
新たな借り入れができなくなる(メリット)
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たな借り入れができなくなります。
一見デメリットのように思えますが、借金を繰り返してしまう人にとっては大きなメリットともいえます。
実際に、債務整理をする人の中には、「過去にも債務整理を経験した」「新たに借金を増やしてしまった」というケースも少なくありません。
借金問題を根本から解決するには、お金の使い方を見直すことが不可欠です。債務整理を機に家計の管理を見直し、新たな借り入れを防ぐことが大切です。
借金の返済額を減らせる(メリット)
債務整理の種類によって借金の減額幅は異なりますが、返済額の大幅な軽減や借金の免除が可能になることが最大のメリットです。
例えば、借金が200万円ある人が任意整理を行うことで、毎月の返済額が4万円~5万円程度に抑えられるケースもあります。
毎月の返済負担が減ることで、精神的な不安が軽減され、生活にも余裕が生まれるでしょう。
住宅ローンや自動車ローンに与える影響(デメリット)
債務整理を行うと、一定期間は住宅ローンや車のローンを組むことができません。それでは、すでに住宅ローンや車のローンを返済中の場合、どのような影響があるのでしょうか。
任意整理の場合、住宅ローンや車のローンを返済中であっても、これらを手続きの対象外にすることが可能です。その他の借金の利息をカットすることで、住宅や車を手放すことなく、無理のない範囲での返済を続けられます。
一方、個人再生の場合は、住宅ローン特則を利用することで住宅を残せる可能性がありますが、車のローンが残っている場合は手放さなければなりません。これは、車のローンには「所有権留保」が付いており、ローン完済まではローン会社が所有権を持っているためです。
自己破産を選択する場合は、高額な財産を処分しなければならないため、住宅や車を維持することは難しくなります。自己破産後は新たなローン契約も制限されるため、慎重な判断が必要です。
信用情報機関に事故情報が記録される(デメリット)
債務整理を行う際の最大のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。これがいわゆる「ブラックリスト」に載るという状態を指します。
事故情報が登録されると、一定期間クレジットカードが使用できなくなり、新たにローンを組むことも難しくなります。
ただし、任意整理の場合は完済から5年、自己破産の場合は7年経過すると事故情報は削除されます。
社会的信用を永遠に失うわけではないため、この期間を生活を立て直すための準備期間と前向きに捉えることが重要です。
夫婦の家計管理方法
法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助すること」「婚姻費用は分担すること」が定められています。つまり、夫婦は共に生活し、生活費を分担しながら支え合うことが求められるのです。(これを怠ると、一方が他方に婚姻費用を請求できたり、正当な理由なく同居や扶助をしない場合は、裁判で離婚原因として認められることもあります。)※婚姻費用とは、結婚生活全般にかかる生活費のことを指します。
理想的な家計管理の方法としては、以下のような形が考えられます。
- 共働きの場合:お互いの収入を合算して生活費を支出し、余ったお金は共同の貯金へ回す。
- 夫が働き、妻が専業主婦の場合:夫の収入で生活するため、夫婦で収入や支出を管理し、計画的にやりくりする。
結婚後は「自分の収入は自分のもの」と考えず、お互いの役割を尊重しながら家計を共有することが大切です。(一方の収入が多い場合でも、それは他方の支えがあってこそ成り立っているものです。)
こうした家計管理ができている夫婦は、借金問題に巻き込まれるリスクが低く、安定した家庭を築きやすいといえるでしょう。
夫婦での家計管理方法: 相談しない関係が借金問題を引き起こす
たとえば、片方がギャンブルに熱中し、内緒で借金を重ねてしまうケースは、事前に防ぐことが難しいものです。(結婚前からギャンブル好きを知っていれば多少の監視はできるかもしれませんが、完全に防ぐのは困難です。)
一方、生活費の不足や教育費の問題などは、日頃から家計について夫婦で話し合い、共同で管理する習慣があれば、大きな借金問題に発展しにくいといえます。借金をする前に支出を見直したり、対策を講じたりすることができるからです。
しかし、家計を別々に管理している夫婦の場合、特に収入格差があると、自分だけが家計に苦しんでいても相手に相談しにくいという状況が生まれることがあります。例えば、
- 夫から渡される生活費だけでやりくりしているが、夫が残りの収入をどう管理しているのか不明である。
- 生活費が足りなくなっても、「任されている以上、足りないとは言い出しにくい」と感じる。
このように、夫婦間で十分な話し合いができない環境では、借金問題が生じる可能性が高まります。
家計管理のスタイル別に見る借金問題の相談傾向
夫婦の家計管理タイプと借金問題の傾向
① 夫が全て管理
- 夫が家計を管理しているため、夫自身の借金問題はあまり発生しにくい。
- 一方で、妻が渡された生活費の範囲でやりくりできず、不足分をカードで補うケースがある。
- 夫には言い出せずに内緒のパターンが多い。
② 妻が全て管理
- 妻が家計を管理しているため、妻自身の借金問題は起こりにくい。
- 夫が渡されたこづかいだけでは足りず、交際費などをキャッシングするケースがある。
- 妻に相談しづらく、夫が内緒で借金を抱えることが多い。
③ 財布を別々に管理
- 夫婦それぞれが独立して家計を管理するスタイル。
- 夫または妻が独身時代に抱えていた借金を相手に隠したまま返済し、結婚後に債務整理するケースもある。
④ 夫婦共同管理
- 夫婦で家計を共有し、どちらか一方に負担が偏らないように管理。
- 借金問題の相談はほとんど見られず、何か困ったときも夫婦で話し合いができる。
- 貯蓄がしやすく、家計が安定しやすいと言われている。
まとめ
夫の借金問題を解決するには妻の協力が重要
夫の借金に関する返済義務は原則として夫本人にあります。ただし、妻が連帯保証人になっていない限り、妻に返済責任が及ぶことはありません。
しかし、借金問題の解決には家族の協力が不可欠であり、特に妻のサポートがあるかどうかで状況は大きく変わります。夫婦で協力して返済を進めるためには、まず「なぜ借金をしたのか」という理由を夫に確認し、借金の原因を断ち切ることが重要です。
応急処置として、妻が家計管理を徹底し、しばらくの間は夫が自由にお金を使えない環境を整えましょう。ただし、借金の根本的な原因を解決しなければ、問題が再発する可能性があります。
もしも借金の原因がギャンブルなどの依存症であれば医療機関の受診を、闇金からの借り入れが問題ならば専門の弁護士に相談するなど、適切な専門家の協力を仰ぐことが必要です。
よくある質問
夫の借金が発覚したらどうする?
夫の借金が発覚した際には、まず「借金の名義」と「借入の理由」を確認することが重要です。借金が夫名義であり、理由も夫個人のものであれば、妻には返済義務がありません。
夫の借金が発覚したときに確認すべき6つのポイント
夫の借金について、正確な情報を把握するために、以下の点を確認しましょう。
- 借金の総額
- 借入先
- 返済状況(滞納の有無)
- 保証人の有無
- 担保の有無
- 借金の理由
夫の借金は誰が払う?
借金が夫名義であり、夫の個人的なものと判断される場合、妻が返済義務を負うことはありません。ただし、夫の借金が「夫婦の共同生活のために生じたもの」と認められた場合、妻にも返済義務が生じる可能性があります。さらに、離婚する際には、借金の内容によって財産分与の対象となる場合もあるため注意が必要です。
夫の借金は夫婦の共有財産にはならない
基本的に、夫名義の借金は夫個人の責任であり、夫婦の共有財産とはなりません。ただし、日常家事債務に該当する借金や、夫婦の生活費のための借入れであれば、夫婦ともに負担する義務が生じる可能性があります。