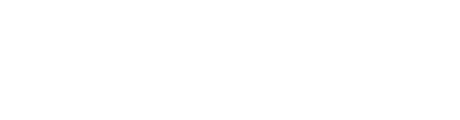※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
自己破産は、多額の借金を法的に整理し、経済的な再スタートを切るための手続きです。
破産後の人生に対して、すべてを失うといった漠然とした不安を抱くかもしれませんが、その後の生活がどうなるかを正しく理解すれば、過度に悲観する必要はありません。
自己破産には一定の制限が伴う一方で、日常生活の基盤は保護されます。
この記事では、自己破産後の生活における具体的な変化や制限、そして変わらない点について網羅的に解説し、新たな人生を歩むための知識を提供します。
自己破産は人生の再スタート!悲観する必要はない理由
目次
自己破産は、返済不能な借金の悩みから解放され、人生をやり直すための前向きな法的手続きです。
手続きが完了すれば、原則として借金の支払い義務が免除され、精神的な負担から解放されます。
自己破産に対してネガティブなイメージを持つかもしれませんが、生活に必要な最低限の財産は手元に残り、その後の収入は自由に使えるため、経済的な更生を図ることが可能です。
万が一、再び経済的に困窮した場合でも、前回の免責許可決定から7年が経過していれば、2度目の自己破産が認められる可能性もあります。
自己破産後の生活で受ける5つの主な制限
自己破産をすると、その後の生活においていくつかの制限を受けます。
これらは永続的なものではなく、多くは一定期間に限定されたものです。
例えば、信用情報機関に事故情報が登録される期間は約5年から7年程度とされています。
また、破産手続き中に特定の資格が制限される期間は数ヶ月です。
これらの制限を正しく理解することは、破産後の生活設計を立てる上で不可欠であり、将来への漠然とした不安を解消することにも繋がります。
制限の具体的な内容と期間を把握し、冷静に対処することが求められます。
マイホームや車など高価な資産は手放す必要がある
自己破産の手続きでは、債権者への配当を目的として、一定以上の価値を持つ財産は処分されます。
具体的には、土地や建物といった不動産、20万円以上の価値が見込まれる自動車、高額な保険の解約返戻金などが対象となります。
これらの資産を失うことは大きな変化ですが、借金の支払いが免除されるための代償と理解する必要があります。
一方で、生活に不可欠な家具や家電製品などは差し押さえの対象外です。
自己破産後のクレジットカードの作成は困難になるため、大きな買い物は現金やデビットカードで行うことになり、資産形成は慎重に行わなければなりません。
自己破産後クレジットカードを再度持つまでには一定期間が必要です。
約5〜7年間は信用情報に事故記録が残る
自己破産をすると、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
これは、いわゆる「ブラックリストに載る」状態を指します。
この記録が残っている間は、金融機関や貸金業者から新たな借入れをしたり、ローンを組んだりすることが極めて困難になります。
情報の登録期間は、JICCやCICでは約5年、KSC(全国銀行個人信用情報センター)では約7年が目安です。
この期間が経過すれば事故情報は削除されますが、それまでは現金主義の生活が基本となります。
なお、破産時に手元に残せる現金の上限である99万という金額と、信用情報への登録期間は直接的な関係はありません。
クレジットカードの作成やローンの契約が困難になる
信用情報に事故記録が登録される直接的な結果として、クレジットカードの新規作成や更新、住宅ローン、自動車ローン、教育ローンといった各種ローンの契約が難しくなります。
金融機関は審査の際に必ず信用情報を照会するため、事故記録があると返済能力に問題があると判断されるからです。
この影響はあくまで破産した本人に限られます。
例えば、夫が自己破産をしても、妻自身の信用情報に問題がなければ、妻名義でクレジットカードを作成することは可能です。
同様に、離婚後に元配偶者が破産した場合でも、自身の信用情報には影響がありません。
手続き中は一部の職業や資格に就けなくなる
自己破産の手続き期間中、具体的には破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの数ヶ月間は、一部の職業や資格に就くことが法律で制限されます。
これは「資格制限」と呼ばれ、弁護士、司法書士、税理士といった士業のほか、警備員、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者などが対象となります。
この制限は一時的なものであり、免責許可が確定すれば「復権」し、再びそれらの職業に就くことが可能です。
したがって、生涯その仕事ができなくなるわけではありません。
一般的な会社員や公務員、アルバイトなど、ほとんどの職業はこの制限の対象外です。
連帯保証人や保証人にはなれなくなる
自己破産をして信用情報に事故記録が登録されている期間は、他人の借金の保証人や連帯保証人になることは事実上不可能です。
ローンなどの契約において、保証人には安定した返済能力が求められますが、自己破産をした記録があると審査でその能力がないと判断されてしまうためです。
例えば、子どもが奨学金を借りる際や、家族がローンを組む際に保証人を頼まれても、その役目を果たすことはできません。
この制約も信用情報が回復すれば解消されますが、それまでの間は、家族や知人の保証人にはなれないという点を理解しておく必要があります。
【誤解しないで】自己破産後も変わらない日常生活のこと
自己破産には「すべてを失い、社会から孤立する」といった厳しいイメージが先行しがちですが、実際には多くの誤解が含まれています。
法律は、破産者が経済的に更生し、人間らしい生活を送る権利を保障しています。
そのため、生活に不可欠な財産は保護され、基本的な日常生活は手続き後も大きく変わることはありません。
戸籍に記録が残ることも、選挙権がなくなることもないのです。
ここでは、自己破産後も変わらずに維持される日常生活の側面を具体的に解説し、過剰な不安を解消します。
99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せる
自己破産をしても、すべての財産が没収されるわけではありません。
「自由財産」として、法律で定められた範囲の財産は手元に残すことが認められています。
具体的には、99万円以下の現金や、生活に必要不可欠な家具、家電、衣類などがこれに該当します。
この制度は、破産者が手続き後の生活を再建していくための基盤を保障するために設けられています。
したがって、自己破産によって明日からの生活に困るような状況に陥ることはありません。
あくまで換価価値の高い財産が処分の対象となるだけで、日々の暮らしは維持されます。
手続き後に得た給料や財産は自由に使える
自己破産手続きで処分の対象となるのは、原則として「破産手続開始決定時」に所有していた財産です。
したがって、免責許可決定が確定した後に得た給料やボーナス、あるいは相続などで新たに取得した財産は「新得財産」と呼ばれ、すべて本人が自由に使うことができます。
この収入が債権者への返済に充てられたり、差し押さえられたりすることはありません。
破産手続きは過去の負債を清算するものであり、未来の収入や財産形成を縛るものではないのです。
努力次第で貯蓄をし、生活を立て直すことが十分に可能です。
今住んでいる賃貸物件から退去する必要はない
自己破産したことだけを理由に、現在住んでいる賃貸物件の大家から立ち退きを要求されることはありません。
賃貸借契約は継続されます。
ただし、家賃を滞納している場合は状況が異なります。
滞納している家賃は破産手続きにおける債権の一つとなるため、大家は滞納を理由に契約を解除し、退去を求めることができます。
したがって、自己破産を検討している場合でも、家賃の支払いは継続することが重要です。
家賃をきちんと支払い続けていれば、破産後も同じ場所に住み続けることができます。
携帯電話やスマートフォンは継続して利用可能
携帯電話やスマートフォンは、現代生活に不可欠なツールですが、自己破産後も利用を続けることが可能です。
ただし、条件があります。
端末本体の分割払いが残っておらず、通信料金に滞納がない場合は、基本的に契約はそのまま継続されます。
もし端末の分割代金が残っている場合、それはローン契約と同じ扱いになるため、自己破産の手続きに含める必要があります。
その結果、携帯電話会社によって端末が回収される可能性がありますが、通信契約自体は解約されないケースも多く、一括で新しい端末を購入すれば利用を続けられます。
戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはない
自己破産をしたという事実は、個人のプライバシーに関わる重要な情報です。
そのため、戸籍謄本や住民票、マイナンバーカードといった公的な身分証明書に、破産の記録が記載されることは一切ありません。
これらの書類を通じて、第三者に破産の事実が知られる心配は不要です。
破産の情報が公になるのは、後述する「官報」への掲載のみであり、これも一般の人が目にする機会はほとんどありません。
行政上の記録に残らないため、日常生活や各種手続きにおいて、破産歴が障壁となることは基本的にないのです。
選挙権などの公民権が剥奪されることはない
自己破産をしても、日本国民として有する基本的な権利である公民権が失われることはありません。
具体的には、選挙で投票する権利(選挙権)や、選挙に立候補する権利(被選挙権)などがこれにあたります。
これらの権利は、個人の経済的な状況によって制限されるものではなく、日本国憲法によって保障されています。
したがって、破産手続き中であっても、あるいは破産後であっても、これまでと同様に政治に参加する権利は維持されます。
経済的な再建と社会的な権利は、全く別の問題として扱われます。
自己破産が周囲の人に与える影響とは?
自己破産を考える上で、家族や勤務先といった周囲の人々にどのような影響が及ぶのかは、大きな懸念事項です。
原則として、自己破産は手続きを行う本人個人の問題であり、他者への直接的な影響は限定的です。
しかし、借金の連帯保証人がいる場合は例外となり、重大な影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、会社、家族、保証人など、周囲との関係性ごとに自己破産が与える影響を具体的に解説し、適切な対応を考えるための情報を提供します。
会社に知られて解雇される可能性は極めて低い
原則として、自己破産をしても会社にその事実が知られる可能性は低いです。
会社が従業員の信用情報を照会することはないため、自ら申告しない限り発覚することはほとんどありません。
万が一、何らかの理由で会社に知られたとしても、自己破産を理由に従業員を解雇することは、労働契約法に違反する不当解雇とみなされる可能性が非常に高いです。
ただし、会社から借金をしている場合や、一部の資格制限のある職業に従事している場合は、業務に影響が出る可能性があるため、事前に弁護士に相談することが賢明です。
家族の信用情報には直接的な影響はない
自己破産は個人の手続きであるため、配偶者や子ども、親など、家族の信用情報に影響が及ぶことはありません。
家族が破産したからといって、他の家族の信用情報に事故記録が登録されることはなく、クレジットカードの作成やローンの契約も通常通り可能です。
ただし、家族が破産する本人の借金の連帯保証人になっている場合は、返済義務がその家族に移るため、直接的な影響を受けます。
また、破産した本人が住宅ローンの審査から外れるため、世帯収入全体で評価されるローン契約などが難しくなる間接的な影響は考えられます。
結婚や離婚の法的な障害にはならない
過去に自己破産をしたという事実が、結婚や離婚の法的な手続きにおいて障害となることはありません。
法律上、自己破産歴を理由に婚姻届が受理されなかったり、離婚の正当事由として認められたりすることはないのです。
ただし、これはあくまで法律上の話です。
結婚を考えている相手には、自身の経済状況について誠実に伝えることが、将来の信頼関係を築く上で重要です。
経済的な価値観は人それぞれ異なるため、隠さずに話し合い、お互いの理解を得ておくことが、円満な関係を維持するために不可欠です。
保証人には借金の返済義務が移ってしまう
自己破産手続きにおいて、周囲に最も大きな影響が及ぶのが保証人や連帯保証人の存在です。
借金をした本人(主債務者)が自己破産によって裁判所から免責許可を得て、借金の支払い義務を免れても、保証人の返済義務はなくなりません。
債権者(貸主)は、残った借金の全額を保証人に対して請求します。
多くの場合、一括での返済を求められるため、保証人も返済が困難となり、連鎖的に債務整理をせざるを得なくなるケースも少なくありません。
そのため、手続きを開始する前に必ず保証人に連絡し、事情を説明して謝罪と相談をすることが最低限のマナーです。
自己破産に関するよくある質問と回答
自己破産という手続きは、多くの人にとって馴染みがなく、さまざまな疑問や不安がつきものです。
「官報に名前が載るとはどういうことか」「税金の支払いはどうなるのか」「生命保険は解約しなければならないのか」など、具体的な質問が数多く寄せられます。
ここでは、自己破産に関して特によくある質問を取り上げ、それぞれに分かりやすく回答します。
正しい知識を持つことで、不確かな情報に惑わされることなく、冷静に手続きを検討するための判断材料となります。
官報に名前が載るが一般の人が見ることはほとんどない
自己破産をすると、国の広報誌である「官報」に氏名と住所が掲載されます。
これは、破産手続きが開始されたことと、免責が許可されたことを公告するための法的な措置です。
しかし、官報を日常的に読んでいる一般の人はほとんどいません。
主に金融機関の担当者や一部の企業などが業務上の必要性から確認する程度です。
インターネット版の官報もありますが、特定の個人情報を検索するのは容易ではありません。
そのため、官報への掲載によって、近所の人や会社の同僚に自己破産の事実が知れ渡る可能性は極めて低いと言えます。
税金や社会保険料の支払い義務は免除されない
自己破産の手続きによって免除されるのは、消費者金融や銀行からの借入れ、クレジットカードの支払いなどの一般的な債務です。
一方で、所得税や住民税、固定資産税といった税金や、国民健康保険料、年金保険料などの社会保険料は「非免責債権」と定められており、自己破産をしても支払い義務はなくなりません。
これらの支払いが困難な場合は、自己破産の手続きとは別に、市役所や税務署の窓口で相談する必要があります。
事情によっては、分割での支払いや減額、免除といった措置を受けられる可能性があります。
生命保険は解約返戻金次第で継続できる
加入している生命保険を継続できるかどうかは、その保険の解約返戻金の額によります。
解約返戻金は個人の財産とみなされるため、その見込み額が裁判所の定める基準(一般的に20万円)を超える場合、原則として保険を解約し、返戻金を債権者への配当に充てる必要があります。
一方、解約返戻金が基準額以下の場合や、掛け捨て型で解約返戻金がほとんどない保険の場合は、解約せずに契約を継続できる可能性が高いです。
具体的な基準は裁判所の運用によって異なるため、事前に弁護士に確認することが重要です。
自己破産後でも生活保護の申請は可能
自己破産と生活保護は、それぞれ異なる目的を持つ制度です。
したがって、自己破産をした後でも、収入や資産が国の定める最低生活費を下回る場合には、生活保護を申請し、受給することが可能です。
自己破産をしたことが、生活保護の審査において不利に働くことはありません。
むしろ、借金問題を自己破産で法的に解決した上で、生活保護制度を利用して生活の基盤を立て直すという流れは合理的です。
経済的に困窮している場合は、ためらわずに居住地の福祉事務所に相談することが大切です。
自己破産後の海外旅行や引っ越しは自由にできる
自己破産の手続きがすべて完了し、裁判所から免責許可決定が確定した後は、海外旅行や引っ越しを自由に行うことができます。
パスポートを取り上げられたり、移動が制限されたりすることはありません。
ただし、制限がかかるのは破産手続き中の期間です。
この間は、裁判所の許可なく長期間居住地を離れたり、住所を変更したりすることができない場合があります。
しかし、この期間は通常数ヶ月で終了します。
手続きが終われば、そのような制約は一切なくなり、国内・海外を問わず自由に移動することが可能です。
自己破産後の人生を前向きに立て直すための3つのポイント
自己破産によって借金の返済義務が免除されても、それだけで安定した生活が約束されるわけではありません。
再び借金に頼る生活に戻らないためには、破産後の生活習慣やお金との付き合い方を見直すことが不可欠です。
経済的な自立を目指し、二度と同じ過ちを繰り返さないための具体的な行動が求められます。
ここでは、破産後の人生をより良いものにするために、すぐに実践できる3つの重要なポイントを解説します。
これらを意識することが、着実な生活再建への道筋となります。
まずは家計簿をつけて収支を正確に把握する
経済的な再建の第一歩は、自分のお金の流れを正確に把握することから始まります。
家計簿をつける習慣を身につけ、毎月の収入に対して、食費、光熱費、通信費など、何にいくら使っているのかを可視化することが重要です。
これにより、無駄な支出や改善すべき点が見えてきます。
スマートフォンのアプリや簡単なノートなど、自分に合った方法で記録を続けることで、収入の範囲内で生活する予算感覚が養われます。
この地道な作業が、計画的なお金の管理と、借金に頼らない生活の土台を築きます。
クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを活用する
自己破産後は約5〜7年間、信用情報の問題でクレジットカードを持つことができません。
現金での支払いが基本となりますが、オンラインショッピングなどキャッシュレス決済が必要な場面もあります。
その際に有効なのが、デビットカードやプリペイドカードです。
デビットカードは、利用すると即座に連携した銀行口座から代金が引き落とされる仕組みです。
プリペイドカードは、事前にチャージした金額の範囲内でのみ利用できます。
どちらも後払いの借金とは異なり、自分の資産の範囲で利用するため、使いすぎる心配がなく、安全にキャッシュレス決済の利便性を享受できます。
借金に頼らない生活習慣を身につける
自己破産を経験したからこそ、根本的に借金に依存しない生活スタイルを確立することが何よりも重要です。
高価なものが欲しくなったときに安易にローンを考えるのではなく、計画的に貯金をしてから購入するという習慣を身につける必要があります。
また、ストレス解消を衝動的な買い物やギャンブルに求めていたなど、借金の原因となった自身の行動パターンを客観的に見つめ直し、改善に努めることも大切です。
健全な趣味を見つけるなど、お金のかからないストレス解消法を確立し、長期的に安定した生活基盤を築いていく意識が求められます。
まとめ
自己破産は、返済不能な借金を法的に整理し、経済的な再出発を可能にするための制度です。
手続き後は信用情報への登録や資産の処分といった一定の制限があるものの、生活必需品や手続き後の収入は保護され、日常生活の大部分はこれまで通り送ることができます。
戸籍に記録が残ることもなく、周囲への影響も保証人がいない限り限定的です。
重要なのは、自己破産を人生の終わりと捉えるのではなく、新たなスタートと認識し、その後の生活設計を真剣に行うことです。
家計管理を徹底し、借金に頼らない生活習慣を身につけることで、安定した未来を築くことは十分に可能です。