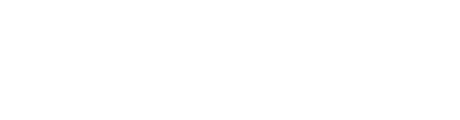※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける

借金の返済に追われ、「借金の救済制度」という言葉を目にしたものの、その仕組みがよくわからず怪しいと感じていませんか。
借金の救済制度とは、国が認めた合法的な手続きであり、返済が困難な状況を解決するための選択肢の一つです。
この記事では、制度が怪しいと感じる理由から、国が認めた具体的な仕組み、利用する上でのデメリットや必要な費用について詳しく解説します。
正しい知識を得ることで、不安を解消し、適切な判断を下すための参考にしてください。
借金救済制度とは国が認めた合法的な借金減額の仕組み
目次
「借金救済制度」とは、一般的に使われる言葉であり、法律で定められた「債務整理」という手続きを指します。
これは、多額の借金を抱え返済が困難になった人を対象とした、国が認める救済措置です。
政府は、貸金業法や破産法などの法律に基づき、支払い不能に陥った個人の経済的再生を支援する仕組みを整備しています。
つまり、借金救済制度とは、法的な根拠に基づき借金の減額や免除を可能にする合法的な手段であり、決して怪しいものではありません。
「借金救済制度は怪しい」と感じてしまう主な理由
なぜ「借金救済制度は怪しい」と感じてしまうのでしょうか。
その一因として、インターネットやSNS上での過剰な広告が挙げられます。
「誰でも借金がゼロになる」といった、メリットのみを強調する表現は、かえって「嘘ではないか」「何か裏のからくりがあるのでは」という疑念を抱かせます。
実際に、これらの手続きには信用情報への影響といったリスクも存在します。
メリットだけでなく、デメリットや条件を正しく理解しないまま安易に飛びつくのは危険であり、本当に自分のためになるのか慎重に判断する必要があると感じるのは自然なことです。
安全に借金救済制度を利用するための相談先
借金救済制度を安全に利用するためには、法律の専門家へ相談することが不可欠です。
主な相談先は、弁護士事務所や司法書士事務所となります。
これらの専門家は、個々の状況を法的な観点から分析し、最適な手続きを提案してくれます。
また、費用面で不安がある場合には、国によって設立された公的な法人である「法テラス(日本司法支援センター)」の利用も検討できます。
法テラスでは、収入などの条件を満たせば無料の法律相談や弁護士費用の立替え制度を利用できるため、安心して相談することが可能です。
【状況別】借金救済制度の4つの種類とそれぞれの特徴
借金の救済制度、すなわち債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、これに「過払い金請求」を加えた4つが代表的な手続きです。
どの手続きが最適かは、借金の総額、収入、財産の状況などによって異なります。
それぞれの手続きには、対象となる人や利用するための条件、手続きの流れ、そして減額される度合いに違いがあります。
自身の状況を正確に把握し、各制度の特徴を理解した上で、最も適した種類を選択することが問題解決の鍵となります。
任意整理:債権者と直接交渉して将来利息をカットする手続き
任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が代理人となって債権者と直接交渉する手続きです。
主な交渉内容は、今後発生する将来利息をカットし、残った元本のみを3年から5年程度の期間で分割返済していく和解を結ぶことです。
この方法は、消費者金融からのキャッシングや、クレジットカードのリボ払い、カードローンなど、特定の借金のみを対象として整理することも可能です。
裁判所を通さないため、手続きが比較的簡易で、周囲に知られにくいという特徴があります。
個人再生:裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画の認可を得ることで借金を大幅に減額する手続きです。
減額幅は借金額に応じて決まりますが、一般的には元本の5分の1から10分の1程度まで圧縮されます。
減額された借金は、原則として3年間で分割して返済していきます。
この手続きの大きな特徴は、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できる点にあります。
この制度を活用すれば、住宅ローンを支払い続けることを条件に、持ち家を手放すことなく他の借金を整理することが可能です。
自己破産:裁判所に返済不能と認めてもらい借金の支払義務を免除してもらう手続き
自己破産は、裁判所に対して支払不能であることを申し立て、免責許可決定を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
税金や社会保険料など一部の債務は免除の対象外ですが、消費者金融や銀行からの借入れは対象となります。
収入が極端に少ない、あるいは生活保護を受給中であるなど、返済の目途が全く立たない場合に最終的な手段として選択されます。
ただし、一定以上の価値がある財産は処分され、債権者への配当に充てられることになります。
過払い金請求:払いすぎた利息を取り戻す手続き
過払い金請求は、過去に貸金業者へ法律の上限金利を超えて支払っていた利息(過払い金)の返還を求める手続きです。
2010年以前に高い金利で長期間借入れをしていた場合に、過払い金が発生している可能性があります。
これは厳密には債務整理とは異なりますが、借金問題の解決策の一つです。
返還された過払い金を現在の借金の返済に充てることで、借金を完済できたり、大幅に減額したりすることが可能になります。
完済後の請求であれば、信用情報への影響もありません。
借金救済制度を利用する2つの大きなメリット
借金救済制度を利用することには、経済的および精神的な側面から大きなメリットがあります。
最も直接的なメリットは、専門家が介入することで貸金業者からの厳しい督促が停止し、精神的な平穏を取り戻せることです。
さらに、月々の返済額が減額または免除されるため、これまで返済に追われていた生活から脱却し、家計を再建する余裕が生まれます。
これにより、将来に向けた新たな一歩を踏み出すことが可能となります。
メリット1:貸金業者からの督促や取り立てが止まる
弁護士や司法書士に借金救済制度の手続きを依頼すると、専門家は債権者に対して「受任通知」という書類を送付します。
貸金業法では、この受任通知を受け取った業者が、正当な理由なく債務者に直接連絡したり取り立てを行ったりすることを禁止しています。
そのため、依頼後は電話や郵便物による督促が止まり、精神的なプレッシャーから解放されます。
これにより、今後の手続きや生活の立て直しに落ち着いて集中でき、安心して日々を過ごせるようになります。
メリット2:月々の返済額が減り生活に余裕が生まれる
借金救済制度を利用することで、月々の返済負担は大幅に軽減されます。
任意整理では将来利息がカットされるため、返済のゴールが明確になり、元本だけを着実に減らしていくことが可能です。
個人再生では元本自体が大きく減額され、自己破産では原則として返済義務が免除されます。
これにより、これまで返済に充てていたお金を食費や住居費といった本来の生活費に充当できるようになり、経済的な余裕が生まれます。
生活再建の基盤を築き直す上で、これは非常に大きな利点です。
知っておくべき借金救済制度の4つのデメリット
借金救済制度は多くのメリットがある一方で、利用する際には理解しておくべきデメリットも存在します。
特に、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストの状態になることは、その後の生活に一定期間影響を及ぼす可能性があります。
また、手続きの種類によっては保証人に迷惑をかけたり、財産を失ったりすることもあります。
これらのデメリットを事前に把握し、メリットと比較検討した上で、慎重に手続きを選択することが重要です。
デメリット1:信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
借金救済制度を利用すると、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。
これが一般的にブラックリストに載ると呼ばれる状態です。
登録される期間は手続きの種類や信用情報機関によって異なりますが、およそ5年から10年間です。
この期間中は、金融機関からの信用が著しく低下するため、新たなクレジットカードの作成、住宅ローンや自動車ローンといった各種ローンの契約、スマートフォンの分割購入などが原則としてできなくなります。
この影響が生活にどう響くかを考慮する必要があります。
デメリット2:手続きの種類によっては保証人に請求がいく可能性がある
借金に保証人や連帯保証人がついている場合、手続きによってはその人に大きな影響が及びます。
個人再生や自己破産は、全ての債権者を対象とするため、保証人がついている借金も整理の対象となります。
その結果、債権者は債務者本人に代わって、保証人に対して残債務の一括返済を請求します。
任意整理の場合は整理対象の借金を選べるため、保証人がついているものを除外して手続きすることも可能ですが、保証人がいる場合には事前に必ず相談し、理解を得ておくことが不可欠です。
デメリット3:自己破産では高価な財産が処分される
自己破産を選択した場合、申立人の所有する一定額以上の価値を持つ財産は、原則として処分(換価)され、債権者への配当に充てられます。
処分の対象となるのは、土地や建物といった不動産、自動車、99万円を超える現金、20万円以上の価値がある預貯金や有価証券、生命保険の解約返戻金などです。
生活に必要不可欠な家財道具や、差し押さえが禁止されている財産は手元に残せますが、高価な財産を維持したまま借金を免除してもらうことはできません。
デメリット4:個人再生や自己破産をすると官報に氏名や住所が載る
裁判所を介して行う個人再生や自己破産の手続きをすると、その事実が国の機関紙である「官報」に掲載されます。
官報には、手続きを行った人の氏名と住所が記載されます。
ただし、官報は一般の人が日常的に閲覧するものではなく、購読しているのは金融機関や信用情報機関、一部の企業などに限られます。
そのため、官報への掲載が原因で、近所の人や勤務先などに知られる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、公に情報が掲載されるという事実自体はデメリットとして認識しておく必要があります。
借金救済制度の手続きにかかる費用の目安
借金救済制度を利用する際には、手続きを依頼する弁護士や司法書士への費用が発生します。
この弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費といった項目で構成されており、決して安い金額ではありません。
料金の総額は、選択する手続きの種類や借入先の数、事案の複雑さによって変動します。
多くの法律事務所では費用の分割払いや後払いに対応しているため、すぐにまとまったお金が用意できなくても相談は可能です。
依頼前には、手数料を含む費用体系を明確に確認することが重要です。
任意整理を依頼した場合の費用相場
任意整理を専門家に依頼した場合の費用は、債権者の数によって決まることが一般的です。
費用の内訳としては、手続きに着手する際に支払う「着手金」と、和解成立時に支払う「解決報酬金」、借金が減額できた場合にその額に応じて支払う「減額報酬金」があります。
着手金と解決報酬金は、それぞれ債権者1社あたり2万円から5万円程度が相場です。
したがって、借入先の数が多ければ多いほど、費用総額は高くなります。
過払い金が発生していた場合は、別途過払い金報酬が必要になることもあります。
個人再生を依頼した場合の費用相場
個人再生は、裁判所への申し立てが必要な複雑な手続きであるため、任意整理よりも費用は高額になります。
弁護士に依頼した場合の費用相場は、総額で50万円から80万円程度です。
この費用には、弁護士への着手金や報酬金のほか、裁判所に納める申立手数料、官報掲載料、郵便切手代などの実費が含まれます。
また、裁判所によって選任される個人再生委員への報酬が別途必要になる場合もあります。
住宅ローン特則を利用するかどうかによっても、費用が変動することがあります。
自己破産を依頼した場合の費用相場
自己破産の費用は、手続きが「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらになるかで大きく異なります。
財産がほとんどなく、手続きが簡易な同時廃止事件の場合、費用相場は30万円から50万円程度です。
一方、一定以上の財産があり、破産管財人が選任される管財事件の場合は、管財人への引継予納金(最低20万円)が追加で必要になるため、総額は50万円から120万円以上になることもあります。
事務所によっては着手金無料を謳っている場合もありますが、その分報酬金が設定されているため、総額で比較検討することが大切です。
借金救済制度は弁護士・司法書士に相談するのがおすすめ
借金救済制度の手続きは、法律の専門知識を要し、書類作成や交渉が複雑なため、個人で行うのは非常に困難です。
そのため、弁護士や司法書士といった専門家に相談するのがおすすめです。
全国各地、例えば福岡、大阪、京都、新潟、沖縄、熊本、長崎、鹿児島などに対応している法律事務所や司法書士法人も増えています。
多くの事務所では無料相談を実施しており、評判などを参考にしながら、まずは自分の状況を話し、どのような解決策があるのかアドバイスを受けることから始めるのが良いでしょう。
債務整理の実績が豊富な事務所を選ぶ
弁護士や司法書士には、それぞれ離婚問題や交通事故、企業法務など得意とする分野があります。
借金問題を解決するためには、債務整理手続きの実績が豊富な事務所を選ぶことが極めて重要です。
事務所のウェブサイトに掲載されている解決事例や、利用者からの評判・口コミなどを参考に判断するとよいでしょう。
経験豊富な専門家であれば、債権者との交渉や裁判所での手続きを円滑に進め、依頼者にとってより有利な条件での解決が期待できます。
相談時には、これまでの実績について具体的に質問してみるのも一つの方法です。
相談しやすく相性の良い担当者か見極める
債務整理の手続きは、依頼から解決まで数ヶ月から1年以上かかることもあり、担当者とは長期的な付き合いになります。
そのため、専門的な知識や実績だけでなく、担当者との相性も非常に重要な要素です。
初回の相談の際に、自分の話を親身になって聞いてくれるか、専門的な内容をわかりやすく説明してくれるか、質問しやすい雰囲気かなどを確認しましょう。
高圧的な態度を取られたり、不安を煽られたりするような場合は、依頼を避けた方が賢明です。
安心して悩みを打ち明け、信頼関係を築ける担当者を見つけることが大切です。
借金救済制度に関するよくある質問
借金救済制度は、日本全国で利用できる法的手続きであり、多くの人が生活を再建するきっかけとしています。
しかし、いざ利用を考え始めると、手続きが周囲に知られてしまわないか、将来の生活にどのような影響があるのかなど、具体的な疑問が浮かんでくるものです。
ここでは、そうした制度の利用を検討する際に、特に多く寄せられる質問とその回答を紹介します。
正しい知識を持つことで、不要な不安を解消し、前向きに検討を進めることが可能になります。
Q. 家族や職場に知られずに手続きはできますか?
弁護士や司法書士に依頼した場合、連絡の窓口はすべてその事務所になるため、原則として家族や職場に知られずに手続きを進めることは可能です。
債権者からの督促状や電話は止まり、裁判所からの書類も事務所宛に送付してもらうなどの配慮がなされます。
ただし、家族が保証人になっている場合や、家計の状況を説明するために家族の協力が必要なケースでは、秘密にしておくことが難しいこともあります。
また、会社から借金をしている場合は、会社も債権者となるため、手続きの事実を隠すことはできません。
Q. 手続き後はクレジットカードやローンが一切利用できなくなりますか?
手続きを行うと、信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間は新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることは困難になります。
この登録期間は、手続きの種類や信用情報機関にもよりますが、おおむね5年から10年です。
この期間が経過し、事故情報が抹消された後であれば、再び申し込みをすることは可能です。
教育ローンを含め、クレジットカードやローンの利用ができるようになる可能性はありますが、審査は各金融機関が独自の基準で行うため、必ずしも契約できるとは限りません。
まとめ
借金の救済制度は、国が認めた法的な手続きであり、借金問題の解決に向けた有効な手段です。
任意整理、個人再生、自己破産といった複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
手続きの利用は信用情報に影響を及ぼし、費用も発生するため、その内容を正確に理解することが不可欠です。
返済に困窮している場合、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自身の状況にとって最適な解決方法を検討することが、生活再建への第一歩となります。