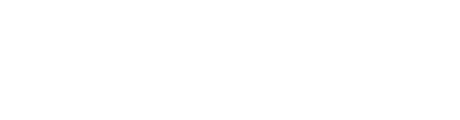※この記事は、広告(PR)を含む場合があります。
 あける
あける
住宅ローン減税(控除)制度を活用するには?確定申告の必要書類や書き方・申請方法を解説!
目次
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、住宅ローン減税(控除)制度を活用することが可能です。この制度を受けるには、初年度に確定申告をおこなう必要があります。確定申告を自身で進める際、どのような書類が必要になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。さらに、住宅ローン減税(控除)制度は、近年大きな見直しが行われています。そこで本記事では、住宅ローン減税(控除)の基本的な仕組みから、変更点、減税を受けるために必要な書類までを詳しく解説していきます。
住宅ローン減税(控除)とはどんな制度?
住宅ローン減税(控除)制度とは、所得税や住民税の負担を軽くするための制度です。
住宅ローン減税(控除)とは、住宅の購入や増改築にともない借り入れた住宅ローンの年末残高に応じて、所得税や住民税から一定の金額が控除される仕組みです。基本的には所得税からの控除となりますが、控除しきれなかった分については住民税から差し引かれるかたちになります。
具体的な内容については後ほど詳しくご説明しますが、この住宅ローン減税制度は初年度に確定申告をおこなうことで適用されます。住宅の取得は大きな出費を伴うため、金銭面でも精神面でも大きな負担となりがちです。そうした状況を踏まえ、住宅の取得を後押しし、国民の暮らしを安定させる目的で設けられたのがこの制度です。
住宅ローン減税(控除)の対象となる条件とは
住宅ローン減税(控除)を利用するには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。具体的な条件は以下のとおりです。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 減税(控除)を受ける年の年末時点で、その住宅に居住していること
- 床面積が50平方メートル以上あること
※自宅で事業をおこなっている場合は、その床面積の2分の1以上を居住用として使用している必要があります - 引き渡しから6カ月以内に居住していること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
これらの要件をすべて満たしてはじめて、住宅ローン減税(控除)を受けることができます。新築に限らず、中古住宅を購入した場合でも適用されますが、ご自身が住むための住宅ローンであることが条件です。投資目的の物件や土地のみの購入では対象とならないため、注意が必要です。
住宅ローン減税(控除)の控除額について
実際にどの程度の控除が受けられるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。控除額は、住宅ローンの年末残高に0.7%を乗じて算出されます。ただし、住宅の種類によって控除の限度額が異なるため、注意が必要です。
それでは、新築住宅の種類ごとに設定されている借入限度額および控除期間について見ていきましょう。
【2022年~2023年に入居】
- 長期優良住宅:5,000万円(13年間)
- 認定低炭素住宅:5,000万円(13年間)
- ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(13年間)
- 省エネ基準適合住宅:4,000万円(13年間)
- その他の住宅:3,000万円(13年間)
【2024年~2025年に入居】
- 長期優良住宅:4,500万円(13年間)
※2024年のみ子育て・若者世帯は5,000万円 - 認定低炭素住宅:4,500万円(13年間)
※2024年のみ子育て・若者世帯は5,000万円 - ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(13年間)
※2024年のみ子育て・若者世帯は4,500万円 - 省エネ基準適合住宅:3,000万円(13年間)
※2024年のみ子育て・若者世帯は4,000万円 - その他の住宅:0円(※一定条件を満たすと2,000万円まで対象・控除期間は10年間)
控除率はすべての期間を通じて一律0.7%です。
また、適用されるためには合計所得金額が2,000万円以下(条件により1,000万円以下)であること、床面積が50平方メートル以上(一部は40平方メートル以上50平方メートル未満)であることが求められます。
※出典:国税庁
2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅については、借入限度額2,000万円・控除期間10年間の対象となります。
さらに、住宅の種類と居住年に応じた年間の控除限度額は以下のとおりです。
【住宅の区分と年間の控除限度額】
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
2022年・2023年:35万円/年
2024年・2025年:31.5万円/年 - ZEH水準省エネ住宅
2022年・2023年:31.5万円/年
2024年・2025年:24.5万円/年 - 省エネ基準適合住宅
2022年・2023年:28万円/年
2024年・2025年:21万円/年 - 一般の新築住宅
2022年・2023年:21万円/年
2024年・2025年:14万円/年
このように、住宅の種類や入居した年によって、控除の上限額や借入限度額が大きく変わります。事前にしっかり確認しておくことが大切です。
2024年以降は省エネ基準のクリアが必須に
2024年以降、住宅ローン減税(控除)を受けるには、住宅が省エネ基準を満たしていることが求められます。では、なぜ省エネ基準をクリアする必要があるのでしょうか。それは、2025年4月以降、すべての建築物に対して省エネ基準の適合が原則義務化されるためです。こうした背景から、省エネ基準に適合した住宅の普及を早期に促す目的で、住宅ローン減税(控除)を利用するための条件として、省エネ基準のクリアが加えられたのです。
子育て・若者世帯に対する優遇措置
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」では、住宅ローン減税(控除)の制度についても変更が盛り込まれました。2024年に入居する子育て・若者世帯に対しては、住宅ローンの借入限度額に一定の上乗せが行われるという内容です。
子育て・若者世帯の定義は以下のとおりです。
- 19歳未満の扶養親族を有する者
- 40歳未満で配偶者がいる者、または40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者
なお、年齢の判定は入居した年の12月31日時点のものとされています。
ただし、これはあくまで実施の方針が決定された段階であり、実際の制度変更には、関連する法律が国会で成立することが前提です。該当する可能性のある方は、最新の情報をこまめに確認しておくことが大切です。
住宅ローン減税(控除)の申請方法とは
住宅ローン減税(控除)を受ける方法についてご紹介します。
この制度を利用するには申請が必要であり、初年度と2年目以降では手続きの内容が異なります。その違いを事前に把握しておきましょう。
初年度は確定申告の手続きが必要
住宅ローン減税(控除)を受けるには、住宅へ入居した翌年の2月16日から3月15日の間に、自分で確定申告をおこなう必要があります。確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの所得を確定させ、所得税を清算するための手続きです。所得税を多く納めていた場合は、「還付」として納め過ぎた税金が戻ってきます。
必要となる書類や手続きの流れについては後ほど詳しく解説しますので、あらかじめ確認しておきましょう。
【初年度】住宅ローン控除の確定申告の手続きとは?必要書類や流れをわかりやすく紹介
住宅を購入した後には、忘れずにおこなうべき重要な手続きがあります。それが、住宅ローン控除を受けるための確定申告です。確定申告をおこなうことで、年末時点での住宅ローン残高に所定の割合をかけた金額が、所得税から控除されます。
2年目以降は年末調整で対応
会社員や公務員などの給与所得者は、2年目以降は必要書類をそろえて勤務先に提出することで、年末調整により住宅ローン減税(控除)が適用されるため、確定申告をする必要はありません。
勤務先に提出する書類は、以下の2点です。
- 住宅ローンの残高証明書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
ただし、個人事業主や年収が2,000万円を超える会社員の方は、2年目以降も引き続き自分で確定申告を行う必要があるため、その点には注意が必要です。
住宅ローン減税(控除)制度を利用するための確定申告に必要な書類一覧
住宅ローン減税制度を利用する際に必要となる書類について解説します。
住宅ローンの減税(控除)制度を活用するためにおこなう確定申告では、以下の書類を準備する必要があります。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書 | 国税庁ホームページ/税務署 |
| (特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書 | ― |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 金融機関 |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 |
| 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し | ― |
| 本人確認書類の写し | ― |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
それぞれの必要書類について、順を追って詳しくご説明していきます。
住宅ローン減税制度を利用する際の準備として、しっかり確認しておきましょう。
確定申告書とは
確定申告書とは、個人の所得・収入・経費などを記載するための書類で、税務署または国税庁のホームページから入手できます。
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、必要な項目を入力するだけで確定申告書を作成できます。記入方法がわからない場合は、最寄りの税務署で職員に確認するか、税理士に相談するのがおすすめです。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅ローン控除の金額を算出するために必要な書類です。
確定申告書と同様に、国税庁のホームページからダウンロードでき、「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、必要な項目を入力するだけで簡単に作成できます。住宅の性能に関係なく、住宅ローン減税制度を利用するすべての方が、この書類を提出する必要があります。
前述のとおり、控除額は住宅の種類や入居時期によって異なるため、正確な計算が求められます。記入の際には、登記事項証明書・売買契約書・住宅ローンの年末残高等証明書などが必要になるため、直前になって慌てないよう、早めに準備しておきましょう。
住宅ローンの残高等証明書について
住宅ローン減税制度を利用するには、住宅ローンを組んで住宅を購入していることが大前提となります。
この制度で控除される金額は、確定申告の前年・年末時点の住宅ローン残高をもとに計算されるため、金融機関から送付される残高等証明書が必要になります。まだ手元にない場合は、早めに金融機関へ再発行を依頼しておくと安心です。
土地・建物の登記事項証明書
登記事項証明書は、不動産の所有者や面積などの情報が記載された書類で、法務局などで取得することができます。
先にご紹介した(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載すれば、土地および建物の登記事項証明書を別途提出する必要はありません。
土地・建物の不動産売買契約書または請負契約書の写し
不動産の購入金額や購入日を証明するためには、売買契約書が必要となります。
また、土地のみを購入し、その後建物を新築した場合には、工事請負契約書が必要となるため、あらかじめその写しを用意しておきましょう。
本人確認書類の準備
住宅ローン減税制度に限らず、確定申告をおこなう際には、確定申告書にマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーが本人のものであることを証明するための書類もあわせて求められます。
具体的には、以下のいずれかの書類を用意する必要があります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーを確認できる書類と、身元確認書類
マイナンバーを確認できる書類としては、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などがあります。
身元確認書類には、運転免許証やパスポートなどが該当するため、確定申告の前に忘れずに準備しておきましょう。
源泉徴収票を用意する
会社員や公務員などの給与所得者は、勤務先から交付される源泉徴収票が必要になります。
2019年分の確定申告からは、源泉徴収票の提出は不要となりましたが、確定申告書の給与所得欄に金額を記入する際の根拠資料として、手元に用意しておくようにしましょう。
省エネ基準クリアを証明する書類
繰り返しになりますが、住宅ローン減税(控除)を受けるには、省エネ基準を満たしていることが条件となります。その基準を満たしていることを証明するためには、所定の書類が必要です。以下は、住宅の区分ごとに必要となる書類をまとめた一覧です。
| 住宅の区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅の場合 | ・長期優良住宅建築等計画等の認定通知書【写し】 ・住宅用家屋証明書【原本または写し】または認定長期優良住宅建築証明書【原本】 |
| 低炭素住宅の場合 | ・低炭素建築物新築等計画の認定通知書【写し】 ・住宅用家屋証明書【原本または写し】または認定低炭素住宅建築証明書【原本】 |
| 低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合 | ・住宅用家屋証明書(特定建築物用)【原本】 |
| ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合 | ・住宅省エネルギー性能証明書【原本】または登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】 |
自分の住宅がどの区分に該当するかは、購入や建築を依頼した不動産会社や建築会社に事前に確認しておくと安心です。
住宅ローン減税制度を受けるための確定申告の進め方
住宅ローン減税(控除)制度を利用する際の流れについて解説します。
この制度を活用するための確定申告は、以下のステップで進めていきます。
STEP1 必要書類を準備する
STEP2 確定申告書類一式を期限内に提出する
STEP3 還付金を受け取る
それでは、各ステップを順に確認していきましょう。
住宅ローン減税(控除)制度の手続きに不安がある方も、流れを把握しておくことでスムーズに進められます。
必要書類の準備をおこなう
まずは、確定申告に必要な書類をそろえることから始めましょう。確定申告の期限までに、前述の必要書類をすべて用意する必要があります。
書類の中には、準備に時間を要するものもあるため、早めに取りかかって余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
確定申告書類一式を期限内に提出する
次に、確定申告書類一式を確定申告の期間内に税務署へ提出しましょう。申告期間は2月16日から3月15日までです。
確定申告書は、税務署または国税庁のホームページから取得できるので、必要事項を記入し、他の必要書類とあわせて提出します。
税務署の窓口で直接提出することも可能ですが、郵送やオンラインでの申告も可能なため、ご自身にとって申告しやすい方法を選ぶのがおすすめです。
申告方法や書類の書き方がわからない場合は、税務署の窓口で職員に相談しながら手続きを進めると安心です。
還付金の受け取りを確認する
確定申告書一式を税務署に提出すると、おおよそ1カ月から1カ月半ほどで還付金が指定口座に振り込まれます。場合によっては振込時期が前後することもありますが、還付金の入金を待ちましょう。
住宅購入後の確定申告のやり方は?住宅ローン控除の手続きや必要書類についても解説
住宅を購入したあと、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。住宅ローン控除とは、新築・中古を問わず、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、年末時点のローン残高に応じて所得税が還付される制度です。
住宅ローン減税(控除)の確定申告書の書き方ガイド
申告をスムーズに進めるためにも、確定申告書の書き方をあらかじめ確認しておきましょう。
住宅ローン減税(控除)を受けて還付金を受け取るには、確定申告書への正確な記入が必要です。申告書の作成に入る前に、まずは控除額を算出するために、(特定増改築等)借入金等特別控除額の計算明細書から記入を始めましょう。
新築または購入した家屋に関する情報の記入
購入した建物や土地の情報を記入しましょう。「取得対価の額」の欄には、購入した金額を記載します。ただし、土地は非課税のため、消費税は含まれないことに注意しましょう。一方、建物は消費税を含めた金額を記載します。
居住用の家屋・土地等に関する住宅借入金の年末残高の記載
住宅ローンを借り入れている金融機関から送付された「住宅ローン年末残高等証明書」に基づいて記入しましょう。控除額の計算に関わる重要な箇所なので、誤りのないよう十分注意が必要です。
「控除証明書の交付を要しない場合」の欄は、そのまま空欄にしておきましょう。ここに誤って丸をつけてしまうと、2年目以降の年末調整で必要となる控除証明書が届かなくなってしまいます。
また、前述のとおり、居住した年によって控除額が異なるため、記入ミスにはくれぐれも注意してください。書類の記載内容に不明点がある場合は、税務署へ問い合わせるのが安心です。
まとめ
住宅ローン減税(控除)制度を利用するには、多くの指定された書類を準備する必要があります。住宅を購入した初年度は、自分自身で確定申告をおこなう必要がありますが、会社員や公務員などの給与所得者であれば、2年目以降は勤務先が年末調整をおこなってくれます。確定申告には定められた期間があるため、余裕を持って必要書類の準備を進めておきましょう。